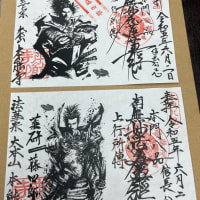慶長8年(1603)9月11日、水戸藩主武田信吉が亡くなりました。享年21歳。
武田姓を称していますが、徳川家康の5男です。
本能寺の変の後、徳川家康は堺見学から居城浜松城へと向かう神君伊賀越えを経験します。このことについては僕もいろいろ想うところがありますが、今回の話とは離れてしまうので割愛します。
神君伊賀越えでは、この直後の家康の行動を決定付ける大きな事件が起こります。それは穴山信君が殺害されたことでした。信君は武田信玄の甥で、信玄の次女・見性尼を妻に迎えている人物で、織田信長の武田攻めの後で武田宗家を継いだ人物だったのです。
こんな信君が殺されたことと、本能寺の変の混乱によって旧武田領とも言える甲斐・信濃は主がいない状態となったのです。
伊賀越えから浜松に帰城した家康は、明智光秀を討つ名目で軍を西に向けて発しますが、山崎の戦いで羽柴秀吉が光秀を討ったことを聞くとすぐに東に進み、駿河・甲斐・信濃を併合して行きます。
それまでは三河・遠江の2国の大名でしかなかった家康が3国を支配下に治めたことで5国を領する大大名に成長したのです。この時に家康が3国を取っていなければ、秀吉に恐れられる大名にも成りきれず豊臣家の一大名として終わっていた可能性すらあるのです。
さて、前置きが長くなりましたが、旧武田領を得た家康がその地を治めるために求めた物が、武田信玄に繋がる血でした。この為にまずは穴山信君の息子である勝千代(武田信治)に武田家を継がせ、家康自身も武田家に繋がる女性を探し出して側室にしたのです。於都摩という名の女性が信玄の末娘という形式を作り信君の養女として家康の許に行きました。
こうして、家康と於都摩の間に生まれたのが信吉でした。
天正15年に勝千代が他界すると、武田宗家が滅亡したので、見性尼を後見として信吉が武田家を相続します。
その後、家康の関東転封に従って関東に移動すると、武田姓を名乗る必要が無く一度は松平姓になりますが、関ヶ原の戦いの後で水戸15万石と穴山家を中心とする武田家臣を与えられます。こうして親藩水戸藩が誕生します。
しかし、江戸幕府が開幕して半年後に信吉は亡くなってしまい、この時点で武田宗家は完全に滅亡します。武田家は信玄の次男武田竜芳の系統が現在まで家名を残しています。
ちなみに水戸藩に残った旧武田家臣の多くはそのまま藩に残り、最終的には徳川御三家になる徳川頼房の家臣となるのです。
同じく旧武田家臣を多く引き連れて関ヶ原を戦い、彦根藩に入った井伊家との幕末の確執を考えると、旧武田家臣の与える影響は大きかった気もしますね。
武田姓を称していますが、徳川家康の5男です。
本能寺の変の後、徳川家康は堺見学から居城浜松城へと向かう神君伊賀越えを経験します。このことについては僕もいろいろ想うところがありますが、今回の話とは離れてしまうので割愛します。
神君伊賀越えでは、この直後の家康の行動を決定付ける大きな事件が起こります。それは穴山信君が殺害されたことでした。信君は武田信玄の甥で、信玄の次女・見性尼を妻に迎えている人物で、織田信長の武田攻めの後で武田宗家を継いだ人物だったのです。
こんな信君が殺されたことと、本能寺の変の混乱によって旧武田領とも言える甲斐・信濃は主がいない状態となったのです。
伊賀越えから浜松に帰城した家康は、明智光秀を討つ名目で軍を西に向けて発しますが、山崎の戦いで羽柴秀吉が光秀を討ったことを聞くとすぐに東に進み、駿河・甲斐・信濃を併合して行きます。
それまでは三河・遠江の2国の大名でしかなかった家康が3国を支配下に治めたことで5国を領する大大名に成長したのです。この時に家康が3国を取っていなければ、秀吉に恐れられる大名にも成りきれず豊臣家の一大名として終わっていた可能性すらあるのです。
さて、前置きが長くなりましたが、旧武田領を得た家康がその地を治めるために求めた物が、武田信玄に繋がる血でした。この為にまずは穴山信君の息子である勝千代(武田信治)に武田家を継がせ、家康自身も武田家に繋がる女性を探し出して側室にしたのです。於都摩という名の女性が信玄の末娘という形式を作り信君の養女として家康の許に行きました。
こうして、家康と於都摩の間に生まれたのが信吉でした。
天正15年に勝千代が他界すると、武田宗家が滅亡したので、見性尼を後見として信吉が武田家を相続します。
その後、家康の関東転封に従って関東に移動すると、武田姓を名乗る必要が無く一度は松平姓になりますが、関ヶ原の戦いの後で水戸15万石と穴山家を中心とする武田家臣を与えられます。こうして親藩水戸藩が誕生します。
しかし、江戸幕府が開幕して半年後に信吉は亡くなってしまい、この時点で武田宗家は完全に滅亡します。武田家は信玄の次男武田竜芳の系統が現在まで家名を残しています。
ちなみに水戸藩に残った旧武田家臣の多くはそのまま藩に残り、最終的には徳川御三家になる徳川頼房の家臣となるのです。
同じく旧武田家臣を多く引き連れて関ヶ原を戦い、彦根藩に入った井伊家との幕末の確執を考えると、旧武田家臣の与える影響は大きかった気もしますね。