「神戸コンチェルト」は、神戸ハーバーランド、モザイク前から出港するレストラン船。
通常、ランチクルーズ、ティークルーズ、ディナークルーズがあります。
乗船料は、大人2,100円。確か乗船だけでもOKのはず。但し自由席?
時間はランチC.が12:00~13:45の1時間45分。
ティーC.は15:00~16:30の1時間30分。当然距離も少し短い。
ディナーC.は17:10~18:55と19:20~21:05の2便。
それぞれにメニューが用意されていて注文すると予約席になります。
事前予約制でモザイク内にチケットカウンターがあります。

じょうせ~ん♪

お見送りです。紙テープは無いですね・・・
出航後は進路を西に取り、明石海峡大橋手前の垂水沖または須磨沖で引き返す。
船上からは、神戸の街並みのほか、神戸空港、複数の造船所、和田岬、摩耶山・
鉄拐山および鉢伏山など須磨アルプスの山々、平磯海岸、明石海峡および
淡路島をはじめとした大阪湾の景色などが眺められるのですが、
ティークルーズは須磨沖でUターンするので明石海峡大橋も遠くにしか見えませんw



よーそろー よろしく候 浪の上



ティータイム 甘いひととき なみとかし
喫茶 CAKE SET、マンゴープリン&スイーツセットです。
フリーソフトドリンク付、1,200円也。これが一番安いメニュー。(^_^ゞ
船内(B-Deck ルビー)は、こんな感じ。


バイオリンとピアノの生演奏が楽しめます。
コンチェルト 生演奏で 酔わせます
・・・船酔いはしません(汗)
ひと息ついて、デッキへと。





デッキあがり 若いふたりは 影ひとつ


ドリンクと スイーツついて サンセット
・・・何のこっちゃ(笑)。いよいよクルーズも佳境、中間地点です。

明石にて そろそろ夕飯 はし渡し
まだお腹減ってませんw 明石海峡大橋が見えたらUターン、帰路に。


90分の短い航海、あまり寒さも感じず楽しいひとときでした。
今度は地中海へ♪・・・行かへん、行かへん。(^_^ゞ

2012.1/8、神戸コンチェルトにて。
通常、ランチクルーズ、ティークルーズ、ディナークルーズがあります。
乗船料は、大人2,100円。確か乗船だけでもOKのはず。但し自由席?
時間はランチC.が12:00~13:45の1時間45分。
ティーC.は15:00~16:30の1時間30分。当然距離も少し短い。
ディナーC.は17:10~18:55と19:20~21:05の2便。
それぞれにメニューが用意されていて注文すると予約席になります。
事前予約制でモザイク内にチケットカウンターがあります。

じょうせ~ん♪

お見送りです。紙テープは無いですね・・・
出航後は進路を西に取り、明石海峡大橋手前の垂水沖または須磨沖で引き返す。
船上からは、神戸の街並みのほか、神戸空港、複数の造船所、和田岬、摩耶山・
鉄拐山および鉢伏山など須磨アルプスの山々、平磯海岸、明石海峡および
淡路島をはじめとした大阪湾の景色などが眺められるのですが、
ティークルーズは須磨沖でUターンするので明石海峡大橋も遠くにしか見えませんw



よーそろー よろしく候 浪の上



ティータイム 甘いひととき なみとかし
喫茶 CAKE SET、マンゴープリン&スイーツセットです。
フリーソフトドリンク付、1,200円也。これが一番安いメニュー。(^_^ゞ
船内(B-Deck ルビー)は、こんな感じ。


バイオリンとピアノの生演奏が楽しめます。
コンチェルト 生演奏で 酔わせます
・・・船酔いはしません(汗)
ひと息ついて、デッキへと。





デッキあがり 若いふたりは 影ひとつ


ドリンクと スイーツついて サンセット
・・・何のこっちゃ(笑)。いよいよクルーズも佳境、中間地点です。

明石にて そろそろ夕飯 はし渡し
まだお腹減ってませんw 明石海峡大橋が見えたらUターン、帰路に。


90分の短い航海、あまり寒さも感じず楽しいひとときでした。
今度は地中海へ♪・・・行かへん、行かへん。(^_^ゞ

2012.1/8、神戸コンチェルトにて。














































































 カイツブリが抱卵してました♪
カイツブリが抱卵してました♪

































































































































































































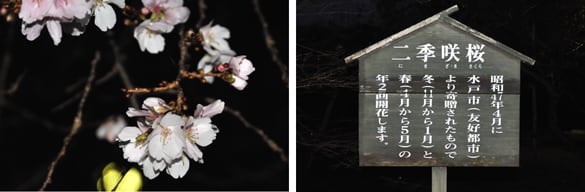



















 入ってる?
入ってる?














