
今回のお気に入りは「彩色写生図 日本の薬用植物」です。
本書は53年前の1966年に発行された彩色写生図がたっぷり収録された薬用植物図鑑です。
長崎大学名誉教授の高取治輔という方が文章と写生図の両方を担当しています。
本書の購入を決定的にしたのは、ネット上に公開されている「長崎大学薬学部会報38-41」の一文でした。
=====
写生図には故高取治輔・長崎大学名誉教授によって描かれた「日本の薬用植物」から抜粋した貴重な八枚の原画があります。
画家の小磯良平氏も脱帽されたという水彩の色の美しさと写生の正確さには感嘆させられます。
写生図が写真や実物よりも優れている点は,花や果実,根茎など特定の季節や生育段階にしかないものも,同時に見ることができることです。
壁を飾るこれらの図は,左手で植物のスケッチをしながら右手で説明文を書いて当時の学生をうならせたという,高取先生ならではの作品と言えましょう。
=====
小磯良平が脱帽するほどの色彩の美しさと写生の正確さ。
それならぜひにも鑑賞したいと思いました。
ちなみにここでなぜ小磯良平が登場したのかについて、思い当たることがあります。
日本洋画界の第一人者・小磯良平はある薬品メーカーの社内報のために10数年もの間、薬用植物を描き続けました。
その数は173点にも上ります。
前半はスケッチ画でしたが、後半は画集化が決まり本腰を入れて描いたそうです。
この経験から小磯良平は高取治輔が描いた薬用植物画に興味を持ちコメントしたのでしょう。
さて実際に写生図を鑑賞すると、予想以上の美しさに驚きました。
小磯画伯のコメントには「素人にしては上手」という含みがあるだろうと思っていましたが、本当に鑑賞に堪えるレベルなのです。
80ページの写生図と簡素な解説文にゆっくりと何日もかけて目を通した日々は至福の時間でした。
ところで本書但し書きに、1ページに2種を描いたページを例にして8年もかけて完成したこと、2種の重なりが多少見づらいことが書かれていました。
時々に合わせて、花、実、葉、幹、根を正確かつ美しく描き足していく高取氏の姿が目に浮かびました。
ここに書いてある通り、80ページに113種は混雑気味。
中には1ページに3種が重なって描かれているページもありました。
たとえ重なりが2種でも、私には「少々見づらい」どころでなく、かなり見づらかったです。
できれば1ページ1種にして欲しかったです。
ただ当時はカラー図版が貴重な時代、贅沢はいえません。
本書にしても、長崎大学の先生の写生図を京都の印刷会社でカラー印刷し、解説文の印刷と製本を東京の出版社が行い、ようやく出来上がっています。
1966年当時の販売価格15,000円は相当高価だったことでしょう。
これは片目をつぶるしかありません。
また本書で意外だったのは「日本の薬用植物」という題名にもかかわらず、海外の植物が多く掲載されていたこと。
国内で普通に栽培されているものならOK、という広い心でまとめたのでしょう。
アロエなどの身近な薬用植物は掲載してもらって正解!とおおいに納得しました。
本書には続編があるそうで、とても気になっています。
ただし最近この手の大型本の購入が続いていて、出費が重なっていることと、本の置き場が無くなってきたことから、しばらく間をあけたいと思います。
本書は53年前の1966年に発行された彩色写生図がたっぷり収録された薬用植物図鑑です。
長崎大学名誉教授の高取治輔という方が文章と写生図の両方を担当しています。
本書の購入を決定的にしたのは、ネット上に公開されている「長崎大学薬学部会報38-41」の一文でした。
=====
写生図には故高取治輔・長崎大学名誉教授によって描かれた「日本の薬用植物」から抜粋した貴重な八枚の原画があります。
画家の小磯良平氏も脱帽されたという水彩の色の美しさと写生の正確さには感嘆させられます。
写生図が写真や実物よりも優れている点は,花や果実,根茎など特定の季節や生育段階にしかないものも,同時に見ることができることです。
壁を飾るこれらの図は,左手で植物のスケッチをしながら右手で説明文を書いて当時の学生をうならせたという,高取先生ならではの作品と言えましょう。
=====
小磯良平が脱帽するほどの色彩の美しさと写生の正確さ。
それならぜひにも鑑賞したいと思いました。
ちなみにここでなぜ小磯良平が登場したのかについて、思い当たることがあります。
日本洋画界の第一人者・小磯良平はある薬品メーカーの社内報のために10数年もの間、薬用植物を描き続けました。
その数は173点にも上ります。
前半はスケッチ画でしたが、後半は画集化が決まり本腰を入れて描いたそうです。
この経験から小磯良平は高取治輔が描いた薬用植物画に興味を持ちコメントしたのでしょう。
さて実際に写生図を鑑賞すると、予想以上の美しさに驚きました。
小磯画伯のコメントには「素人にしては上手」という含みがあるだろうと思っていましたが、本当に鑑賞に堪えるレベルなのです。
80ページの写生図と簡素な解説文にゆっくりと何日もかけて目を通した日々は至福の時間でした。
ところで本書但し書きに、1ページに2種を描いたページを例にして8年もかけて完成したこと、2種の重なりが多少見づらいことが書かれていました。
時々に合わせて、花、実、葉、幹、根を正確かつ美しく描き足していく高取氏の姿が目に浮かびました。
ここに書いてある通り、80ページに113種は混雑気味。
中には1ページに3種が重なって描かれているページもありました。
たとえ重なりが2種でも、私には「少々見づらい」どころでなく、かなり見づらかったです。
できれば1ページ1種にして欲しかったです。
ただ当時はカラー図版が貴重な時代、贅沢はいえません。
本書にしても、長崎大学の先生の写生図を京都の印刷会社でカラー印刷し、解説文の印刷と製本を東京の出版社が行い、ようやく出来上がっています。
1966年当時の販売価格15,000円は相当高価だったことでしょう。
これは片目をつぶるしかありません。
また本書で意外だったのは「日本の薬用植物」という題名にもかかわらず、海外の植物が多く掲載されていたこと。
国内で普通に栽培されているものならOK、という広い心でまとめたのでしょう。
アロエなどの身近な薬用植物は掲載してもらって正解!とおおいに納得しました。
本書には続編があるそうで、とても気になっています。
ただし最近この手の大型本の購入が続いていて、出費が重なっていることと、本の置き場が無くなってきたことから、しばらく間をあけたいと思います。


















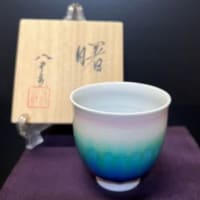







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます