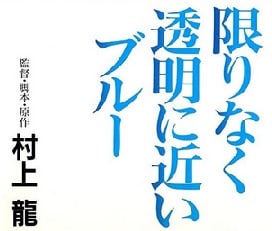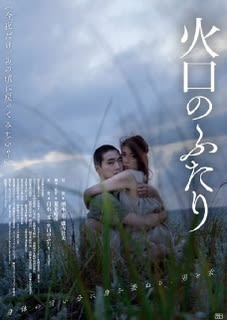(原題:Crime of Passion)84年作品。ケン・ラッセル監督のアヴァンギャルドな個性が全面展開している一編で、とても楽しめる。もちろん、通常のラブストーリーやサスペンス劇を期待して接すると完全に裏切られるが(笑)、同監督の持ち味を認識しているコアな観客にとっては、濃密な時間を堪能出来ること請け合いであろう。
ロスに住むボビーとエイミーの夫婦は、2人の子供と一見平穏な家庭生活を送っている。しかし、実は夫婦仲は冷え切っていた。ファッションデザイナーのジョアンナは有能なキャリアウーマンに見えて、夜になるとチャイナ・ブルーという名の大胆な娼婦として街を闊歩する。ある日ボビーは、ひょんなことから企業スパイの疑いが掛かったジョアンナを密かに調査する仕事を依頼される。

ジョアンナを尾行したボビーは、ジョアンナの二重生活を知って驚くが、同時に彼女の魅力のとりこになってしまった。一方、ジョアンナはピーターという奇妙な客となじみになる。彼は聖職者らしく、夜ごと娼婦たちの告解を聞いている。だが、やがて自身の価値観と相容れない存在のジョアンナに対し、ピーターは殺意を抱いてゆく。
作者は、外的側面の裏側に潜む人間意識を執拗に追求しているようだ。映画の序盤に参加者が互いの悩みを告白し合うサロンのようなものが紹介されるが、それも“上っ面”に過ぎない。悩みなんてものは、多くは打ち明けた瞬間に各人の“仮面”の一部となってしまう。本当の内面は他人はもちろん当人にとっても把握するのは難しいのだ。
その意味で、本作に於けるピーターの存在は欺瞞そのものである。人の悩みを聞いてやる立場だが、本当は何も分かっておらず、夜郎自大な振る舞いに出る。昼と夜の“仮面”を使い分けるジョアンナや、表面的に夫婦仲をよく見せるボビーも同様で、彼らは“裏の顔”こそが“本当の姿”だと思っているが、実はそれも“仮面”に過ぎない。アイデンティティを喪失して彷徨する人間像を、意地悪く描くラッセルの筆致は冴え渡る。終盤のトリック描写も鮮やかだ。
ジョアンナに扮するキャスリーン・ターナーはまさに怪演で、二つの顔を毒々しく演じ分ける。この頃の彼女は絶好調だった。ピーター役のアンソニー・パーキンスも得意の変態演技で盛り上げてくれる。ジョン・ローリンとアニー・ポッツの演技も悪くない。音楽担当は何とリック・ウェイクマンで、彼らしい持ち味は控え目だが、しっかりと仕事をこなしている。
ロスに住むボビーとエイミーの夫婦は、2人の子供と一見平穏な家庭生活を送っている。しかし、実は夫婦仲は冷え切っていた。ファッションデザイナーのジョアンナは有能なキャリアウーマンに見えて、夜になるとチャイナ・ブルーという名の大胆な娼婦として街を闊歩する。ある日ボビーは、ひょんなことから企業スパイの疑いが掛かったジョアンナを密かに調査する仕事を依頼される。

ジョアンナを尾行したボビーは、ジョアンナの二重生活を知って驚くが、同時に彼女の魅力のとりこになってしまった。一方、ジョアンナはピーターという奇妙な客となじみになる。彼は聖職者らしく、夜ごと娼婦たちの告解を聞いている。だが、やがて自身の価値観と相容れない存在のジョアンナに対し、ピーターは殺意を抱いてゆく。
作者は、外的側面の裏側に潜む人間意識を執拗に追求しているようだ。映画の序盤に参加者が互いの悩みを告白し合うサロンのようなものが紹介されるが、それも“上っ面”に過ぎない。悩みなんてものは、多くは打ち明けた瞬間に各人の“仮面”の一部となってしまう。本当の内面は他人はもちろん当人にとっても把握するのは難しいのだ。
その意味で、本作に於けるピーターの存在は欺瞞そのものである。人の悩みを聞いてやる立場だが、本当は何も分かっておらず、夜郎自大な振る舞いに出る。昼と夜の“仮面”を使い分けるジョアンナや、表面的に夫婦仲をよく見せるボビーも同様で、彼らは“裏の顔”こそが“本当の姿”だと思っているが、実はそれも“仮面”に過ぎない。アイデンティティを喪失して彷徨する人間像を、意地悪く描くラッセルの筆致は冴え渡る。終盤のトリック描写も鮮やかだ。
ジョアンナに扮するキャスリーン・ターナーはまさに怪演で、二つの顔を毒々しく演じ分ける。この頃の彼女は絶好調だった。ピーター役のアンソニー・パーキンスも得意の変態演技で盛り上げてくれる。ジョン・ローリンとアニー・ポッツの演技も悪くない。音楽担当は何とリック・ウェイクマンで、彼らしい持ち味は控え目だが、しっかりと仕事をこなしている。