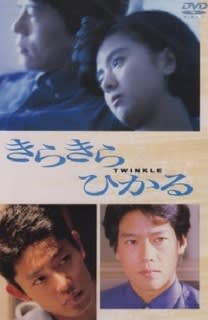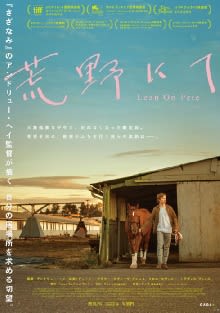(原題:MAD DOG AND GLORY )93年作品。ジョン・マクノートン監督はそれまで「ヘンリー」(86年)や「ボディ・チェンジャー」(91年)といった刺激の強いB級ホラー・サスペンスを手掛けていたが、本作ではなぜかスタイリッシュに仕上げられたラブコメという娯楽王道路線にシフトしている。よくある“突出した個性を持っていた作家が、ハリウッド・メジャー作品を撮った途端にフツーの監督に変貌する”というパターンのように見えるが、実はそうでもないところが興味深い。
シカゴ市警の刑事ウェイン・ドビーは、勤務後に近くのスーパーで強盗事件に遭遇するが、見事に解決する。救出された人質の男マイロは、偶然にもマフィアのボスだった。感激したマイロはドビーに礼を述べると共に、若い情婦のグローリーを一週間トビーに“レンタル”すると申し出る。戸惑うトビーだが、対面したグローリーに惚れてしまい、彼女の方も彼に好意を持つ。一週間はあっという間に過ぎ、ドビーのところへマイロがグローリーを“回収”するためにやって来るが、ドビーは頑として断る。それでは面子が立たないマイロは、ドビーとの“決闘”に臨むのであった。

臆病で慎重なことから、皮肉をこめて狂犬というあだ名で呼ばれていたドビーが、グローリーとの出会いで現実に立ち向かっていく様子は、「ヘンリー」の主人公とヒロインの関係に通じるところがある。また「ボディ・チェンジャー」のエイリアンが凶悪犯と接触したことをきっかけで、本来の姿に目覚めたように、本作では図らずもヤクザの親分とやり合うハメになったドビーが、本当は向こう見ずな熱血漢であったことを自覚する。つまりは従来のマイナーな作品と同じモチーフを、違うジャンルで巧みにキープし続けているという見方も出来るのだ。
ドビー役のロバート・デ・ニーロとグローリーに扮するユマ・サーマン、そしてマイロを演じるビル・マーレイのコンビネーションは万全で、特にマーレイのコメディ的な持ち味とマクノートンのスムーズな演出も相まって、ラブコメとしての体裁は十分整えられている。撮影のロビー・ミュラーと音楽のエルマー・バーンスタインの仕事ぶりも申し分なく、気の利いたラストと共に、鑑賞後の印象は良好だ。
シカゴ市警の刑事ウェイン・ドビーは、勤務後に近くのスーパーで強盗事件に遭遇するが、見事に解決する。救出された人質の男マイロは、偶然にもマフィアのボスだった。感激したマイロはドビーに礼を述べると共に、若い情婦のグローリーを一週間トビーに“レンタル”すると申し出る。戸惑うトビーだが、対面したグローリーに惚れてしまい、彼女の方も彼に好意を持つ。一週間はあっという間に過ぎ、ドビーのところへマイロがグローリーを“回収”するためにやって来るが、ドビーは頑として断る。それでは面子が立たないマイロは、ドビーとの“決闘”に臨むのであった。

臆病で慎重なことから、皮肉をこめて狂犬というあだ名で呼ばれていたドビーが、グローリーとの出会いで現実に立ち向かっていく様子は、「ヘンリー」の主人公とヒロインの関係に通じるところがある。また「ボディ・チェンジャー」のエイリアンが凶悪犯と接触したことをきっかけで、本来の姿に目覚めたように、本作では図らずもヤクザの親分とやり合うハメになったドビーが、本当は向こう見ずな熱血漢であったことを自覚する。つまりは従来のマイナーな作品と同じモチーフを、違うジャンルで巧みにキープし続けているという見方も出来るのだ。
ドビー役のロバート・デ・ニーロとグローリーに扮するユマ・サーマン、そしてマイロを演じるビル・マーレイのコンビネーションは万全で、特にマーレイのコメディ的な持ち味とマクノートンのスムーズな演出も相まって、ラブコメとしての体裁は十分整えられている。撮影のロビー・ミュラーと音楽のエルマー・バーンスタインの仕事ぶりも申し分なく、気の利いたラストと共に、鑑賞後の印象は良好だ。