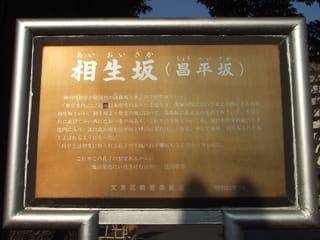東京都葛飾区から江戸川を渡ると千葉県松戸市です、古くは徳川氏の旗本知行地で水戸街道の宿場として栄えました。
今日では全くその面影を留めていませんが、かってこの地にあった松戸城の跡が戸定が丘歴史公園となっていました、園内には第15代将軍徳川慶喜の弟で水戸藩最後の藩主 徳川昭武の別邸として明治17年(1884年)に建てられた戸定邸が残されております。
大政奉還により将軍職を引いた慶喜も何度かこの地を訪れていたそうです、心ならずも徳川幕府の幕引きをせざるを得なかった最後の将軍は同じく水戸徳川家最後の藩主となった実弟とどの様な話をしたのでしょうか。
現在、国の重要文化財にも指定されている邸内は一般に解放されており見学することが可能です、建物内は華美さがなく簡素なもので大名の別邸(下屋敷)らしくない佇まいでした。
昨年は天皇、皇后陛下も邸を訪れています。
公園内にはこじんまりとした梅園があって、訪れたこの日は梅の花が満開でした。
戸定が丘歴史公園の園内案内 趣のある茅葺の正門



戸定邸 簡素な造りの玄関 松戸市戸定歴史館



梅園の梅が見ごろでした