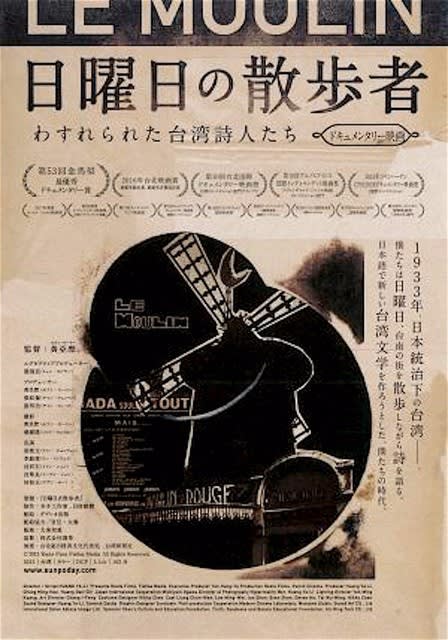「チェコ・アニメの夜」と言うアニメまつりのくくりで上映したら、最も浮くに違いないヤン・シュヴァンクマイエルの長編作品『悦楽共犯者』(1996年/83分)を見てきた。シュヴァンクマイエルの静的なアート作品の過剰なほどのフェチシズムは、驚きを伴ってむしろ私は好きなのだ。だが、それが動き出すとどうだ!この稚拙なまでの陳腐さは?これはフェチシズム映画のパロディか?と一瞬疑ったほどである。(評価:★1/2)
ただこの作品の中で、唯一見るべきものがあるとすれば、おそらくシュヴァンクマイエルの創作の過程といったものが、明かされていると推察できる場面である。
机の引き出しを開けると引き出し一杯に詰まった粘土!ゴミ箱から拾ってきた藁束があれば、ズタ袋一杯の鳥の羽!狐のマフラーの尻尾を強奪し、それはそれは肌さわりも感触も抜群の、世にも妙なる悦楽自慰マシーンを男は制作するのだ。
モニターに映った憧れの女性アナの口元をアップにしながら…。肉体を直接交わすだけでは、快楽を得られないひとびと。その熱情のあまり電子回路をハンダ付けし、モーターを取り付け、女性アナの白き両手を想定したマネキンの手をご丁寧にも4本も取り付け、指先には真っ赤なエナメルのマニキュアを塗り、モニターに口づけしながら、自動するフェルトや狐の尻尾の肌触りに震えおののくのだ。
どうだ、これは映像よりも文章で書き起こした方が、悦楽的に感じ入るものがあるではないか(笑)!エクリチュールの快楽!汝はエクリチュールのフェチなるや?
これは呪物崇拝のコメディなのだが、そこで笑い飛ばされるのは「人間」それも厳密に言うなら特殊な性癖を持った「男」・「女」なのだ。シュヴァンクマイエルと同じ性を持つ男は、その不能なまでのフェチシズムを快楽追求型に追い求めるのだが、その快楽は不可能性いや、不能性によって終わりなき旅となる。
女は?女のフェチもあるではないか。郵便配達人の女は、パンをくり抜き、ふっくらとした中身で小さな球を執拗に丸めあげる。夜、睡眠時にそれらの丸球を鼻から吸い込んで、耳に詰め、1日の疲れを癒すのだ(!)。
コウモリ傘でコウモリの翼を作った男は、隣室の女にマゾヒスチックに鞭で攻められては、藁が詰まった悦楽の涙を流す。
その不能なまでの快楽追求の旅は、異性たる性を対象としながら<究極の自慰>なのだ。究極の一人芝居としての自慰!マスターベーションをマスターせよ!
実際、共産主義体制だった時代に徹底的に無視され、理解されなかったシュヴァンクマイエルのアート、アニメ、人形劇はその冷酷な政治体制の中で、自慰行為と同然だったし、そう社会に目されていた。シュヴァンクマイエルは内面の自由、精神の自由を求めて徹底的に示威行為たるアート行為を貫いていた。むしろそこにしか、彼の自由はなかったであろう。
そして、翌日(27日)はヤン・シュヴァンクマイエルの短編特集だ。これは良かった。ヤン・シュヴァンクマイエルの面目躍如である。そうか、シュヴァンクマイエルは、ボクらがハイスクール時代を過ごしていた頃、共産主義国家から一切の制作費援助も受けられずに、これらのコマ撮り短編映画を作っていたのか!
確かにシュヴァンクマイエルの作品には、イデオロギーもプロパガンダも感じることができない。これじゃ、国家も制作助成金を出すわけがない。
1. 棺の家(1966年/10分)
2.ドン・ファン(1972年/33分)
3.対話の可能性(1982年/12分)
4.男のゲーム(1988年/15分)
5.闇・光・闇(1989年/7分)
6.セルフポートレート(1988年/2分) / 監督ヤン・シュヴァンクマイエル/イジー・バルタ/パヴェル・コウツキー
(評価:★★★★)
上映された短編6本の中でも、『闇・光・闇』が抜群に良かった。似た傾向の作品だが、『対話の可能性』も気持ちが悪くなるくらいいい(笑)!シュヴァンクマイエルの粘土成形の見事な技術が発揮されている。壊しては、成形し、粘土が溶け合っては再び個体の身体を取り戻す!まさしくアニメーションの命を吹き込むかのような原義が発揮される。物体(粘土)が生命を得たかのように動き出す。コマ撮りの技法によって!
しかし、ここで注目したいのは『ドン・ファン』の人形の素朴な様式美である。以前、展覧会で見たチェコ操り人形のような作品はこれだったのだろうか?
御存知だろうが、チェコは人形劇を伝統的に得意とし、また世界的にも評価されている。さらにはスラブ民族にはゴーレム伝説があるから、人形劇への偏愛は民族的なのかもしれない。
その伝統は、そのまま人形アニメ(コマ撮りアニメ)の世界へ繋がり、シュヴァンクマイエルのような国際的な人気を持つ作家が登場した。
かって共産主義国家に制作助成もされなかった上に、弾圧もされたらしいシュヴァンクマイエルはいまや国際的な名声を得て国家も無視できなくなった。いやむしろ外貨獲得ではかなりの貢献を国家にしている以上、文化大臣はもとより首相も無視できない存在となっているらしいのだ(上映後のトークによる)。
チェコの国賓級の外国要人がことごとく一番会いたがる最重要人物が、シュヴァンクマイエルだと言う。さもありなん。
ところで、シュヴァンクマイエルは現代を生きるシュールレアリストだと目されることが多い。
だが、国際シュールレアリズム運動が第四インターの衰退とともに消滅している以上、そのレッテルは本人にも迷惑だろう。ただ、彼のオブジェに対する偏執狂的な偏愛は、かってのシュールレアリストとの共通点が多いことは、認めよう。
だが、私にはシュヴァンクマイエルの作品世界は、物質に満ちたこの巨大な消費社会の中で、呪物崇拝(フェチシズム)を取り戻すことによって古代的な心(原始的心象・アニミズム)を取り戻させようとしているとしか思えない。
物質は全て生命を持つ。いや、そう言っては誤解を招く。こう言い換えよう。物質は全て霊魂(アニマ)を持つ。それゆえ、シュヴァンクマイエルはそのフェチシズムを遺憾なく発揮して、物質に霊魂(アニマ)を吹き込むあの、あの創造主と同じかりそめの「人形アニメ作家」の顔をしているのである、と。
『チェコアニメの夜2017』9月26日、27日ユジク阿佐ヶ谷にて
(ジゴクの季節にJUN爺誌す。2017年9月29日)
ただこの作品の中で、唯一見るべきものがあるとすれば、おそらくシュヴァンクマイエルの創作の過程といったものが、明かされていると推察できる場面である。
机の引き出しを開けると引き出し一杯に詰まった粘土!ゴミ箱から拾ってきた藁束があれば、ズタ袋一杯の鳥の羽!狐のマフラーの尻尾を強奪し、それはそれは肌さわりも感触も抜群の、世にも妙なる悦楽自慰マシーンを男は制作するのだ。
モニターに映った憧れの女性アナの口元をアップにしながら…。肉体を直接交わすだけでは、快楽を得られないひとびと。その熱情のあまり電子回路をハンダ付けし、モーターを取り付け、女性アナの白き両手を想定したマネキンの手をご丁寧にも4本も取り付け、指先には真っ赤なエナメルのマニキュアを塗り、モニターに口づけしながら、自動するフェルトや狐の尻尾の肌触りに震えおののくのだ。
どうだ、これは映像よりも文章で書き起こした方が、悦楽的に感じ入るものがあるではないか(笑)!エクリチュールの快楽!汝はエクリチュールのフェチなるや?
これは呪物崇拝のコメディなのだが、そこで笑い飛ばされるのは「人間」それも厳密に言うなら特殊な性癖を持った「男」・「女」なのだ。シュヴァンクマイエルと同じ性を持つ男は、その不能なまでのフェチシズムを快楽追求型に追い求めるのだが、その快楽は不可能性いや、不能性によって終わりなき旅となる。
女は?女のフェチもあるではないか。郵便配達人の女は、パンをくり抜き、ふっくらとした中身で小さな球を執拗に丸めあげる。夜、睡眠時にそれらの丸球を鼻から吸い込んで、耳に詰め、1日の疲れを癒すのだ(!)。
コウモリ傘でコウモリの翼を作った男は、隣室の女にマゾヒスチックに鞭で攻められては、藁が詰まった悦楽の涙を流す。
その不能なまでの快楽追求の旅は、異性たる性を対象としながら<究極の自慰>なのだ。究極の一人芝居としての自慰!マスターベーションをマスターせよ!
実際、共産主義体制だった時代に徹底的に無視され、理解されなかったシュヴァンクマイエルのアート、アニメ、人形劇はその冷酷な政治体制の中で、自慰行為と同然だったし、そう社会に目されていた。シュヴァンクマイエルは内面の自由、精神の自由を求めて徹底的に示威行為たるアート行為を貫いていた。むしろそこにしか、彼の自由はなかったであろう。
そして、翌日(27日)はヤン・シュヴァンクマイエルの短編特集だ。これは良かった。ヤン・シュヴァンクマイエルの面目躍如である。そうか、シュヴァンクマイエルは、ボクらがハイスクール時代を過ごしていた頃、共産主義国家から一切の制作費援助も受けられずに、これらのコマ撮り短編映画を作っていたのか!
確かにシュヴァンクマイエルの作品には、イデオロギーもプロパガンダも感じることができない。これじゃ、国家も制作助成金を出すわけがない。
1. 棺の家(1966年/10分)
2.ドン・ファン(1972年/33分)
3.対話の可能性(1982年/12分)
4.男のゲーム(1988年/15分)
5.闇・光・闇(1989年/7分)
6.セルフポートレート(1988年/2分) / 監督ヤン・シュヴァンクマイエル/イジー・バルタ/パヴェル・コウツキー
(評価:★★★★)
上映された短編6本の中でも、『闇・光・闇』が抜群に良かった。似た傾向の作品だが、『対話の可能性』も気持ちが悪くなるくらいいい(笑)!シュヴァンクマイエルの粘土成形の見事な技術が発揮されている。壊しては、成形し、粘土が溶け合っては再び個体の身体を取り戻す!まさしくアニメーションの命を吹き込むかのような原義が発揮される。物体(粘土)が生命を得たかのように動き出す。コマ撮りの技法によって!
しかし、ここで注目したいのは『ドン・ファン』の人形の素朴な様式美である。以前、展覧会で見たチェコ操り人形のような作品はこれだったのだろうか?
御存知だろうが、チェコは人形劇を伝統的に得意とし、また世界的にも評価されている。さらにはスラブ民族にはゴーレム伝説があるから、人形劇への偏愛は民族的なのかもしれない。
その伝統は、そのまま人形アニメ(コマ撮りアニメ)の世界へ繋がり、シュヴァンクマイエルのような国際的な人気を持つ作家が登場した。
かって共産主義国家に制作助成もされなかった上に、弾圧もされたらしいシュヴァンクマイエルはいまや国際的な名声を得て国家も無視できなくなった。いやむしろ外貨獲得ではかなりの貢献を国家にしている以上、文化大臣はもとより首相も無視できない存在となっているらしいのだ(上映後のトークによる)。
チェコの国賓級の外国要人がことごとく一番会いたがる最重要人物が、シュヴァンクマイエルだと言う。さもありなん。
ところで、シュヴァンクマイエルは現代を生きるシュールレアリストだと目されることが多い。
だが、国際シュールレアリズム運動が第四インターの衰退とともに消滅している以上、そのレッテルは本人にも迷惑だろう。ただ、彼のオブジェに対する偏執狂的な偏愛は、かってのシュールレアリストとの共通点が多いことは、認めよう。
だが、私にはシュヴァンクマイエルの作品世界は、物質に満ちたこの巨大な消費社会の中で、呪物崇拝(フェチシズム)を取り戻すことによって古代的な心(原始的心象・アニミズム)を取り戻させようとしているとしか思えない。
物質は全て生命を持つ。いや、そう言っては誤解を招く。こう言い換えよう。物質は全て霊魂(アニマ)を持つ。それゆえ、シュヴァンクマイエルはそのフェチシズムを遺憾なく発揮して、物質に霊魂(アニマ)を吹き込むあの、あの創造主と同じかりそめの「人形アニメ作家」の顔をしているのである、と。
『チェコアニメの夜2017』9月26日、27日ユジク阿佐ヶ谷にて
(ジゴクの季節にJUN爺誌す。2017年9月29日)