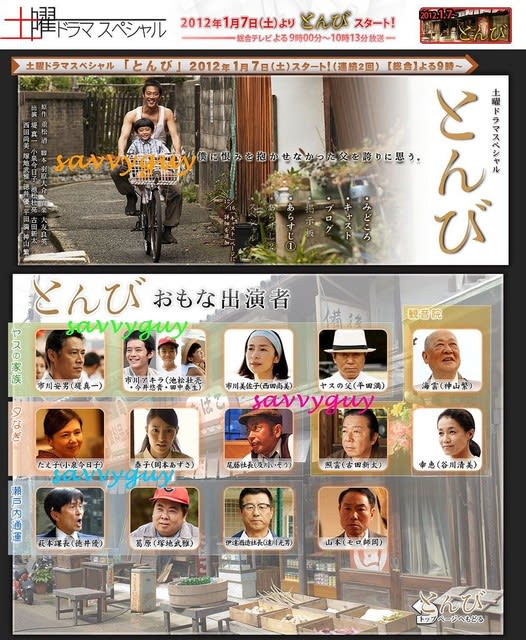12月1日(土):








昨日、念願の山田洋次監督の映画「学校」(1993)のBS放送があった。録画をして久しぶりに繰り返し観た。
中国残留孤児を母に持つ中国人青年(日本国籍?)、在日コリアンのオモニ、戦後の混乱期貧しく仮名文字すら学べなかった高齢の労働者、不登校の女の子とヒビのいった夫婦(その後離婚、家庭崩壊)、何らかの理由で学べず働きながら、あるいはぶらぶらしながら寄る辺なく学びに来ている若い男女、心身ともに少し弱くて普通の学校に通えなかった青年、みんなが自らの「居場所」がなく、誇りを持てなかった人たちである。それでも、前を向いて生きよう、前を向いていきたいと思った時に「学校に行きたい。学びたい。」と考えた。
競争ではなく、学力ではなく、みんながお互いの「学びたい」という思いを大切にし合いながら集い、寄り添いながら学ぶ場所、それが夜間中学だった。そして、夜間中学の存在意義をまさに体現した存在としての西田敏行、竹下景子をはじめとする先生たちがいる。誰がなんと言おうとここには「学びたい」という思いだけを大切に認め合うユートピアが存在している。
25年前の映画である。月並みな問いだが、「今の日本は当時よりも少しは良くなっただろうか。」。俺には、状況はかえってひどくなっている、としか思えない。何よりも本質的なことは、25年前には「世の中を少しでも良くしていこう。良くしていかねばならない。今はできていなくても、日本社会にいる人間はみんな人間としての尊厳を持てるように大切にされなければいけないのだ」という前向きな理念、志(こころざし)が生きていた。いつの時代も理想が実現することは難しいだろう。しかし、この前向きな理念、志(こころざし)さえ大切にされていれば、社会に希望が持てる。
今の日本は、あの頭の悪いどぶの目をした男を担ぎ上げて、自分たちの利益やゆがんだ主義主張を押し通そうという少数の勢力が日本社会を乗っ取る腐敗した構造ができ上り、かつての未来への希望ある展望は失われている。今のままではどぶの目をした男が政権の座から墜落しても、この男を利用できてきた構造自体は残っているので、別の神輿が担ぎ出されて目先を変えても結局同じ状態が続くだろう。
再び手を変え品を変え「パンとサーカス」が供されて、少なくとも2025年まで「日本人(とは何か?)」はバカ踊りを続けるのだ。本当に大切な、そして難しい「人間存在の多様性を認め合い尊重されなければならない」「一人一人の個人が人間として尊重されなければならない」という課題は置き去りにされ、政府がきちんと向き合うことはない。それらは、ますます少数の限られた個人のボランティアの取り組みに片付けられて、問題は深刻化し後戻りできないところに行きつくしかない。構造的差別、構造的貧困、「自分さえ良ければよい」「今さえやり過ごせればいい」という刹那主義の蔓延する中で、目の前で苦しみ泣いている人間の存在が見えなくなる。すべては<自己責任>、弱い者が自分より弱い者を探し出して安堵しながら、さらに弱い者いじめをする。強者は高みの見物をして、自分の力の固定化、世襲化にのみ力を注ぐ。
25年前の映画なのに、ここで提示された問題を日本社会は何ひとつ自らの意志と努力で解決できなかった。
すべては弱者による自己解決と老齢化による消滅を待つのみだった。それでも、当時は「それではいけない」という前向きな理念と志(こころざし)があったが、今は意図的に(!?)無関心がはびこらされてそれらすら忘れ去られている。
日本社会の抱える問題は、どぶの目をした虚言癖の男と口と心のねじ曲がったゲスが政権に付いたこの6年間で取り返しがつかないほど、それこそ不可逆的に深刻化してきた。古くからの弱者、マイノリティの取り組まねばならない問題は、ほとんど置き去りにされたままで、新たに取り組むべき弱者、マイノリティの問題が、今後急速に加速度をもって雪だるま式に増えていく。
衆議院を何ら審議しないまま強行採決した外国人労働者受け入れの法案は、日本の将来にとって恐るべき禍根を残すだろう。
事実上の移民となる外国人労働者の数が一定数を越えた段階で、今の日本社会の形は大きく決壊して無残なことになるだろう。何より、外国人労働者は日本のこれまでの価値観とは違う、例えばイスラム教など独自の強固な価値観(ドグマ)を持つ人々であり、少子化の日本社会にあって急速に多くの子供を産み育て始めるだろう。しかし、忘れてならないのは彼らは「人権を尊重されるべき人間なのだ」ということ、「彼らは日本で子供をもうけ、その子供たちは
<日本生まれの人間>であり、急速に増加していく」ということ。簡単に、ルールに従って帰ってもらうべき存在ではないのだ。
人間を<道具>のように付け外し自由と考える国家や社会は恐ろしい世界だ。
また、急速に増える外国人労働者やその子ども(<日本生まれの人間>)は、単に弱い存在ではない強固なドグマを持ち、これまでの日本社会や民主主義の手続きとは相容れない存在の人々もいるだろう。住民間で様々な問題、軋轢が生じるだろう。
法治主義を掲げても、“差別に対する絶望”を前提にした若者の<暴力>、<自爆>を防ぐ手立てはあるのか。イスラムの教えに対応する社会の準備はできているのか。
目先の労働者不足を解消するために、女性や障碍者、社会的弱者の人権、社会参加、低賃金労働者の待遇改善などの問題を置き去りにして、受け入れを急いだ外国人労働者の労働条件が人間らしいまともさを保障されたものとなるとは思えない。今後ますます矛盾は広がり深刻化していくことだろう。人間はすべて、賢さ以外に弱さ、愚かさ、過激さなども抱えた存在だ。いつまでも不当な差別や暴力に耐えるだけの存在ではない。人間としての存在を主張し、闘いを挑み、時に暴力、犯罪にも手を染めることもありうる。そんな時、「予想もしていなかった」として国家権力の暴力で対応するのか。<日本で生まれた外国人>の若者たちに、警察は銃口を向けるのか。あり得ない。
いくら十分に起こりうる事態を想定しておいても足りることはないだろう。それなのに内容スカスカの目先だけしか見えてない外国人労働者受け入れ法案を現政権が強行採決するのを「実行力がある」「頼もしい」とする一定数の国民がいることが空恐ろしくなる。将来必ず、日本人(って何?)、日本社会は天罰を受ける。その責めはすべて現在の我々にある。
子どもたちにひどい矛盾と苦しみを付けとして残していくことに心から申し訳ないと思う。
若い時の俺は少なくとも「世の中は、いや日本社会は、少しずつであってもよくなる方向に進んでいくのだ」と信じて疑わなかった。今、それが大きな誤りだったと言わざるを得ない。25年前の弱者・マイノリティの人権問題が、愚劣な政治屋の不作為、ポピュリズムに迎合するマスコミの無責任、グローバルのはずが内向化して無関心・無行動の日本人(って何?)たちのもとで、何も解決しないで、むしろ後退してきた。弱者・マイノリティの差別・人権問題は新たな装いに改めて拡大再生産されていく。
息を吐くように政治屋や官僚が嘘をつき、見せしめの弱い者いじめを平気でする。当然のように<人権>が軽視され、踏みにじられる。それを多くの子供や若者が見つめている。絶対、教育によくない!。今後、悪い影響が必ず出てくる。沖縄、福島、地震・台風の避難民、自分さへ関わらなければよいと思っていたことが、いつの間にか大変な思いをして納めている血税は、どぶに捨てられ、数千億、兆を超える莫大な金がアメリカからの武器購入に回されている。もう少しだけでも
従米的でない自立的安全保障政策を模索し防衛費をしぼったお金を社会保障費に回せれば、日本の社会は劇的に変わるはずなのだが、一体日本の政策はどこを見て行われているのか。
今の日本は、アメリカの最大の植民地だと言っても過言ではないだろう。
今の時代「国益を犯す」というのが、絶対的なきめ言葉になっているそうだ。しかし、
「国益」とは何か。誰の利益が、国の利益なのか。「国民」の利益か、全くそういう風に見えないのはどうしてだ。そもそも「国家」とは何のために存在するのか。そこに住む人々の福利、社会保障を目的とするものではないのか。こんなことを考える俺は日本国籍を持っているが「非国民」なのか。今時「日本人」って何なのか。由緒正しい「日本人」というのがいたとして、そいつらだけが「日本人」なのか。そいつらが「日本(って何?)」のことを本当に思ってくれているのか。そんな風には全く思えないのはどうしてだ!
そろそろ、朝起き後の頭のさえた状態が鈍ってきた。昨夜、録画撮りしたかった山田洋次の映画「学校」(1993)を久しぶりに繰り返し観て感じた由無しごとを、特に推敲もせず徒然なるままに書き連ねてみただけなので、乱文お許しいただきたい。また、手を入れられたら入れます。
結局、今の日本は25年前よりもよくなっていないどころか、前向きな理念、志(こころざし)が失われた分だけ卑しく悪くなっている。何よりも未来に希望を持てなくなっている。そして、これはファシズムの起こるお膳立てができ上ったということだ。
181215追加:
政治がこれほど平気で簡単に悪用されるものだとは知らなかった。
戦後日本は間違いなく、悪い方で“新たなステージ(段階)”に突入した。すでに取り返しのつかないことになっているが、それでも一刻も早く新たな対抗運動を創り上げなければいけない。