7月30日(土) 天気:曇り 十一時 雨 後 晴れ 室温:31.8℃
皆さん 今週は いい一週間でしたか? 私には つらく しんどい 一週間でした。 風邪は 引かないと思っ
ていた私が 風邪を ひいていしまい・・・・・
通年性の鼻炎との相乗作用で のどは 痛いし 咳は 出るし タンは 詰まるし
38.5度くらいの微熱が 続き 体がふらつくし
食後の薬を飲むため 無理に お茶漬けを流し込み・・・
薬の副作用なのか 眠気はするし 口の中に 苦みが残り 味がおかしく 余計に食欲もなく
なにもすることができず ほとんど 死んだような一週間でした。
風邪は まだ 治りませんが 体のふらつきは収まったようなので 出かけてきました。 播州・清水寺です。
「はりまハイキング」で 紹介されています。 標高552.3mのどっしりとした山容と書いていますが この山
には 三角点はないし 地図を見ても 540mの等高線しかありません。 この本の著者は 一体 何を考え
ているのか理解できません。
この前の NHKの『新兵庫史を歩く』で 加東市を歩き 清水寺も 訪れていました。 また この前の地元
の『歴史教室』で 姫路周辺の古代寺院を 勉強したこともあるので それを 訪れるのもいいでしょう。
西国二十五番札所・播州清水寺は 「播磨六ヶ寺」のひとつで 法道仙人の開基と言われ この地は 水に
乏しく 法道仙人が 水神に祈ったところ 霊泉が湧出し それ故 清水寺 と名付けられたそうです。
9:27 出発。 姫路バイパスは 事故の後遺症か 思うようには 走れません。 花田ICから播但道に廻り
福崎ICから中国道に 入る辺りから 雨が降ってきました。 10:18 滝野社ICを降りて 国道372号線に
廻ります。 上鴨川の信号で右折して 県道311号線で東へ廻ります。 体調万全なれば 「新兵庫史・・」
の鴨川の郷や 住吉神社へ寄りたいのですが きょうは 清水寺だけ にしましょう。


清水寺の登山口に料金所があり 拝観料500円を支払います。 駐車料金込みです。 坂道を 2.8km
登ると 仁王門前の広い駐車場に出ます。 10:46 駐車。 滝野社ICから 20.9km、家から 78.3km。
観光バスもあり 結構な人です。 雨は上がったようです。
仁王門は 旧参道にあったものが 壊れ 昭和54年末 再建。 金剛力士像は 大正10年 奈良仏師の菅
原大三郎の作。 すっきりした感じには 見えますが 悪人を通さないという 力強さ、迫力が ありません。



雨に濡れた参道を歩いて 大講堂へ向かいます。 道の脇には 青いアジサイが多くあります。 手水舎
の向かい側に 薬師堂があり 入口が開いているので 中へ入ると 小さい仏像が 祀ってありましたが
薬師如来像でしょうか? 十二支の酉の彫像は 私の干支ですが 東京芸大 薮内佐斗司教授作で 「十
二神将」 のひとつです。



大講堂の前にある大きな燈籠に彫ってあるのは 四天王? 大講堂の前を 宝篋印塔を見ながら
旧参道へ降り 白壁の右の門を潜ると 庭園になっています。 ナツツバキもありますが 花は 見
当たりません・・・ 下には 苔のような緑の絨毯で 申し分ないのですが・・・



奥は 本坊です。 本坊から階段を上がり 大講堂の回廊へ出ることもできます。 このように 山の
斜面を利用し 平坦地を設け 仏殿を直線的に並べる伽藍配置は 「禅宗式」 というのでしょうか?
ここ清水寺には 国宝級の建物は ありませんが 根本中堂、大講堂、鐘楼、本坊が 登録文化財。
どこにあったのか 分かりませんが 阿弥陀堂は 源頼朝により建立されたそうです・・・。






大講堂に戻り 靴を脱いで お参りしました。 周囲の回廊は 展望台ですが きょうは 明石大橋を見る
ことはできません。 大講堂は 十一面千手観音菩薩を本尊に 神亀二年(725) 聖武天皇が 行基菩薩
に勅願し 建立したもの。 御詠歌 : あわれみや あまねき門の 品々に なにをか波の ここに清水



大講堂の上に 道標がありました。 こんな場所にあってもと 思いますが・・。 右 なつやま? 左
ふ○あい? 階段を上がると 右が 地蔵堂で 本尊は 地蔵菩薩。 常行堂の跡地に 昭和12年創建。
この地にあった常行堂は 後白河法皇の創建と伝えられる。
地蔵堂の左上に 鐘楼があります。 大正2年消失、同9年再建。 釣鐘は山上にて 大正8年に鋳造
された。 武田五一博士の意匠で 銘は 吉田源応天台座主。 この鐘の音は 播磨、丹波、摂津にひび
きわたり ”開運の鐘”として 親しまれているそうです。 釣鐘は 高い位置にあり 写真を撮るのは 難し
い・・。 鐘は 自由に 撞くことができるようですが・・・。



階段を上がると 根本中堂があります。 立派な建物ですが 肝心の木鼻や蟇股が見当たりません。
本尊は 十一面観世音菩薩で 脇士は 毘沙門天王と吉祥天女。 本尊は 法道仙人一刀三礼の秘仏。
創建は 推古天皇35年(627)で 推古天皇の勅願で 金堂として創建されましたが 大正二年の火
災により焼失。 同6年 武田五一博士の設計により 再建。



根本中堂の裏から 100mほど奥に ”滾浄水”(お陰の井戸)があります。 開山の法道仙人が 水神
に祈って湧出した霊泉で 清水寺と称せられる由緒の地。 この井戸を覗き込んで 自分の顔を写したら
「寿命が三年延びる」らしいので 私も少なくとも 後三年は 生きられるかも・・・。 かやぶき屋根で覆わ
れ 今でも大切に守られています。
一番高い所(標高540m?)に 多宝塔跡がありますが その前に 下にある宝篋印塔へ寄りました。
昭和九年 護摩堂跡に 般若心経の写経を 3333巻納め 建立されたそうです。 丸いドーム型の台上
に 宝篋印塔が 立っていますが あまり いい雰囲気ではありません。 やはり ひっそりとある方が・・。



最後に 多宝塔跡へ。 多くの礎石があります。 現在 再建予定の多宝塔(大塔)は 平清盛の母とい
われる祇園女御により建立されたと言われている。 高い位置にありますが 見晴らしは よくありません。
多宝塔跡から 右へ降りて 参道へ戻り 駐車場へ戻りました。 12:10 車に戻りましたが 何台か
あった車は なくなっていました。 清水寺に お参りする人は 大講堂を往復するだけ なのでしょうか?


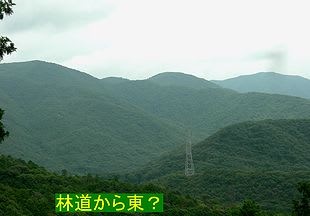
すぐ帰路につき 来た道を戻ります。 国道372号線の戻り 滝野社ICから中国道に入り 加西
SAへ寄り ラーメンを食べましたが すごい人でした。
播但道、姫路バイパスを走り 13:57 家に帰ってきました。
本日の走行距離は 往路:78.3km 復路:78.5kmで 計:156.8kmでした。
次は 神積寺と八葉寺ですが・・・・。
。。。。。。。。。。。





 。。。。。。。。
。。。。。。。。
皆さん 今週は いい一週間でしたか? 私には つらく しんどい 一週間でした。 風邪は 引かないと思っ
ていた私が 風邪を ひいていしまい・・・・・
通年性の鼻炎との相乗作用で のどは 痛いし 咳は 出るし タンは 詰まるし
38.5度くらいの微熱が 続き 体がふらつくし
食後の薬を飲むため 無理に お茶漬けを流し込み・・・
薬の副作用なのか 眠気はするし 口の中に 苦みが残り 味がおかしく 余計に食欲もなく
なにもすることができず ほとんど 死んだような一週間でした。
風邪は まだ 治りませんが 体のふらつきは収まったようなので 出かけてきました。 播州・清水寺です。
「はりまハイキング」で 紹介されています。 標高552.3mのどっしりとした山容と書いていますが この山
には 三角点はないし 地図を見ても 540mの等高線しかありません。 この本の著者は 一体 何を考え
ているのか理解できません。
この前の NHKの『新兵庫史を歩く』で 加東市を歩き 清水寺も 訪れていました。 また この前の地元
の『歴史教室』で 姫路周辺の古代寺院を 勉強したこともあるので それを 訪れるのもいいでしょう。
西国二十五番札所・播州清水寺は 「播磨六ヶ寺」のひとつで 法道仙人の開基と言われ この地は 水に
乏しく 法道仙人が 水神に祈ったところ 霊泉が湧出し それ故 清水寺 と名付けられたそうです。
9:27 出発。 姫路バイパスは 事故の後遺症か 思うようには 走れません。 花田ICから播但道に廻り
福崎ICから中国道に 入る辺りから 雨が降ってきました。 10:18 滝野社ICを降りて 国道372号線に
廻ります。 上鴨川の信号で右折して 県道311号線で東へ廻ります。 体調万全なれば 「新兵庫史・・」
の鴨川の郷や 住吉神社へ寄りたいのですが きょうは 清水寺だけ にしましょう。


清水寺の登山口に料金所があり 拝観料500円を支払います。 駐車料金込みです。 坂道を 2.8km
登ると 仁王門前の広い駐車場に出ます。 10:46 駐車。 滝野社ICから 20.9km、家から 78.3km。
観光バスもあり 結構な人です。 雨は上がったようです。
仁王門は 旧参道にあったものが 壊れ 昭和54年末 再建。 金剛力士像は 大正10年 奈良仏師の菅
原大三郎の作。 すっきりした感じには 見えますが 悪人を通さないという 力強さ、迫力が ありません。



雨に濡れた参道を歩いて 大講堂へ向かいます。 道の脇には 青いアジサイが多くあります。 手水舎
の向かい側に 薬師堂があり 入口が開いているので 中へ入ると 小さい仏像が 祀ってありましたが
薬師如来像でしょうか? 十二支の酉の彫像は 私の干支ですが 東京芸大 薮内佐斗司教授作で 「十
二神将」 のひとつです。



大講堂の前にある大きな燈籠に彫ってあるのは 四天王? 大講堂の前を 宝篋印塔を見ながら
旧参道へ降り 白壁の右の門を潜ると 庭園になっています。 ナツツバキもありますが 花は 見
当たりません・・・ 下には 苔のような緑の絨毯で 申し分ないのですが・・・



奥は 本坊です。 本坊から階段を上がり 大講堂の回廊へ出ることもできます。 このように 山の
斜面を利用し 平坦地を設け 仏殿を直線的に並べる伽藍配置は 「禅宗式」 というのでしょうか?
ここ清水寺には 国宝級の建物は ありませんが 根本中堂、大講堂、鐘楼、本坊が 登録文化財。
どこにあったのか 分かりませんが 阿弥陀堂は 源頼朝により建立されたそうです・・・。






大講堂に戻り 靴を脱いで お参りしました。 周囲の回廊は 展望台ですが きょうは 明石大橋を見る
ことはできません。 大講堂は 十一面千手観音菩薩を本尊に 神亀二年(725) 聖武天皇が 行基菩薩
に勅願し 建立したもの。 御詠歌 : あわれみや あまねき門の 品々に なにをか波の ここに清水



大講堂の上に 道標がありました。 こんな場所にあってもと 思いますが・・。 右 なつやま? 左
ふ○あい? 階段を上がると 右が 地蔵堂で 本尊は 地蔵菩薩。 常行堂の跡地に 昭和12年創建。
この地にあった常行堂は 後白河法皇の創建と伝えられる。
地蔵堂の左上に 鐘楼があります。 大正2年消失、同9年再建。 釣鐘は山上にて 大正8年に鋳造
された。 武田五一博士の意匠で 銘は 吉田源応天台座主。 この鐘の音は 播磨、丹波、摂津にひび
きわたり ”開運の鐘”として 親しまれているそうです。 釣鐘は 高い位置にあり 写真を撮るのは 難し
い・・。 鐘は 自由に 撞くことができるようですが・・・。



階段を上がると 根本中堂があります。 立派な建物ですが 肝心の木鼻や蟇股が見当たりません。
本尊は 十一面観世音菩薩で 脇士は 毘沙門天王と吉祥天女。 本尊は 法道仙人一刀三礼の秘仏。
創建は 推古天皇35年(627)で 推古天皇の勅願で 金堂として創建されましたが 大正二年の火
災により焼失。 同6年 武田五一博士の設計により 再建。



根本中堂の裏から 100mほど奥に ”滾浄水”(お陰の井戸)があります。 開山の法道仙人が 水神
に祈って湧出した霊泉で 清水寺と称せられる由緒の地。 この井戸を覗き込んで 自分の顔を写したら
「寿命が三年延びる」らしいので 私も少なくとも 後三年は 生きられるかも・・・。 かやぶき屋根で覆わ
れ 今でも大切に守られています。
一番高い所(標高540m?)に 多宝塔跡がありますが その前に 下にある宝篋印塔へ寄りました。
昭和九年 護摩堂跡に 般若心経の写経を 3333巻納め 建立されたそうです。 丸いドーム型の台上
に 宝篋印塔が 立っていますが あまり いい雰囲気ではありません。 やはり ひっそりとある方が・・。



最後に 多宝塔跡へ。 多くの礎石があります。 現在 再建予定の多宝塔(大塔)は 平清盛の母とい
われる祇園女御により建立されたと言われている。 高い位置にありますが 見晴らしは よくありません。
多宝塔跡から 右へ降りて 参道へ戻り 駐車場へ戻りました。 12:10 車に戻りましたが 何台か
あった車は なくなっていました。 清水寺に お参りする人は 大講堂を往復するだけ なのでしょうか?


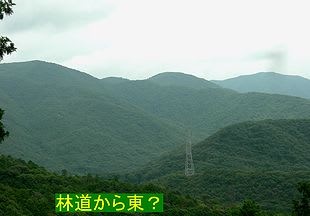
すぐ帰路につき 来た道を戻ります。 国道372号線の戻り 滝野社ICから中国道に入り 加西
SAへ寄り ラーメンを食べましたが すごい人でした。
播但道、姫路バイパスを走り 13:57 家に帰ってきました。
本日の走行距離は 往路:78.3km 復路:78.5kmで 計:156.8kmでした。
次は 神積寺と八葉寺ですが・・・・。
。。。。。。。。。。。






 。。。。。。。。
。。。。。。。。













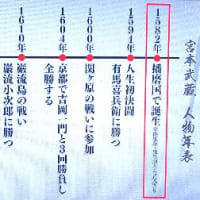











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます