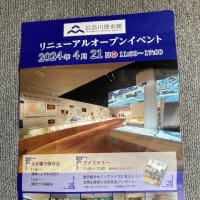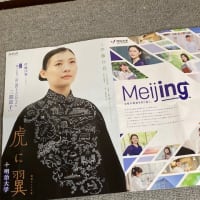井の中の蛙状態の日本で、築地市場時代に付き合っていた日本食品輸出業者から海外の新聞情報とは違った話を聞いていた。特にチョット前の日本は日本の農産物の価格競争力が無いと諦め、国際規格競争に遅れた。水産日本は魚は冷凍ものは一段下と見られているように築地でも豊洲でも花形の売り場ではない。やはり大間のマグロのように生が一番でセリ場も絵になる。冷凍とか養殖は量が多く、天候異変時以外は目だたない。青果も同様で冷凍野菜は加工部でひっそりと売られている。
水産物の国際取引規格はEUが先行していて、魚食はアメリカは遅れている。クジラがあれほど騒がれたのはアメリカ西部で石油が発見されたためでクジラ漁船が衰退していて反捕鯨を声高に主張出来ていた。幕末の日本へやってきたのは鯨油のためだったことを忘れている。ハワイ島にはクジラの博物館があり、オアフ島の博物館でクジラの展示扱いからハワイにおけるクジラ産業の重要性を知った。
今でこそ日本の食品を輸出することを日本の政治家が考えているが為替が1ドル80円になれば輸出も危ない。水産日本の缶詰が衰退したのは人件費と為替である。農産物の形の整っていないものを缶詰にきれいに詰めるには若い女性の目と手先の器用さが必要となる。40年ほど前、タイでパイナップルの缶詰工場を見学していた時そのように感じた。