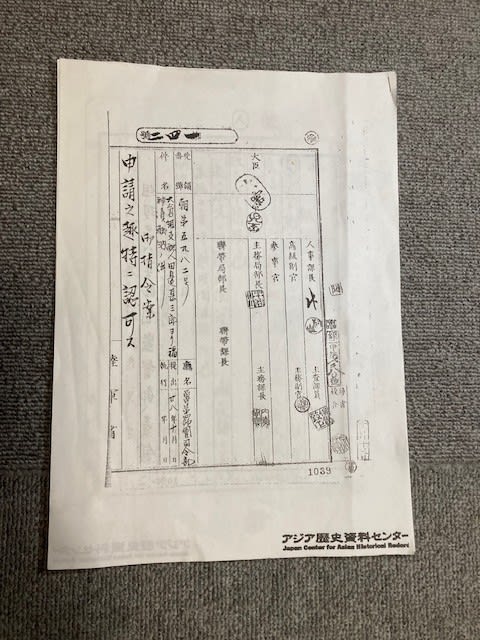福神漬の命名の成立時期を文献で調べることを気にしていた。東京柳巷新誌という本がネット検索で出てきた。調べると著者は服部撫松(誠一郎)だった。この人は幕末から明治の廃藩置県まで福島県二本松の公用人(県における中央の情勢収集)で待合での接待要員だった。この接待で明治初期の花柳界隈を漢文戯作風の文章で東京新繁盛記を出版し、財を成した。そして明治10年頃、銀座8丁目の所で雑誌社公益問答新聞社を経営した。そこで記者として論説を担っていたのが佐藤清・花香恭次郎でこの二人は福島で自由民権運動で活躍した。今の日本と違って、言論規制の緩やかな時代で諸外国から日本に流入してきた考え方を日本人に馴染むような回答で、多くの読者は一種の自由という文明の娯楽のようだった。今の感覚だと読者の質問に回答するようなものと言うが国会図書館で探さないとまだ読めない。自分が数冊ほど駒場の 日本近代文学館で読んだ。
明治10年の創刊だったが社主の服部と花香の意見が西南戦争で衝突し、花香が退社し、遅れて佐藤が退社した。日本近代文学館所蔵の雑誌は編集者がまだ佐藤でいつ退社したのだろうか。さらにこの雑誌を寄贈した人は誰なのだろうか気になる。公益問答新聞の寿命は短かった。明治9年.6.月15日「広益問答新聞」創刊、明治12年9月( 第376号)終刊 週2回ほどの発行なのだろうか。廃刊理由は不明だが徐々に明治政府が言論統制を強化している時期だった。親旧幕の人が多い、江戸東京の読者を捕まえることが出来なかったのだろうか。現物を読んでみたい。
この雰囲気は今の野球場の応援団演説に気分は似ている。ライバルとなった明治政府をいらだてるようなヤジ演説はそれを阻止する警察官と揉める様子が見える。今の時代と違って、音声の記録がないため、文献では演説の題目しか残っていないので、文章として紙媒体に残るのは今でも参考になる。
明治10年の創刊だったが社主の服部と花香の意見が西南戦争で衝突し、花香が退社し、遅れて佐藤が退社した。日本近代文学館所蔵の雑誌は編集者がまだ佐藤でいつ退社したのだろうか。さらにこの雑誌を寄贈した人は誰なのだろうか気になる。公益問答新聞の寿命は短かった。明治9年.6.月15日「広益問答新聞」創刊、明治12年9月( 第376号)終刊 週2回ほどの発行なのだろうか。廃刊理由は不明だが徐々に明治政府が言論統制を強化している時期だった。親旧幕の人が多い、江戸東京の読者を捕まえることが出来なかったのだろうか。現物を読んでみたい。
この雰囲気は今の野球場の応援団演説に気分は似ている。ライバルとなった明治政府をいらだてるようなヤジ演説はそれを阻止する警察官と揉める様子が見える。今の時代と違って、音声の記録がないため、文献では演説の題目しか残っていないので、文章として紙媒体に残るのは今でも参考になる。