雫石鉄也の
とつぜんブログ
ハイカラ神戸幻視行 紀行篇 夢の名残り

西秋生 神戸新聞総合出版センター
神戸は3度大きな災厄にあっている。1938年の阪神大水害。1945年の神戸大空襲。そして1995年の阪神大震災。神戸は大きな災厄に見舞われるたびに変貌をとげてきた。
さすがに大震災以前の神戸は知っているが、もう20年以上たっている。忘れていることが多い。神戸の街を歩いていても、あれ、ここは地震の前には何があったのだろうと、首を傾けることが多い。それが、戦前、大空襲以前となると小生の親の世代に聞かないと判らない。その親たちも最近は認知症が進んでよく覚えてない。となると、戦前とか昭和初期、大正の神戸となると、小生たちにとってファンタジーの世界といっていいかも。
神戸。ハイカラモダンという枕詞がもっとも似つかわしい街。著者西も小生(雫石)も神戸人だ。西は神戸で生まれ神戸で育ち神戸で亡くなった。小生は生まれは西宮だが育ちは神戸で、50年以上神戸に住んでいる。
人それぞれ自分の生まれ育った街には愛着を持っているが、神戸人はそれが特に強い。それは神戸が美しいから。あたかも美人の妻を持った男が、妻を誇らしく思うのに似ている。
正直、震災前の神戸と、20年たった今の神戸は違う街といっていい。例えばJR新長田駅前、JR六甲道駅前、両方とも特に震災の被害がひどかった地域である。震災復興再開発とやらで、すっかり新しくなったが、リンク先の写真を見てもらえれば判ると思うが、全国どこにでもある駅前広場である。でも、たんねんに歩き、子細に見て回れば震災前の神戸が残っている。
20年前の地震でこうである。それが70年前の戦前大正時代となると「現代」に完全に埋もれている。でも、まだまだ神戸の街には、こういう昔の「ハイカラ神戸」の面影が残っている。
著者は、その「ハイカラ神戸」を垣間見ることのできる「のぞき窓」を歩いて探し出し、その窓から「ハイカラ神戸」を見せてくれるのだ。それはカタカタと動く幻燈というか、のぞきからくりである。
幻想小説の優れた書き手でもある著者は、小生たちからすれば、幻想の神戸を幻視させてくれるのである。本書は幻想の都ハイカラ神戸を描写した著者西秋生の優れた幻想小説ともいえる。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
サピエンス全史
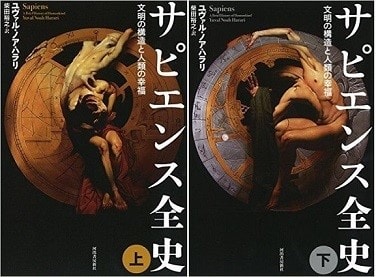
ユヴァル・ノア・ハラリ 柴田裕之訳 河出書房新社
ホモ・サピエンスのきみが、同じような体格のネアンデルタール人と1対1の素手のケンカをやれば100%きみは負ける。きみが格闘技の達人であっても負けるだろう。きみでなくとも、アレサンドル・カレリンでも木村政彦でもたぶん負けるだろう。ところが、きみが100人ともだちを集めて、100人のネアンデルタール人とケンカすれば、100%きみが勝つ。
原始人にもいろいろあった。10万年前、ホモ・サピエンス、ホモ・ネアンデルタールレンシス、ホモ・エレクトスなど。ホモ・サピエンスだけが生き残り、他のホモ属はみんな絶滅してしまった。だからきみもわたしもここにいるわけだ。
ホモ・サピエンスたるきみやわたしはなぜここにいるのか。ホモ・サピエンスはなぜ他のホモ属を出し抜き、あまつさえ全生命のトップにまで上り詰めたか。
7万年前、ホモ・サピエンスの脳の中で大きな変化が起こった。だから100対100のケンカで体力で勝るネアンデルタールに勝てるのだ。
三つの「革命」がホモ・サピエンスに「文明」をもたらし、この地球の支配者たらしめているのだ。「認知革命」「農業革命」そして「産業革命」
ホモ・サピエンスはなぜこれらの「革命」を成し遂げられたのか。「虚構を信じる力」があったからだ。例えば「貨幣」あんなものは、ただの貝殻であり、石ころである。現代でもただの金属片で紙切れだ。これらのモノが価値あるものとの「虚構」を信じることができるから、今の経済は回っている。
上手いたとえ話を使いながら展開する論はわかりやすく、知的興奮を誘う。ホモ・サピエンスのはるか太古から未来まで、リニアに語られるサピエンス史は長編SFを読むがごとき面白さである。
コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )
SFマガジン2017年2月号
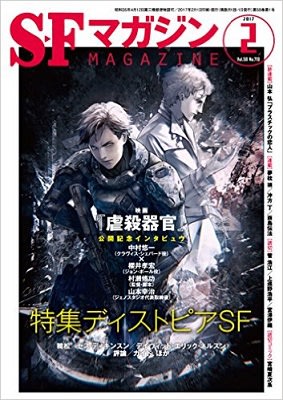
SFマガジン2017年2月号 №719 早川書房
雫石鉄也ひとり人気カウンター
1位 博物館惑星2・ルーキー 第一話 黒い四角形 菅浩江
2位 セキュリティ・チェック 韓松 幹遥子訳
3位 力の経済学 セス・ディキンスン 金子浩訳
4位 新入りは定時に帰れない デイヴィッド・エリック・ネルスン 鈴木潤訳
5位 裏世界ピクニック ステーション・フェブラリー 宮澤伊織
6位 交換人間は平静を欠く(前篇) 上遠野浩平
連載
プラスチックの恋人(新連載) 山本弘
小角の城(第42回) 夢枕獏
マルドゥック・アノニマス(第13回) 冲方丁
幻視百景(第6回) 酉島伝法
近代日本奇想小説史(大正・昭和篇)(第29回) 横田順彌
SFのある文学誌(第50回)長山靖生
アニメもんのSF散歩(第14回) 藤津亮太
現代日本演劇のSF的諸相(第23回) 山崎健太
にゅうもん!西田藍の海外SF再入門 特別篇 西田藍
オズの国の一駅手前―第74回世界SF大会ミダメリコンⅡ日記 巽孝之
人間廃業宣言 特別編 第49回シチェス・ファンタ レポート 友成純一
ディストピア特集である。久しぶりにSF専門誌らしい特集を企画した。それは評価してもいいだろう。ディストピアSFなるモノの解説。ディストピアSFブックガイド、関連エッセイなど、特集企画としておさえるべき所はちゃんとおさえてある。
で、それはいいだけど、また伊藤計劃がらみの企画。「虐殺器官」がアニメ映画化。今回の特集ディストピア企画もそれにちなんだもの。しかし、早川もいいかげん伊藤計劃を成仏させてやれよ。もう亡くなってから7年もたっているんだぞ。「虐殺器官」も「ハーモニー」も小生は読んだ。確かに後世に残すべき傑作だ。それで早川もじゅうぶんうるおっただろう。しかし、こうしょっちゅう伊藤計劃ネタをやると、とことんまで絞りつくすという感じで感じは良くない。こら早川いいかげんにしろ。
菅浩江が「博物館惑星」の新作を始めた。喜ばしい。前作は傑作だった。今回は学芸員ではなく博物館の警備員が主人公。どういう展開になるか楽しみ。小生が冗談でSFマガジン2015年3月号(SFマガジンにそんな号はない)の紹介をやったとき、ネタで新連作シリーズ開幕.「新・博物館惑星」と記したが、それが実現するとはうれしいかぎり。少し前に掲載していた「誰に見しょとて」は小生にはもひとつピンとこなかったので、今回は期待しておるぞスガちゃん。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
2016年に読んだ本ベスト5
小生の読書の時間は次の四つ。まず、朝。小生の朝は早い。きっちり4時には目を覚ます。ブログをざっと見て、朝食まで朝の読書にかかる。そして電車の中も大切な読書の時間だ。面白い本だと乗り過ごす時がある。
会社に着く。人より30分は早く着く。CEタンクの点検とバルブ開放のあと始業時間まで少し間がある。この時も読書の時間。そして1日の最後、寝る前。しかし、寝る前の読書は数ページ読んだだけで寝てしまう。さて、昨年読んだ本のベスト5は次の5冊だ。
1位 コロンビア・ゼロ 谷甲州 早川書房
久しぶりの航空宇宙軍である。現場SFの第一人者、甲州の真骨頂。戦争を始める止めるは政治家の決めること。われわれはなすべき任務を果たすだけ。
2位 戦場のコックたち 深緑野分 東京創元社
第2次世界大戦ヨーロッパ戦線のコック兵たち。出色の戦争小説であり、青春小説で、お仕事小説で、そして反戦小説でもある。
3位 シャンタラム グレゴリ-・デイヴィッド・ロバーツ 田口俊樹訳 新潮社
2720円のインド旅行。ただし観光旅行ではない。インドの裏をたっぷりと見せてくれる。
4位 桜花忍法帳 山田正紀 講談社タイガ
かの甲賀忍法帖の続編。風太郎の衣鉢継ぐのは正紀で決まり。読み進むにしたがってだんだん風呂敷がでかくなる。
5位 神樂坂隧道 西秋生 西秋生作品集刊行委員会
出色の短編幻想小説集。あの筒井康隆をして「完璧」といわしめた「マネキン」も収録。かえすがえすも早世が惜しまれる。
会社に着く。人より30分は早く着く。CEタンクの点検とバルブ開放のあと始業時間まで少し間がある。この時も読書の時間。そして1日の最後、寝る前。しかし、寝る前の読書は数ページ読んだだけで寝てしまう。さて、昨年読んだ本のベスト5は次の5冊だ。
1位 コロンビア・ゼロ 谷甲州 早川書房
久しぶりの航空宇宙軍である。現場SFの第一人者、甲州の真骨頂。戦争を始める止めるは政治家の決めること。われわれはなすべき任務を果たすだけ。
2位 戦場のコックたち 深緑野分 東京創元社
第2次世界大戦ヨーロッパ戦線のコック兵たち。出色の戦争小説であり、青春小説で、お仕事小説で、そして反戦小説でもある。
3位 シャンタラム グレゴリ-・デイヴィッド・ロバーツ 田口俊樹訳 新潮社
2720円のインド旅行。ただし観光旅行ではない。インドの裏をたっぷりと見せてくれる。
4位 桜花忍法帳 山田正紀 講談社タイガ
かの甲賀忍法帖の続編。風太郎の衣鉢継ぐのは正紀で決まり。読み進むにしたがってだんだん風呂敷がでかくなる。
5位 神樂坂隧道 西秋生 西秋生作品集刊行委員会
出色の短編幻想小説集。あの筒井康隆をして「完璧」といわしめた「マネキン」も収録。かえすがえすも早世が惜しまれる。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
獄門島

横溝正史 角川書店
小生は大藪春彦のファンである。日本のアクション活劇小説のジェダイマスターである大藪。文壇の諸氏とは群れ集わず、一人、孤峰を形成しているが、大藪と仲の良い作家もいた。星新一とは仲が良かったそうだ。その大藪がいち読者として大ファンだったのが横溝正史だ。晩年、横溝正史賞の審査員を務めている。
その大藪いち推しの横溝作品が、この「獄門島」
と、いうわけで「獄門島」を読んだわけ。実は、小生、本格ミステリーはあまりなじみがなく、横溝正史を読んだのは初めて。野村さんごめんなさい。
SFファンである小生が初めて横溝正史を読んだ。横溝はたいへんにサービス精神にあふれた、優れたエンタティメント作家であることがよくわかった。
惨劇の舞台である獄門島とはいかなる島であるか。そこにはいかなる住民が住んでいるのか。そこによそ者の金田一耕助がなんの用で行くのか。そこへ行く船の中で、だれと会ったのか。冒頭で手際よく記述されている。登場人物の相関関係が少々複雑であるが、判りやすく書かれているので安心して読める。
ミスディレクションも伏線も過不足なく張られているので、意外感も味わえる。なるほど本格ミステリーとはこういうものか。SFファンの小生が読んでも楽しめた。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
コロンビア・ゼロ

谷甲州 早川書房
「航空宇宙軍史」22年ぶりの新刊である。さすが甲州、二昔以上待たせたかいがあった。なかなかけっこうな作品集に仕上がっている。作品集とはいいつつも、甲州の航空宇宙軍史は短編集ではない。彼がヒマラヤの山奥でSFを書き始めてから(いや、ひょっとすると大阪工大SF研の時代からかも)、現代に到るまで、ずっと書き続けている大長編と見たほうが正鵠を得ているだろう。たぶん、この大長編は甲州が死ぬまで書き続けていかれるのではないか。
甲州は小松左京の後継者とみなされ「日本沈没第2部」を書いているが、光瀬龍の後継者でもあるといってもいいのではないか。星群の会ホームページで「SFマガジン思い出帳」を連載している。いま、1970年代のSFマガジンを紹介しているのだが、ちょうど、いま、光瀬の「派遣軍還る」を連載中のところだ。これを読むと甲州と光瀬のよく似ていると思ったしだい。
地球、月といった太陽系の内側を勢力圏とする航空宇宙軍と、木星、土星圏の衛星群の外惑星連合とが衝突した第1次外惑星動乱から40年。航空宇宙軍側の勝利に終わったが、敗戦側の外惑星連合も捲土重来を期して、着々と軍備を整備していく。いずれ第2次外惑星動乱の勃発はさけられない。本書はその第1と第2次の外惑星動乱の間を描いたもの。
開戦直前ではあるが、戦争を回避しようという動きは書かれない。そいう政治向きの話はこのシリーズには出て来ない。甲州の作品には政治家は不向きだ。現場。甲州は徹底的に現場を描く作家なのだ。本書もそうである。軍人はたくさん出てくるが、将官クラスは出て来ない。尉官、佐官が甲州作品の登場人物である。
「航空宇宙軍史」これからも楽しみである。甲州より長生きしくなては。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
神樂坂隧道

西秋生 西秋生作品集刊行委員会
出色の短編幻想小説集である。昨年、早世した西秋生の初めての作品集。西は神戸を題材とした著作は「ハイカラ神戸幻視行」があるが、小説集が世に出たのは初めてだ。
西秋生はもともとはSFを出発点とした作家。大学のクラブはSF研究会だった。眉村卓がパーソナリティを務めた深夜ラジオ番組「チャチャヤング」の常連投稿者となり、その後、筒井康隆主宰の同人誌「NULL」に入会。同誌にショートショートを投稿、あの筒井さんをして「完璧」といわしめた。今まで、「知る人ぞ知る」的な作家だった西秋生の作品が、こうしてまとめて読めるわけだ。
内容は、西のエッセイと9編の短編小説。それに、眉村卓、高井信、かんべむさし、江坂遊、井上雅彦、森下一仁、堀晃、大町聡、西ゆかりの八氏の追悼エッセイ。あとがきは夫人の妹尾凛が書いている。
「1001の光の物語」12段の文章の光の点の集合体。一つ一つがハイカラモダン。タルホ的文章のルミナリエ。
「マネキン」兄貴は壊れたマネキン。筒井康隆が完璧といった作品。
「走る」バイクで走る。走り続ける。
「いたい」幻肢痛。姉さんは何を失ったのだ。
「星の飛ぶ村」村にUFO。村人は気にしない。それより神かくしの方が気にかかる。
「チャップリンの幽霊」実はチャップリンは神戸で死んだ。その神戸は新開地に新聚楽館ができる。西秋生ならではの摩訶不思議玄妙な架空歴史モノ。
「神樂坂隧道」神樂坂の隧道に招き入れられた主人公。隧道の中は妖しげな見世物小屋がある不思議な世界。旧かなづかひで書かれた傑作ホラー。
「翳りのそしてまぼろしの黄泉」大事件が続いている。夜見湖で見つかった不思議な二体の死体。それをネタに3人の作家が競作する。
「5:46」5:46とは1995年1月17日午前5時46分のこと。阪神大震災の瞬間を濃密に描写。
かえすがえすも西秋生の早すぎる死が惜しまれる。年とって年季を経た西がどんな素晴らしいモノを書いていたことか。
この本はオンデマンド出版。ご注文はこちらからどうぞ。
コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )
シャンタラム
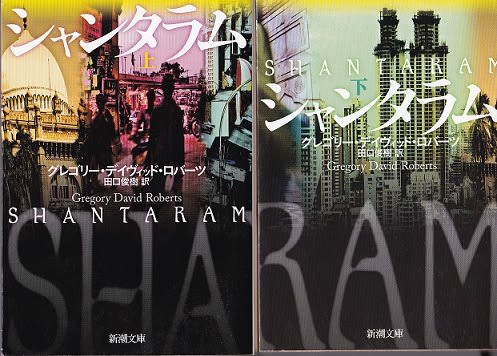
グレゴリー・デイヴィッド・ロバーツ 田口俊樹訳 新潮社
なにごとも表があれば裏がある。国もそうだ。大きな出版社のガイドブックを頼りに旅行すれば、その国の表しか見えない。しかし、どんな国にも裏がある。スラムのない国、犯罪者のいない国はないだろう。古くて大きな国は、特に奥深い裏がある。インド。世界で2番目に人口が多く、古い大国だ。この小説、裏から見たインドをたっぷりと見せてくれる。NHKの「世界ふれあい街あるき」なんかでは決して見せてくれないインドだ。
主人公リンは犯罪者で逃亡者。武装強盗で20年の懲役。オーストラリアの刑務所から脱獄。インドはボンベイ(いまはムンバイ)に流れ着く。パスポートが偽造なのでまともな所には行けない。
空港で魅力的な笑顔の男と知り合う。プラバカルはガイドでタクシードライバー。プラバカルと親友になる。
リンはスラムに腰を落ち着ける。そこでム所で覚えた救急看護の知識を生かして診療所を開設する。もちろん医師免許はない。それでもスラムの人たちはリンを頼りに大勢押しかける。こうして赤ひげみたいなことをしながらスラムの住民たちの人望を得る。プラバカルのつてで友人をどんどん増やしていく。そこはワケ有りの外国人のたまり場。美人のスイス人女性。なんでも屋のフランス人。映画タレントの周旋屋のアメリカ人女性。武道家のイラン人。
このあたりのインドはムンバイの描写はこの小説の魅力のひとつ。雑多な人種人間がごちゃごちゃになって生きている。その臭いが紙面から臭ってくる。香りなんて上品なものではない。臭いだ。大麻ヘロインはそのへんに普通にある。リンが診療所で使う薬は盗品だ。ここでは非合法は悪いことではない。
悪事とは悪い目的を行うためにする行為をいう。良い目的を行うためなら、非合法なことでも悪事とはいわない。
このボンベイでリンは人生の師と会う。アフガニスタン人のボンベイ・マフィアのボス。アブデル・カーデル・ハーン。リンはカーデルの忠実な手下としてマフィアの仕事にせいを出す。密輸、パスポートの偽造、などなどヤクザ仕事でシノギを稼ぎ、カーデルに従って戦乱のアフガニスタンにまで出張する。
上中下の3巻。1800ページを超える超大作であるが、読みやすく途中でだれない。インドに行きたし金はなし。と、いう人におすすめ。
コメント ( 11 ) | Trackback ( 0 )
SFマガジン2016年12月号
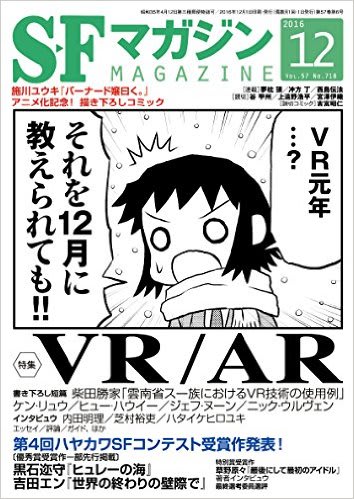
SFマガジン2016年12月号 №718 早川書房
雫石鉄也ひとり人気カウンター
1位 航空宇宙軍戦略爆撃隊(前編) 谷甲州
2位 シミュラクラ ケン・リュウ 古沢嘉通訳
3位 裏世界ピクニック 八尺様サバイバル 宮澤伊織
4位 ノーレゾ ジェフ・ヌーン 金子浩訳
5位 最強人間は機嫌が悪い 上遠野浩平
6位 キャラクター選択 ヒュー・ハウイー 大谷真弓訳
7位 あなたの代わりはいない ニック・ウルヴェン 鳴庭真人訳
8位 雲南省スー族におけるVR技術の使用例 柴田勝家
連載
小角の城(第41回) 夢枕獏
マルドゥック・アノニマス(第12回) 冲方丁
幻視百景(第5回) 酉島伝法
近代日本奇想小説史(大正・昭和篇)(第28回) 横田順彌
SFのある文学誌(第49回) 長山靖生
にゅうもん!西田藍の海外SF再入門(第13回) 西田藍
アニメもんのSF散歩(第13回)藤津亮太
現代日本演劇のSF的諸相(第22回) 山崎健太
特集 VR/AR
第4回ハヤカワSFコンテスト受賞作発表!
今号は読みきり短編が8編もあった。久しぶりに、まともに「読めた」SFマガジンであった。
で、今号の特集だが、VR(仮想現実)AR(拡張現実)である。どういうモノかというと、あの何かと問題なポケモンGOみたいなもんと小生は解釈しているが。
電車の中で、スマホとにらめっこしてる人と、本を読んでいる人。どっちが多いかというと、これは、もう、圧倒的にスマホ派である。悲しいかな本を読んでいる人は少ない。で、スマホでなにをやっているかというと、だいたいがゲームをやっているのだろう。
本が売れない。活字文化が衰退している。なぜか。携帯電話、なかんずくスマホの普及がその大きな要因であろう。今号の特集であるVRとかARとかいうもんは本を売れなくした元凶の代表ではないのか。それを活字文化たる雑誌のSFマガジンが特集してもいいのだろうか。いうなれば利敵行為ではないのか。とはいいつつも、かようなモノが、いまや大きな「文化」と成長したのだから、SF専門誌として取り扱う意義は認めざるを得ない。
それに、仮想現実/拡張現実といったモノを小説のネタに使えるのはSFだけだろう。いろんな文芸文学のジャンルがあるが、SFほど貪欲かつ寛容なジャンルはないだろう。この世の(あの世もその世も)森羅万象、およそSFのネタにならないモノはない。そういう意味からも、今号はSFの持つしたたかさを認識した号といえる。
それはそれとして、なんだこの表紙はアホか。最悪。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
作家になってどうする

本の雑誌11月号を読む。特集は「めざせ新人賞!」読んだあと暗澹たる気分になる。新人賞とってどうする。作家になる。で、作家になっても本が売れない。専業作家だけではとうてい食えない。
新人賞。応募作品のほとんどは、ハシにも棒にもかからないクズ。だから、ある程度文章の基本が身についた人なら、いいところまでは行ける。新人賞を取るのはさほどむつかしくない。新人賞を取っただけではダメなのだ。問題は2作目。新人賞を取ったがいいが、ほとんどの人は2作目を出さずにポシャてしまう。で、こんなに苦労して作家になっても、まったく本が売れない。困ったもんだ。まったく。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
SFマガジン2016年10月号
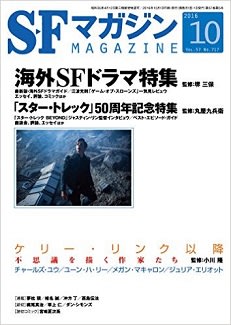
SFマガジン2016年10月号 №717 早川書房
雫石鉄也ひとり人気カウンター
1位 宝はこの地図 草上仁
2位 七千六日の少女 怨讐星域 特別編 梶尾真治
3位 ウルフェント・バンデローズの指南鼻(後篇) ダン・シモンズ 酒井昭伸訳
4位 魔法使いの家 メガン・マキャロン 鈴木潤訳
5位 ワイルド家の人たち ジュリア・エリオット 小川隆訳
6位 弓弦をはずして ユーン・ハ・リー 小川隆訳
7位 OPEN チャールズ・ユウ 円城塔訳
連載
小角の城(第40回) 夢枕獏
椎名誠のニュートラル・コーナー(第53回)
時間流刑者は暇な午後に三葉虫を釣りにいく 椎名誠
マルドゥック・アノニマス(第11回) 冲方丁
幻視百景(第4回) 酉島伝法
SFのある文学誌(第48回) 長山靖生
にゅうもん!西田藍の海外SF再入門(第12回) 西田藍
アニメもんのSF散歩(第12回) 藤津亮太
現代日本演劇のSF的諸相(第21回) 山崎健太
海外SFドラマ特集 監修 堺三保
「スタートレック」50周年記念特集 監修 丸屋九兵衛
ケリー・リンク以降―不思議を描く作家たち 監修 小川隆
小生、海外SFドラマに興味なし。「スタートレック」も昔の(レオナード・ニモイが出ててたヤツ)モノはリアルタイムで観てたが、今のモノに興味なし。よって、この二つの特集はパス。
しかし、このSFマガジンはSF専門誌だろ。だったら専門誌ならではの責務があるはずだろう。しかも日本で唯一のSF専門誌だ。そのことの自覚がないこと、はなはだしい。
この1年の特集を見てみよう。まず、今号はご覧のとおりの「海外SFドラマ」特集。
2016年8月号。ハヤカワSFシリーズ総解説。
6月号。やくしまるえつこのSF世界
4月号 デビッド・ボウイ追悼
2月号 スターウォーズ
2015年12月号 SFアニメ
10月号 伊藤計劃
毎年やっていたヒューゴー賞ネビュラ賞特集はない。非英語圏SF特集もない。まったく、これではとてもSF専門誌といっていいのだろうか。なんどもいってるがSFとはまず文芸だ。SF専門誌というからには文芸としてのSFに焦点をあてた編集をすべきではないのか。
とはいえ今月号は少し反省の色が見える。第3特集として「ケリー・リンク以降―不思議を描く作家たち」を企画した。これは評価できる。分類不可能な、不思議としかいいようがない作家を4人紹介していた。雫石鉄也ひとり人気カウンター4位、5位、6位、7位の作品がそれ。小生は低い評価をつけたが、このジャンル可能性はある。ただ、4人だけの紹介ではよく判らん。どうせやるのなら、第1特集としてもっと多くの作家作品を紹介すべし。
ケリー・リンク?不勉強ながら小生はこの作家知らなんだ。それに「以降」と呼ばれる作家ならば、なんでケリー・リンクの作品を掲載しない。片手落ちである。
コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )
火神(アグニ)を盗め
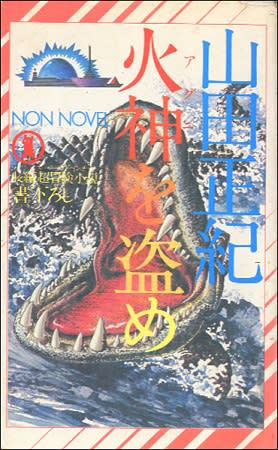
山田正紀 祥伝社
山田正紀はエンタティメント小説の万能職人作家だ。出発点のSFはいうにおよばず、ミステリー、伝奇小説、時代劇、ホラー、冒険小説とひと通りの分野で水準作以上の作品を1974年のデビュー以来40年以上にわたって発表し続けている。これはすごいことだ。その山田正紀の冒険小説の代表作がこの作品だ。
インドに建設された原子力発電所アグニ。そのアグニ建設に関わった日本の商社亜紀商事の原発技術者工藤。その工藤が極秘にアグニに仕掛けられた爆弾を発見する。うらにはアメリカCIAの存在が。工藤はCIAのエージェントに命を狙われる。助かる方法はアグニの爆弾を取り外すこと。会社はCIAを敵に回したくない。
「会社存続のために個人は切り捨てる」これに対して工藤は「生存のために会社を利用する」かくして亜紀商事は爆弾除去チームを編成する。会社としては本音はこのプロジェクトは失敗して欲しい。工藤は助かるために成功しなくてはならない。
で、会社が選んだメンバーは、工藤以外に落ちこぼれの社員ばかり。女性にしか興味のない社史編纂室の佐文字、謹厳実直だけがとり得の経理課の仙田、上方落語の大御所の落としだね営業部接待係の桂。
このとても冒険には不向きな連中が実現不可能なミッションに挑む。追って来るのはCIAの腕っこき殺し屋。立ち向かうは、触圧反応装置、対地レーダー、赤外線探知装置、高圧電流、前の川には飢えたワニがうじゃうじゃ、警備するはインド陸軍の精鋭、異常ともおもえるほどの警戒厳重な、最新鋭の原子力発電所。
小生が特に印象に残ったのは、営業部接待係の桂正太。彼は上方落語の某大物噺家が東京に来た時にできた子。認知はされていないようだ。関西の父の元では育ってない。血がなせる業が、上方落語が大好き。自分でも演じる。関西弁をしゃべる。でも、東京育ちのため関東なまりの関西弁しかしゃべれないため、プロの上方落語家にはなれない。落語以外に能力がない彼は亜紀商事で接待専門の社員として生きている。一度は高座に上がって大勢の客の前で上方落語を演じたいと思っている。
桂正太のミッションは音響反応警備装置の無力化。ところが彼は大音響を発する機械をなくしてしまう。どうしたか。音響反応装置の前で、大声で上方落語を演じた。インドの山奥の原子力発電所の前、そこが彼の高座だ。
大声で演じられる「夢八」ヒマラヤの山々に桂正太入魂の落語が鳴り響く。
「さあ、こっちはいっといで」「実は来てもろたんはほかでもないねんけどな」「ジンベはんなんでんの」原子力発電所内に、関東なまりの関西弁が、うわんうわんと鳴り響く。
上方落語ファンの小生は、涙なくしてここを読めなかった。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
アステロイド・ツリーの彼方へ

大森望・日下三蔵 編 東京創元社
毎年吉例、この年刊日本SF傑作選も9冊目となった。20編の作品が収録されている。短編集としては、かなりの大量の作品が収録されているわけ。当然、ページ数も増え、今回は610ページ。今までいちばん分厚くなったのではないか。
で、満腹したのかと問われれば、まったく満腹しなかった。このシリーズ、年々SFっ気が少なくなっている。編者の大森は「SFの多様性が実感できるはずだ」といっとるが、あれもSFこれもSFとSFの定義を拡大解釈すれば、この本のような水ぶくれアンソロジーができるのだ。
あれもコーヒーこれもコーヒーといって、コーヒーゼリーやコーヒーキャンディー、コーヒーぜんざい、コーヒーフロートなどといったコーヒー味のモノばかり集めて、これが年刊コーヒー傑作選だといってるくせに、肝心のレギュラーコーヒーが選ばれていない。そういう感じなのだ。
20編もあるが、小生が読んでSFを感じたのは表題作の上田早夕里の「アステロイド・ツリーの彼方へ」だけ。
これが、本当に昨年度の日本SFの頂上ならば、大森、日下両名が豊作と喜んでいるのは、まったく検討違いというべきだろう。それともこのお二人が知らない傑作がどっかに埋もれているのか。小生はそう思う。大森望氏、日下三蔵氏、それに東京創元社編集部の小浜徹也氏。お三方の、よりいっそうのがんばりに期待する。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ミッドナイト・ジャーナル

本城雅人 講談社
新聞記者モノである。新聞記者モノといえば横山秀夫さんが第一人者だと思うが、この作品もなかなかの力作である。
さいたま支局の関口、本社遊軍の藤瀬、整理部の松本。この3人は7年前、新聞記者として致命的なミスを犯す。7年前連続女児誘拐事件発生。3人の女の子が誘拐された。二人の女児は殺された。3人の記者は、あと一人の被害者女児遺体で発見と報じる。女児は生きていた。大誤報である。3人は左遷。飛ばされた。
あれから7年。同じような連続女児誘拐事件が起こる。二人の女児は車に連れ込まれる寸前に逃げて助かるが、3人目は殺される。助かった子の証言。車の中にもう一人いた。犯人は複数?関口は7年前の事件でも犯人複数説をつかんでいた。7年前の実行犯は死刑執行すみ。あの時もう一人いたとしたら、今回の事件と関連はあるのか。女性記者藤瀬は女子高校生になっている7年前の生き残り被害者に取材におもむく。
この作品では、犯人の描写はほとんどされない。だから、幼い女の子を誘拐して「暴行」して殺すといった、ロリコン凶悪無残な特異な犯人像で読ませる話ではない。貴志祐介の「悪の経典」は特異な犯人像で読ませるが、この作品の犯人はあくまで、遠くのほうにいて、新聞記者たちがいかにそこのたどり着くかが描かれる。極端にいえば、この作品で描かれているのは、新聞記者と、それの取材を受ける警察だけである。それも警察が主語になることなく、この小説を構成している文章の主語はすべて新聞記者である。真実を報道する。そのことを追求する新聞記者の物語である。
ところで、なにかコトを成すにおいて、メンツほど邪魔なモノはない。新聞記者も警察も他のセクション、他の県警ともメンツのはりあいをせずに、虚心坦懐にコトにあたれば、もっと早くコトが成るはず。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
火星鉄道一九

谷甲州 早川書房
表題作は1987年の星雲賞日本短編部門受賞作。1987年の日本SF大会は石川県は山中温泉で開催された。小生も甲州も参加していた。今から29年も前のことだ。
十九で受賞するかもしれないということは聞いていた。受賞が決まった直後、小生と甲州は山中温泉の街中をぶらぶら歩いていた。
「星雲賞おめでとう」「ありがとう。ところでたこ焼きが食いたいな」
甲州は関西人の常として、たこ焼き好きである。どこででもたこ焼きを食いたがる。
「こんな北陸の温泉地にたこ焼きなんぞあらへんやろ」
「あそこにあるで」
えらいもので甲州の指差す先にたこ焼きの屋台があるではないか。たこ焼きをおごってやった。この時の、小生の星雲賞受賞お祝いはたこ焼きひとふねである。
この本には次の7編が収録されている。
火星鉄道一九
ドン亀野郎ども
木星遊撃隊
小惑星急行
タイタン航空隊
土砂降り戦隊
ソクラテスの孤独
航空宇宙軍史でいうと、外惑星連合が地球に宣戦布告。連合軍VS航空宇宙軍の戦いが始まったころ。だから登場人物はすべてが軍人。宇宙空間での戦闘といっても、この航空宇宙軍史はスペースオペラではない。映画スターウォーズのようにハデにレーザー光線やミサイルが飛び交うわけではない。
やっていることは軌道計算であり、燃料の残量をにらみつつ、任務を達成できるのか頭を悩ませるのである。
谷甲州のこの「航空宇宙軍史」は「現場のおじさん」SFといっていいだろう。現場のおじさんはたいへんなのだ。
コメント ( 10 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |



