雫石鉄也の
とつぜんブログ
とつぜんSFノート 第114回
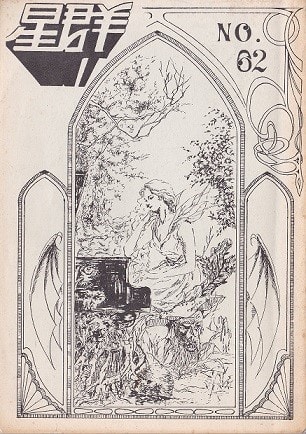
第13回星群祭は1986年7月27日に行われた。会場はいつもの京大会館。この時の星群祭は、いつもと違う特異なモノとなった。テーマが「幻想としてのSF」ゲストが、植島啓司氏、風見潤氏、高梨久氏、東雅夫氏、堀晃氏、眉村卓氏、渡辺恒人氏、という例年の星群祭に比べて異質な顔ぶれとなった。SFプロパーの人は風見氏、堀氏、眉村氏の3人で、あとの植島氏、高梨氏、東氏、渡辺氏の3人は他のSF関係のイベントでは、まず、お目にかかれない人たちだ。この第13回星群祭は実行委員長村上栄次氏の意向が強く反映された星群祭といえよう。
第13回星群祭当日の様子は、レポートも残っていなし、小生の記憶も薄れていて、ここに記すことはできない。
この第13回星群祭の4日あと、1986年8月1日の日付で発行された星群62号は、この星群祭の準備と並行して編集された号。「幻想とSF」が特集。だから第13回星群祭と星群62号はメディアミックスで展開していたわけだ。
星群62号の内容は「恐怖・不条理・ゲーム・存在論ファンタジーをめぐる雑想」なるエッセイを山本弘が書いている。
山尾悠子私論。やはり幻想小説といえばこの人にふれないわけにはいかない。そして日本の幻想小説のジェダイマスターといえば泉鏡花。その泉鏡花の幻想小説・戯曲の索引を載せた。
それから32年。その山尾悠子が「飛ぶ孔雀」で泉鏡花賞を受賞した。星群62号は32年後を予言したのかな。
あと、アンケートを実施した。設問は、
「幻想文学とは」
「海外の幻想文学ベスト5」
「日本の幻想文学ベスト5」
伊藤典夫、大宮信光、岡部宏之、岡本俊弥、紀田順一郎、児島冬樹、柴野拓美、仁賀克雄、水鏡子、高井信、巽孝之、田中光二、田中芳樹、野阿梓、星新一、森下一仁、矢野徹、夢枕獏、横田順彌、渡辺恒人の各氏から返答をいただいた。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
とつぜんSFノート 第113回
小生はSFファンであるがコレクション癖はない。それでも普通の人より本はたくさん持っている方だろう。さして広くないマンションに住んでおるから本棚は2本しかもっていない。大きな本棚ではない。水鏡子先生のように書庫を持つなんて夢のまた夢である。
コレクション癖はないが、本はよく読むので本はどうしても増える。単行本は本棚がいっぱいになれば処分する。保存状態の良い本は古書店に売りに行く。そうでないモノは資源ゴミの時に出す。本をゴミとして出すのは気がひけるのである。小生が読了して用がなくなった本であっても、本のためには、できれば愛書家の手にわたり、読んでもらいたいものだ。本はだれかに読んでもらってこそ本なのだ。
というわけで、単行本は厳選された本しか手元に置かない。小生、作家にも何人か知り合いはいるが、そういう人たちにはたまにサインを頂くことがある。もちろんそういうサイン本は手元に置いておき永久保存だ。
単行本はまだいい。問題は雑誌である。以前は、「SFマガジン」「SFアドベンチャー」「奇想天外」「幻想と怪奇」といった雑誌を、ほぼ全巻そろいで持っていた。いまはSFマガジンだけである。
小生、いままでに本の大幅減が3度あった。最初は引っ越し。次に結婚。そして阪神大震災。小生の住いおる神戸の東灘は震度7の激震にみまわれた。マンションの建物は無事だったが部屋の中はぐじゃぐじゃ。本棚はぜんぶ全壊。震災後、避難場所から帰って落ちついて本の整理をはじめた。このさい、本の整理をしようと思い切った。まず、SF関係の友だちを何人か呼んで、不要本で欲しい本を持って帰ってもらった。これで単行本は半減。あと、「SFアドベンチャー」「奇想天外」「幻想と怪奇」も手放した。SFマガジンだけを残した。
いまはSFマガジンは本棚に入らないのでボテ箱に入れてある。これがけっこう場所をくう。小生、別に火の鳥の血を吸ったわけではないので永遠に生きるわけではない。ボテ箱のSFマガジンはどうにかしなければならない。と、こう思うSFファンは多いだろう。また、SFマガジン全巻揃いを残して逝ってしまう同好の士もいるだろう。
今のSFマガジンをずっと揃えておこう、ついては古いSFマガジンも欲しいといって、コレクションを始める若いSFファンがそんなに多くいるとは思えぬ。小生たちの世代は数が多い。なんでもやたら頭数ばかりが多い。分母が多けりゃ分子も多いだろう。SFマガジン全巻揃いを持っているSFファンも多いだろう。そういう小生の世代のSFファンがこれからどんどん死んでいく。あとにはSFマガジンが残る。興味のない者にとってそんなモノ紙くず以外なにものでもない。ヘリコニア談話室さんがおっしゃっているように、SFマガジン全巻揃いが古書市場にあふれかえるということになる。ほんと、小生のぶんも早々にどないかしなくてはならない。
コレクション癖はないが、本はよく読むので本はどうしても増える。単行本は本棚がいっぱいになれば処分する。保存状態の良い本は古書店に売りに行く。そうでないモノは資源ゴミの時に出す。本をゴミとして出すのは気がひけるのである。小生が読了して用がなくなった本であっても、本のためには、できれば愛書家の手にわたり、読んでもらいたいものだ。本はだれかに読んでもらってこそ本なのだ。
というわけで、単行本は厳選された本しか手元に置かない。小生、作家にも何人か知り合いはいるが、そういう人たちにはたまにサインを頂くことがある。もちろんそういうサイン本は手元に置いておき永久保存だ。
単行本はまだいい。問題は雑誌である。以前は、「SFマガジン」「SFアドベンチャー」「奇想天外」「幻想と怪奇」といった雑誌を、ほぼ全巻そろいで持っていた。いまはSFマガジンだけである。
小生、いままでに本の大幅減が3度あった。最初は引っ越し。次に結婚。そして阪神大震災。小生の住いおる神戸の東灘は震度7の激震にみまわれた。マンションの建物は無事だったが部屋の中はぐじゃぐじゃ。本棚はぜんぶ全壊。震災後、避難場所から帰って落ちついて本の整理をはじめた。このさい、本の整理をしようと思い切った。まず、SF関係の友だちを何人か呼んで、不要本で欲しい本を持って帰ってもらった。これで単行本は半減。あと、「SFアドベンチャー」「奇想天外」「幻想と怪奇」も手放した。SFマガジンだけを残した。
いまはSFマガジンは本棚に入らないのでボテ箱に入れてある。これがけっこう場所をくう。小生、別に火の鳥の血を吸ったわけではないので永遠に生きるわけではない。ボテ箱のSFマガジンはどうにかしなければならない。と、こう思うSFファンは多いだろう。また、SFマガジン全巻揃いを残して逝ってしまう同好の士もいるだろう。
今のSFマガジンをずっと揃えておこう、ついては古いSFマガジンも欲しいといって、コレクションを始める若いSFファンがそんなに多くいるとは思えぬ。小生たちの世代は数が多い。なんでもやたら頭数ばかりが多い。分母が多けりゃ分子も多いだろう。SFマガジン全巻揃いを持っているSFファンも多いだろう。そういう小生の世代のSFファンがこれからどんどん死んでいく。あとにはSFマガジンが残る。興味のない者にとってそんなモノ紙くず以外なにものでもない。ヘリコニア談話室さんがおっしゃっているように、SFマガジン全巻揃いが古書市場にあふれかえるということになる。ほんと、小生のぶんも早々にどないかしなくてはならない。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
とつぜんSFノート 第112回
怪獣。SFファンの大好物であろう。子供も怪獣は好きだ。SFファンという人種は体内に子供的要素がたくさん残しているので、このことは当たっているだろう。
ここでいう子供とは男の子限定と思ってもらいたい。小生は女の子になった経験はないので、女の子、女とはいかなるモノかは想像するしかないが、男の子、男の経験はあるので、だいたい判る。
小生、思うに、男は年齢を積み重ねる。女は年齢を通り過ぎるのではないだろうか。40の男の中には、10代の、20代の、30代の男が残っている。女は10代、20代、30代と通り過ぎていく、だから40の女の中には10代の女は残っていない。
で、SFファンの男というモノは、中に残っている子供の部分が大きいのだろう。だからSFファンは子供の好きな怪獣が好きなのではないだろうか。
小生もご他聞にもれず、怪獣の好きな子供であった。
子供ころ住んでいた家から歩いて20分ほどの所に、甲南朝日という映画館があった。今は映画館は街中のシネコンぐらいしかないが、昔は各町内に映画館は最低一軒はあった。小生の近在には大映、東映、東宝の3社の映画館があった。甲南朝日は東宝の封切館であった。怪獣好きな小生は、この中の甲南朝日に一番よく行った。子供だから親に連れて行ってもらうのだが、ここでゴジラやモスラを観たあとで、映画館のすじ向かいにあるナダシンでぼたもちや大福もちを買ってもらって食べるのが楽しみであった。
そうなのだ。怪獣は映画館に行かなくては観れないモノだった。それが家で、しかも毎週観られる。それを知った時の喜びはご想像いただけるであろうか。
ウルトラQである。この番組はほんとうに革新的であった。毎週、特撮ものの怪獣が家で観れる。もう親に頼んで甲南朝日まで連れて行ってもらわなくていいのだ。
1966年の正月にウルトラQ第1回「ゴメスを倒せ!」まるで2014年の阪神以外のセリーグのピッチャーみたいなタイトルだが、これが記念すべきウルトラQの第1回だ。
その前年、1965年の年の瀬ほど楽しみな年の瀬はなかった。テレビの6チャンネルをつけるとウルトラQの予告をやっていた。特に印象に残っているのが、大きな卵が割れると、中からでかいナメクジが出てくる。そやつが柄についた眼から光線を出している。どうも第3回のナメゴンのようだ。それから毎週日曜日の午後7時からはテレビに釘づけであった。
ここでいう子供とは男の子限定と思ってもらいたい。小生は女の子になった経験はないので、女の子、女とはいかなるモノかは想像するしかないが、男の子、男の経験はあるので、だいたい判る。
小生、思うに、男は年齢を積み重ねる。女は年齢を通り過ぎるのではないだろうか。40の男の中には、10代の、20代の、30代の男が残っている。女は10代、20代、30代と通り過ぎていく、だから40の女の中には10代の女は残っていない。
で、SFファンの男というモノは、中に残っている子供の部分が大きいのだろう。だからSFファンは子供の好きな怪獣が好きなのではないだろうか。
小生もご他聞にもれず、怪獣の好きな子供であった。
子供ころ住んでいた家から歩いて20分ほどの所に、甲南朝日という映画館があった。今は映画館は街中のシネコンぐらいしかないが、昔は各町内に映画館は最低一軒はあった。小生の近在には大映、東映、東宝の3社の映画館があった。甲南朝日は東宝の封切館であった。怪獣好きな小生は、この中の甲南朝日に一番よく行った。子供だから親に連れて行ってもらうのだが、ここでゴジラやモスラを観たあとで、映画館のすじ向かいにあるナダシンでぼたもちや大福もちを買ってもらって食べるのが楽しみであった。
そうなのだ。怪獣は映画館に行かなくては観れないモノだった。それが家で、しかも毎週観られる。それを知った時の喜びはご想像いただけるであろうか。
ウルトラQである。この番組はほんとうに革新的であった。毎週、特撮ものの怪獣が家で観れる。もう親に頼んで甲南朝日まで連れて行ってもらわなくていいのだ。
1966年の正月にウルトラQ第1回「ゴメスを倒せ!」まるで2014年の阪神以外のセリーグのピッチャーみたいなタイトルだが、これが記念すべきウルトラQの第1回だ。
その前年、1965年の年の瀬ほど楽しみな年の瀬はなかった。テレビの6チャンネルをつけるとウルトラQの予告をやっていた。特に印象に残っているのが、大きな卵が割れると、中からでかいナメクジが出てくる。そやつが柄についた眼から光線を出している。どうも第3回のナメゴンのようだ。それから毎週日曜日の午後7時からはテレビに釘づけであった。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
とつぜんSFノート 第111回
喫茶店ホワイトローズ。あれから35年たった。この喫茶店はいまはもうないだろう。どこにあったのか、記憶がはっきりしないが、確かシネラマのOS劇場の前の道を行ってすぐのところだと記憶する。地名でいうと北区小松原町だろう。
OS劇場。シネラマを上映する関西でただ1つの映画館だった。ここで「2001年宇宙の旅」を観たときの衝撃を今も忘れられない。感動のあまり腰が抜けてしばらく座席から立ち上がれなかった。
それはそれとしてホワイトローズだ。2階にかなり広いスペースがあって、飲物を頼めばそこで会議もできる。なん時間いても追い出されることはない。
1984年の8月にホワイトローズでやった会議が、第25回日本SF大会の第1回実行委員会である。(北海道からの帰途列車内でやった4人の話し合いを第1回とするのなら第2回実行委員会である。
どれぐらいの人数が集まったのか記憶にないが、20人ぐらいではなかっただろうか。小生、山根、清水の3人の人脈でかき集めた人たちだ。男女は半々ぐらいだっただろう。この第1回実行委員会に集まったメンバーはほとんどが最後までメンバーであって抜けた人は少数であった。もちろんゼネプロの息のかかったモノはいなかった。
最初に話し合ったこと。まず、これだけの人数ではSF大会はできない。各自知人友人地縁血縁人脈を活用して実行委員を増やすべし。会場をどこにするか。1000人規模のイベントである。2年後のことだ。早々に手を打つ必要がある。最高責任者たる実行委員長にはだれがなる。実務を取り仕切る事務局長はだれがなる。とりあえず第25回日本SF大会は第一歩を歩み始めたわけ。
さて、ひととおり最初の話し合いは終わった。そのあと阪急ファイブのほど近くの喫茶店れいに移動。ここはKSFA関西海外SF研究会が毎週日曜日に例会をやっていて、大野万紀、水鏡子、英保未来(大森望)、桐山芳男といった関西ファンダムのおおどころが集っている。彼らに協力を要請する。そのあと阪急かっぱ横丁の居酒屋「あせんぼ」へ。
居酒屋でSFのお仲間とよく飲む。男同士ならそうではないが、女性が混じると会計が終わったあとのレシートが長くなる。この実行委員会のあとの「あせんぼ」での飲み会は女性の割合は半数。女性は小鉢もんや、なんやかんやとアテ、食べ物をよく頼む。20人近くの多人数で女性が半分。一度レシートの長さが1メートル近くなったことがある。
ホワイトローズ→れい→あせんぼ。これがこのころの小生の日曜日の行動パターンであった。今から35年前だ。今も人数は少なくなったが月に一度同じようなことをやっている。しかし、まあ、みんなトシとったから2次会までで、男ばかりだからレシートの長さも15センチほどだ。
OS劇場。シネラマを上映する関西でただ1つの映画館だった。ここで「2001年宇宙の旅」を観たときの衝撃を今も忘れられない。感動のあまり腰が抜けてしばらく座席から立ち上がれなかった。
それはそれとしてホワイトローズだ。2階にかなり広いスペースがあって、飲物を頼めばそこで会議もできる。なん時間いても追い出されることはない。
1984年の8月にホワイトローズでやった会議が、第25回日本SF大会の第1回実行委員会である。(北海道からの帰途列車内でやった4人の話し合いを第1回とするのなら第2回実行委員会である。
どれぐらいの人数が集まったのか記憶にないが、20人ぐらいではなかっただろうか。小生、山根、清水の3人の人脈でかき集めた人たちだ。男女は半々ぐらいだっただろう。この第1回実行委員会に集まったメンバーはほとんどが最後までメンバーであって抜けた人は少数であった。もちろんゼネプロの息のかかったモノはいなかった。
最初に話し合ったこと。まず、これだけの人数ではSF大会はできない。各自知人友人地縁血縁人脈を活用して実行委員を増やすべし。会場をどこにするか。1000人規模のイベントである。2年後のことだ。早々に手を打つ必要がある。最高責任者たる実行委員長にはだれがなる。実務を取り仕切る事務局長はだれがなる。とりあえず第25回日本SF大会は第一歩を歩み始めたわけ。
さて、ひととおり最初の話し合いは終わった。そのあと阪急ファイブのほど近くの喫茶店れいに移動。ここはKSFA関西海外SF研究会が毎週日曜日に例会をやっていて、大野万紀、水鏡子、英保未来(大森望)、桐山芳男といった関西ファンダムのおおどころが集っている。彼らに協力を要請する。そのあと阪急かっぱ横丁の居酒屋「あせんぼ」へ。
居酒屋でSFのお仲間とよく飲む。男同士ならそうではないが、女性が混じると会計が終わったあとのレシートが長くなる。この実行委員会のあとの「あせんぼ」での飲み会は女性の割合は半数。女性は小鉢もんや、なんやかんやとアテ、食べ物をよく頼む。20人近くの多人数で女性が半分。一度レシートの長さが1メートル近くなったことがある。
ホワイトローズ→れい→あせんぼ。これがこのころの小生の日曜日の行動パターンであった。今から35年前だ。今も人数は少なくなったが月に一度同じようなことをやっている。しかし、まあ、みんなトシとったから2次会までで、男ばかりだからレシートの長さも15センチほどだ。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
とつぜんSFノート 第110回
そのころは、7月になればそわそわしてきたものだ。小生が7月生まれで夏好きということもあるが、7月になれば星群祭がある。
1985年7月27日。土曜日である。毎年そうだが、この日は朝からウキウキソワソワしてた。土曜なれど出勤。会社での仕事が手につかない。夜になるのが待ちきれない。一年中で最も楽しい夜が、あと数時間でやってくる。
5時になった。着替えるのももどかしく会社を出る。そのころの小生の勤務地は大阪北区の豊崎。阪急梅田駅はすぐそこ。京都河原町行きの特急に乗る。目的地は東山区の旅館きのゑ。純和風旅館である。ここが星群祭前泊の合宿の会場。SFのイベントに参加されたご仁なら賛成してくれると思うが、かようなイベントにおいて最も楽しいことは合宿でおこる。この法則は星群祭の合宿にもあてはまる。京都例会出席メンバーなら毎月会うが、地方の星群会員とはこういう機会でないと会えない。1年ぶりの顔も多数。あとは飲めや歌えやのドンチャン騒ぎに麻雀、議論、激論、旧交を温める。
狂乱の一夜があけた。二日酔あたまを振りたてて星群祭会場の京大会館に行く。1985年7月28日。午前中である。いかなる天気であるかは忘れたが、雨天ではない。小生の記憶に間違いがなければ、雨の星群祭というのはなかった。たぶん、京都らしい底意地の悪い暑い日であったろう。
と、いうわけで第12回星群祭は始った。テーマは「ファン創作の構造」実行委員長は亀沢邦夫氏。ゲストは荒巻義雄氏、風見潤氏、豊田有恒氏、堀晃氏、眉村卓氏、安田均氏。
まず、最初のゲスト講演。風見潤氏。楳図かずおの「漂流教室」を原作として風見氏が小説化した。その時の過程をケーススタディとして解説。漫画と小説の違い。多くの絵も小説なら数行ですむことがある。1枚の絵になん枚もの原稿を費やすこともある。
荒巻義雄氏。荒巻氏はファン創作の強力な支援者だ。SFアドベンチャーでファンジン評のページを担当されていたし、星群の同人たちも特別にお教えを賜ったこともある。荒巻氏は、このころ出始めたワードプロセッサについて話された。氏はこの最新の文章作成マシンを早々に導入され、その便利さにおどろかれたとのこと。
堀晃氏。堀氏は二足ワラジ作家である。会社員とSF作家を兼業されている。会社勤めをしながら創作活動するために克服すべき課題について。会社ではトシを取ると偉くなる。仕事も増える。結婚すれば家族も増える。かような課題をいかに克服するか。ポイントは土曜日曜日の活用ということ。
眉村卓氏。全力で書く。才能の食いちらかしはするべきではない。この1作で小説を書くのはやめようと思うぐらいで書くように。
豊田有恒氏。作家は『なる』ものだ。なにがなんでも作家になるというコケの一念が大切だ。
ゲストの講演が終わると。星群祭名物、星群ノベルズ批評となる。星群ノベルズに掲載された作品に対して、ゲスト諸氏の容赦のない批評が加えられる。この時の標的となったのは。
「エデンの産声」石坪光司
「洪水のあとで」山田博一
「G線上のマリア」井上祐美子
「シュレージンガーのチョコパフェ」山本弘
「逆ユートピア」坂本裕子
「白き闇のオデュセウス」立川みどり
「流謫祭」小沢淳
の、七人の同人。星群ノベルズは毎年発行していたが、この年初めて女性執筆者の数が男性執筆者を越えた。女性が元気になる社会を星群の会は先取りしていたのである。最近のヒューゴー賞受賞者をみると女性作家が目立つ。
なお、「シュレージンガーのチョコパフェ」は1986年ファンジン大賞創作部門賞を受賞した。
1985年7月27日。土曜日である。毎年そうだが、この日は朝からウキウキソワソワしてた。土曜なれど出勤。会社での仕事が手につかない。夜になるのが待ちきれない。一年中で最も楽しい夜が、あと数時間でやってくる。
5時になった。着替えるのももどかしく会社を出る。そのころの小生の勤務地は大阪北区の豊崎。阪急梅田駅はすぐそこ。京都河原町行きの特急に乗る。目的地は東山区の旅館きのゑ。純和風旅館である。ここが星群祭前泊の合宿の会場。SFのイベントに参加されたご仁なら賛成してくれると思うが、かようなイベントにおいて最も楽しいことは合宿でおこる。この法則は星群祭の合宿にもあてはまる。京都例会出席メンバーなら毎月会うが、地方の星群会員とはこういう機会でないと会えない。1年ぶりの顔も多数。あとは飲めや歌えやのドンチャン騒ぎに麻雀、議論、激論、旧交を温める。
狂乱の一夜があけた。二日酔あたまを振りたてて星群祭会場の京大会館に行く。1985年7月28日。午前中である。いかなる天気であるかは忘れたが、雨天ではない。小生の記憶に間違いがなければ、雨の星群祭というのはなかった。たぶん、京都らしい底意地の悪い暑い日であったろう。
と、いうわけで第12回星群祭は始った。テーマは「ファン創作の構造」実行委員長は亀沢邦夫氏。ゲストは荒巻義雄氏、風見潤氏、豊田有恒氏、堀晃氏、眉村卓氏、安田均氏。
まず、最初のゲスト講演。風見潤氏。楳図かずおの「漂流教室」を原作として風見氏が小説化した。その時の過程をケーススタディとして解説。漫画と小説の違い。多くの絵も小説なら数行ですむことがある。1枚の絵になん枚もの原稿を費やすこともある。
荒巻義雄氏。荒巻氏はファン創作の強力な支援者だ。SFアドベンチャーでファンジン評のページを担当されていたし、星群の同人たちも特別にお教えを賜ったこともある。荒巻氏は、このころ出始めたワードプロセッサについて話された。氏はこの最新の文章作成マシンを早々に導入され、その便利さにおどろかれたとのこと。
堀晃氏。堀氏は二足ワラジ作家である。会社員とSF作家を兼業されている。会社勤めをしながら創作活動するために克服すべき課題について。会社ではトシを取ると偉くなる。仕事も増える。結婚すれば家族も増える。かような課題をいかに克服するか。ポイントは土曜日曜日の活用ということ。
眉村卓氏。全力で書く。才能の食いちらかしはするべきではない。この1作で小説を書くのはやめようと思うぐらいで書くように。
豊田有恒氏。作家は『なる』ものだ。なにがなんでも作家になるというコケの一念が大切だ。
ゲストの講演が終わると。星群祭名物、星群ノベルズ批評となる。星群ノベルズに掲載された作品に対して、ゲスト諸氏の容赦のない批評が加えられる。この時の標的となったのは。
「エデンの産声」石坪光司
「洪水のあとで」山田博一
「G線上のマリア」井上祐美子
「シュレージンガーのチョコパフェ」山本弘
「逆ユートピア」坂本裕子
「白き闇のオデュセウス」立川みどり
「流謫祭」小沢淳
の、七人の同人。星群ノベルズは毎年発行していたが、この年初めて女性執筆者の数が男性執筆者を越えた。女性が元気になる社会を星群の会は先取りしていたのである。最近のヒューゴー賞受賞者をみると女性作家が目立つ。
なお、「シュレージンガーのチョコパフェ」は1986年ファンジン大賞創作部門賞を受賞した。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
とつぜんSFノート 第109回
小生、何が嫌いかっていうと、占いが大嫌い。かような非科学的なものは信じられない。占いと同じく、オカルトだとか心霊現象、幽霊、お化け、かようなモノは、小生は信じられないタチである。
生まれてから、このかた、夢のお告げとか金縛りとか、心霊現象的なことは経験したことがない。幽霊も見た事もないし、ツチノコだとかUFOも見たことがない。
人が非業の死を遂げた場所には、よく幽霊が出るなんていう。小生の住いおる神戸の東灘は阪神大震災で多くの人が亡くなったところだ。震災直後は路傍のあちこちに花がいけてあった。人が死んだ場所だと判る。かような地に住んでいるが幽霊を見たことはないし、そんな話も聞かない。
病院というのも怪談話がよくあるところだ。先年、入院したとき、「病院の怪談」を経験してやろうと思って、真夜中、病室を抜け出して、廊下をうろうろした。なんにも出なかった。「真夜中にうろうろしてはいけません」と夜勤の看護師さんにしかられただけだった。
学校も病院と同じく怪談話が多いところ。小生が卒業した小学校ではそんな話を聞いたことがない。その小学校は新設校で小生で確か3期生であった。新しい学校には怪談はないのかな。神戸出身の浅野ゆう子が後輩でその小学校卒業だから、浅野さんとお知り合いのムキはそのことをたずねればいい。
こういう小生だから、肝だめしにはめっぽう強く、子供のころキャンプなんかで、深夜、墓場を歩いても平気だった。ちなみに深夜の神社というのも肝だめしで行ったことがあるが、墓場と神社、どっちが不気味かというと神社の方が不気味であった。墓場は地下にいるのが元人間だったので、なんかにぎやかな感じがする。神社はほんとうにシーンとしてて、人智を超えたモノに見られているようであった。
かように怖いモノが少ない小生であるが、生まれてから今までで一番怖かったのは夜の海だ。小生、水産学科であったので実習で船に乗ることもあった。すぐに引き上げられたが、深夜の海に落ちたことがあった。泳げるので溺れなかったが、怖かった。真っ暗で、陸の灯りも見えない。つかまるモノもない。深い海の中からなにか出てきて引き込まれそうであった。時間にして10分もなかったと記憶するが、ほんとうに怖かった。
幽霊もUFOもみたことがないし、信じない。かような小生であるがSFファンである。奇妙奇天烈、奇想天外な話が大好きである。矛盾しているように思われるであろう。矛盾していない。架空、空想が好きなのであって、現実に不可思議なことは信じないのである。SFは昔、「空想科学小説」といわれた。空想な科学の小説がSFなのである。摩訶不思議な話であっても、科学的合理的な説明がなされてすっきりする。それがSFの魅力なのである。小生は最後には科学を信頼したい。あやしのモノは科学の光に照らされて白日のもとにあらわになり、なんだ、これだけのもんか、幽霊の正体見たりかれすすきの面白さ。それもSFの大きな魅力なのではないだろうか。
生まれてから、このかた、夢のお告げとか金縛りとか、心霊現象的なことは経験したことがない。幽霊も見た事もないし、ツチノコだとかUFOも見たことがない。
人が非業の死を遂げた場所には、よく幽霊が出るなんていう。小生の住いおる神戸の東灘は阪神大震災で多くの人が亡くなったところだ。震災直後は路傍のあちこちに花がいけてあった。人が死んだ場所だと判る。かような地に住んでいるが幽霊を見たことはないし、そんな話も聞かない。
病院というのも怪談話がよくあるところだ。先年、入院したとき、「病院の怪談」を経験してやろうと思って、真夜中、病室を抜け出して、廊下をうろうろした。なんにも出なかった。「真夜中にうろうろしてはいけません」と夜勤の看護師さんにしかられただけだった。
学校も病院と同じく怪談話が多いところ。小生が卒業した小学校ではそんな話を聞いたことがない。その小学校は新設校で小生で確か3期生であった。新しい学校には怪談はないのかな。神戸出身の浅野ゆう子が後輩でその小学校卒業だから、浅野さんとお知り合いのムキはそのことをたずねればいい。
こういう小生だから、肝だめしにはめっぽう強く、子供のころキャンプなんかで、深夜、墓場を歩いても平気だった。ちなみに深夜の神社というのも肝だめしで行ったことがあるが、墓場と神社、どっちが不気味かというと神社の方が不気味であった。墓場は地下にいるのが元人間だったので、なんかにぎやかな感じがする。神社はほんとうにシーンとしてて、人智を超えたモノに見られているようであった。
かように怖いモノが少ない小生であるが、生まれてから今までで一番怖かったのは夜の海だ。小生、水産学科であったので実習で船に乗ることもあった。すぐに引き上げられたが、深夜の海に落ちたことがあった。泳げるので溺れなかったが、怖かった。真っ暗で、陸の灯りも見えない。つかまるモノもない。深い海の中からなにか出てきて引き込まれそうであった。時間にして10分もなかったと記憶するが、ほんとうに怖かった。
幽霊もUFOもみたことがないし、信じない。かような小生であるがSFファンである。奇妙奇天烈、奇想天外な話が大好きである。矛盾しているように思われるであろう。矛盾していない。架空、空想が好きなのであって、現実に不可思議なことは信じないのである。SFは昔、「空想科学小説」といわれた。空想な科学の小説がSFなのである。摩訶不思議な話であっても、科学的合理的な説明がなされてすっきりする。それがSFの魅力なのである。小生は最後には科学を信頼したい。あやしのモノは科学の光に照らされて白日のもとにあらわになり、なんだ、これだけのもんか、幽霊の正体見たりかれすすきの面白さ。それもSFの大きな魅力なのではないだろうか。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
とつぜんSFノート 第108回
今年もあとわずか。小生、自分がSFもんであることを自覚して、もうずいぶん経つ。そうだなあ。50年近い年月がたったかな。ま、これだけ長いことSFもんをやっているわけだから、いまご好誼いただいている、SF仲間諸賢とのつきあいも、40年を超すつきあいとなったしだい。長いつきあいとなった。
長いといえばSFマガジンとのつきあいも、ずいぶんと長い。
小生が初めて買って読んだSFマガジンは1967年9月号通巻98号。51年のつきあいである。この間、発行されたSFマガジンは1号も欠かさず読んでいる。最新号2019年2月号は731号だから633冊のSFマガジンを読んでいることになる。
また、2007年より星群の会ホームページで「SFマガジン思い出帳」を連載している。そのため古いSFマガジンを読んでいる。最新のモノは1977年11月号を紹介した。41年ぶりの再読である。さすがにすっかり忘れている。この企画はひと月に1冊だから、小生が死ぬまでやっても現代の号には追いつかないだろう。
というわけで、SFマガジンは最新号は隔月刊だからふた月に1冊。バックナンバーはひと月に1冊のペースで読んでいる。
そのSFマガジンだが、最新の2019年2月号はえらいことになっているとか。特集企画は「百合」発売と同時に在庫がなくなった。えらい売れ行き。重版している。SFマガジンで重版は2011年8月号の初音ミク特集以来だ。しかし、この印刷媒体が売れないご時勢で、雑誌が重版だなんて、他の出版社からみればうらやましい限りだろう。今は書店の店頭になく、ネットでも入手が困難だそうだ。小生は定期購読しているから25日に早川から送って来たが。
しかし、早川書房はときどき大ヒットを飛ばすな。2017年のカズオ・イシグロのノーベル賞特需、そしてこのたびの百合特需。早川書房におかれましてはまことにご同慶のいたりである。
長いといえばSFマガジンとのつきあいも、ずいぶんと長い。
小生が初めて買って読んだSFマガジンは1967年9月号通巻98号。51年のつきあいである。この間、発行されたSFマガジンは1号も欠かさず読んでいる。最新号2019年2月号は731号だから633冊のSFマガジンを読んでいることになる。
また、2007年より星群の会ホームページで「SFマガジン思い出帳」を連載している。そのため古いSFマガジンを読んでいる。最新のモノは1977年11月号を紹介した。41年ぶりの再読である。さすがにすっかり忘れている。この企画はひと月に1冊だから、小生が死ぬまでやっても現代の号には追いつかないだろう。
というわけで、SFマガジンは最新号は隔月刊だからふた月に1冊。バックナンバーはひと月に1冊のペースで読んでいる。
そのSFマガジンだが、最新の2019年2月号はえらいことになっているとか。特集企画は「百合」発売と同時に在庫がなくなった。えらい売れ行き。重版している。SFマガジンで重版は2011年8月号の初音ミク特集以来だ。しかし、この印刷媒体が売れないご時勢で、雑誌が重版だなんて、他の出版社からみればうらやましい限りだろう。今は書店の店頭になく、ネットでも入手が困難だそうだ。小生は定期購読しているから25日に早川から送って来たが。
しかし、早川書房はときどき大ヒットを飛ばすな。2017年のカズオ・イシグロのノーベル賞特需、そしてこのたびの百合特需。早川書房におかれましてはまことにご同慶のいたりである。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
とつぜんSFノート 第107回
と、いうわけで、長い旅路の果て、やっと関西にたどり着いた。この時点では第25回日本SF大会DAICN5の実行委員会は小生も入れて3人だった。一番の年長でSFファン歴が最も長いのが小生である。
新大阪で新幹線を降りて、在来線で大阪まで来て、やっと関西へ帰って来たと実感する。とりあえずどっかで一休みしようということで、確か、阪急三番街の喫茶店に入ったと記憶する。
コーヒーを飲みながら、これからやるべきことを再確認する。なによりも最優先すべきは人集めである。これは年長者でSFファンに知り合いも多い小生がメインで行わなければならない。
喫茶店を出た、そこにあった公衆電話(もちろん当時は携帯電話はなかった)で、小生は3人の人物に電話した。小浜徹也(現東京創元社編集部)、高橋章子(現三村美衣)そして清水宏祐の3人である。小浜は当時星群の会員であり京大SF研にも所属している大変に活動的なSFファンであった。高橋は菅浩江と同じく幼くして星群に入会、活発な女性SFファンであった。清水宏祐は1975年の第14回日本SF大会SHICONの実行委員長を務めた。SF大会を実行した経験者である。
3人とも、唐突な話であるとびっくりしたが、とりあえず、この3人はわれわれの企てを聞いてくれた。もちろん、ただ2年後にSF大会をやるということしか、なんにも決まっていない。当然、賛同も賛成もしていない。当然である。とりあえず、今月中(1984年8月)に、どっかで集まろうということになった。
清水はSHICON終了後SFファンダムから離れていた。当時はVOC(ビデオ・オーナーズ・クラブ)という映像関係の同好会を主宰していた。当時はビデオデッキを所有している人たちで、かような会をやっていたのだ。それだけビデオデッキを持っている人は多くなかったということ。
思えば、この小生の電話で清水を9年ぶりにSFファンダムに引き戻したわけだ。その清水に相談する。ホワイトローズという喫茶店がいいと推奨してくれた。
星群の会ホームページ連載の「SFマガジン思い出帳」が更新されました。どうぞご覧になってください。
新大阪で新幹線を降りて、在来線で大阪まで来て、やっと関西へ帰って来たと実感する。とりあえずどっかで一休みしようということで、確か、阪急三番街の喫茶店に入ったと記憶する。
コーヒーを飲みながら、これからやるべきことを再確認する。なによりも最優先すべきは人集めである。これは年長者でSFファンに知り合いも多い小生がメインで行わなければならない。
喫茶店を出た、そこにあった公衆電話(もちろん当時は携帯電話はなかった)で、小生は3人の人物に電話した。小浜徹也(現東京創元社編集部)、高橋章子(現三村美衣)そして清水宏祐の3人である。小浜は当時星群の会員であり京大SF研にも所属している大変に活動的なSFファンであった。高橋は菅浩江と同じく幼くして星群に入会、活発な女性SFファンであった。清水宏祐は1975年の第14回日本SF大会SHICONの実行委員長を務めた。SF大会を実行した経験者である。
3人とも、唐突な話であるとびっくりしたが、とりあえず、この3人はわれわれの企てを聞いてくれた。もちろん、ただ2年後にSF大会をやるということしか、なんにも決まっていない。当然、賛同も賛成もしていない。当然である。とりあえず、今月中(1984年8月)に、どっかで集まろうということになった。
清水はSHICON終了後SFファンダムから離れていた。当時はVOC(ビデオ・オーナーズ・クラブ)という映像関係の同好会を主宰していた。当時はビデオデッキを所有している人たちで、かような会をやっていたのだ。それだけビデオデッキを持っている人は多くなかったということ。
思えば、この小生の電話で清水を9年ぶりにSFファンダムに引き戻したわけだ。その清水に相談する。ホワイトローズという喫茶店がいいと推奨してくれた。
星群の会ホームページ連載の「SFマガジン思い出帳」が更新されました。どうぞご覧になってください。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
とつぜんSFノート 第106回
小生はSFファンだ。もうずいぶん長いことSFファンをやっている。そうだな、50年は超えているだろう。昨日今日のSFファンではない。小生はただのSFファンではあるが、今も新作を発表している現役のSF作家でも、小生より年長のSF作家は、眉村卓さんと筒井康隆さんのお二方ぐらいではないだろうか。
小生がSFを読み始めたころはSFの地位はまだまだ確立されていなかった。SFマガジン創刊から、まだ10年経っていなかった。柴野拓美氏、矢野徹氏、福島正実氏たちの尽力によって、日本のSFはやっと巣から飛び立とうとする雛鳥であった。SFに対する世の偏見はまだ根強く残っていて、初代SFマガジン編集長で「SFの鬼」福島正実氏は、SFに対する偏見は絶対に見逃さなかった。そして、かような偏見を見つけると、こまめに的確に反論していた。その後、福島氏はあまりに妥協のない言動ゆえかSFマガジン編集長の職を辞し早川書房を去った。その後ほどなく福島氏は早世する。
小生がSFファンになったころの日本のSFはかような状況であった。だによって、小生はSFファンとしての幼少期、SFは渡世の裏街道を行く日陰者であったのだ。
それから幾星霜、日本のSFは諸先輩方の努力で、日本の文化文芸において確固たる地位を築いた。
と、ここまで書いて、われながらオジンだなあと思う。いつまで、SFは日陰者との認識をもっているのか。リストラされいくつもの会社を渡り歩いた、お前が自分のことを日陰者と思ってイジケテいるのではないか。と、問われれば、少々、否定はしにくいかも知れない。
ところが現実の日本のSFは、70年代に筒井さんがいった「SFの浸透と拡散」が充分に行き渡り、SFはことさらSFSFといわなくても、小説や漫画といった印刷媒体、映画、アニメといった映像媒体に、ごく自然に遍在している。今の若いもん(こんなことをいうのはオジンの証拠だ)はSFなんて意識していないのだ。ことさらSFを意識しなくても、ごく自然にSFが身の回りにあるわけ。
こういう現代において、いつまでも大昔の認識を引きずって、「あ、これはSFだ」「これはSFでない」なんていってるワシら年寄りは老害といってもいいかも知れない。とはいいつつも、いまさら治せん。古狸は古狸のままSFファンをやっていこう。
小生がSFを読み始めたころはSFの地位はまだまだ確立されていなかった。SFマガジン創刊から、まだ10年経っていなかった。柴野拓美氏、矢野徹氏、福島正実氏たちの尽力によって、日本のSFはやっと巣から飛び立とうとする雛鳥であった。SFに対する世の偏見はまだ根強く残っていて、初代SFマガジン編集長で「SFの鬼」福島正実氏は、SFに対する偏見は絶対に見逃さなかった。そして、かような偏見を見つけると、こまめに的確に反論していた。その後、福島氏はあまりに妥協のない言動ゆえかSFマガジン編集長の職を辞し早川書房を去った。その後ほどなく福島氏は早世する。
小生がSFファンになったころの日本のSFはかような状況であった。だによって、小生はSFファンとしての幼少期、SFは渡世の裏街道を行く日陰者であったのだ。
それから幾星霜、日本のSFは諸先輩方の努力で、日本の文化文芸において確固たる地位を築いた。
と、ここまで書いて、われながらオジンだなあと思う。いつまで、SFは日陰者との認識をもっているのか。リストラされいくつもの会社を渡り歩いた、お前が自分のことを日陰者と思ってイジケテいるのではないか。と、問われれば、少々、否定はしにくいかも知れない。
ところが現実の日本のSFは、70年代に筒井さんがいった「SFの浸透と拡散」が充分に行き渡り、SFはことさらSFSFといわなくても、小説や漫画といった印刷媒体、映画、アニメといった映像媒体に、ごく自然に遍在している。今の若いもん(こんなことをいうのはオジンの証拠だ)はSFなんて意識していないのだ。ことさらSFを意識しなくても、ごく自然にSFが身の回りにあるわけ。
こういう現代において、いつまでも大昔の認識を引きずって、「あ、これはSFだ」「これはSFでない」なんていってるワシら年寄りは老害といってもいいかも知れない。とはいいつつも、いまさら治せん。古狸は古狸のままSFファンをやっていこう。
コメント ( 12 ) | Trackback ( 0 )
とつぜんSFノート 第105回
真夏の京都は暑い。真夏はどこでも暑いが、京都の真夏は底意地の悪い暑さだ。星群祭は酔狂にもその真夏の京都で行われた。1984年、京都にも真夏はあった。そして、この年も星群祭はあった。
1984年7月15日第11回星群祭が行われた。会場はいつもの京大会館。う~む。阪神タイガース日本一の前年だ。テーマは「小説のことば」ゲストは石川英輔氏・風見潤氏・志賀隆生氏・柴野拓美氏・新戸雅章氏・巽孝之氏・安田均氏。
オープン制の前日合宿はこの時も行われた。東山の旅館「きのゑ」に70人で泊まりこんだ。創作教室、麻雀、夕食、酒盛り、自己紹介大会、深夜の女性3人による酒買出し事件、原稿書き、原稿督促、ゲーム、オークション、情報交換、ゴシップ交換、わる口交換、翌日の打ち合わせ、電話連絡、仕事いいつける、仕事いいつけられる、睡眠。と、楽しい一夜をすごしたのである。
さて、楽しい一夜が開け星群祭当日となった。二日酔頭をかかえて京大会館へ向かう。定刻の午前10時開会。開会宣言で椎原実行委員長が今回のテーマについて説明。
「物質の基本要素が原子であるように、小説の基本要素はことばである。小説というモノを考える時、このことばというモノを考える必要がある」
この第11回星群祭はパネルディスカッション形式で行われた。
パネルディスカッション1 翻訳家編
パネラー/柴野拓美氏、安田均氏、風見潤氏、桐山芳男氏、米村秀雄氏 司会/椎原豊氏
「作家と翻訳家はことばの見つけ方が違う。作家はそれでなくてはならないことばを見つける。翻訳家はいくつかの選択肢から選ぶ」
「原作を原語で読んだイメージを日本語で伝える」
「普通小説とSFでは訳す違いはある。SFにおけることばの特殊性はたくさんある」
パネルディスカッション2 編集者編
パネラー/柴野拓美氏、村上栄次氏、椎原豊氏 司会/信次秀郎氏
「小説の体をなしているかをまずチェック。その後アイデア、テーマを吟味する」
「あえて編集カラーは出さない」
「私の目にあったモノを通すから、おのずと編集カラーは出てくる」
「私の雑誌と違うカラーの作品が送られて来る時がある。どういう雑誌か投稿前に知るべきだ」
「文章を書く上で基本的なことを教えるのも編集者の仕事」
パネルディスカッション3 作家編
パネラー/石川英輔氏、石飛卓美氏、石坪光司氏、松本富雄氏 司会/村上栄次氏
「なぜSFを書くか」
「そこにSFがあったから」
「自分のイメージを全部伝えたいがムリがある。わりきった」
「別世界を書くのが好き」
「SFを書く時、特別なことばを使わないように気をつけている」
「特殊な状況を一般の人にもわかるように書くのも腕のみせどころ」
パネルディスカッション4 批評家編
パネラー/新戸雅章氏、信次秀郎氏、巽孝之氏、椎原豊氏、志賀隆生氏 司会/小浜徹也氏
「ファン創作を読むのは苦か楽か」
「批評を行う時はプロ、アマ区別しない」
「作品より作家を見るように心がけている」
「ファン創作の場合、まれに天才が現れる」
最後のプログラムは星群祭吉例。ノベルズ批評。事前に参加者、ゲスト全員に配布された星群ノベルズ№9「光の賢者」を俎上に上げて、ゲスト諸氏より忌憚のない厳しい批評が加えられる。なお、この№9掲載の石飛卓美「ミネルヴァの森話」はSFアドベンチャーに転載。ファンジン大賞創作部門受賞を受賞した。
このころの星群ノベルズはSF作家への登竜門としての役割を果たしていた。
1980年.星群ノベルズ№5「塔とう名の箱舟」石坪光司「塔-75」SFアドベンチャーに転載。菅浩江「ブルーフライト」SF宝石に転載。
1983年、星群ノベルズ№8「伝説・永劫都市」虚青裕「影に満ちる領主の星」SFアドベンチャーに転載。
星群祭というイベントも日本のSFにある程度の貢献を果たしたといえよう。
1984年7月15日第11回星群祭が行われた。会場はいつもの京大会館。う~む。阪神タイガース日本一の前年だ。テーマは「小説のことば」ゲストは石川英輔氏・風見潤氏・志賀隆生氏・柴野拓美氏・新戸雅章氏・巽孝之氏・安田均氏。
オープン制の前日合宿はこの時も行われた。東山の旅館「きのゑ」に70人で泊まりこんだ。創作教室、麻雀、夕食、酒盛り、自己紹介大会、深夜の女性3人による酒買出し事件、原稿書き、原稿督促、ゲーム、オークション、情報交換、ゴシップ交換、わる口交換、翌日の打ち合わせ、電話連絡、仕事いいつける、仕事いいつけられる、睡眠。と、楽しい一夜をすごしたのである。
さて、楽しい一夜が開け星群祭当日となった。二日酔頭をかかえて京大会館へ向かう。定刻の午前10時開会。開会宣言で椎原実行委員長が今回のテーマについて説明。
「物質の基本要素が原子であるように、小説の基本要素はことばである。小説というモノを考える時、このことばというモノを考える必要がある」
この第11回星群祭はパネルディスカッション形式で行われた。
パネルディスカッション1 翻訳家編
パネラー/柴野拓美氏、安田均氏、風見潤氏、桐山芳男氏、米村秀雄氏 司会/椎原豊氏
「作家と翻訳家はことばの見つけ方が違う。作家はそれでなくてはならないことばを見つける。翻訳家はいくつかの選択肢から選ぶ」
「原作を原語で読んだイメージを日本語で伝える」
「普通小説とSFでは訳す違いはある。SFにおけることばの特殊性はたくさんある」
パネルディスカッション2 編集者編
パネラー/柴野拓美氏、村上栄次氏、椎原豊氏 司会/信次秀郎氏
「小説の体をなしているかをまずチェック。その後アイデア、テーマを吟味する」
「あえて編集カラーは出さない」
「私の目にあったモノを通すから、おのずと編集カラーは出てくる」
「私の雑誌と違うカラーの作品が送られて来る時がある。どういう雑誌か投稿前に知るべきだ」
「文章を書く上で基本的なことを教えるのも編集者の仕事」
パネルディスカッション3 作家編
パネラー/石川英輔氏、石飛卓美氏、石坪光司氏、松本富雄氏 司会/村上栄次氏
「なぜSFを書くか」
「そこにSFがあったから」
「自分のイメージを全部伝えたいがムリがある。わりきった」
「別世界を書くのが好き」
「SFを書く時、特別なことばを使わないように気をつけている」
「特殊な状況を一般の人にもわかるように書くのも腕のみせどころ」
パネルディスカッション4 批評家編
パネラー/新戸雅章氏、信次秀郎氏、巽孝之氏、椎原豊氏、志賀隆生氏 司会/小浜徹也氏
「ファン創作を読むのは苦か楽か」
「批評を行う時はプロ、アマ区別しない」
「作品より作家を見るように心がけている」
「ファン創作の場合、まれに天才が現れる」
最後のプログラムは星群祭吉例。ノベルズ批評。事前に参加者、ゲスト全員に配布された星群ノベルズ№9「光の賢者」を俎上に上げて、ゲスト諸氏より忌憚のない厳しい批評が加えられる。なお、この№9掲載の石飛卓美「ミネルヴァの森話」はSFアドベンチャーに転載。ファンジン大賞創作部門受賞を受賞した。
このころの星群ノベルズはSF作家への登竜門としての役割を果たしていた。
1980年.星群ノベルズ№5「塔とう名の箱舟」石坪光司「塔-75」SFアドベンチャーに転載。菅浩江「ブルーフライト」SF宝石に転載。
1983年、星群ノベルズ№8「伝説・永劫都市」虚青裕「影に満ちる領主の星」SFアドベンチャーに転載。
星群祭というイベントも日本のSFにある程度の貢献を果たしたといえよう。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
とつぜんSFノート 第104回
関西のSF界は上方落語とたいへん親和性が強い。お江戸のSF界はどうかな。不勉強にてよく知らないが、落語好きは横田順彌氏ぐらいではないだろうか。確か横田氏は法政大学落語研究会の出身だった。
関西では落語好きのSF関係者が多い。小松左京氏は桂米朝師匠と終生変わらぬ親交を深めておられた。堀晃氏、かんべむさし氏、田中啓文氏たちも落語好きで落語への造詣もたいへんに深い。
また、関西でSF関係の大きなイベントが行われる時には、上方の落語家が呼ばれて1席高座が設けられることが多い。
1975年神戸で開催された第14回日本SF大会では、桂米朝師匠が「地獄八景亡者戯」を演じた。小生、この時、生まれて初めて米朝師匠の「地獄八景」を生で観た。
1979年の第4回日本SFショーでは桂枝雀師匠、1985年神戸で開かれた第11回日本SFフェスティバルでは桂春輔師匠、1986年の第25回日本SF大会では桂吉朝師匠が高座を務めていた。
最近は関西で日本SF大会は開かれていないが、もしDAICON8(だれか関西の元気のいいSFファンがやってくれないかな。小生、足痛、尿酸値高め、高血圧をおしてなんとか参加するぞ)が開催されるのなら、きっとその時の旬の上方落語家の高座を見られるであろう。今ならだれかな笑福亭たまさんあたりはどうかな。
なぜ関西のSF界と上方落語は親和性が強いのか。これを理解するキーワードは「いちびり」ということではないか。「いちびり」関西弁である。ふざける、ちょうしにのる、といった意味だ。
上方落語は元は大道芸であった。江戸落語はお座敷芸であるが、上方落語は、初代露の五郎兵衛とか米沢彦八といった芸人が道端に簡単な演台を設けて道行く人に、語りかけ投げ銭を得てた。江戸落語のようにお座敷に座っている人相手ではなく、道行く人の足を止め、耳を傾けさせ、投げ銭までしてもらおうというのである。ハデに陽気にやらなくてはならない。だから上方落語は見台ひざかくしを置き、ハリせん、小拍子を使って、パチパチと大きな音をたて、下座ではカネや笛三味線でハメモノが入るのである。ようするに上方落語はハデで陽気で濃い笑いをとるのである。これを演じる演者の上方の噺家自身も「いちびり」であることが必須条件である。
SFもまた「いちびり」なジャンルの文芸ではないか。小生が考えるSFのキモは「センス・オブ・ワンダー」だ。「びっくり素敵」といえばいいだろうか。「びっくり」のないSFはSFとはいえないだろう。人をびっくりさせようと思えば、その人は「いちびり」でなければならない。冒頭にあげたSF作家諸氏は失礼ながら、みなさん「いちびり」である。
関西では落語好きのSF関係者が多い。小松左京氏は桂米朝師匠と終生変わらぬ親交を深めておられた。堀晃氏、かんべむさし氏、田中啓文氏たちも落語好きで落語への造詣もたいへんに深い。
また、関西でSF関係の大きなイベントが行われる時には、上方の落語家が呼ばれて1席高座が設けられることが多い。
1975年神戸で開催された第14回日本SF大会では、桂米朝師匠が「地獄八景亡者戯」を演じた。小生、この時、生まれて初めて米朝師匠の「地獄八景」を生で観た。
1979年の第4回日本SFショーでは桂枝雀師匠、1985年神戸で開かれた第11回日本SFフェスティバルでは桂春輔師匠、1986年の第25回日本SF大会では桂吉朝師匠が高座を務めていた。
最近は関西で日本SF大会は開かれていないが、もしDAICON8(だれか関西の元気のいいSFファンがやってくれないかな。小生、足痛、尿酸値高め、高血圧をおしてなんとか参加するぞ)が開催されるのなら、きっとその時の旬の上方落語家の高座を見られるであろう。今ならだれかな笑福亭たまさんあたりはどうかな。
なぜ関西のSF界と上方落語は親和性が強いのか。これを理解するキーワードは「いちびり」ということではないか。「いちびり」関西弁である。ふざける、ちょうしにのる、といった意味だ。
上方落語は元は大道芸であった。江戸落語はお座敷芸であるが、上方落語は、初代露の五郎兵衛とか米沢彦八といった芸人が道端に簡単な演台を設けて道行く人に、語りかけ投げ銭を得てた。江戸落語のようにお座敷に座っている人相手ではなく、道行く人の足を止め、耳を傾けさせ、投げ銭までしてもらおうというのである。ハデに陽気にやらなくてはならない。だから上方落語は見台ひざかくしを置き、ハリせん、小拍子を使って、パチパチと大きな音をたて、下座ではカネや笛三味線でハメモノが入るのである。ようするに上方落語はハデで陽気で濃い笑いをとるのである。これを演じる演者の上方の噺家自身も「いちびり」であることが必須条件である。
SFもまた「いちびり」なジャンルの文芸ではないか。小生が考えるSFのキモは「センス・オブ・ワンダー」だ。「びっくり素敵」といえばいいだろうか。「びっくり」のないSFはSFとはいえないだろう。人をびっくりさせようと思えば、その人は「いちびり」でなければならない。冒頭にあげたSF作家諸氏は失礼ながら、みなさん「いちびり」である。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
とつぜんSFノート 第103回
遥かな旅路であった。北海道から関西まで。空路を使わず旅をする。その遥かなる旅路すら、われわれが行う第25回日本SF大会DAICON5までの2年間の旅に比べれば、助走にすぎない。
そんなわけで飛行機に乗りそこなった、われわれ4人は列車を乗り継いで北海道から関西へ帰ることになった。
札幌から函館までの列車で、列車の冷房が故障するという経験をしたりして、なんとか函館までたどり着いた。
当時は青函トンネルなんてハイカラなもんはなかった。船である。青函連絡船で津軽海峡を渡った。
船室は一番安い船室だったと記憶する。船底である。沈没すれば確実に死ねる場所だ。「ポセイドン・アドベンチャー」のように船がひっくりかえれば、助かるかもしれない。
われわれのいた所は、船底の安い船室の中でももっとも居心地の悪い場所であった。エンジンルームのすぐ近く。船の巨大なディーゼルエンジンのゴトゴトゴトという音と振動が休むことなく響いていた。
さだかな記憶ではないが、船室は畳敷きであった。そこにゴロリンと寝転がって、ひたすら時間が経過するのを待つ。ゴトゴトゴトゴト。船舶用ディーゼルエンジンの単調な音が聞こえる。退屈なので外に出る。夜の航海であった。真っ暗でなにも見えない。4時間ほどの航海であったと記憶する。
青森に着いた。もちろん東北新幹線はない。在来線で東京まで。この車中で2年後に行う第25回日本SF大会の方向性を話し合った。4人の基本的な認識は、DAICON5をお祭騒ぎにはせず、サーコンなSF大会とすること。このあたりのことは第99回で書いた。
青森から東京までは遠かった。やっと東京に着いたときは、ホッとした。東京からは、さすがに新幹線に乗った。ほんと、やれやれである。
新大阪まで3時間とちょっと。青函連絡船で函館から青森に行くより早い。あっという間に新大阪。新幹線のありがたさがよくわかった。
さて、関西に帰って来た。まずやるべきことは実行委員会の組織作り。この時点では第25回日本SF大会実行委員会の委員は4人だけ。このうち星群のYSは星群の仕事に専念するためSF大会にはかかわらないことになった。あとは小生と山根啓史と山根の同人誌仲間の若いの。
イベントの実行委員会の組織作りは、人脈が重要である。この3人の中で一番の年長でファンダム歴が長いのは小生である。手持ちの人脈をフルに活用する必要があると考える。
小生は大阪に着いて、まず3人に電話した。
そんなわけで飛行機に乗りそこなった、われわれ4人は列車を乗り継いで北海道から関西へ帰ることになった。
札幌から函館までの列車で、列車の冷房が故障するという経験をしたりして、なんとか函館までたどり着いた。
当時は青函トンネルなんてハイカラなもんはなかった。船である。青函連絡船で津軽海峡を渡った。
船室は一番安い船室だったと記憶する。船底である。沈没すれば確実に死ねる場所だ。「ポセイドン・アドベンチャー」のように船がひっくりかえれば、助かるかもしれない。
われわれのいた所は、船底の安い船室の中でももっとも居心地の悪い場所であった。エンジンルームのすぐ近く。船の巨大なディーゼルエンジンのゴトゴトゴトという音と振動が休むことなく響いていた。
さだかな記憶ではないが、船室は畳敷きであった。そこにゴロリンと寝転がって、ひたすら時間が経過するのを待つ。ゴトゴトゴトゴト。船舶用ディーゼルエンジンの単調な音が聞こえる。退屈なので外に出る。夜の航海であった。真っ暗でなにも見えない。4時間ほどの航海であったと記憶する。
青森に着いた。もちろん東北新幹線はない。在来線で東京まで。この車中で2年後に行う第25回日本SF大会の方向性を話し合った。4人の基本的な認識は、DAICON5をお祭騒ぎにはせず、サーコンなSF大会とすること。このあたりのことは第99回で書いた。
青森から東京までは遠かった。やっと東京に着いたときは、ホッとした。東京からは、さすがに新幹線に乗った。ほんと、やれやれである。
新大阪まで3時間とちょっと。青函連絡船で函館から青森に行くより早い。あっという間に新大阪。新幹線のありがたさがよくわかった。
さて、関西に帰って来た。まずやるべきことは実行委員会の組織作り。この時点では第25回日本SF大会実行委員会の委員は4人だけ。このうち星群のYSは星群の仕事に専念するためSF大会にはかかわらないことになった。あとは小生と山根啓史と山根の同人誌仲間の若いの。
イベントの実行委員会の組織作りは、人脈が重要である。この3人の中で一番の年長でファンダム歴が長いのは小生である。手持ちの人脈をフルに活用する必要があると考える。
小生は大阪に着いて、まず3人に電話した。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
とつぜんSFノート 第102回
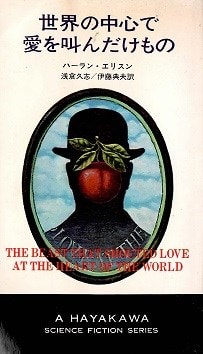
ハーラン・エリスンが亡くなった。享年84歳。そうかエリスンがもう84歳だったのか。しかも亡くなったのか。
人間だれでも歳を取るし、亡くなる。しかし、この事実とエリスンはどうも違和感がある。他の人ならいざ知らず、エリスンが歳取ってなくなる。不思議な感じだ。
今の若い人はベタな恋愛小説の元ネタの作者ぐらいの認識しかないかも知れないが。エリスンの小説をSFマガジンでリアルタイムで読んでいた、小生のごとき古狸SFファンはハーラン・エリスンといえば、アメリカSF界の大スターであった。
才人とはエリスンのような人をいうのだろう。ヒューゴー賞、ネビュラ賞、ローカス賞、そしてもちろん日本の星雲賞海外部門、主たるSFの賞の大常連にして受賞した賞は凄まじいばかりの数である。エリスンの才能はSFばかりではない。「スタートレック」「アウターリミッツ」「ラット・パトロール」など数多のテレビドラマの脚本を書き、まさに八面六臂の大活躍である。
人間、賞を取ったら大人しくなるとか。福本豊さんは国民栄誉賞を打診された時「そんなんもろたら立ちしょんべんもでけへん」といったとか。エリスンは違う。立ちしょんべんはしたかしてないか知らないが。アメリカSF界一のカリスマであり、たいへんなごんたくれ。問題児、トリックスターなる立居地は維持していた。
その戦闘的な姿勢は仕事にもあらわれていて、「危険なビジョン」なんて先鋭的なアンソロジーを編んでいる。
「死の鳥」は読もうと思って買ってある。読まなくっちゃ。
ハーラン・エリスンさんのご冥福をお祈りする。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
とつぜんSFノート 第101回
第9回星群祭は星群の会創立10周年の記念で、2日間の拡大バージョンであった。その翌年1983年第10回星群祭は通常の1日バージョンの星群祭であった。日時は1983年7月24日(日曜)会場は京大会館。
例によって真夏のイベントである。それでなくても暑い7月下旬。場所が京都。京都の真夏は底意地の悪い暑さである。
第10回星群祭のテーマは「ジュヴィナイルというもの」ゲストは、新井素子、荒巻義雄、風見潤、柴野拓美、巽孝之、豊田有恒、堀晃、眉村卓、安田均の各氏。あいかわずの多彩なゲスト陣である。
24日の本会に先立って、オープン制の合宿が行われた。宿は祇園のきのえ。ここは星群祭の定宿である。風見潤氏の創作教室、柴野拓美氏のフリートーク。そして当時は星群の同人であった山本弘氏による大ロールプレイングゲーム大会が行われた。もちろん酒つきである。星群の、というか小生の知ってる限り、しらふのSFファンの合宿は寡聞にして知らない。
さて翌朝、いささか二日酔いぎみの頭をかかえつつ京大会館へ向かう。実行委員長の開会あいさつ。この時の実行委員長はアマチュア時代の水野良が務めた。
午前の最初の講演者は豊田有恒氏。福島正実氏をはじめ、第一期のSF作家たちが情熱をそそいだ、昔の児童向けSFはあまり良い環境ではなかった、俗悪な「大衆児童文学」と「純児童文学」サイドから白眼視されていた。その昔のSFジュビナイルを支えたのが学習誌であった。また、アニメのノベライズもあまり良い条件ではなかった。
柴野拓美氏。アメリカのSFにはジュビナイルというカテゴリーはなかった。なぜならSF全部がジュビナイルであったから。SFがジュビナイルでなくなったのは60年代ニューウェーブの洗礼を受けてからだ。
午前中の最後は風見潤氏。翻訳、翻案の発想の話を交えつつ、ジュビナイルのお話。最近のジュビナイルは、決してSF入門とは同義語ではない。
昼食。昼休みはファンジン即売が行われた。
午後の最初は新井素子氏。ある意味新井氏の登場が日本のSFジュビナイルの本格的夜明けであったといえる。その新井氏の講演。話し相手は堀晃氏が務めた。
「いまやジュビナイルというコバルトの新井さんというイメージですが」
「ジュビナイルと意識して書いたことはない。自分と同世代の女の子に読まれたいと思って書いてきた」
安田均氏。従来の「大人が与えるもの」「大人もの」の、「子供だまし」でもない。生物的にいうと「幼形成体」というイメージではないか。
辻真先氏が一般参加者として参加されていた。ごあいさつをいただく。
荒巻義雄氏は「時代に敏感たれ」とおっしゃった。子供にも判り、なおかつ大人が読んでも面白いもの。なんど読んでも新しい発見があるモノが名作だ。「宝島」が好例。ジュビナイルを書く人は「宝島」を座右の書とすべし。
巽孝之氏。「子供/大人」を直線と並列でとらえる読み方が必要。
さて、この星群祭最後の講演は眉村卓氏。ジュビナイルを書く時は、自分の子供時代に頼るが、昔の子供と今の子供は違う。児童文学は、読む側の心理を考えて書かれるが、ジュビナイルはマーケティングを考慮して書かれがちだが、読者の新しい方向性を打ち出す必要がある。
最後に全員参加のパネルディスカッションを行って、第10回星群祭は無事終了した。
例によって真夏のイベントである。それでなくても暑い7月下旬。場所が京都。京都の真夏は底意地の悪い暑さである。
第10回星群祭のテーマは「ジュヴィナイルというもの」ゲストは、新井素子、荒巻義雄、風見潤、柴野拓美、巽孝之、豊田有恒、堀晃、眉村卓、安田均の各氏。あいかわずの多彩なゲスト陣である。
24日の本会に先立って、オープン制の合宿が行われた。宿は祇園のきのえ。ここは星群祭の定宿である。風見潤氏の創作教室、柴野拓美氏のフリートーク。そして当時は星群の同人であった山本弘氏による大ロールプレイングゲーム大会が行われた。もちろん酒つきである。星群の、というか小生の知ってる限り、しらふのSFファンの合宿は寡聞にして知らない。
さて翌朝、いささか二日酔いぎみの頭をかかえつつ京大会館へ向かう。実行委員長の開会あいさつ。この時の実行委員長はアマチュア時代の水野良が務めた。
午前の最初の講演者は豊田有恒氏。福島正実氏をはじめ、第一期のSF作家たちが情熱をそそいだ、昔の児童向けSFはあまり良い環境ではなかった、俗悪な「大衆児童文学」と「純児童文学」サイドから白眼視されていた。その昔のSFジュビナイルを支えたのが学習誌であった。また、アニメのノベライズもあまり良い条件ではなかった。
柴野拓美氏。アメリカのSFにはジュビナイルというカテゴリーはなかった。なぜならSF全部がジュビナイルであったから。SFがジュビナイルでなくなったのは60年代ニューウェーブの洗礼を受けてからだ。
午前中の最後は風見潤氏。翻訳、翻案の発想の話を交えつつ、ジュビナイルのお話。最近のジュビナイルは、決してSF入門とは同義語ではない。
昼食。昼休みはファンジン即売が行われた。
午後の最初は新井素子氏。ある意味新井氏の登場が日本のSFジュビナイルの本格的夜明けであったといえる。その新井氏の講演。話し相手は堀晃氏が務めた。
「いまやジュビナイルというコバルトの新井さんというイメージですが」
「ジュビナイルと意識して書いたことはない。自分と同世代の女の子に読まれたいと思って書いてきた」
安田均氏。従来の「大人が与えるもの」「大人もの」の、「子供だまし」でもない。生物的にいうと「幼形成体」というイメージではないか。
辻真先氏が一般参加者として参加されていた。ごあいさつをいただく。
荒巻義雄氏は「時代に敏感たれ」とおっしゃった。子供にも判り、なおかつ大人が読んでも面白いもの。なんど読んでも新しい発見があるモノが名作だ。「宝島」が好例。ジュビナイルを書く人は「宝島」を座右の書とすべし。
巽孝之氏。「子供/大人」を直線と並列でとらえる読み方が必要。
さて、この星群祭最後の講演は眉村卓氏。ジュビナイルを書く時は、自分の子供時代に頼るが、昔の子供と今の子供は違う。児童文学は、読む側の心理を考えて書かれるが、ジュビナイルはマーケティングを考慮して書かれがちだが、読者の新しい方向性を打ち出す必要がある。
最後に全員参加のパネルディスカッションを行って、第10回星群祭は無事終了した。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
とつぜんSFノート 第100回
小生、SFファンとなってずいぶん経つ。そうだな。ファン歴は半世紀に近いかな。子供のころから、この年になるまで、ずっとSFファンをやってきた。
小生、あくまでSFの愛好家であってプロではない。SFでメシを食っているわけではない。SFは趣味でありアマチュアである。では、小生はなにして食って家族を養っているのか。小生の本業はなにかと聞かれれば、資材購買であろう。
若いころはコピーライターをしていた。広告制作の足を洗ってから、ずっと資材とか購買仕入れといった仕事をかれこれ30年やっている。今の会社でも購買屋である。
広告業界から転身して、最初に入った会社では電子部品を扱った。まず最初は在庫管理から。抵抗、コンデンサー、半導体、コネクター、リレー、スイッチ、コイル、基板。電子部品の種類はものすごく多い。それら覚えていかなくてはならない。これらの品物は小さなモノが多い。ほとんどのモノが手のひらに乗る。それを1つ1つ目で見て手でさわって(中には素手でさわってはいけないモノもある)覚えるのだ。コネクターで最もよく扱ったヒロセ電機のサミコンなら、小生は手で握っただけでも型名がわかる。
在庫管理と購買は両輪。在庫管理がまともにできない者は購買もできない。そらそうだろう。在庫量を把握してないで、どうして発注数が決められる。
在庫管理で最も大切なことは先入れ先出しということ。先に仕入れた品物から払い出していくということ。以前、こんなことがあった。某大手の菓子メーカーでのこと。菓子の原材料の残が少なくなった。購買が発注。納品された。納品された原材料を残の原材料の上に置いて保管。上の原材料から使っていって、下の古いモノは古くなる一方。で、たまたまこの下の古い原材料を使って菓子を製造。品質が悪い菓子となって問題となった。
かようなことは資材の人間としては絶対にしてはならない。ゆえにモノを発注するのならば、まず倉庫の整理からしなければならない。残と新に入荷するモノをはっきりと区分するようにしなければならないのである。
さて、購買である。在庫管理業務は社内だけで完結する。購買業務はそうではない。購買とは読んで字のごとくモノを買う仕事である。当然、仕入先がある。購買を行うにおいて、最も大切なことは仕入先といかに良好な関係を築くかということだ。厳に慎まなくてはいけないことは、「買ってやるんだ」という意識を持つこと。買う方がえらく売る方が下ということは決してない。購買と営業はあいみたがい、お互いさまである。こっちは会社の仕事でモノを買う、営業も会社の仕事でモノを売っているのだ。お互い会社のカネでモノを買い、モノを売って会社のカネとしているのである。
だから、小生、30年購買をやってきて、仕入先には損はさせていない。もちろん小生も自分の会社のカネを使うのだ、極力安く買うのはもちろんである。しかし、仕入先に損をさせてまで仕入れるのは良くない。複数の仕入先に見積もりを出してもらい、極端に安い見積もりを出した仕入先には発注しない。損を出してなければ、そこに発注するが、あきらかに損を覚悟で見積もりを出した業者には発注しない。取引先、仕入先とは長い良好な関係を続けたい。そんなムリをしている所とはいびつな関係になってしまうからである。
小生、あくまでSFの愛好家であってプロではない。SFでメシを食っているわけではない。SFは趣味でありアマチュアである。では、小生はなにして食って家族を養っているのか。小生の本業はなにかと聞かれれば、資材購買であろう。
若いころはコピーライターをしていた。広告制作の足を洗ってから、ずっと資材とか購買仕入れといった仕事をかれこれ30年やっている。今の会社でも購買屋である。
広告業界から転身して、最初に入った会社では電子部品を扱った。まず最初は在庫管理から。抵抗、コンデンサー、半導体、コネクター、リレー、スイッチ、コイル、基板。電子部品の種類はものすごく多い。それら覚えていかなくてはならない。これらの品物は小さなモノが多い。ほとんどのモノが手のひらに乗る。それを1つ1つ目で見て手でさわって(中には素手でさわってはいけないモノもある)覚えるのだ。コネクターで最もよく扱ったヒロセ電機のサミコンなら、小生は手で握っただけでも型名がわかる。
在庫管理と購買は両輪。在庫管理がまともにできない者は購買もできない。そらそうだろう。在庫量を把握してないで、どうして発注数が決められる。
在庫管理で最も大切なことは先入れ先出しということ。先に仕入れた品物から払い出していくということ。以前、こんなことがあった。某大手の菓子メーカーでのこと。菓子の原材料の残が少なくなった。購買が発注。納品された。納品された原材料を残の原材料の上に置いて保管。上の原材料から使っていって、下の古いモノは古くなる一方。で、たまたまこの下の古い原材料を使って菓子を製造。品質が悪い菓子となって問題となった。
かようなことは資材の人間としては絶対にしてはならない。ゆえにモノを発注するのならば、まず倉庫の整理からしなければならない。残と新に入荷するモノをはっきりと区分するようにしなければならないのである。
さて、購買である。在庫管理業務は社内だけで完結する。購買業務はそうではない。購買とは読んで字のごとくモノを買う仕事である。当然、仕入先がある。購買を行うにおいて、最も大切なことは仕入先といかに良好な関係を築くかということだ。厳に慎まなくてはいけないことは、「買ってやるんだ」という意識を持つこと。買う方がえらく売る方が下ということは決してない。購買と営業はあいみたがい、お互いさまである。こっちは会社の仕事でモノを買う、営業も会社の仕事でモノを売っているのだ。お互い会社のカネでモノを買い、モノを売って会社のカネとしているのである。
だから、小生、30年購買をやってきて、仕入先には損はさせていない。もちろん小生も自分の会社のカネを使うのだ、極力安く買うのはもちろんである。しかし、仕入先に損をさせてまで仕入れるのは良くない。複数の仕入先に見積もりを出してもらい、極端に安い見積もりを出した仕入先には発注しない。損を出してなければ、そこに発注するが、あきらかに損を覚悟で見積もりを出した業者には発注しない。取引先、仕入先とは長い良好な関係を続けたい。そんなムリをしている所とはいびつな関係になってしまうからである。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ |



