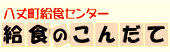みなさま、こんにちは!海風おねいさんです。
今日は穏やかな八丈島です。今日は全国的に暖かでしょうか。
日本全国各地の郷土名物料理をご紹介しております今週ですが、
今日は、おもしろい炊き込みご飯、弓ヶ浜半島の「いただき」をご紹介します。
弓ヶ浜半島は、どこにあるかご存知ですか?鳥取県にありますよ。
 弓ヶ浜半島観光コース
弓ヶ浜半島観光コース  クリック
クリック
最近は、水木しげるロードで有名なところです。
この辺りの漁師さんや農家の方々のお弁当によく作られるという「いただき」です。

「弓ヶ浜半島のいただき」
おあげに入った「いなり寿司」のような炊き込みご飯です。おもしろいですね。
だいぶ前に「きつねコロッケ」や「袋煮」をご紹介しましたが、
炊き込みご飯は、おねいさんもはじめて見ました。
今日は、炊飯器で簡単にできる作り方をご紹介します。



[作り方]
牛蒡をささがき、水で戻した干し椎茸と人参は千切りにし、
洗ってザルにあげた米(2合)と混ぜておきます。
半分に切って袋にした薄あげ(6枚=12個分)を熱湯で油抜きし、
これに米+具材を詰めて爪楊枝で止めます。
炊飯釜にだし昆布と煮干を敷き、これに、
水(4合)と酒、醤油、みりんを足して注ぎます。(計4合半位)

そこに12個の袋を並べ、炊飯器のスイッチを入れます。

炊き上がりは、こんなかんじです。
底が若干焦げますので、わたしは炊き上がり5分前位に「炊飯」を止めました。
そのまま少し蒸らして、おいしくできました。
焦げた匂いがしてきたら、止めた方が無難だと思います。
※焦げ止めの意味もあり、底に昆布と煮干を敷いてるものと思われます。


地元八丈島のお豆腐やさん、村田豆腐店さんと山下豆腐店さんの薄あげです。
今日は、山下さんものを使いましたが、山下さんの薄あげは小ぶりですので、
米+具材が分量の1/3ほど余りました。
大き目の薄あげ使用では、上記分量で大丈夫だと思いますが、
薄あげの大きさにより、米+具材の分量は加減してくださいね。

切り口は、こんなかんじ。素朴でおいしい炊き込みご飯です。
本日は、現地のレシピどおりの具材で素朴に作りましたが、
家庭用には、アサリや鶏肉を細かく切ったものを入れてもおいしいかと思います。
ほんとにお弁当にいいと思います。とても食べやすいです。
(炊き込みご飯は傷みやすいので、夏場はやめたほうが無難ですが)

弓ヶ浜半島の「いただき」または、「ののこめし」「ののこ」
この名前を聞いたときに、「いただき!」と横取りしたいほどおいしいの?
と思いました。「ままかり」と同じような語源かと。
正しくは、弓ヶ浜から見える大山の「いただき」からきているようです。
このお料理は、本来は大きな三角形のあげで作るそうで、
それが山のいただきに似てるから、というものらしいです。
 弓ヶ浜から見る大山
弓ヶ浜から見る大山  クリック
クリック
また、「ののこめし」「ののこ」とも呼ばれていて、
綿入れの「布子(ぬのこ)」に似ているところからつけられたとか。
郷土料理は、料理名にも地方色の見える面白い名前が多いのです。
その昔から、境港の漁師さんや農家の方々が、
仕事の合間でも手っ取り早く食べられるお弁当として持っていったという
アイディア料理の「いただき」。
そのナイスなアイディアをわたしたちもいただきましょう♪
みなさま、どうぞ作ってくださいね。



 今週末の特売チラシは、コチラです。
今週末の特売チラシは、コチラです。
※本日は、編集に時間がかかり、更新が遅くなりました。ごめんなさい!
今日は穏やかな八丈島です。今日は全国的に暖かでしょうか。

日本全国各地の郷土名物料理をご紹介しております今週ですが、
今日は、おもしろい炊き込みご飯、弓ヶ浜半島の「いただき」をご紹介します。

弓ヶ浜半島は、どこにあるかご存知ですか?鳥取県にありますよ。
 弓ヶ浜半島観光コース
弓ヶ浜半島観光コース  クリック
クリック
最近は、水木しげるロードで有名なところです。
この辺りの漁師さんや農家の方々のお弁当によく作られるという「いただき」です。

「弓ヶ浜半島のいただき」
おあげに入った「いなり寿司」のような炊き込みご飯です。おもしろいですね。
だいぶ前に「きつねコロッケ」や「袋煮」をご紹介しましたが、
炊き込みご飯は、おねいさんもはじめて見ました。

今日は、炊飯器で簡単にできる作り方をご紹介します。




[作り方]
牛蒡をささがき、水で戻した干し椎茸と人参は千切りにし、
洗ってザルにあげた米(2合)と混ぜておきます。
半分に切って袋にした薄あげ(6枚=12個分)を熱湯で油抜きし、
これに米+具材を詰めて爪楊枝で止めます。
炊飯釜にだし昆布と煮干を敷き、これに、
水(4合)と酒、醤油、みりんを足して注ぎます。(計4合半位)

そこに12個の袋を並べ、炊飯器のスイッチを入れます。

炊き上がりは、こんなかんじです。
底が若干焦げますので、わたしは炊き上がり5分前位に「炊飯」を止めました。
そのまま少し蒸らして、おいしくできました。
焦げた匂いがしてきたら、止めた方が無難だと思います。
※焦げ止めの意味もあり、底に昆布と煮干を敷いてるものと思われます。


地元八丈島のお豆腐やさん、村田豆腐店さんと山下豆腐店さんの薄あげです。
今日は、山下さんものを使いましたが、山下さんの薄あげは小ぶりですので、
米+具材が分量の1/3ほど余りました。
大き目の薄あげ使用では、上記分量で大丈夫だと思いますが、
薄あげの大きさにより、米+具材の分量は加減してくださいね。

切り口は、こんなかんじ。素朴でおいしい炊き込みご飯です。
本日は、現地のレシピどおりの具材で素朴に作りましたが、
家庭用には、アサリや鶏肉を細かく切ったものを入れてもおいしいかと思います。
ほんとにお弁当にいいと思います。とても食べやすいです。

(炊き込みご飯は傷みやすいので、夏場はやめたほうが無難ですが)

弓ヶ浜半島の「いただき」または、「ののこめし」「ののこ」
この名前を聞いたときに、「いただき!」と横取りしたいほどおいしいの?
と思いました。「ままかり」と同じような語源かと。

正しくは、弓ヶ浜から見える大山の「いただき」からきているようです。
このお料理は、本来は大きな三角形のあげで作るそうで、
それが山のいただきに似てるから、というものらしいです。
 弓ヶ浜から見る大山
弓ヶ浜から見る大山  クリック
クリック
また、「ののこめし」「ののこ」とも呼ばれていて、
綿入れの「布子(ぬのこ)」に似ているところからつけられたとか。
郷土料理は、料理名にも地方色の見える面白い名前が多いのです。
その昔から、境港の漁師さんや農家の方々が、
仕事の合間でも手っ取り早く食べられるお弁当として持っていったという
アイディア料理の「いただき」。
そのナイスなアイディアをわたしたちもいただきましょう♪
みなさま、どうぞ作ってくださいね。




 今週末の特売チラシは、コチラです。
今週末の特売チラシは、コチラです。※本日は、編集に時間がかかり、更新が遅くなりました。ごめんなさい!