医療法改正で、薬局が「調剤を実施する薬局」という文言で、規定される。薬局関係者にすれば、薬局とは、薬店と異なり、調剤をするところだから、“調剤を実施する”と形容されることはいささかくどい表現だ。
薬局の指定を受けていても、外観上、物品販売に注力するドラッグストアの中にも、ささやかに調剤をしていたり、その設備を設けて、薬店の顔をしながら、おれは薬局だ、という2面性を持っていたりする。
社会に薬を供給する側面があることで、薬局も薬店も共通しているが、どちらで生計を立てているか、活動の軸足をどちらに置いているかで、性格は全くことなる。別の業種と言ってもいい。
まぁ、そんなわけで、街の中で、どれが薬局で、どれが薬店かは、見分けがつきにくい。とくに「薬局でありながら、薬店といっても過言ではない」ところが問題だ。そんなところが「医療提供施設」になんて、なれない・なりえない。
医師会が「調剤を実施する」という文言にこだわった理由は何か。株式会社の医療への参入を懸念して、ということだが。換言すれば、医療の分野で「営利優先」がまかり通って、人々の健康が営利優先、利益確保の文化の中で行われることだけは許されない、ということではないだろうか。
医療機関にしてみれば当たり前のことだ。薬局の中には、物品販売が、セルフメディケーションのサポート程度にしか、行われていないことも多い。OTC等の販売額など、経営全体からしたら微々たる“調剤薬局”も少なくない。それは、逆手に考え、物販も医療機関として営利非優先、売上げ無関係で行うことだ。それは、消費者から見れば、大歓迎ではないか。薬は(サプリメントや健康食品もそうだが)飲めば飲むほどいいものではないのだから。
規制緩和も進む中(是非は別に)、薬局たるもの、限りなく医療機関であるべきだ。
たまたま、調剤と物販が半々くらいで、経営的に2面性を持たざるを得ないところもあろう。あるときは医療従事者、あるときは営業、その使いわけは倫理感に委ねるしかないと思われ、苦しい立場に立たされているように思う。
薬局の指定を受けていても、外観上、物品販売に注力するドラッグストアの中にも、ささやかに調剤をしていたり、その設備を設けて、薬店の顔をしながら、おれは薬局だ、という2面性を持っていたりする。
社会に薬を供給する側面があることで、薬局も薬店も共通しているが、どちらで生計を立てているか、活動の軸足をどちらに置いているかで、性格は全くことなる。別の業種と言ってもいい。
まぁ、そんなわけで、街の中で、どれが薬局で、どれが薬店かは、見分けがつきにくい。とくに「薬局でありながら、薬店といっても過言ではない」ところが問題だ。そんなところが「医療提供施設」になんて、なれない・なりえない。
医師会が「調剤を実施する」という文言にこだわった理由は何か。株式会社の医療への参入を懸念して、ということだが。換言すれば、医療の分野で「営利優先」がまかり通って、人々の健康が営利優先、利益確保の文化の中で行われることだけは許されない、ということではないだろうか。
医療機関にしてみれば当たり前のことだ。薬局の中には、物品販売が、セルフメディケーションのサポート程度にしか、行われていないことも多い。OTC等の販売額など、経営全体からしたら微々たる“調剤薬局”も少なくない。それは、逆手に考え、物販も医療機関として営利非優先、売上げ無関係で行うことだ。それは、消費者から見れば、大歓迎ではないか。薬は(サプリメントや健康食品もそうだが)飲めば飲むほどいいものではないのだから。
規制緩和も進む中(是非は別に)、薬局たるもの、限りなく医療機関であるべきだ。
たまたま、調剤と物販が半々くらいで、経営的に2面性を持たざるを得ないところもあろう。あるときは医療従事者、あるときは営業、その使いわけは倫理感に委ねるしかないと思われ、苦しい立場に立たされているように思う。










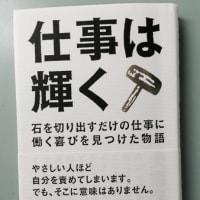
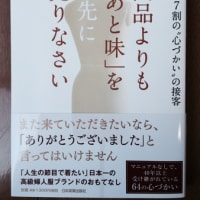
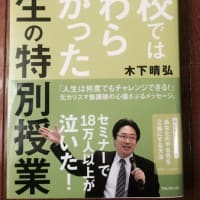
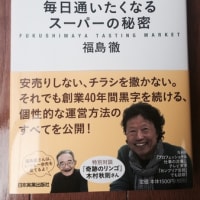
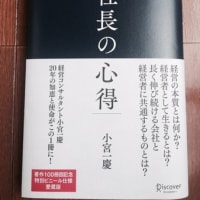
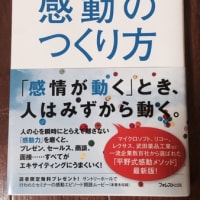
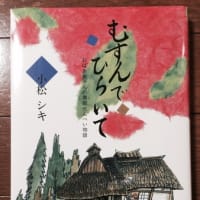
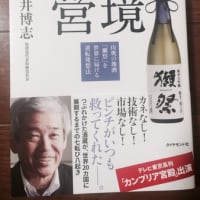
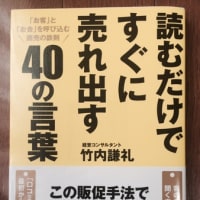
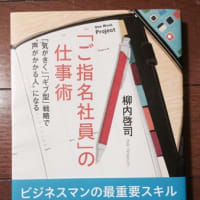





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます