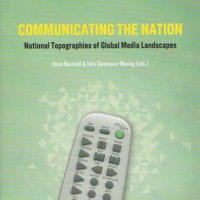マンハッタンのアッパーイーストサイドにあるAquevella Galleryにて、Marie-Thérèseと一緒であった時のピカソをテーマとした美術展を見てくる。ピカソが45歳の時、17歳のマリ-・テレーズと出会ってから描いたテレーズの肖像画のシリーズが主な展示作品だったのだが、素晴らしいの一言であった。
その中でも特に、1932年1月22日に描いたRepose (Le Repos)という作品が特に素晴らしくて、ずっと眺めていた。
2m近くある大型の絵画なのだが、人間の身体の有機性そのものが、おへそとして描かれているカンバスの中心に位置する黒い点から放心円上に拡大し、その支持体である椅子までも飲み込んでしまっているかの様だ。そして、赤色とオレンジ色の燃える様な色が、とても印象的だった。自分の愛する女性の身体のオブジェ性を、ここまで極端なまでに肥大化させるのは、やはりピカソの天才だろう。
しかしギャラリーから帰る道の中で、あの絵、良かったな、と思いながら、”あの絵”を思いだそうと思っても、なかなか思い出せない。他の絵を思いだすのは簡単なのに、なぜだろう?と疑問に思った。
このピカソのReposeは、抽象の度合が高く、既存の形体に落とし込んで考えるのが難しい構成物である。私はどうやら、ピカソの”あの絵”という「現象」を、自然的な態度として、私の内部にある実在の概念や理念で無意識に理解しようとしていることに気づいた。しかし、”あの絵”は、そういった概念的なものさえも寄せ付けない抽象度を維持しているのだ。(実際、このイメージを見て、鑑賞者はどんな形容ができると言うのだろう?!)この絵画には、人間が描かれている、という私の中に実在している概念的な作用面と、絵画作品の対象面が、かなり離れてしまっているのだ。フッサールの言う所の「エポケー」を持ちださないと、咀嚼さえできず、無理に飲み込もうとすれば、のどにつっかえてしまうような代物だ。
そんなことを考えていたら、「妖怪ひだる」のことを思い出した。
日本人は、自然現象などを擬人化することを頻繁に行っているが、西日本には「ひだる」と呼ばれる妖怪がいると信じられていた。これに取り憑かれると、人は脱力感に襲われ、何かにのしかかられたような重みを感じ、歩くことも出来なくなるそうだ。長いこと、この妖怪の存在と実際に起こる脱力感の現象との関係性は謎だったのだが、それが科学的に証明できる様になってきた。この「ひだる」が出没する地域は山中の窪地で、こういった場所には、植物の枯れ葉などの有機物が腐る際に大量の腐食性の二酸化炭素が発生し、大気中の二酸化炭素濃度が通常の大気濃度の約20倍にも達することがあると言う。この二酸化炭素を吸うと脱力感に襲われるそうなのだが、昔の日本人はこれを妖怪ひだるの仕業だと考えたのだ。
人間は、経験した現象を、個人の概念的なコンテクストに落とし込んで理解していると思うのだが、自然を擬人化しているのは面白いと思う。例えば、ラップ現象と呼ばれる、ものがバチっと音を立てる、ポルターガイストとも呼ばれることのある現象があるが、私は子供の頃に、木製のテレビ台の上に置いたテレビが、長時間使用して温まってくると、膨張して「バチ」っという音がするのが不思議でならなかった。
そして数年前、アイスランドのレイキャビクのカフェに行った際、隣のテーブルに置いてあったコーヒーカップが、テーブルの上でバランスを崩して、カチャ、と高い音を立てた際、近くにいたアイスランド人たちが「エルフが歩いたんだ。エルフの仕業だ」と言ったのには、驚いた。西洋の端の島国で、こんな擬人化をする人たちがいるのか、と思うと驚きであった。
ピカソのせいなのか、それとも、ひだるか、エルフか。。。現象をどう捉えるのか、そんな所にも、人間の自然な癖が出てくるのが面白い。
その中でも特に、1932年1月22日に描いたRepose (Le Repos)という作品が特に素晴らしくて、ずっと眺めていた。
2m近くある大型の絵画なのだが、人間の身体の有機性そのものが、おへそとして描かれているカンバスの中心に位置する黒い点から放心円上に拡大し、その支持体である椅子までも飲み込んでしまっているかの様だ。そして、赤色とオレンジ色の燃える様な色が、とても印象的だった。自分の愛する女性の身体のオブジェ性を、ここまで極端なまでに肥大化させるのは、やはりピカソの天才だろう。
しかしギャラリーから帰る道の中で、あの絵、良かったな、と思いながら、”あの絵”を思いだそうと思っても、なかなか思い出せない。他の絵を思いだすのは簡単なのに、なぜだろう?と疑問に思った。
このピカソのReposeは、抽象の度合が高く、既存の形体に落とし込んで考えるのが難しい構成物である。私はどうやら、ピカソの”あの絵”という「現象」を、自然的な態度として、私の内部にある実在の概念や理念で無意識に理解しようとしていることに気づいた。しかし、”あの絵”は、そういった概念的なものさえも寄せ付けない抽象度を維持しているのだ。(実際、このイメージを見て、鑑賞者はどんな形容ができると言うのだろう?!)この絵画には、人間が描かれている、という私の中に実在している概念的な作用面と、絵画作品の対象面が、かなり離れてしまっているのだ。フッサールの言う所の「エポケー」を持ちださないと、咀嚼さえできず、無理に飲み込もうとすれば、のどにつっかえてしまうような代物だ。
そんなことを考えていたら、「妖怪ひだる」のことを思い出した。
日本人は、自然現象などを擬人化することを頻繁に行っているが、西日本には「ひだる」と呼ばれる妖怪がいると信じられていた。これに取り憑かれると、人は脱力感に襲われ、何かにのしかかられたような重みを感じ、歩くことも出来なくなるそうだ。長いこと、この妖怪の存在と実際に起こる脱力感の現象との関係性は謎だったのだが、それが科学的に証明できる様になってきた。この「ひだる」が出没する地域は山中の窪地で、こういった場所には、植物の枯れ葉などの有機物が腐る際に大量の腐食性の二酸化炭素が発生し、大気中の二酸化炭素濃度が通常の大気濃度の約20倍にも達することがあると言う。この二酸化炭素を吸うと脱力感に襲われるそうなのだが、昔の日本人はこれを妖怪ひだるの仕業だと考えたのだ。
人間は、経験した現象を、個人の概念的なコンテクストに落とし込んで理解していると思うのだが、自然を擬人化しているのは面白いと思う。例えば、ラップ現象と呼ばれる、ものがバチっと音を立てる、ポルターガイストとも呼ばれることのある現象があるが、私は子供の頃に、木製のテレビ台の上に置いたテレビが、長時間使用して温まってくると、膨張して「バチ」っという音がするのが不思議でならなかった。
そして数年前、アイスランドのレイキャビクのカフェに行った際、隣のテーブルに置いてあったコーヒーカップが、テーブルの上でバランスを崩して、カチャ、と高い音を立てた際、近くにいたアイスランド人たちが「エルフが歩いたんだ。エルフの仕業だ」と言ったのには、驚いた。西洋の端の島国で、こんな擬人化をする人たちがいるのか、と思うと驚きであった。
ピカソのせいなのか、それとも、ひだるか、エルフか。。。現象をどう捉えるのか、そんな所にも、人間の自然な癖が出てくるのが面白い。