
久し振りに静岡の実家に帰り、家族と時間を過ごしてくる。
自分が移動、そして年齢を重ねる度に、実家という場所の意味がある程度客観的に捉えられる様になってきて、自分が生まれ育った場所を、冷静に考えることができる様になったと思う。高校生までは、あんなに嫌で早く出たい!と切望した実家のエリアを、ノスタルジックに思えてしまう私がいることに対しても、いろんな感情が交差する。
駅まで迎に来てくれた父と一緒に、父の経営する魚問屋があった港のあたりをぐるりと散歩した。問屋業がすたれつつあり、港が観光地化しているのを見ると寂しくなると同時に、観光という、ある種いびつな産業を成立させることにより、ようやく成り立っている地元の漁港を見ると、あながち否定もできない。
そんなことを思いながら散歩しいていると、道すがら、おばさんに「あれ?真也君だよね?」と声をかけられた。
私は沼津の港町で小学校2年生まで育ち、その後家が手狭になった為、隣の校区に建てた新築の家へと引っ越したことがあるのだが、このご近所のおばさんは、小学校2年生までご近所に住んでいた私を覚えていると言う。このおばさんの記憶力に驚くと同時に、20年前のご近所さんの子供と、その顔まで覚えている、というコミュニティ意識に、私は驚かされた。小さい頃からマルヨの三代目、と呼ばれていた私の亡霊が、会社を継がなかた私に代わって、この辺りを徘徊しているのだろうか。
家族に会って、沖縄での出来事を話しているうちに、私が気にしていた祖父の記憶の話へと発展して行った。そんな話が進む中、父が大切に保管していた、祖父の軍隊手帳や、中国戦での記録写真などを、見せてもらった。
私の祖父は、中国にて宣撫官として活躍していたと言う。戦時中、祖父は中国人の校長先生の息子を人質に取って、日本風の教育をしたそうなのだが、その中国人の少年と、祖父が仲良さげに写っている写真が、とても印象的だった。この子供は、父である校長先生に、「渡辺教官はどうだ?」と聞かれて、「とても優しくて、好きだ」と答えると、この父親は子供の面前で号泣した、という出来事を、祖父に話したそうだ。その話を、一体祖父はどんな気持ちで私の父に話したのだろう、と考えると、私はすっかり分からなくなってしまう。圧倒的に政治的な状況が物事を規定してしまう、という状況は、あまりにも苦しい。とはいえ、宣撫官、という言葉を単語として初めて知った私は、祖父の記憶に一歩近づいたのかもしれない。
話は飛ぶが、最近、謙譲語のメカニズムについて不思議に思うことがあった。
例えば、日本では、組織の内部の人間として、外部と受け答えする際、形式として身内をへりくだって話すという形態を取る。いくら自社の社長や組織のトップであったとしても、「うちの三木谷が・・」とか、「うちの麻生が・・・」という具合だ。しかし、これが対外的な取引ではなく、内部でのやりとりとなると、謙譲語ではなく、敬語や尊敬語でのやりとりとなる。
廣松渉の共同主観性ではないが、日本語での会話の際、主観的要素の中に、関係性の要素が入りすぎるな、という印象を受ける。しかも、その関係性の要素が複雑に入り組んでいるものが自明のものとなり、あたかもエーテルの如く、日本社会をすっぽりと覆ってしまっている。もっと言うと、廣松の共同主観性は、日本語構造から出てきた思想であり、それは吉本隆明の「共同幻想論」においても同じ構図なのではないか。
構造的に考えると、日本で唯一謙譲語が使えないのは皇室の人間のみだが、それを指摘してもどうにもならない、というのと同じくらい、中空構造とも言えるものが、自明性を持ってしまい、それに対する論理的な反論が意味を持たない、という場所性を日本に感じてしまう。自我の問題と一神教の不在の問題が、この関係性の自明性に現われていると思うのだが、これが「他者」と出会った際に、かなりやっかいな問題になるのではないかと思う。このあたりは、自分なりに考えてみたい問題ではある。
自分が移動、そして年齢を重ねる度に、実家という場所の意味がある程度客観的に捉えられる様になってきて、自分が生まれ育った場所を、冷静に考えることができる様になったと思う。高校生までは、あんなに嫌で早く出たい!と切望した実家のエリアを、ノスタルジックに思えてしまう私がいることに対しても、いろんな感情が交差する。
駅まで迎に来てくれた父と一緒に、父の経営する魚問屋があった港のあたりをぐるりと散歩した。問屋業がすたれつつあり、港が観光地化しているのを見ると寂しくなると同時に、観光という、ある種いびつな産業を成立させることにより、ようやく成り立っている地元の漁港を見ると、あながち否定もできない。
そんなことを思いながら散歩しいていると、道すがら、おばさんに「あれ?真也君だよね?」と声をかけられた。
私は沼津の港町で小学校2年生まで育ち、その後家が手狭になった為、隣の校区に建てた新築の家へと引っ越したことがあるのだが、このご近所のおばさんは、小学校2年生までご近所に住んでいた私を覚えていると言う。このおばさんの記憶力に驚くと同時に、20年前のご近所さんの子供と、その顔まで覚えている、というコミュニティ意識に、私は驚かされた。小さい頃からマルヨの三代目、と呼ばれていた私の亡霊が、会社を継がなかた私に代わって、この辺りを徘徊しているのだろうか。
家族に会って、沖縄での出来事を話しているうちに、私が気にしていた祖父の記憶の話へと発展して行った。そんな話が進む中、父が大切に保管していた、祖父の軍隊手帳や、中国戦での記録写真などを、見せてもらった。
私の祖父は、中国にて宣撫官として活躍していたと言う。戦時中、祖父は中国人の校長先生の息子を人質に取って、日本風の教育をしたそうなのだが、その中国人の少年と、祖父が仲良さげに写っている写真が、とても印象的だった。この子供は、父である校長先生に、「渡辺教官はどうだ?」と聞かれて、「とても優しくて、好きだ」と答えると、この父親は子供の面前で号泣した、という出来事を、祖父に話したそうだ。その話を、一体祖父はどんな気持ちで私の父に話したのだろう、と考えると、私はすっかり分からなくなってしまう。圧倒的に政治的な状況が物事を規定してしまう、という状況は、あまりにも苦しい。とはいえ、宣撫官、という言葉を単語として初めて知った私は、祖父の記憶に一歩近づいたのかもしれない。
話は飛ぶが、最近、謙譲語のメカニズムについて不思議に思うことがあった。
例えば、日本では、組織の内部の人間として、外部と受け答えする際、形式として身内をへりくだって話すという形態を取る。いくら自社の社長や組織のトップであったとしても、「うちの三木谷が・・」とか、「うちの麻生が・・・」という具合だ。しかし、これが対外的な取引ではなく、内部でのやりとりとなると、謙譲語ではなく、敬語や尊敬語でのやりとりとなる。
廣松渉の共同主観性ではないが、日本語での会話の際、主観的要素の中に、関係性の要素が入りすぎるな、という印象を受ける。しかも、その関係性の要素が複雑に入り組んでいるものが自明のものとなり、あたかもエーテルの如く、日本社会をすっぽりと覆ってしまっている。もっと言うと、廣松の共同主観性は、日本語構造から出てきた思想であり、それは吉本隆明の「共同幻想論」においても同じ構図なのではないか。
構造的に考えると、日本で唯一謙譲語が使えないのは皇室の人間のみだが、それを指摘してもどうにもならない、というのと同じくらい、中空構造とも言えるものが、自明性を持ってしまい、それに対する論理的な反論が意味を持たない、という場所性を日本に感じてしまう。自我の問題と一神教の不在の問題が、この関係性の自明性に現われていると思うのだが、これが「他者」と出会った際に、かなりやっかいな問題になるのではないかと思う。このあたりは、自分なりに考えてみたい問題ではある。


















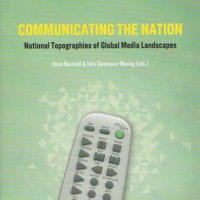

info@shinyawatanabe.net