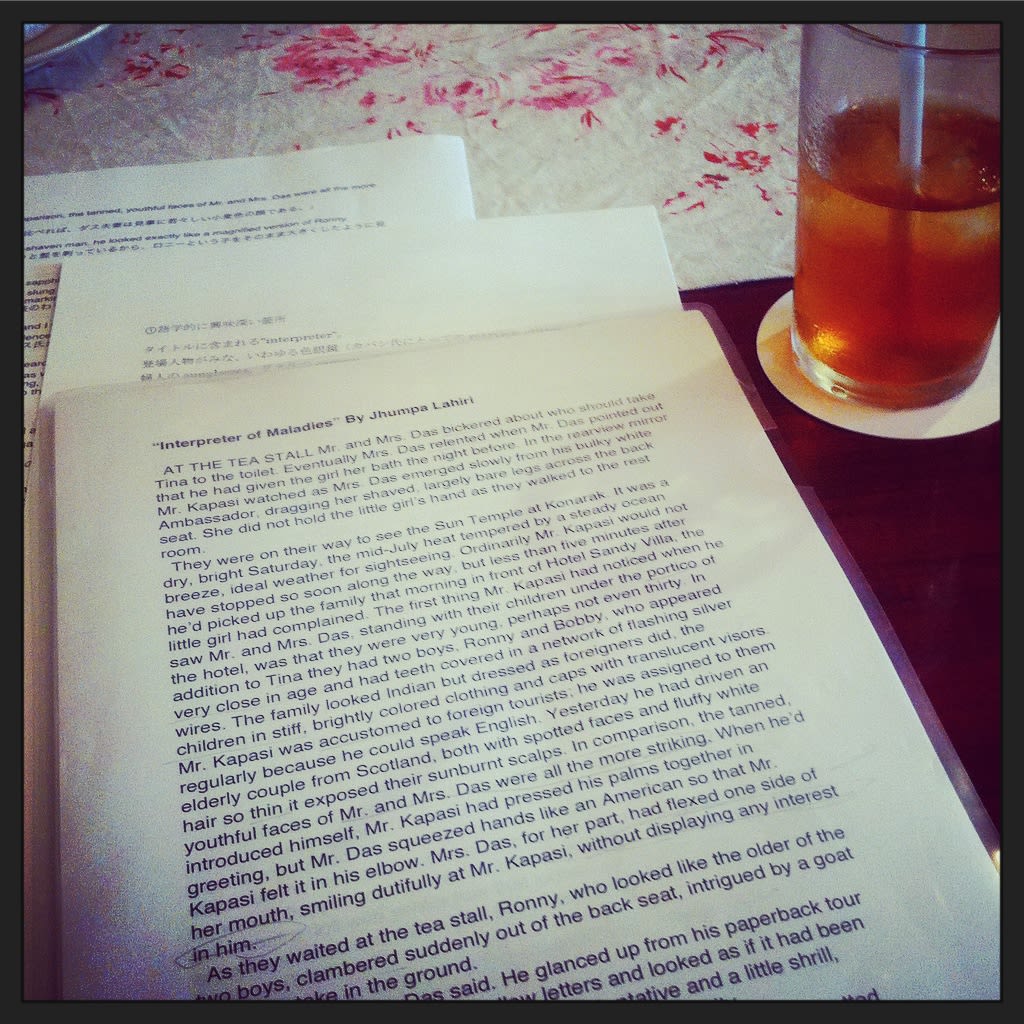アフタヌーンティという雑貨屋さんのカフェって、
不味くはないけど特においしいわけでもないのに高い、コスパの悪い店と思ってて、
宝塚阪急や梅田阪神のとこの店なんかはテーブルの間隔も狭くていつも人が多くて
落ち着かなかったんだけど、
うちの近所の店はかなりゆったりとしたテーブル配置で、
昼間はランチの人がとても多いけど、
夕方の空いてる時間なら読むものを持って長居しやすいかなと思ってました。
バーで本を読むのも好きだけど、年をとると暗い場所で本を読むのが
結構つらくなってくるので、落ち着くカフェはいい。
そして、この夏にやってるここの夜のセットはなんだかとても好きかも。
フードとスイーツとドリンク2つのセットに、
書き下ろし短編やエッセイの入った小さな冊子が付いてるセットなのです。

ゆっくり読書してくださいという意味で、ドリンクが2つセットに入ってるというのは、
鷹揚なことだなと思う。食後のドリンクと読書。素敵だ。
この小冊子も細長い形で、なんかかわいい。
本とカフェという組み合わせが気持ちいいだけでなく、
ゆっくりしていいんですよというお店の姿勢が、いいなと思うのです。
これって、お店が、お客の回転ということを捨てているわけで、
カフェというのは多少のフードは出していても、
多くのレストランに比べると客単価は少なめで、
回転で売り上げを確保してやっていくことの多い業態ですよね。
飲食店が、お客さんの回転を捨てるって、客単価が大きい店でないと損だし、
うちの近所みたいな夜はすいてる店ならともかく、
繁華街のお客さんの多い店だと、店的にはもったいないことだと思うんだけど
チェーン店なので全国的にやっているのでしょう。
個人オーナーのお店には時々あると思うけど、チェーン店でこういう
あんまり儲からなくていいから、楽しいことをしようという姿勢は珍しいような。
で、夜だけのセットだけど一度行ってみようと翌々日に行ったら
なんとこの小冊子がなくなったら終わりと言うことで、やってなかった。

あー残念。またやらないかなぁ〜
不味くはないけど特においしいわけでもないのに高い、コスパの悪い店と思ってて、
宝塚阪急や梅田阪神のとこの店なんかはテーブルの間隔も狭くていつも人が多くて
落ち着かなかったんだけど、
うちの近所の店はかなりゆったりとしたテーブル配置で、
昼間はランチの人がとても多いけど、
夕方の空いてる時間なら読むものを持って長居しやすいかなと思ってました。
バーで本を読むのも好きだけど、年をとると暗い場所で本を読むのが
結構つらくなってくるので、落ち着くカフェはいい。
そして、この夏にやってるここの夜のセットはなんだかとても好きかも。
フードとスイーツとドリンク2つのセットに、
書き下ろし短編やエッセイの入った小さな冊子が付いてるセットなのです。

ゆっくり読書してくださいという意味で、ドリンクが2つセットに入ってるというのは、
鷹揚なことだなと思う。食後のドリンクと読書。素敵だ。
この小冊子も細長い形で、なんかかわいい。
本とカフェという組み合わせが気持ちいいだけでなく、
ゆっくりしていいんですよというお店の姿勢が、いいなと思うのです。
これって、お店が、お客の回転ということを捨てているわけで、
カフェというのは多少のフードは出していても、
多くのレストランに比べると客単価は少なめで、
回転で売り上げを確保してやっていくことの多い業態ですよね。
飲食店が、お客さんの回転を捨てるって、客単価が大きい店でないと損だし、
うちの近所みたいな夜はすいてる店ならともかく、
繁華街のお客さんの多い店だと、店的にはもったいないことだと思うんだけど
チェーン店なので全国的にやっているのでしょう。
個人オーナーのお店には時々あると思うけど、チェーン店でこういう
あんまり儲からなくていいから、楽しいことをしようという姿勢は珍しいような。
で、夜だけのセットだけど一度行ってみようと翌々日に行ったら
なんとこの小冊子がなくなったら終わりと言うことで、やってなかった。

あー残念。またやらないかなぁ〜