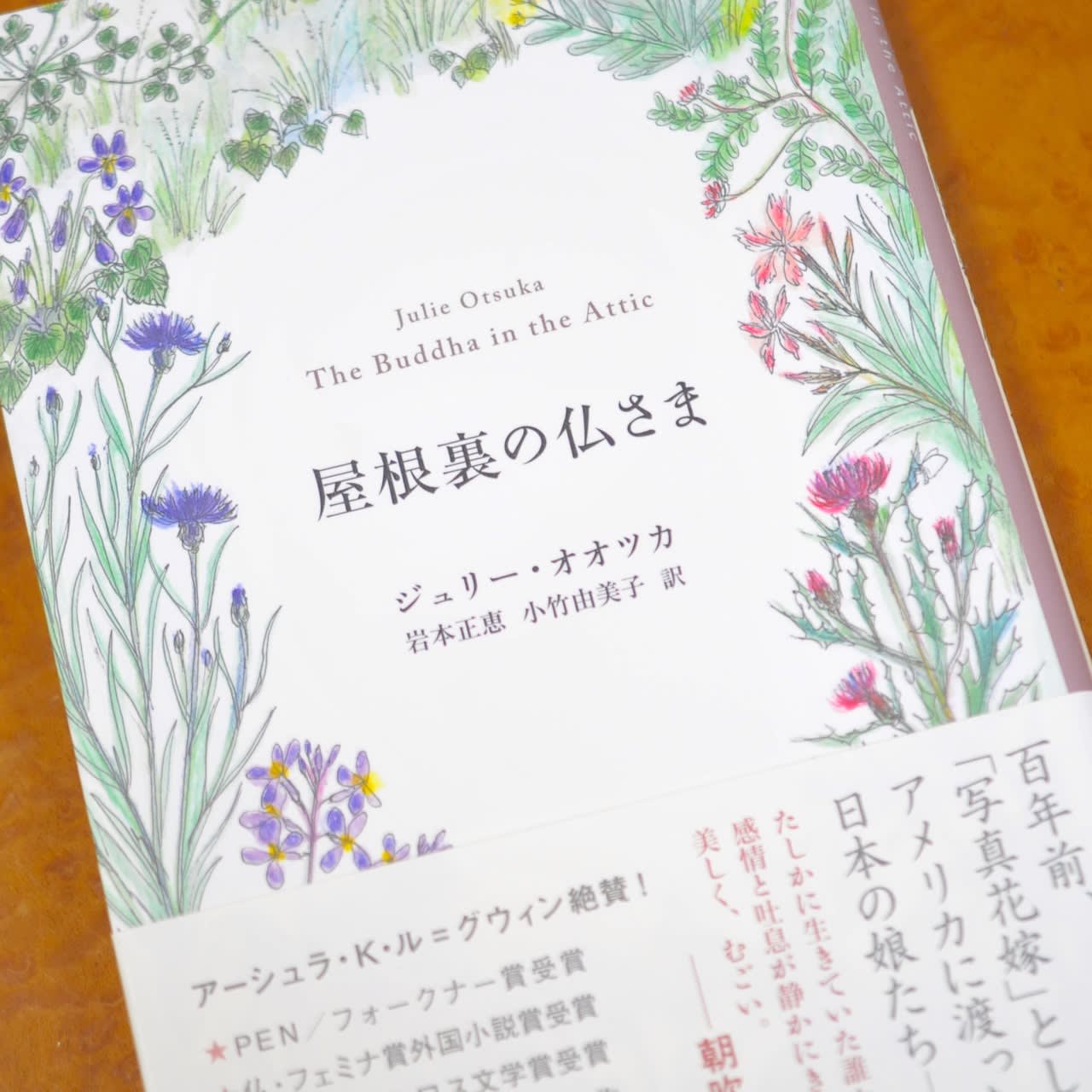これ、前に軽く一度感想を書いてるんですけど、
その後行った読書会の課題がこれで、その時もう一度読んだので、
ちゃんと感想など書こうと思ったけど
それからまたずいぶん経っちゃったので、もう感想はいいや。
好きな抜粋だけひたすら貼ります。
ああ、やっぱり好きだ好きだ好きだ、この本、というかこの作家。
ソ連と西ドイツが舞台の、シロクマの祖母・母・息子3代の話。
モスクワのサーカスから西ドイツへ亡命、さらに東ドイツへと。
伝記を書いたり伝説の芸を成し遂げたり、動物園の人気者になったり、
と説明してもほんの1%もわからないと思う不思議な話。
クマも考えたりしゃべったり、しゃべらなかったりします。
静かで内省的で、すごくおもしろい物語です。
「人間は不自然と言うことをとても嫌っているんだよ」とミヒャエルが説明してくれた。「熊は熊らしく、下層階級は下層階級らしくしなければ不自然だと思っている。」「それならば人間はどうして動物園なんか作ったんだ。」「うん、それは多分、矛盾しているところが人間の唯一自然なところだからだ。」「そんなのずるいよ。」「君は、自然か不自然かなんて気にしないで、君がいいと思う通りに生きればいいよ。」
ウルズラはわたしと向かい合ってきりっと立ち、唇だけを柔らかく差し出す。その時、彼女の喉が闇の中で大きく開いて、魂が奥でちらちら燃えているのが見える。一度接吻する度に、人間の魂が少しずつわたしの中に流れ込んで来た。人間の魂と言うのは噂に聞いたほどロマンチックなものではなく、ほとんど言葉でできている。それも、普通にわかる言葉だけでなく、壊れた言葉の破片や言葉になり損なった映像や言葉の影なども多い。
「人権」などというものはそもそも人間のことしか考えていない人間が考え出した言葉だと思っていたからだ。タンポポに人権はない。ミミズにもない。雨にもない。兎にもない。ところが鯨となると、人権のようなものを持っている。「捕鯨と資本主義」という資料を昔、会議の準備で読んでいてそんな印象を持った。どうやら人権とは、図体が大きいものの持つ権利らしい。だから、みんなわたしに人権を持たせようとするのかも知れない。何しろわたしたち一族は、肉を食べ、陸に生きるものの中では、一番体が大きい。
人間は痩せているくせに動きが鈍く、大事な時に何度も瞬きをするので敵が見えない。どうでもいい時はせかせかしているくせに、大事な戦いの時には動きが遅い。戦いには向いていないのだから兎や鹿のように賢く逃げることを考えればいいのに、なぜか戦い好きなのがいる。人間ほど愚かな動物を何のために誰が作ったのか。人間が神の似姿だと言う人がいるが、それは神様に対して大変失礼である。神様はどちらかというと人間よりも熊に似ていたということを今でも覚えている民族が北方には点在しているそうだ。
それまで積んできた動物調教師としてのキャリアを捨てて、主婦になった。空虚というのは空っぽで重さがないものかと思っていたらその逆で、日中ふと仕事の手をとめると胸の中で膨張し続けるそれが重すぎて、夜はそれが胸にのしかかってきて寝返りばかり打っていた。
当時は国営の保育園に子供を預けっぱなしにして週末しか会わない母親はたくさんいた。職種によっては何ヶ月も子供の顔を見ない女性もいた。母性愛という神話が囁かれることはごく希だったし、宗教は弾圧されていたので聖母マリアが幼子イエスを抱く絵も見たことがなかった。これはずっと後になってからの話だが、東ドイツの終焉とともに母性愛の神話が蜃気楼のようにドイツの地平線に現れ……第一に「ストレス」などという言葉は西側の「製品」で東ドイツにはなかったし、第二に育児本能などという本能は人間にはあるのかもしれないが動物にはない。動物が子供を育てるのは本能ではなくアートである。アートだから育てるのは我が子でなくてもいい。
人間は紙を必要とするものである。ホッキョクグマのように地平線まで続く巨大な白紙と向かい合って生きるのは無理だとしても、せめて一日に便箋一枚くらいは配給して欲しいものだ。
ところがサーカスに戻ると間もなく戦争が始まってしまった。「北極には戦争がなくていいわね。」「でも戦争がないのに鉄砲を持って北極に来る人たちがいるの。その鉄砲で理由もなく生き物を打って殺す。」「どうして?」「分からない。人間には狩猟本能という本能があるって聞いいたことがある。でもその狩猟本能っていうのがよく分からないの。」「昔は生き残るのに必要だったある行動が意味を失ってからも動きだけが残っている、そういうことじゃないかしら。人間ってそういう動きの集まりに過ぎないのかもしれない。生きるために必要な動きはもう分からなくなっていて、記憶の残骸みたいな身振りばかりが残ってる。」
…乾いた草だけ食べていても風のように走れることが不思議に思えてくる。もしそうなら、なぜ肉を食べるというような骨の折れる危険な道を選ぶ動物がいるのだろう。……自然の中では十分な草を捜すのだって大変だよ……だから草食から肉食になっていったんだと思うよ。アザラシなんてすごく捕まえにくいし、まずいかも知れない。でもそれを食べてかろうじて生き残ってきた。食べるというのは惨めなことなんだ。だから僕は美食家は嫌いだ。食べるということの惨めさをごまかして、何か素敵なことでもしているように気取っているから。」
猛獣の稽古で大切なのは、意欲的でありながら、いつもあっさりあきらめることができるということだった。勇気など何の役にも立たない。……雪山を登る時と同じで名誉欲にかられて無理をすれば命取りになる。
生きるということはどうやら外へ出たいという気持ちのことらしい。
何が聞こえても耳を澄ましているうちに、あらゆる音声の中に宿る微妙な違い、その違いの組み合わせによってなりたっている今という不思議な空間の一回きりの色合いが聞き分けられるようになってきた。
せっかく外に出られたと思って喜んでいたけど、動物園にはまたその外があるのだ。外には外がある。どこまで行ったらそれ以上、外に出られないくらいの究極の外に行き着くんだろう。
ところが哺乳類はその名の通り、生まれてすぐはミルクからしか栄養が取れないようにできている。だから鳥のようにいつも前向きに考えることができなくて、つい乳くさい昔を振り返ってしまう。
もし生きていても、二度と逢えないのかも知れない。でもひょっとしたら逢えたかもしれない。ひょっとしたらと思いながら生きていくことを人間は希望と呼んでいる。その希望が死んだ。
その後行った読書会の課題がこれで、その時もう一度読んだので、
ちゃんと感想など書こうと思ったけど
それからまたずいぶん経っちゃったので、もう感想はいいや。
好きな抜粋だけひたすら貼ります。
ああ、やっぱり好きだ好きだ好きだ、この本、というかこの作家。
ソ連と西ドイツが舞台の、シロクマの祖母・母・息子3代の話。
モスクワのサーカスから西ドイツへ亡命、さらに東ドイツへと。
伝記を書いたり伝説の芸を成し遂げたり、動物園の人気者になったり、
と説明してもほんの1%もわからないと思う不思議な話。
クマも考えたりしゃべったり、しゃべらなかったりします。
静かで内省的で、すごくおもしろい物語です。
「人間は不自然と言うことをとても嫌っているんだよ」とミヒャエルが説明してくれた。「熊は熊らしく、下層階級は下層階級らしくしなければ不自然だと思っている。」「それならば人間はどうして動物園なんか作ったんだ。」「うん、それは多分、矛盾しているところが人間の唯一自然なところだからだ。」「そんなのずるいよ。」「君は、自然か不自然かなんて気にしないで、君がいいと思う通りに生きればいいよ。」
ウルズラはわたしと向かい合ってきりっと立ち、唇だけを柔らかく差し出す。その時、彼女の喉が闇の中で大きく開いて、魂が奥でちらちら燃えているのが見える。一度接吻する度に、人間の魂が少しずつわたしの中に流れ込んで来た。人間の魂と言うのは噂に聞いたほどロマンチックなものではなく、ほとんど言葉でできている。それも、普通にわかる言葉だけでなく、壊れた言葉の破片や言葉になり損なった映像や言葉の影なども多い。
「人権」などというものはそもそも人間のことしか考えていない人間が考え出した言葉だと思っていたからだ。タンポポに人権はない。ミミズにもない。雨にもない。兎にもない。ところが鯨となると、人権のようなものを持っている。「捕鯨と資本主義」という資料を昔、会議の準備で読んでいてそんな印象を持った。どうやら人権とは、図体が大きいものの持つ権利らしい。だから、みんなわたしに人権を持たせようとするのかも知れない。何しろわたしたち一族は、肉を食べ、陸に生きるものの中では、一番体が大きい。
人間は痩せているくせに動きが鈍く、大事な時に何度も瞬きをするので敵が見えない。どうでもいい時はせかせかしているくせに、大事な戦いの時には動きが遅い。戦いには向いていないのだから兎や鹿のように賢く逃げることを考えればいいのに、なぜか戦い好きなのがいる。人間ほど愚かな動物を何のために誰が作ったのか。人間が神の似姿だと言う人がいるが、それは神様に対して大変失礼である。神様はどちらかというと人間よりも熊に似ていたということを今でも覚えている民族が北方には点在しているそうだ。
それまで積んできた動物調教師としてのキャリアを捨てて、主婦になった。空虚というのは空っぽで重さがないものかと思っていたらその逆で、日中ふと仕事の手をとめると胸の中で膨張し続けるそれが重すぎて、夜はそれが胸にのしかかってきて寝返りばかり打っていた。
当時は国営の保育園に子供を預けっぱなしにして週末しか会わない母親はたくさんいた。職種によっては何ヶ月も子供の顔を見ない女性もいた。母性愛という神話が囁かれることはごく希だったし、宗教は弾圧されていたので聖母マリアが幼子イエスを抱く絵も見たことがなかった。これはずっと後になってからの話だが、東ドイツの終焉とともに母性愛の神話が蜃気楼のようにドイツの地平線に現れ……第一に「ストレス」などという言葉は西側の「製品」で東ドイツにはなかったし、第二に育児本能などという本能は人間にはあるのかもしれないが動物にはない。動物が子供を育てるのは本能ではなくアートである。アートだから育てるのは我が子でなくてもいい。
人間は紙を必要とするものである。ホッキョクグマのように地平線まで続く巨大な白紙と向かい合って生きるのは無理だとしても、せめて一日に便箋一枚くらいは配給して欲しいものだ。
ところがサーカスに戻ると間もなく戦争が始まってしまった。「北極には戦争がなくていいわね。」「でも戦争がないのに鉄砲を持って北極に来る人たちがいるの。その鉄砲で理由もなく生き物を打って殺す。」「どうして?」「分からない。人間には狩猟本能という本能があるって聞いいたことがある。でもその狩猟本能っていうのがよく分からないの。」「昔は生き残るのに必要だったある行動が意味を失ってからも動きだけが残っている、そういうことじゃないかしら。人間ってそういう動きの集まりに過ぎないのかもしれない。生きるために必要な動きはもう分からなくなっていて、記憶の残骸みたいな身振りばかりが残ってる。」
…乾いた草だけ食べていても風のように走れることが不思議に思えてくる。もしそうなら、なぜ肉を食べるというような骨の折れる危険な道を選ぶ動物がいるのだろう。……自然の中では十分な草を捜すのだって大変だよ……だから草食から肉食になっていったんだと思うよ。アザラシなんてすごく捕まえにくいし、まずいかも知れない。でもそれを食べてかろうじて生き残ってきた。食べるというのは惨めなことなんだ。だから僕は美食家は嫌いだ。食べるということの惨めさをごまかして、何か素敵なことでもしているように気取っているから。」
猛獣の稽古で大切なのは、意欲的でありながら、いつもあっさりあきらめることができるということだった。勇気など何の役にも立たない。……雪山を登る時と同じで名誉欲にかられて無理をすれば命取りになる。
生きるということはどうやら外へ出たいという気持ちのことらしい。
何が聞こえても耳を澄ましているうちに、あらゆる音声の中に宿る微妙な違い、その違いの組み合わせによってなりたっている今という不思議な空間の一回きりの色合いが聞き分けられるようになってきた。
せっかく外に出られたと思って喜んでいたけど、動物園にはまたその外があるのだ。外には外がある。どこまで行ったらそれ以上、外に出られないくらいの究極の外に行き着くんだろう。
ところが哺乳類はその名の通り、生まれてすぐはミルクからしか栄養が取れないようにできている。だから鳥のようにいつも前向きに考えることができなくて、つい乳くさい昔を振り返ってしまう。
もし生きていても、二度と逢えないのかも知れない。でもひょっとしたら逢えたかもしれない。ひょっとしたらと思いながら生きていくことを人間は希望と呼んでいる。その希望が死んだ。