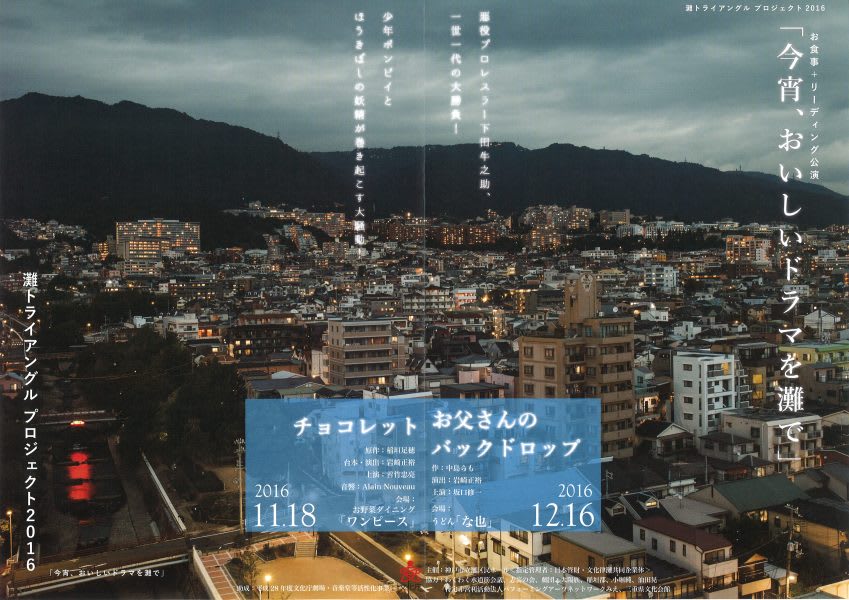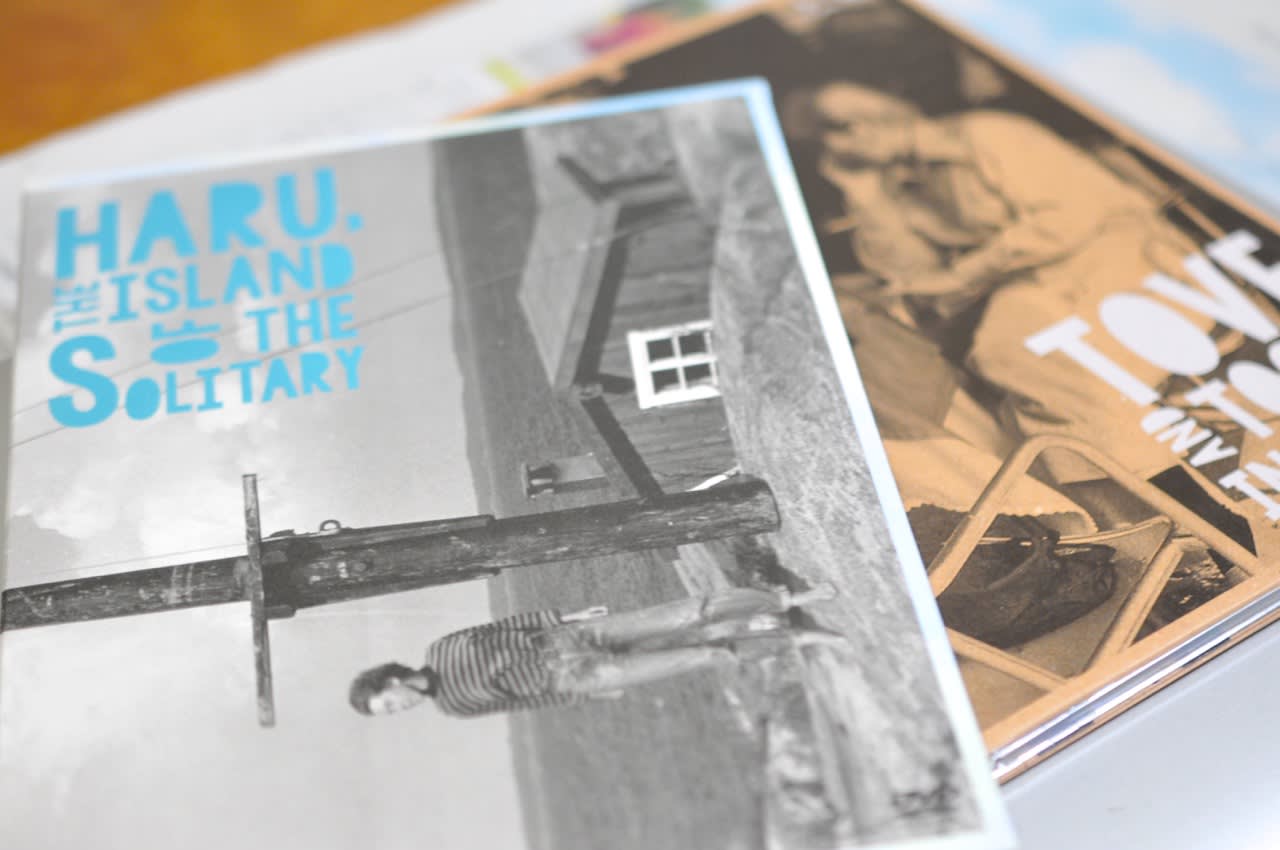”ファンタスティック・エキセントリック
アール・ブリュットの「王」が描いた夢物語”
アールブリュットやアウトサイダーアートに関しては
話を聞いたり本を読んだりしても、知識と気持ちがどうもぎくしゃくして
あんまりわざわざ見に行こうと思わないことが多いのです。
作品が素晴らしくて感嘆しても、なんだかとても疲れてしまうし
流行モノ的にもてはやされてたりすると、作品じゃなく
世間の簡単さがいやになるし。
今回、兵庫県立美術館で、一緒にやってるハナヤ勘兵衛の写真展も見たくて、
両方見てきたんだけど、やっぱり結局ヴェルフリが強烈すぎて、
ハナヤ勘兵衛の印象が薄くなっちゃった。
ヴェルフリの、鉛筆だけで描かれた最初の1、2枚目からもう、
ふぁ〜!と圧倒されてしまった。
欧米でのアウトサイダー・アート、アール・ブリュットといえば日本では
ヘンリー・ダーガーがわりと有名なんじゃないかと思うけど
世界的にはアドルフ・ヴェルリフの方が有名なくらいなのだそうです。
それも納得できる質と量でした。
展示では、普段は芸術家の年表はさほど熱心には見ないけど
ヴェルフリのは隅々まで見てしまった。
アドルフ・ヴェルフリ(Adolf Wölfli 1864-1930)はスイス郊外で生まれ
貧困の中里子に出され、成人後には幼女強姦未遂事件など幾つか起こした末に、
1895 年にヴァルダウ精神病院に収容されました。
病院では、彼の症状はいっそうひどくなり、衝動的に暴れたりするので
個室に移され、以後66歳で亡くなるまでそこで暮らしたそうです。
病院に入って数年後、30代半ばから大量の作品を創作するようになります。
これが、量もすごいけど質もすごい。
『揺りかごから墓場まで』、『地理と代数の書』、『葬送行進曲』といった
自叙伝や冒険譚、その他分類不可能な膨大な量の本にまとめられていて、
絵だけでなく物語や彼オリジナルの楽譜(のようなもの)や数字のようなもの、
言葉のようなもので溢れかえっています。
自身を聖アドルフ2世と名乗り、自分だけの王国を紙の上に縦横無尽に描き出し、
世界を旅したり、独自の数字の単位や言葉を作ったり。
こういうのって、以前子供のアートクラスをしてた時のことを思い出すと、
想像力豊かで感受性の強い小学生の男子に近い感性だなと思うんだけど、
ただ、それがひたすら過剰なところが違う。過剰という豊穣。
そしてこのような濃い集中がどこまでも続くということに驚きます。
ヴェルフリは、なくなる前にすでに多少評価されてたようで
絵を求められることもあったらしく、物語ではなく一枚ずつの紙に
売るために描かれた「ブロード・クンスト」という作品もあり、
それらが並ぶ様は、少し、先日見たクートラスのカルトを思い出させました。
色々な意味で似ているところは多いと思います。
ヴェルフリは、なくなる前にすでに多少評価されてたようで
絵を求められることもあったらしく、物語ではなく一枚ずつの紙に書かれた
「ブロード・クンスト」という作品もあり、それらが並ぶ様は、少し
先日見た→クートラスのカルトを思い出させました。
色々な意味で共通点は多いと思う。
他のアール・ブリュット作品もそうだけど、ヴェルフリを見てつくづく、
人間の想像力というものが、分別や常識などの誰にでもありがちな重石を外せば
ここまで広がるものなのだということに、
その言葉を失う豊饒さ、過剰さの嵐に感嘆しました。
そしてわたし自身の持つ、自分自身を縛り余計で凡庸な仕事をさせる、
自我や自意識というつまらない重石について考えてしまいます。
それが人並みにあるおかげで、なんとか社会生活ができているわけだけど、
よく考えて、もう少し重石を軽くして、
もう一度絵を描こうかとか、ちょっと思ってしまった。
アール・ブリュットの「王」が描いた夢物語”
アールブリュットやアウトサイダーアートに関しては
話を聞いたり本を読んだりしても、知識と気持ちがどうもぎくしゃくして
あんまりわざわざ見に行こうと思わないことが多いのです。
作品が素晴らしくて感嘆しても、なんだかとても疲れてしまうし
流行モノ的にもてはやされてたりすると、作品じゃなく
世間の簡単さがいやになるし。
今回、兵庫県立美術館で、一緒にやってるハナヤ勘兵衛の写真展も見たくて、
両方見てきたんだけど、やっぱり結局ヴェルフリが強烈すぎて、
ハナヤ勘兵衛の印象が薄くなっちゃった。
ヴェルフリの、鉛筆だけで描かれた最初の1、2枚目からもう、
ふぁ〜!と圧倒されてしまった。
欧米でのアウトサイダー・アート、アール・ブリュットといえば日本では
ヘンリー・ダーガーがわりと有名なんじゃないかと思うけど
世界的にはアドルフ・ヴェルリフの方が有名なくらいなのだそうです。
それも納得できる質と量でした。
展示では、普段は芸術家の年表はさほど熱心には見ないけど
ヴェルフリのは隅々まで見てしまった。
アドルフ・ヴェルフリ(Adolf Wölfli 1864-1930)はスイス郊外で生まれ
貧困の中里子に出され、成人後には幼女強姦未遂事件など幾つか起こした末に、
1895 年にヴァルダウ精神病院に収容されました。
病院では、彼の症状はいっそうひどくなり、衝動的に暴れたりするので
個室に移され、以後66歳で亡くなるまでそこで暮らしたそうです。
病院に入って数年後、30代半ばから大量の作品を創作するようになります。
これが、量もすごいけど質もすごい。
『揺りかごから墓場まで』、『地理と代数の書』、『葬送行進曲』といった
自叙伝や冒険譚、その他分類不可能な膨大な量の本にまとめられていて、
絵だけでなく物語や彼オリジナルの楽譜(のようなもの)や数字のようなもの、
言葉のようなもので溢れかえっています。
自身を聖アドルフ2世と名乗り、自分だけの王国を紙の上に縦横無尽に描き出し、
世界を旅したり、独自の数字の単位や言葉を作ったり。
こういうのって、以前子供のアートクラスをしてた時のことを思い出すと、
想像力豊かで感受性の強い小学生の男子に近い感性だなと思うんだけど、
ただ、それがひたすら過剰なところが違う。過剰という豊穣。
そしてこのような濃い集中がどこまでも続くということに驚きます。
ヴェルフリは、なくなる前にすでに多少評価されてたようで
絵を求められることもあったらしく、物語ではなく一枚ずつの紙に
売るために描かれた「ブロード・クンスト」という作品もあり、
それらが並ぶ様は、少し、先日見たクートラスのカルトを思い出させました。
色々な意味で似ているところは多いと思います。
ヴェルフリは、なくなる前にすでに多少評価されてたようで
絵を求められることもあったらしく、物語ではなく一枚ずつの紙に書かれた
「ブロード・クンスト」という作品もあり、それらが並ぶ様は、少し
先日見た→クートラスのカルトを思い出させました。
色々な意味で共通点は多いと思う。
他のアール・ブリュット作品もそうだけど、ヴェルフリを見てつくづく、
人間の想像力というものが、分別や常識などの誰にでもありがちな重石を外せば
ここまで広がるものなのだということに、
その言葉を失う豊饒さ、過剰さの嵐に感嘆しました。
そしてわたし自身の持つ、自分自身を縛り余計で凡庸な仕事をさせる、
自我や自意識というつまらない重石について考えてしまいます。
それが人並みにあるおかげで、なんとか社会生活ができているわけだけど、
よく考えて、もう少し重石を軽くして、
もう一度絵を描こうかとか、ちょっと思ってしまった。