予告編見て、なんか薄っぺらな映画なんじゃないかと、見ないつもりでいたら
近くの映画館で小栗康平監督のトークがあるというので聴きに行きました。
そして、そのあと映画も続けてみたのですが、
トークも映画も面白かったです。見てよかった。
予告編では、この映画の良さは出てないなぁと思いました。
小栗監督は、もう70代だと思うのですが滅法頭の切れる方ですね。
訥々と落ち着いた話し方ながら、とても整理されて筋道立っていて、
自然で余裕のある語りをなさいます。
映画のカット数の話から(「FOUJITA」は結構長回しの多い映画)、
画角とワンショットの長さとの関係、といったところから始まって、
1時間ほどの間に、いくつも興味深い話をされました。
最後のお客さんからの質問の時に、
映画の中に出てくるクリュニー美術館のタペストリーを
藤田が見るシーンは史実に基づくのか?と聞かれて、
いえ、そういう記録はないんですけど、だってあれ美しいでしょ?
本当に美しいんですよね~。だから。と答えてらした口調が
しみじみとしてよかった。
またラストに説明がなさすぎて、知識がない者にはわからないんじゃないか?
という質問には、藤田のその後を見事に簡潔な数行の説明で述べてから、
~という字幕を最後に流せば、そのことはわかるでしょうけど
わかっても、だからなに・・・?
っていうことですよ、と答えられた。そうだなぁ。
さて映画ですが、藤田嗣治がパリで時代の寵児としてもてはやされた20年代と
日本で戦争に協力して戦争絵画を描いていた時期とが描かれます。
パリでも、パーティーに明け暮れた破天荒な日々ばかりではなく、
日本人の画家を連れて、ここで君らは勝てるのか?と話したり、
考え深く複雑でやや変わり者の性格に描かれています。
日本では日本人の妻(中谷美紀がちょっと怖いメイクでやってますが
それはそれで、なんともいえない雪女みたいな美しさがあります)と
田舎に疎開して、田舎の名士的に大事にされながら
戦争絵画を描き、戦争絵画展を開き、何かの名誉職についたりしている日々。
家のトタン屋根まで軍に提供しないといけない苦しい状況の中でも
結構いい着物を着て、芸術のことを考え、一目置かれ尊敬されています。
オダギリジョーは頑張っているけど、大きな動きが苦手な人なんですかねぇ?
あと、みんな、本物にそっくりっていうけど
あの髪型とあのメガネとあのヒゲにしたら割と誰でも藤田に似ると思うんだけど。
小栗監督は、細かいところでは何箇所か、
あちこちからお叱りを受けた、など笑って言いながら
でも映像には力を入れた自負心があるようで、
映画制作にはお金がかかるという話の中で
この映画の画面の重厚さや深みを出すには
あんまり低予算では無理なんです、これくらいはかかるんです、
だからしょっちゅうは作れないんです、と言ってただけあって
(とても寡作な監督です)映像は丁寧に作られてたと思います。
予告編はなんか安っぽい気もするけど実際はもっといいと思った。
ここに描かれるちょっと舞台じみた20年代のパリの喧騒と絢爛は、
ヘミングウェイの、パリは移動祝祭日だと言った言葉を思い出させるし、
前述したクリュニー美術館ののタペストリーもきれいで、
実物を以前→中之島の国立国際美術館で見たのを思い出しました。
モンマルトルの女王キキを演じた女優さんは、とっても豊満で、歌が上手くて
実物もこんな感じだったのかな。フランス女感ムンムンでした。
一方、日本の田舎では、幻想的なシーン、もやに包まれた景色が、
それはそれはきれいです。
そして最後の方に出るキツネのシーン・・・。
(以下ちょっとネタバレですが)
CGのキツネが跳び回るシーンがあって、これが
とってつけたようだとか、ぶち壊しだだとか批判されてるんですが
自分では気に入ってるんです!と監督は言いきってたけど、
わたしは少し不満かなぁ。
茶色いふっくらした大きなキツネではなく、
もう少し痩せた、真っ白いきつねならよかったのに、と。
思い出したのは去年の10月、大阪の難波宮で見た野外文楽のキツネでした。

文楽ですから黒子の人形遣いが操るのですが、
ちょっとユーモラスな動きを交えながらも怪しく素早く
右に左に跳び回る様をとても興味深く見たので、
あのキツネのイメージの方がずっとぴったりくるのに、と思ったのでした。
暗がりの中でぼうっと白く光るキツネなら、もっとよかったのになぁ。

藤田の絵についてはここでは説明しません。興味のある人は調べてください。
当時のパリで、日本的なところがあってユニークでありながら、
西洋にも受け入れられる美があり、これは売れただろうなぁと思います。
個人的には嫌いじゃないけど特に好きというわけではなかったのですが、
一度ちゃんとまとめてみてみようと思いました。
監督の話からもう一点。
映画の中で藤田の友達が高村光太郎の詩を朗読するところがあるのですが、
藤田はその青臭さ泥臭さが好きじゃなかったという感じがちょっと描かれています。
高村光太郎も戦争協力をして、戦志高揚の詩を書いていますが
敗戦後はその過ちを認めはっきりと謝ったそうで、
戦争協力しながら謝ることなどなく、フランスへ行っちゃった藤田が面白いと。
そんなみっともないことできるかい、という感じだったのかな?
実際の藤田は戦争が終わるまで日本は勝つと信じていたようなのですが
そういうダサい自分をなかったことにしたかったのでしょうか?
モラルからでも誠実さからでもなく、美意識から、
ダサい自分が許せない人だったのかなと、ちょっと勝手に想像しました。












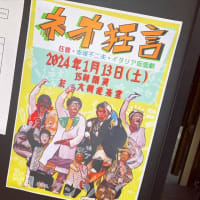





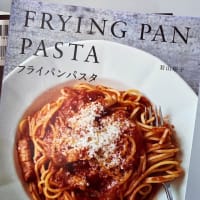

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます