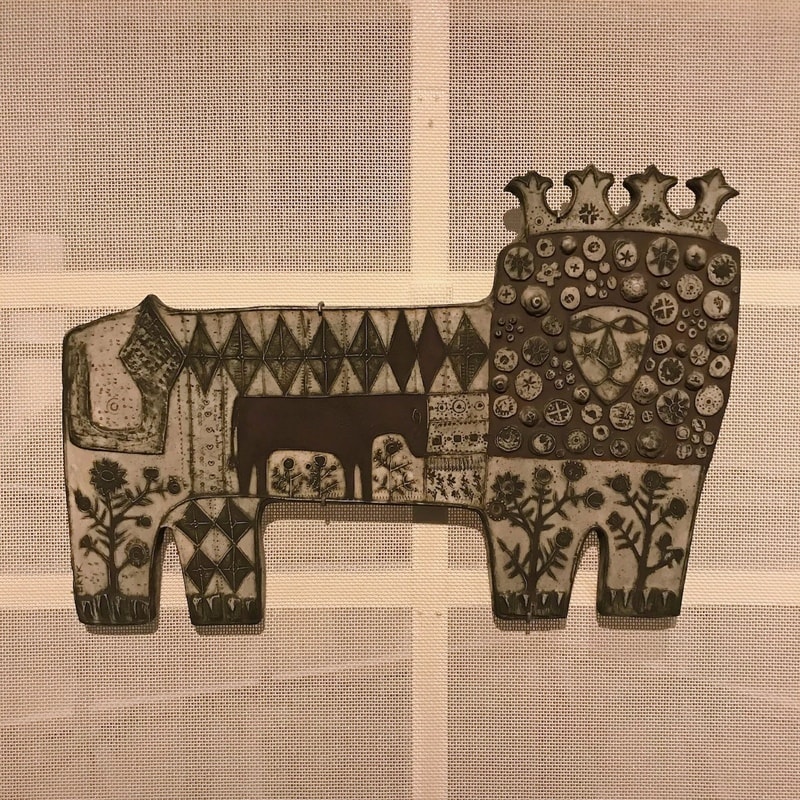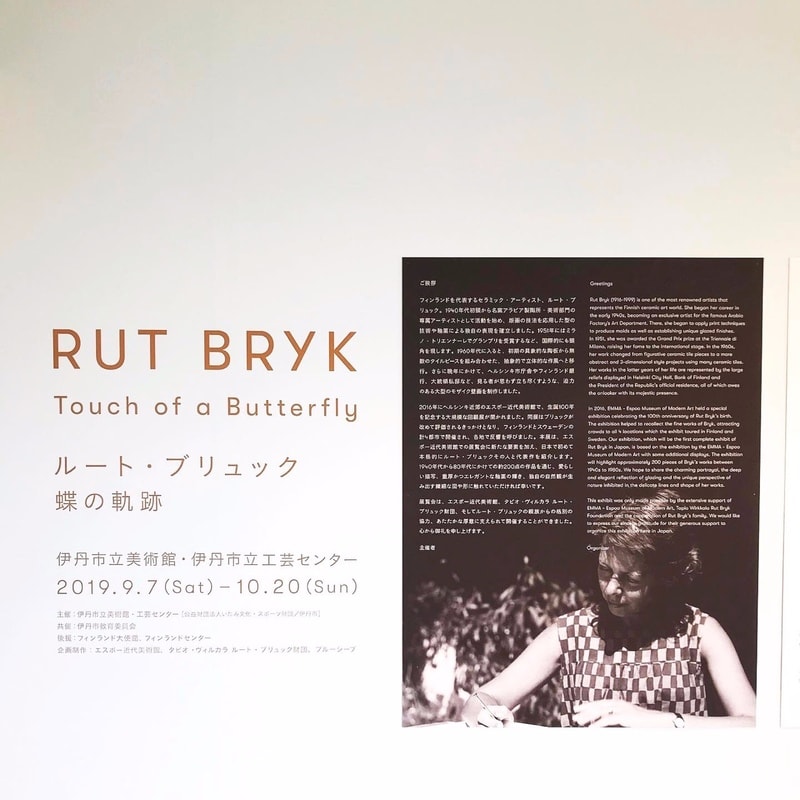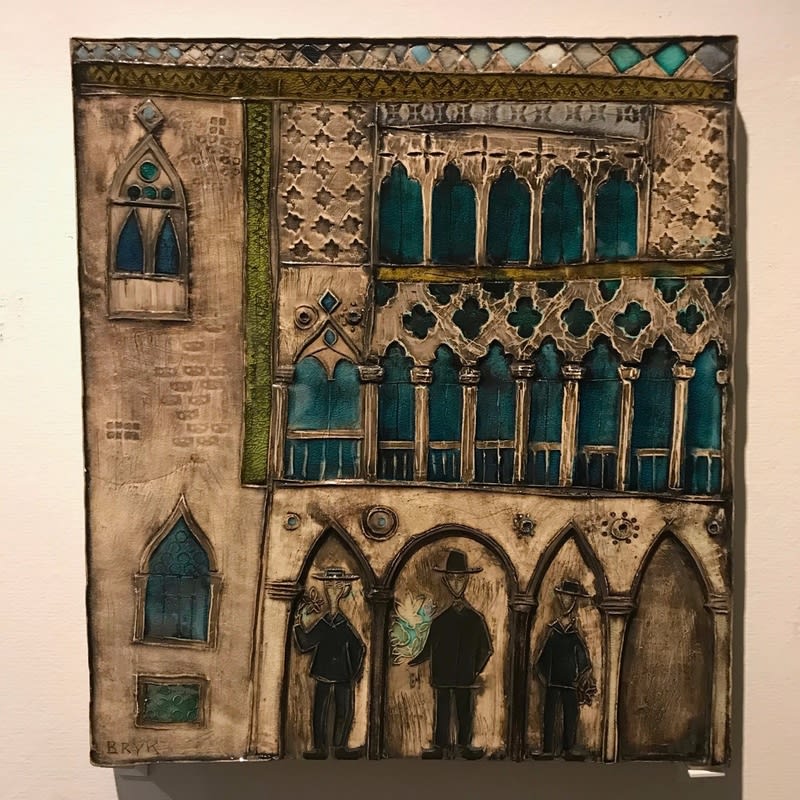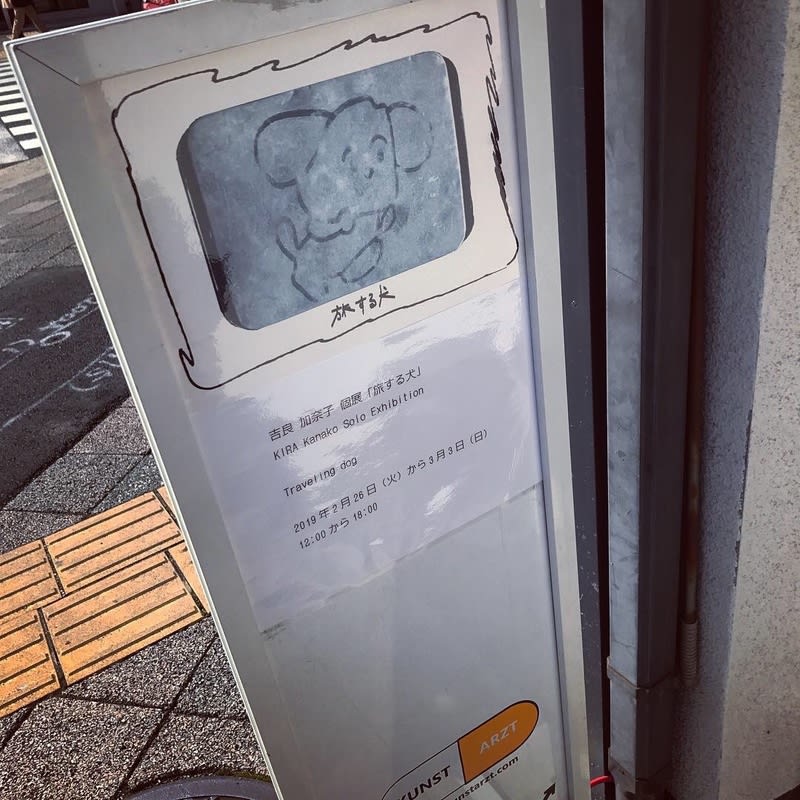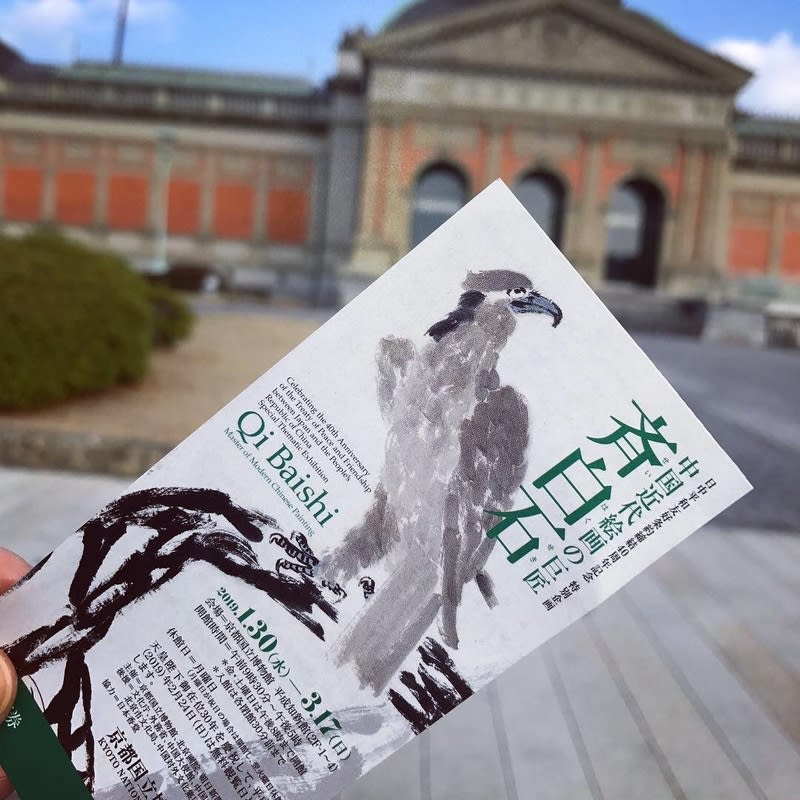あいちトリエンナーレの一連のことを振り返ってて、
実際に何度か行った人の展示があった時と撤去後の比較レポートを読んだりしてて、
根本的なところでモヤモヤし続けていました。
聡明でニュートラルに見える人でも、
表現の自由には大きくイエス、でも慰安婦問題にはそぉっとノー、という発言なんだよね。
展示内容に問題はあるけど表現の自由のためには展示するべき、ってスタンス。
この展示内容に問題がある=「歴史修正主義者の日本人を不快にさせるもの」は問題である
という認識ってことよね?結局慰安婦問題にはノー、ってことよね。うーん。
むしろそう言うスタンスこそが聡明ということになっているのかもしれない。うーん。
アート畑の人はすごく賢い人もそんな感じで、こっそり、がっかりしている。
わたしにはとうていわからない難しいことを、大変な知識と教養を元に話すような人でも。
表現の自由の方が賛同を得やすいのか大きな声で主張しやすい、とは思う。
でも、慰安婦問題は微妙だしどうかと思うけど表現の自由はアートには大事だからね、
という姿勢は、結局もっと根本的で大きな問題から目を背けてるだけだと思うんだけどな。
元々の歴史問題、人権問題をスルーして、単に表現の自由イシューにしてしまうのって、
慰安婦問題は問題であるというのを既成事実のようにしてしまうところもあって
それって歴史修正主義に加担することになっちゃうと思うんだけど。
そういう人たちにもやもやしていたところで、東京藝大の元学長、文化庁の宮田長官。
この人が、あいちトリエンナーレに関しても、ずっと黙ってた末に弾圧側として発表をして
仮にも東京藝大の元学長が、まさかそこまでひどくはないよね?という思いを砕かれた。
東京藝大に、私個人はなんのしがらももないけど、日本でただ「芸大」といえば
この学校としか思われないほど、日本の芸術アカデミズムの中心で頂点であるわけで、
芸術が好きで好きでやりたくてやりたくて、芸術のために死ねるくらいの気持ちで
死ぬ努力をしてそこに入ったはずの人やその周りにいる人たちが、今、怒ってくれれば
わたしもまだまだスッキリするのだけど、どうもそういう声を見ない。
むしろ、この人はいい人なんだとか板挟みで苦しんでいるはずとか庇う声ばかり耳にした。
わたしもそれでしばらくは板挟みは確かに辛いしな、と思って様子を見ていたけど
結局わかったのは、はっきり、この人は単なる政権の犬だということです。
権力の手先。そんな者に芸術をどうこうする資格はないと思うくらいの、腐った犬。
(罪のないわんこたちごめんよ)
基本的に激しい言い方をかなり避けるわたしが人に対して腐った犬とまで言うのは珍しいよ。
それだけ裏切られた思いがつらいのです。心からがっかりしたし怒ってる。
宮田文化庁長官が、文楽のパンフレットに書いてる挨拶文を見ても、よくわかる。
権力の犬以外何者でもない。この人を擁護してた藝大関係者の甘さを改めて感じた。
というかこの人を批判しない藝大にはもう、裏切られた感しかなくて、余計腹たつ。
権力の犬だった人で優れた芸術家っているんだろうか?
反語的表現ではなく、普通の疑問。いるのかな?
あいちトリエンナーレの問題で、わたしが一番怒っているのは実はこの人に対してです。
馬鹿なだけの河村名古屋市長なんかより、この人の欺瞞の方が許せないのです。
それでもこの人をかばうなら、
もう日本の現代アート界に見るものなんかないわ、とやけくそになるほど残念。
心を権力に売り渡した政府御用達の芸術なんか、滅びればいい。
お金と権威で磨かれたきれいな服できれいな場所で腐った作品を褒めていればいい。
人権問題や歴史を振り返ることに背を向ける人や、表現の自由より権力に媚びる人たちの
アート畑なんか、ほんとうにどうでもいい。わたし忘れないからねこれ。
実際に何度か行った人の展示があった時と撤去後の比較レポートを読んだりしてて、
根本的なところでモヤモヤし続けていました。
聡明でニュートラルに見える人でも、
表現の自由には大きくイエス、でも慰安婦問題にはそぉっとノー、という発言なんだよね。
展示内容に問題はあるけど表現の自由のためには展示するべき、ってスタンス。
この展示内容に問題がある=「歴史修正主義者の日本人を不快にさせるもの」は問題である
という認識ってことよね?結局慰安婦問題にはノー、ってことよね。うーん。
むしろそう言うスタンスこそが聡明ということになっているのかもしれない。うーん。
アート畑の人はすごく賢い人もそんな感じで、こっそり、がっかりしている。
わたしにはとうていわからない難しいことを、大変な知識と教養を元に話すような人でも。
表現の自由の方が賛同を得やすいのか大きな声で主張しやすい、とは思う。
でも、慰安婦問題は微妙だしどうかと思うけど表現の自由はアートには大事だからね、
という姿勢は、結局もっと根本的で大きな問題から目を背けてるだけだと思うんだけどな。
元々の歴史問題、人権問題をスルーして、単に表現の自由イシューにしてしまうのって、
慰安婦問題は問題であるというのを既成事実のようにしてしまうところもあって
それって歴史修正主義に加担することになっちゃうと思うんだけど。
そういう人たちにもやもやしていたところで、東京藝大の元学長、文化庁の宮田長官。
この人が、あいちトリエンナーレに関しても、ずっと黙ってた末に弾圧側として発表をして
仮にも東京藝大の元学長が、まさかそこまでひどくはないよね?という思いを砕かれた。
東京藝大に、私個人はなんのしがらももないけど、日本でただ「芸大」といえば
この学校としか思われないほど、日本の芸術アカデミズムの中心で頂点であるわけで、
芸術が好きで好きでやりたくてやりたくて、芸術のために死ねるくらいの気持ちで
死ぬ努力をしてそこに入ったはずの人やその周りにいる人たちが、今、怒ってくれれば
わたしもまだまだスッキリするのだけど、どうもそういう声を見ない。
むしろ、この人はいい人なんだとか板挟みで苦しんでいるはずとか庇う声ばかり耳にした。
わたしもそれでしばらくは板挟みは確かに辛いしな、と思って様子を見ていたけど
結局わかったのは、はっきり、この人は単なる政権の犬だということです。
権力の手先。そんな者に芸術をどうこうする資格はないと思うくらいの、腐った犬。
(罪のないわんこたちごめんよ)
基本的に激しい言い方をかなり避けるわたしが人に対して腐った犬とまで言うのは珍しいよ。
それだけ裏切られた思いがつらいのです。心からがっかりしたし怒ってる。
宮田文化庁長官が、文楽のパンフレットに書いてる挨拶文を見ても、よくわかる。
権力の犬以外何者でもない。この人を擁護してた藝大関係者の甘さを改めて感じた。
というかこの人を批判しない藝大にはもう、裏切られた感しかなくて、余計腹たつ。
権力の犬だった人で優れた芸術家っているんだろうか?
反語的表現ではなく、普通の疑問。いるのかな?
あいちトリエンナーレの問題で、わたしが一番怒っているのは実はこの人に対してです。
馬鹿なだけの河村名古屋市長なんかより、この人の欺瞞の方が許せないのです。
それでもこの人をかばうなら、
もう日本の現代アート界に見るものなんかないわ、とやけくそになるほど残念。
心を権力に売り渡した政府御用達の芸術なんか、滅びればいい。
お金と権威で磨かれたきれいな服できれいな場所で腐った作品を褒めていればいい。
人権問題や歴史を振り返ることに背を向ける人や、表現の自由より権力に媚びる人たちの
アート畑なんか、ほんとうにどうでもいい。わたし忘れないからねこれ。