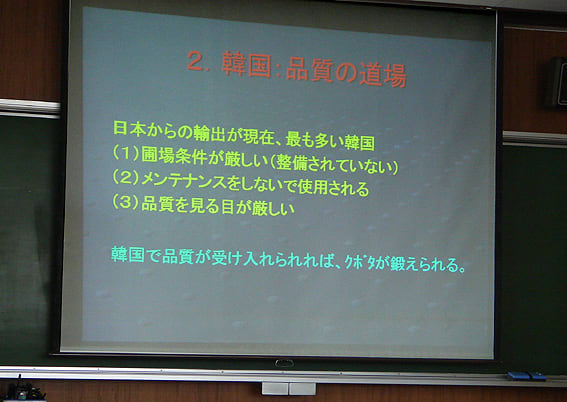「新車販売30年ぶり低水準、若者の車離れか
日本自動車販売協会連合会が2日発表した上半期(1~6月)の新車販売台数は、前年同期比10・5%減の178万8440台だった。前年同期を下回ったのは2年連続で、1977年上期(174万2109台)以来30年ぶりの低水準。
不振の背景には、ガソリン価格高騰や若者の「車離れ」などが指摘されている。自販連は「月間でも24カ月連続のマイナス。車に関する税金の簡素化などの対策が必要だ」と訴えている。
車種別では販売の約5割を占める小型乗用車が15・1%減と大きく落ち込んだほか、トラックやバスも2年ぶりの減少に。会社別では日産自動車が13・2%減、トヨタ自動車(レクサスを除く)も10・9%減、ホンダが5・6%減と大手3社がそろって減少した。
一方、全国軽自動車協会連合会が同日発表した上半期の新車販売台数は、1・7%減の105万4080台と4年ぶりに前年同期を下回った。新車投入が相次ぎ、売れ行きが好調だった前年からの反動減が要因だった。」
次に若者達の「声」を紹介しよう。
>免許取るのに金かかりすぎだと思う(広島県の男性)
>保険や駐車場代やらかかるもんね。いらないよね(北区の男性)
>いつホームレスになるか分からんし1円でも多く現金を持ってたほうがいいと思う(熊本県の男性)
>駐車できる所がないから乗れない(千葉県の男性)
>車買わないだけで、自動車産業と保険・税金の魔の手か逃れることができるから買わねーんだよw
>生活保護以下で、いつ首を切られるかわからないワープアで結婚も出来ないのに車なんて維持したら家賃払えません
以上を要約したコメントがあった。
>若者が夢も車も持てない社会それが今の日本の現状。
中小正社員=ほとんど昇給がない
非正規雇用=生きてくだけで精一杯
ニート =外に出る必要が薄い
上記についてはくわどんさん(http://kuwadong.blog34.fc2.com/blog-entry-612.html)がズバリと言い当てている。
すなわち
「所得が相対的に高く安定している正社員が減り、
所得が相対的に低く不安定な派遣などの非正社員比率が
高くなった。特に若い世代でそうなっていった。
また、トヨタなどは、過去最高の利益を上げているにも
関わらず、賃金のベアは上げず、賃金上昇は抑制ぎみだ。
そうなれば、所得の伸びは小幅か、伸びないので、
消費は弱くなる。その結果、自動車の売り上げが低下
するのは当然だ。
それで、自動車の売り上げが上がらないと嘆いているのは
笑止千万だ!! 」
まさにその通りだと思う。
くわどんさんはこう結んでいる。
「フォードを作ったヘンリー・フォードは
労働者の賃金を高めにした。
それは、労働者も消費者であり
彼らの所得が上がらないと、
車は売れないと考えたからだ。
労働者への高賃金は将来の投資であったのだ。
今の大企業の幹部の発想はあまりにも近視眼的に
感じる。
労働者への分配を将来への投資と思えばいいのではないか。」
そうしてみると
トヨタ・富士重が共同開発 スポーツカーを検討
http://www.asahi.com/business/update/0809/TKY200708090396.html というのは的外れ、大いなる勘違いといえる。
加えて自動車産業の下請けいじめの悪しき常套手段のCD(コストダウン)もこの傾向に一役買っている。何の根拠があって、毎年5%もの値下げを押し付けられるのだろうか?半ば強制的なISO(典型的な資格商売!)取得押し付けも企業経営を圧迫し、そのはけ口が正規社員の縮小、派遣や非正規雇用の拡大につながっている。そのくせ、「紹介販売」と称して系列に自社の自動車を買わせるノルマを強要しているのは納得がいかない。現状で自動車産業に働く中小下請けの若者たちが自動車(新車)購入意欲を持つとは到底思えない。
「車は嗜好品で一つの選択肢である。」という考え方が最近の一般の見方である。事実、都会では「選択」されない事態が進行している。ならば車を売る側も視野を広げ多元的な観点でのぞまなければ、両者はかみ合わず、いずれ日本の車社会は崩壊していくのではなかろうか。
おまけ→車の維持費について知りたい方はこちら「くるまをやめる」をごらん下さい。