近くの生協で九州物産の販売をしていたのでめぼしいものがないかと暫らく眺めていたが、「一口香(いっこっこう)」が展示してあったので買った。「一口香」は長崎名物、故郷島原でも生産販売していたので、何度も食べたことがある。生協のフロアーには、他にも「黒棒」や「 兵六餅」「ボンタンアメ」「からいも飴」などの好物が並んでいたが、やはり先に手が出るのは「一口香」。
 「買ってすぐに半分無くなった一口香」
「買ってすぐに半分無くなった一口香」
長崎名物のお菓子と言えば、カステラの次ぐらいに有名なのが「一口香」。福砂屋の「カステラ」などのブランド菓子と違い、極普通に食べられるお菓子で、饅頭のような外見のカリッとした焼き菓子だが、特徴的なのが中身が空洞。今回の製造元をみると、雲仙市の国見町(昔の多比良町)の菓子屋(牧瀬製菓)製造の製品とある。食べてみると、田舎の島原で食べていたものと少し違う。8個入り200円。記憶では大体が10個入り200円だったように覚えているので少し高い。国見町と言えば有名なサッカー選手を輩出した国見高校の地元だが、直径約6.5cmと中くらいの大きさで、外形は平たいけど肉厚で中は本当の中空ではなく食感はソフト。ショウガ味がした。島原で食べていたものは、もうすこし皮が固く、中は本当の中空で表皮がすこし窪んでいた。食べると、少しゴマの香りがしたように記憶している。どちらが美味いかは、食べた記憶だけだけど、どちらも旨い。が、食べた食感と味が少し違うが、好みを言えば中が中空の方が良いかなと言う範囲。
早い話、どうでも良いことなんだが、この時期、生協西明石の展示場ではチョコレートの占拠率が高くなっている。しかし店を見ていると、チョコレートより九州の菓子を見ている買い物客が多い。北海道物産展だと六花亭のチョコに手が出るし、九州物産では大昔、小さい頃に食べた100円前後のお菓子をついつい買う羽目になる。そうは言っても、近くのスーパーでは九州か北海道の物産展が多く他は見ることも少なく、時には名古屋物産の「青柳ういろう」や「あわ雪」も食べて見たい。
 「買ってすぐに半分無くなった一口香」
「買ってすぐに半分無くなった一口香」長崎名物のお菓子と言えば、カステラの次ぐらいに有名なのが「一口香」。福砂屋の「カステラ」などのブランド菓子と違い、極普通に食べられるお菓子で、饅頭のような外見のカリッとした焼き菓子だが、特徴的なのが中身が空洞。今回の製造元をみると、雲仙市の国見町(昔の多比良町)の菓子屋(牧瀬製菓)製造の製品とある。食べてみると、田舎の島原で食べていたものと少し違う。8個入り200円。記憶では大体が10個入り200円だったように覚えているので少し高い。国見町と言えば有名なサッカー選手を輩出した国見高校の地元だが、直径約6.5cmと中くらいの大きさで、外形は平たいけど肉厚で中は本当の中空ではなく食感はソフト。ショウガ味がした。島原で食べていたものは、もうすこし皮が固く、中は本当の中空で表皮がすこし窪んでいた。食べると、少しゴマの香りがしたように記憶している。どちらが美味いかは、食べた記憶だけだけど、どちらも旨い。が、食べた食感と味が少し違うが、好みを言えば中が中空の方が良いかなと言う範囲。
早い話、どうでも良いことなんだが、この時期、生協西明石の展示場ではチョコレートの占拠率が高くなっている。しかし店を見ていると、チョコレートより九州の菓子を見ている買い物客が多い。北海道物産展だと六花亭のチョコに手が出るし、九州物産では大昔、小さい頃に食べた100円前後のお菓子をついつい買う羽目になる。そうは言っても、近くのスーパーでは九州か北海道の物産展が多く他は見ることも少なく、時には名古屋物産の「青柳ういろう」や「あわ雪」も食べて見たい。










 「FB Nagasaki365」」
「FB Nagasaki365」」
 「日経」
「日経」

 「六角精児の呑のみ鉄本線・日本旅「春・島原鉄道を呑(の)む!」
「六角精児の呑のみ鉄本線・日本旅「春・島原鉄道を呑(の)む!」
 「標高 1483mの平成新山」
「標高 1483mの平成新山」

 「NHK」
「NHK」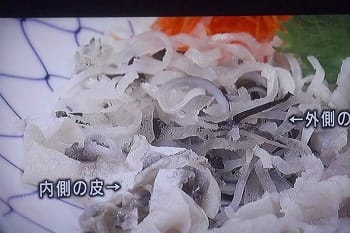

 「Nagasaki 365」
「Nagasaki 365」


 本件、気になったのでネット検索すると、「
本件、気になったのでネット検索すると、「 「曽木の滝:じゃらんネット」
「曽木の滝:じゃらんネット」 「焼酎のミニボトル」
「焼酎のミニボトル」

 「錦町役場 FB」
「錦町役場 FB」







