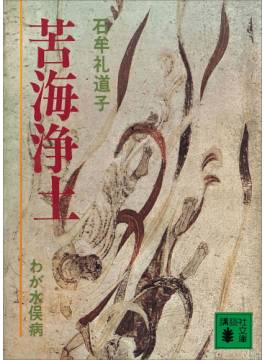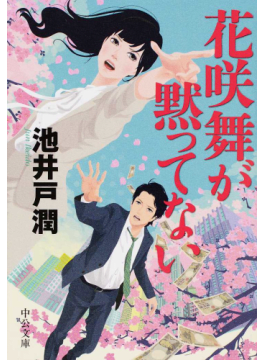なかなか文庫化されないので単行本を買ってしまいました。『アンマーとぼくら』(2016)は、かりゆし58の「アンマー」に着想を得て書き下ろされた長編だそうで、「かりゆし58」もその名曲だという「アンマー」も知らなかった私は早速YouTubeで検索して、その曲の生誕秘話のビデオまで見てしまったのですが、そうして受けた印象は確かにこの『アンマーとぼくら』の作品の中に生きています。設定は全然違うのですが。
主人公のリョウは休暇で沖縄に帰って来て、親孝行のために「おかあさん」と島内観光して3日間を過ごすお話しですが、この「おかあさん」は実は継母で、実の母親「お母さん」は北海道で教師をしていましたが、彼が小学生の時に癌で亡くなってしまっていました。カメラマンの父親はその喪失に耐えられなかったらしく、撮影旅行に出ることが一層増え、死後1年かそこらで沖縄でガイドをしてもらった女性「晴子さん」に恋していまい、再婚することになり、早々に北海道の家を売って、息子を連れて沖縄に移住していまいます。
作品ではこの無神経ダメ父との思い出が丹念に語られます。お母さんの今際の際の言葉「お父さんを許してあげてね。お父さんは、ただ、子供なだけなのよ」というプロローグで始まるだけあって、この作品は「アンマー(母)」にだけ捧げられる息子の感謝の気持ちだけではなく、この再婚後たった4年であまりにも早くこの世を去ってしまったダメ父にも和解と理解の気持ちが捧げられています。
また、かりゆし58の前川真吾氏が「「女性」と「母性」、この小説に出てくる母親たちの愛情には、二つ分の深さがある、二乗分の美しさがある。」とコメントされたらしいですが、その通り、二人の母、「お母さん」と「おかあさん」の女性としての父に対する愛情も切なく描写されています。その辺はやはり女性の視点なのかなと思いますが。
そしてこの「3日間」が、沖縄が起こしたある種の奇跡であるという趣向も味わい深いです。過去の回想というだけでなく、妙に過去の出来事とその当時の自分の姿を質感を持って感じられることや、自分の「現在」の記憶があやふやであることなどただの休暇の日々でないという違和感が漂っています。それがどういう現象だったのかという説明はありませんし、野暮でしょう。ただ最後にリョウこと坂本竜馬がなぜ沖縄に来ていたのかという現在の本当の理由と状況は説明されています。
偉大な母の愛情やダメ父の分かりづらい愛情も結構ぐっときますが、一番ぐっと来たのは女性としての晴子さんが亡くなった夫に思いを馳せて「いつかニライカナイで会いましょう」と言うところと、あの世で取り合いにならないようにと前妻のお墓参りに行って彼の「魂を分ける」取り決めをしてきたというところでしょうか。女性としても人間としても懐が深い感じがしますね。あと、棺の中のダンナにひっそりとキスをするところも切なくていいシーンでした。
泣けるところが結構あるので外で読む時は要注意かもしれませんね。
親子関係が希薄な私はこうした親子の絆みたいなものが羨ましくもあります。
書評:有川浩著、『レインツリーの国 World of Delight』(角川文庫)
書評:有川浩著、『ストーリー・セラー』(幻冬舎文庫)
書評:有川浩著、自衛隊3部作『塩の街』、『空の中』、『海の底』(角川文庫)
書評:有川浩著、『クジラの彼』(角川文庫)
書評:有川浩著、『植物図鑑』(幻冬舎文庫)
書評:有川浩著、『ラブコメ今昔』(角川文庫)
書評:有川浩著、『県庁おもてなし課』(角川文庫)
書評:有川浩著、『空飛ぶ広報室』(幻冬舎文庫)
書評:有川浩著、『阪急電車』(幻冬舎文庫)
書評:有川浩著、『三匹のおっさん』(文春文庫)&『三匹のおっさん ふたたび』(講談社文庫)
書評:有川浩著、『ヒア・カムズ・ザ・サン』(新潮文庫)
書評:有川浩著、『シアター!』&『シアター!2』(メディアワークス文庫)
書評:有川浩著、『キケン』(新潮文庫)
書評:有川浩著、『フリーター、家を買う』(幻冬舎文庫)
書評:有川浩著、『旅猫リポート』(講談社文庫)
書評:有川浩著、『キャロリング』(幻冬舎文庫)
書評:有川浩著、『明日の子供たち』(幻冬舎文庫)