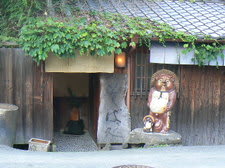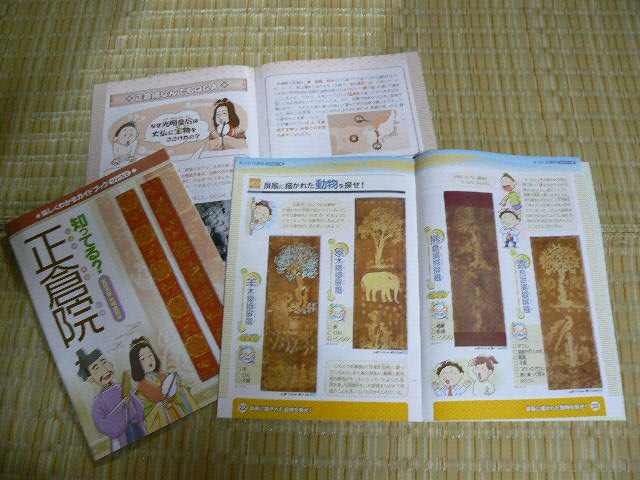先日(6日)、まじくんと再び奈良へ行ってきました。まずは、金堂(大仏殿)と大仏さまなどの様子を前ブログでお伝えしました。
その後、前日ブログでお伝えしたとおり、おそば屋さんで昼食をとり、そのお店の前の道を通って東大寺戒壇院(かいだんいん)へ行きました。お店を出て「まじくん、あの戒壇院まで行くよ。」「もう、帰りたい・・・。」「もう一つだけ、戒壇院だけ見せてね。すぐだから。」と、なだめ、歩き始めました。
到着すると「おかーさん、階段ついたし、帰ろ・・・。」「階段じゃなくて戒壇院!こないだ行ったお寺【前ブログ】の和尚さんが作った戒壇だよ。」「おぼうさんが階段作らはったの?」「じゃなくて・・・うーん。(><)」
ガイドブックなどで何度も出てくる「戒壇」・・・「戒」を授けるという僧にとって重要な儀式のための戒壇というのはわかるものの、イメージがわかず(^^;)なんか、階段登りながら儀式なのかな?なんて、漠然と思っていました。まじくんが言うように、この階段なのかも???(写真右上)
とりあえず、拝観料(大人500円・小学生300円)を払って中に入りました。戒壇院は、唐から来日した鑑真和上が天平勝宝6年(754)、大仏殿前で聖武天皇らに授戒をされ、その翌年に建立したお寺です。創建当時は、金堂、講堂、軒廊、僧坊などの伽藍がありましたが、3度の火災にあい、今の建物は享保18年(1733)の再建です。
堂内の中央には、多宝塔があり、四隅には国宝の四天王が安置されています。(堂内は撮影禁止です)多宝塔は、再建の時に作られたとされ、中には鑑真和上が来日の際に唐からもってこられた釈迦仏、多宝仏(模造)を祀っています。2体とも約25センチのかわいらしい仏様です。
多宝塔の周り(四隅)に建つ四天王は、もともと銅造のものでしたが、現在のものは塑造(そぞう)で、東大寺の中門から移されたものといわれています。塑造とは、木で組んだ心材に粘土を貼り付けていく方法で天平時代に流行しました。自由に肉付けできるために写実的な表現が可能ですが、壊れ安いのが難点です。「鬼さん、踏まれてはる、なんで?」と、邪鬼を踏みつけた像に近づくまじくん・・・触らぬように、静かに!と職員さんがつかず離れずでした。(^^;)
 さて、問題の「戒壇はどこに?」本堂へ入っても私の疑問は続きます。中には階段らしきものもないし、出口で職員さんにたずねました。すると「戒壇は、先ほど堂内に入った時に、3段登られたでしょ?(須弥壇みたいになっています)あの多宝塔のまわりに、受戒する人が並んで、僧になる儀式を行うのです。ここで受戒された人は、当時の国家公務員つまり国僧となります。だから、このお寺の門には菊の御紋がついてます。」とのことでした。なーるほど。(@@)
さて、問題の「戒壇はどこに?」本堂へ入っても私の疑問は続きます。中には階段らしきものもないし、出口で職員さんにたずねました。すると「戒壇は、先ほど堂内に入った時に、3段登られたでしょ?(須弥壇みたいになっています)あの多宝塔のまわりに、受戒する人が並んで、僧になる儀式を行うのです。ここで受戒された人は、当時の国家公務員つまり国僧となります。だから、このお寺の門には菊の御紋がついてます。」とのことでした。なーるほど。(@@)
ちなみに、奈良時代の日本では、僧侶を任命する権限は朝廷がもっていて、受戒の儀式は、仏前で自らが誓う自誓受戒という方式でしたが、文明の中心地だった唐では、3人の戒師から7人の証人となる僧の立会いの下で、戒律(自らを戒め心身に良い習慣をみにつけるための決まり事)を授ける儀式が行われていました。
ところが日本では10人の僧が揃わず、唐から戒師を招くこととしました。その招きに答えたのが鑑真で、弟子たちが拒否する中で「それならば私が行こう」と決め、それに従った20数名の弟子たちとともに来日を試みたとのことです。その来日の苦労に関しては、唐招提寺【前ブログ】にて触れています。
ふむふむ、やっと戒壇の事がなんとなくわかりました。やはり、階段じゃないですよねー。鑑真さんは現場監督じゃないのよね。(^^;)
なお、余談ですが、当時の受戒は、男性が250項目、女性は348項目だそうです。女性の方がはるかに多いです。もともと僧の世界が男性中心だったのに加え、女性の方が煩悩が深いと考えられていたからだそうです。でも、348項目もしちゃいけないことがあったら、逆になにすりゃOKなの?って気分になりますね。(><)ちなみに、お坊さんにならなくても、在家信者で5項目の戒律・・・不殺生、不邪淫、盗みをしない、嘘をつかない、お酒を飲まない、です。これだけでも、守るのに自信ないかも。(^m^;)
次は、戒壇院から歩いて10分ぐらいの「依水園(いすいえん)」をご案内します。でも・・・雨が降り出しました(T0T)