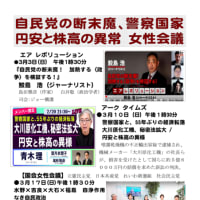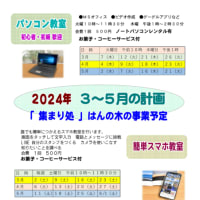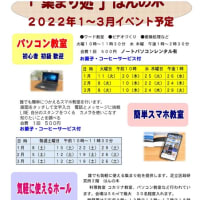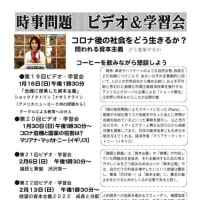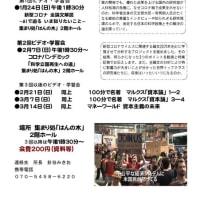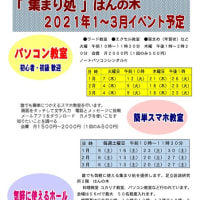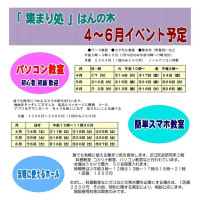足立区議会の予算特別委員会で足立区の教育行政について質問しました。Q&A方式です。
不登校が10年間で2倍に増える
●質問ー児童の虐待相談とともに、不登校が小学生、中学生ともに増えている。 特に足立区の場合16年度から26年までに不登校が2倍になっている。3年間に中学生では24年度456人、26年度は675人と急増している。この原因はどう考えるか。

●答弁ー無気力、登校しないことへの罪悪感が少ない児童・生徒が増えている。一つの原因である。
●質問ー原因について足立区の教育改革の影響はどうなのか、分析してみる必要がある。一つは教員の多忙化により、児童生徒と接する時間がつくれない。不登校やいじめによる共通した問題についての把握が難しくなっているのが原因ではないか。もっと向き合うことによって解明できるのではないかと思うが、認識はどうか。

●答弁(教育長)今、900人の不登校児がいる。1月に学校の接触度を調査をした。教育委員会や学校のことがどれ位通じているかと言えば、最終的に届かない子が5名いた。このようなこともやはり、学校と児童、生徒の繋がりを強化していくべきだと、私自身は思っている。
●質問ー足立区のいじめに関する調査委員長であった中央大学横湯園子教授は、教師が努力するとともに教育委員会に事務作業の軽減と教師数の増員が不可欠であると提言したとのべた。これが今、求められていると思うがどうか。
●答弁ー指導主事が担当校訪問も行い丁寧に各学校を巡っている。今後も学校と連携しながら丁寧な対応をしたい。
●質問ー教育委員の小川正人氏の著書「教育改革のゆくえ」で「教員は授業や学習指導以外に部活、生徒指導、給食指導、地域との連携等多様な業務を担っている。実態調査によると教員は学校で11~12時間勤務しているが、授業を行っている時間は小学校で3時間52分にすぎず、その他の多くの時間を生徒指導、給食指導などの仕事に費やしている実態であり、他の先進国では、ありえない超過勤務である。
教員には時間外手当はないが、教職員手当は月8時間を想定して支給されており、全国調査でわかったことは約6000億円がただ働き分となる。この金額は10万人分の教員を新規採用できる。
教員の過重な業務から解放することが必要であり、教員の多忙化解消が必要と思うがどうか。
●答弁(教育長) 教員の多忙化は認識している。一方で子どもたちの為に部活も授業も給食の指導も自らやりたいという気持ちもわかる。教員でなくてもできる仕事はできるだけ削減したい。地域のボランティアとか色々な資源を導入して多忙化解消に努めたい。

そだち指導員は安易な学力テスト対策だー大事なのは副担任講師を復活を
●質問ー新年度の教育予算のそだち指導員の問題だが、これは学力向上対策として小学校3年生の算数と国語の2教科において、学力テストで50点から70点の児童を選び、通常授業から抜き出して、そのつまずきに対応した指導で、1対1で学習上の困難を改善する取り組みだが、マンツーマンの指導という点ではそれだけなら効果がでるのはあたりまえで、私もこれ自体は否定するものではない。しかし、このそだち指導員について、足立区総合教育会議で学識者から疑問と懸念が紹介されている。
1つは、授業以外でこれだけの取り組みをしているということは、教員の本務である授業づくりという点ではどのような取り組みをしているのか。いわゆる授業の取り組みがおろそかになるような状況はないのだろうか。と指摘されている。この指摘についてどう考えるか。
●答弁(教育長)そだち指導という新しい仕組みを入れてきたわけだが、効果を検証しながらいろんな議論があることは知っている。そのような議論を踏まえて次のステップに進んでいく。
●質問ーもう一つは家庭での学習はどのように取り組まれ、家庭における学習に対する学校や教育委員会の支援施策がどう組まれているのか、そういう家庭での学習と学校のプログラムが本当に連携してやられているのか、という指摘がされているが、この点はどうか。
●答弁ー本区の児童生徒の学習実態を見たとき中々家庭で学習できない一面も問題になっている。そうしたことが改善、解消すれば学力改善に一定程度効果があると思う。
●質問ーそだち指導員は対象が中程度の子どもを対象にしている、導入の動機は学力テストの平均正答率のアップにあるといっても過言ではない。教育に携わっているものならわかるが、中程度のこどもの点数を引き上げることが一番容易であり、最も困難なのは下位のこどもの学力向上だ。
学校の公共的な使命と責任は「一人残らず子どもの学ぶ権利を保障し、その学びの質を高めること」にあり、学びの質と平等の同時追求こそ教育者と教育行政の責任の責任である。
地域の小学校長や副担任講師などに直接話を聞いた。ある校長は「そだち指導員はよくやってくれている。3年生のつまずきというのは1、2年生の時にしっかりやっていれば、つまずかない面もある。学校現場で一番困っているのは、1、2年生の時に一番力を発揮していた副担任講師がいなくなったこと。ぜひ、復活してもらいたい」という意見が複数の校長から聞いている。区教委はそうした意見を聞いているか。
●答弁(教育長)先生方から以前の副担任講師は非常に効果があったと話は聞いている。

学校現場の生の声を聞き、区教委の教育行政を改めよ
●質問ー次に現場の声を教育行政に生かす教育委員会の在り方について聞く。今回、私は教員の生の声を聞いた。区内の教師のアンケート313人の声をいくつか紹介する。
これは2015年の8月の調査だが、①学力テストの点数アップに汲々としているようにみえる。②学力向上に向けた施策が多く実施されて家庭環境改善が図られないと負の連鎖からぬけ出せない。③4月の区の学力調査(テスト)までは授業はいいから過去問をと言われました。週案に何と書くんですか。指導要領から離れて年間指導計画がどんどん遅れてしまう。④出張研修、小中連携、部活などなど教材研究ができない教材研究に集中したい。⑤他区から移動して驚いた足立区は何を恐れているのか。区調査(テスト)でGランクになると対策案をださないと校長は帰れないなどと伝聞情報もあります。人権的にアウトなことはやめたほうがいい。⑥学力向上のためある学年だけ7時間目を1週間もやっている。6時間目までも空きがなく、クタクタな上、7時間目の授業、諸会議、実習生の世話、残務整理..と仕事は果てしなく続く、体も心も疲れ切っている。テストの結果もいちいちポートフォリオに入力する必要性は感じない。子どもの課題はわかっている。子どもや職場の同僚と向き合う時間より。パソコンと向き合う時間の方がずっと長くなっているなど改善してほしいという、こうした訴えは届いているか。
●答弁(教育長)アンケートの中身は知らないが、そういう声をいただいているのは事実。
●質問ー全文(P14)を区教委に届けたと聞いている。ぜひ読んでいただきたい。次に子どもの権利条約は、子どものために営まれる教育や教育行政でこそ重視すべきものだ。子どもの権利条約で重視されていることは「意見表明権」「余暇・休息、遊び、文化の権利」など子どもの権利を学校などあらゆる教育の場で生かすことに尽きる。
文京区教育委員会では、子どもの権利条約についての学習会を開催しているが、足立区ではどうか。
●答弁ー本区では学習会は開催していない。
ぜひ教育委員会事務局で子どもの権利条約についての学習会を開催してもらいたい。
●質問ー第7回総合教育会議で二期制から3学期制に、夏季休業日と土曜授業の問題について、議論がされ、見直すことが示されました。私たちはかねてより、二期制も夏季休業の短縮はすべきでないことを明らかにしてきましたが、教育委員会としてのどのような判断でこの2つの改革を見直すべきと判断したのか。伺う。
●答弁ー学力の効果、デメリット・メリットも勘案して最終的には4月頃まとめて議会に報告したい。
●質問ー「21世紀型学力が、議論されて、アクティブラーニングという新しい考え方も出ている。ただ単に知識をいっぱい持っているというふうなことではなくて、自尊心とか自分自身に対する自信というもの、教育の基本というのは最終的にはそこにあると思っています。」という。世界トップレベルと評価されたフィンランド、カナダなどの諸国における教育の成功は、いずれも「質と平等の同時追求」によるものであると考えられます。
「21世紀型の学校」における教育の様式に見られる変化は、カリキュラムが、一斉授業から協同的学びへの転換であるといわれている。そうした方向へ舵を切ったといわれていますが、どういう認識でしょうか。
●答弁ーこれから求められる学力はご指摘の通り。単なる知識だけでなく考える力こそが大事だと思う。
少人数学級を区独自に実施すべき
●質問ー区内でいじめによる中学生の自殺があり、第三者機関による「調査報告書(区への提言)」が提出され、区独自の教員の採用が提案された。ところが区長は自らの公約であった35人学級に道を開く、足立区独自の教員の採用をしませんでした。
区として独自の教員採用をしない理由は何か。
●答弁ー少人数学級については、国の方針で小学校1年生から順番に入れていくということから区として独自採用はしないことにした。
●質問ー教育は人だ。貧困の連鎖の解消を目指すのなら教員の多忙化など独自の教員採用に踏み出すべきだがどうか
●答弁ー多忙化は何とかしなければいけない問題だとそこは同じ意見だ。ただ教員を増やす問題は、学校全体の経営や財政的な問題も含め総合的に考えるべきだと思っている。足立区としてできることをやりたい。