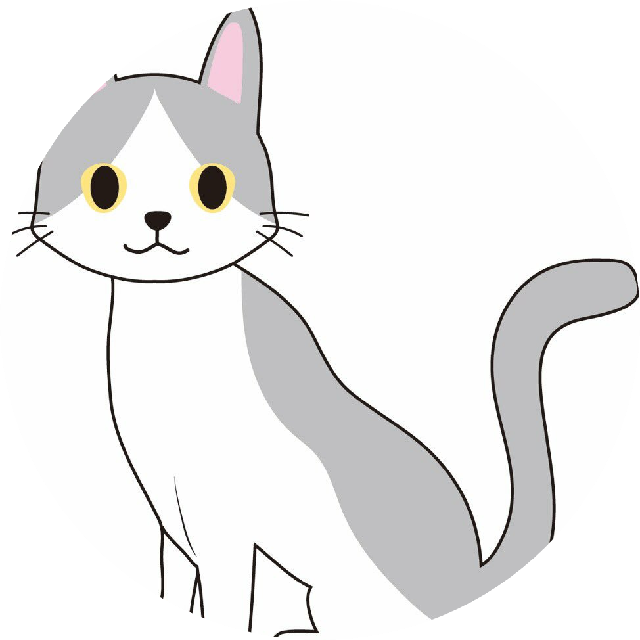橋本胖三郎『治罪法講義録 』・第六回講義
第六回講義(明治18年5月8日)
第三章 誰に対して公訴・私訴を行うべきか
( はじめに)
前章では、公訴・私訴を起こすことができる人を説明しました。この章では、公訴私訴を受けるべき人は誰なのか、つまり公訴私訴の被告となる人を論じます。
この章は、前章に比べて考察すべき範囲がやや狭いため、前回よりも理論は少ないです。
しかし、よく分析して考察を加えれば、論究すべきことは相応にあります。
この章は次の二つの款に分けて述べます。
第一款 誰に対して公訴を行うべきか
第二款 誰に対して私訴を行うべきか
まずは第一款から説明しましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(第一款の第一) 重罪、軽罪、違警罪を犯した人
第一款 誰に対して公訴を行うべきか
公訴と私訴を提起する主体が異なることは前回論じました。主体が異なるのですから、その対象者も異なります。以下に、公訴を受けるべき人について論じます。
第一 重罪、軽罪、違警罪を犯した人
公訴の被告となる者は、重罪、軽罪、違警罪を犯した人です。
刑法第104条の「正犯」は公訴の対象となります。なぜ正犯に対して公訴を行うのかという問題を治罪法の視点から見ると、公訴は刑を適用することを目的としているため、正犯に対して公訴を行うのは当然のことと言えます。
もっとも、本問題は刑法においてなぜ正犯を罰するのかという問題と同義です。よって、この問題は、治罪法よりも刑法の議論においてより詳しく論じられるべきものであり、ここではこの程度とします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(第一款の第二)
第二 教唆者
実行行為はしていないが、人をそそのかして罪を犯させた者(教唆者)は、正犯と同様に公訴の対象となります。
教唆者を公訴するときの注意点を申し上げましょう。
刑法第105条には「人を教唆して重罪軽罪を犯させた者亦正犯と為す」と規定されています。
重罪及び軽罪と規定されていますが、違警罪の文言はありません。刑法では違警罪の教唆者は罰しないのです。したがって、教唆者が公訴の対象となるのは重罪や軽罪に限られており、違警罪の教唆者が公訴の対象となることはありません。
しかし、だからといって違警罪に教唆者が存在しないわけではありません。たとえば、刑法第425条第9項に規定されている、人を殴打して創傷や疾病に至らない場合の罪のようなものは、実際には教唆者がいることが少なくありません。違警罪のような軽微な罪であっても、事実上、教唆者が存在しないわけではないのです。しかし、刑法でこれを罰しない以上、違警罪の教唆者に対して公訴を行うことはできません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(第一款の第三)
第三 従犯
第三に、重罪や軽罪の従犯は公訴の対象となります。従犯者は、教唆者と同様、違警罪に関しては公訴の対象とはなりません。
以上まとめますと、公訴の対象者は、第一に正犯、第二に教唆者、第三に従犯です。そして、刑は犯罪者その人にのみ適用されるという原則に従い、これらの者の親戚には及ばないことは言うまでもありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(第一款に付随する問題①〜第三者の関与)
この第一款については、注意を要する問題が二つあります。以下にそれを考察します。
第一の問題は、「検察官と被告人との間に公訴が起こり、まだその結審がなされていない場合に、第三者がその公訴に関与することができるかどうか」ということです。
〈民事訴訟に関する考察〉
この問題を検討するにあたり、まず民事上の事例から考察します。民事訴訟では、甲と乙の訴訟の間に丙が関与することは許される場合があります。
例えば、不動産の売買において、甲を売主、乙を買主とした場合に、丙という者が現れて乙を被告としてその不動産の取り戻しの訴えを起こしたとしましょう。この場合、乙と丙の間に訴訟が係属することになります。乙丙間の訴訟に、甲が関与するには二つの方法があります。一つは、甲自身が被告となり、乙に代わって答弁を行うことができるというものです。これはほかでもなく、売主がその売買対象物件の担保責任を負うためです。乙丙間の訴訟において、仮に乙が敗訴することになれば、売主である甲は乙に対して損害賠償の責任を負うことになるからです。
もう一つの方法は、甲が被告ではなく、乙と共同して答弁を行うことです。この方法はどの国の訴訟法でも概ね認められているものです。フランス民事訴訟法第339条ではこれを明示しています。わが国においても民事上このような例がないわけではありません。フランス語でこれを「アンテルバンション・ド・チェール」と言います。第三者が訴訟に関与するという意味です。これは民事訴訟上不可欠な制度です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〈刑事訴訟に関する考察〉
民事訴訟については以上のとおりです。では、刑事上の場合はどうでしょうか。
甲が公訴を受けた後に、乙が「これは甲とは全く無関係である、私が被告となって答弁するべきだ」と自ら被告になろうとする者が現れたというような場合です。
例えば、親が公訴を受けた場合に、子が親が獄中で呻吟するのを坐視することができず、自ら被告となって答弁しようとする場合です。
また、甲が公訴を受けた事件について、自分も関与しており、甲と共に答弁しようとするような例が考えられます。共犯であれば、一刻も早くその訴訟に関与し、答弁を行うことが自分の利益となるからです。
・刑事事件において許容できるか
では、刑事上でこのようなことを許すべきでしょうか。この点について治罪法の規定はありませんので、条理によって考えざるをえません。
私は、条理が指示するところに従い、次のように考えます。「民事ではこれを許すべきだが、刑事ではこれを許すべきではない」と。
・許容できない理由
以下、理由を述べましょう。
公訴は一個人の私的意向に左右されるものではありません。よって、公訴を受理しその裁判を行うのは、治罪法で規定されているところによらなければません。
公訴を受理するのは、検察官の起訴又は民事原告人の申立てある場合に限られ、その他の場合に裁判所が公訴を受理することは許されません。その例外は現行犯の場合(治罪法第202条)、弁論によって発見された附帯の事件、または法廷内での犯罪です。この例外の場合を除き、裁判官は自ら公訴を受理することができません(無告不理の原則)。
したがって、たとえ被告人が自ら甘んじて刑を受けようとする場合でも、それはただ一個人の私意に過ぎないため、法律で定められた手続きに従って起訴されたものでなければ、被告人となることはできません。第三者が自ら甘んじて被告人になろうとする場合でも、決してこれを許すべきではありません。
これを許してしまうと弊害もあります。例えば、富者が被告となり有罪の判決を受けるかもしれない不幸に見舞われた場合、すぐに大金を投じて貧者を自分の代わりに被告とさせ、自分の責任を免れようとする者がでてくるでしょう。
民事上は、基本的にすべての人の自由を尊重するものなので、自ら進んで被告人になりたいという者があれば、それを許しても大きな弊害はありません。自らに義務ありと告白する者を、法律上あえてこれを否定する理由に乏しいともいえます。
しかし、刑事上では自ら進んで刑を受けようとする者がいても、その人が犯罪者でない限り、決してこれを罰してはいけないのです。
これは、刑事と民事は性質の異なるものだからです。
・フランスにおける通説・判例とその批判
フランスの学説および判例を見ると、フランスでは刑事においても第三者が関与することを認めているようです。
その理由は、フランス治罪法には第三者の関与を禁止じていないから、というものです。
理論的には、同一事件はできるだけ一回で審理し、できるだけ同時に同じ法廷で裁判することで、判決の矛盾を来さないようにすることができるからと論じられています。
この議論は学説のみならず、フランスの大審院でも採用されています。
しかし、これらの学説及び大審院の判決は、刑法と民法を混同しているとものと評価せざるを得ません。
民事に関することは各個人の意思に委ねるべきものですが、刑事に関することは国家の秩序に関わるものであり、決して一個人の私的な意思に任せるべきではないのです。しかし、フランスでの議論は、この区別を全く考慮していないのです。
以上述べた理由から、私は民事の目的に関する事柄については第三者の関与を許し、刑事の目的に関する事柄については第三者の関与を許すべきではないと信じます。
(治罪法の規定からの自説の補強)
我が国の治罪法第303条第1項には、「民事担当人は、始審終審を問わず、いつでもその訴訟に参加することができる」と規定しています。
この規定は、民事を目的とする者に限って、民事担当人という第三者に公訴に関与することを許したに過ぎないものです。被告人が有罪判決を受ける場合、直ちに民事担当者の責任に影響を及ぼすため、その訴訟に立ち入って自らの権利を保護することを許したのです。
このような関与の仕方であれば、民事担当人だけでなく、その他の関係者にも関与を許すことが非常に理にかなっているというのが、私の考え方です。
例えば、甲が乙から物品を買い受けた場合に、甲がその訴訟に関与し、その物品が犯罪によって得られたものでないことを証明する権利を有することは、条理にかなっています。
民事担当人だけでなく、その他の関係者にも関与を許すのが妥当です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(第一款に付随する問題②)
第二の問題は、「訴訟事件の審理中に被告人が他人をその訴訟に引き入れようとすることは許されるか」です。
民事上では許されます。先の例でいえば、被告(買主)は売主をその訴訟に引き入れることができることになります。実際に我が国においてもこのようなことは既に行われています。では、刑事上ではどうでしょうか。被告が「これを行ったのは自分ではなく、別の人である」として、その人を訴訟に引き入れることができるでしょうか。
私は許すべきではないと考えます。なぜなら、刑事上においてこのようなことを許可することは、被告人自身に公訴を行わせることと何ら変わりがないからです。これを許さなくても、被告人は証人としてその人を呼び出すことができるので、不利益とななりません。証人の呼び出しについては、治罪法に厳格な規定があり、証人が出廷に応じない場合には制裁が加えられるため、特に他人を被告とする必要はないのです。
以上で第一款の説明を終わります。次に第二款に移ります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(第二款 誰に対して私訴を行うべきか)
第二款 誰に対して私訴を行うべきか
公訴を受ける者は犯罪者に限られますが、私訴を受けるべき者は犯罪者に限られません。
以下この点を論じます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(第二款 第一 公訴の被告人は私訴の対象となる)
第一 公訴の被告人は私訴の対象となります。
公訴の被告人は犯罪に関して既に刑法上の責任を負っている者です。したがって、それに関連する民事、つまり私訴においてもその責を免れることはできません。ここで「犯罪者」というのは、正犯のほか、教唆者、従犯者も含まれます。
教唆者、実行犯、従犯者は私訴ではその責任を連帯して負います。刑法第47条に「数人の共犯による裁判費用、贓物の還付、損害賠償は共犯者に連帯責任を負わせる」と規定されています。
同条の「共犯」とは、教唆者、実行犯および従犯者の三者を包含するものであり、複数の教唆者や実行犯がいる場合、その全員を含みます。これを狭く解釈し、共犯とは教唆者および実行犯のみを指し、従犯者は含まれないという説もありますが、正しいとは思えません。正犯、従犯はすべて連帯責任を負うべきです。
その理由は、教唆者、実行犯、従犯がいて人を殺した場合、その責任を分けて一部を教唆者の責任とし、また一部を実行犯の責任とするというようなことはできないからです。その責任に差を設けようとすると、不平等な分割法に陥ってしまうのは必然です 。よって、犯罪者に連帯責任を負わせるほかないのです。
もっとも、連帯責任を負うのは被害者に対する関係であり、犯罪者同士の間ではその責任を分割することは可能です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(第二款 第二 民事担当人は私訴の対象となる)
第二 民事担当人は、 私訴の対象となります。
民事担当人に関しては、明治14年12月8日の第73号布告で規定されており、次のとおりです。
第一 未成年者の父または母、もしくは同居している親族で監督を行う者
第二 知的障害者・精神障害者の保護者
第三 雇主
ただし、雇人がその雇主の命じた事案を行うとき
以上の四者は民事担当人として、民事上の責任を負うべき者です。この者が民事上の責任を負う理由は、自己の過失によってその責任が生じるのと同じだからということにあります。
親はその子を教育すべき責任を有しており、子が他人に損害を与えたときは、その教育が適切でなかった過失によるものであるから、その責任を免れることができないのです。
また、知的障害者・精神障害者の保護者についても、同様の理由によります。これらは結局、すべて自己の不注意によって他人に損害を及ぼすことに至ったものですので、その責任は注意を欠いた民事担当人が負うべきことは当然のことです。
雇人の行為によって他人に損害を与えた場合に、雇主がその責任を負うことは、一見非常に奇妙に思えるかもしれません。しかし、人を雇うにあたっては、注意を払うべきです。
他人に害を及ぼすような者を雇ったのは、雇い主の不注意であると言わざるを得ません。雇主が責任を負うのはこの理由によります。
もっとも、雇主が責任を負うのは、雇人が雇主の命令を実行する際に行った行為から生じた損害のみです。馭者が馬車を疾駆させて他人に害を与えた場合は、雇主の命令を実行している間に加えた損害であるため、雇主はその責任を負わなければなりません。
フランスでは、上記の四種類の他に、さらに民事担当人とされるものがあります。例えば、工業の授業をする講師や学校の教師などは、その業務を行っている間はその責任を負う者とされています。しかしながら、我が国ではこれを民事担当人とはしていないため、ここではこれ以上説明致しません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━