アーサー・ケスラー/小尾信弥・木村博訳『ヨハネス・ケプラー-近代宇宙観の夜明け-(文庫)』筑摩書房、2008年
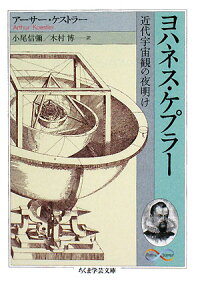
ドイツの天文物理学者ケプラー(1571-1630)の評伝です。
本書の原題は「分水嶺(The Watershed)」。これは知性の分水嶺を意味し、古代・中世の思考を近代の観測科学の精神から分かつ地点に天才ケプラーがたっていたことを意味しています。
ケストラーの『夢遊病者たち』(1959年)からケプラーについて書かれた1章を取り出して独立の本にしたものが本書です。
ケプラーは「ケプラーの3つの法則」で知られています。すなわち、惑星は、太陽をひとつの焦点とする楕円軌道上を動く(第1法則 )、惑星と太陽とを結ぶ線分が単位時間に描く面積は、一定である(面積速度一定)(第2法則)、惑星の公転周期の2乗は、軌道の半長径の3乗に比例する(第3法則)です。
第1法則および第2法則は1609年に発表され、第3法則は1619年に発表されました。
この本を読むとケプラーはもともとは占星術などにこっていた人物のようで、あらゆることでの奇行の目立つ人だったようです。ケプラーの業績は惑星の軌道を楕円と考えたことです。
それまでは天動説のプトレマイオスはもちろん、地動説のコペルニクスも惑星の運動は円軌道として考えていました。
また、ケプラーは太陽と惑星はその距離の二乗に反比例する力によって引かれていると考えました。その力の証明はニュートンの万有引力の発見につながったとか。
ケプラーは数を宇宙の秩序の中心と考え、天体音楽論を提唱するなどピタゴラスの信奉者であり、法則の予想は専ら幾何学的の発想からスタートして物理学の要素を取り入れることで成しえたようです。
またチコ・ブラーエは独自に膨大な観測を行ってデータをもっていましたが、そのデータの解析からもケプラーの予想は実証されました。
ケプラー自身は法則の発見者ということにあまり頓着がなく、上記3法則の意義はニュートンによって認められました。
本書はケプラーの著者『宇宙の神秘』『新天文学』『世界の調和』『ヨハネス・ケプラー全集』などからの多くの引用を行いながら、ケプラーの業績と人となりを論じています。その宗教的立場、人格形成、職業的不安定、チコ、ガリレオとの交流、2度の結婚の顛末、母親が魔女と攻撃されたことなどについても詳しく書かれています。
ケプラーは今から考えると恐ろしく非合理的で、難しい社会、人間関係のなかを生きるなかで、宇宙と天体にたいする驚異的な粘着力と執着心が近代科学の扉をこじあけたということになるのではないでしょうか?
全編で421ページ。あまり読みやすくはありませんが、読後感は充実でした。
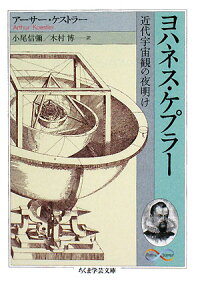
ドイツの天文物理学者ケプラー(1571-1630)の評伝です。
本書の原題は「分水嶺(The Watershed)」。これは知性の分水嶺を意味し、古代・中世の思考を近代の観測科学の精神から分かつ地点に天才ケプラーがたっていたことを意味しています。
ケストラーの『夢遊病者たち』(1959年)からケプラーについて書かれた1章を取り出して独立の本にしたものが本書です。
ケプラーは「ケプラーの3つの法則」で知られています。すなわち、惑星は、太陽をひとつの焦点とする楕円軌道上を動く(第1法則 )、惑星と太陽とを結ぶ線分が単位時間に描く面積は、一定である(面積速度一定)(第2法則)、惑星の公転周期の2乗は、軌道の半長径の3乗に比例する(第3法則)です。
第1法則および第2法則は1609年に発表され、第3法則は1619年に発表されました。
この本を読むとケプラーはもともとは占星術などにこっていた人物のようで、あらゆることでの奇行の目立つ人だったようです。ケプラーの業績は惑星の軌道を楕円と考えたことです。
それまでは天動説のプトレマイオスはもちろん、地動説のコペルニクスも惑星の運動は円軌道として考えていました。
また、ケプラーは太陽と惑星はその距離の二乗に反比例する力によって引かれていると考えました。その力の証明はニュートンの万有引力の発見につながったとか。
ケプラーは数を宇宙の秩序の中心と考え、天体音楽論を提唱するなどピタゴラスの信奉者であり、法則の予想は専ら幾何学的の発想からスタートして物理学の要素を取り入れることで成しえたようです。
またチコ・ブラーエは独自に膨大な観測を行ってデータをもっていましたが、そのデータの解析からもケプラーの予想は実証されました。
ケプラー自身は法則の発見者ということにあまり頓着がなく、上記3法則の意義はニュートンによって認められました。
本書はケプラーの著者『宇宙の神秘』『新天文学』『世界の調和』『ヨハネス・ケプラー全集』などからの多くの引用を行いながら、ケプラーの業績と人となりを論じています。その宗教的立場、人格形成、職業的不安定、チコ、ガリレオとの交流、2度の結婚の顛末、母親が魔女と攻撃されたことなどについても詳しく書かれています。
ケプラーは今から考えると恐ろしく非合理的で、難しい社会、人間関係のなかを生きるなかで、宇宙と天体にたいする驚異的な粘着力と執着心が近代科学の扉をこじあけたということになるのではないでしょうか?
全編で421ページ。あまり読みやすくはありませんが、読後感は充実でした。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます