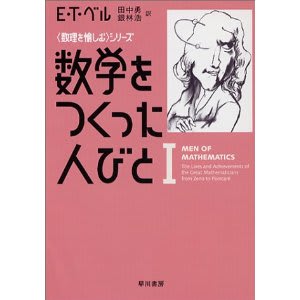
数学の歴史で大きな貢献を成した学者の何人かの名前は、知っています。教科書で習った人では、ピタゴラス、アルキメデス、ニュートン、パスカルぐらいは、誰でもしっています。彼らの業績もそれなりに言うことはできます。ピタゴラスであれば「直角三角形のピタゴラスの定理」、アルキメデスなら「アルキメデスの原理」、ニュートンは「万有引力の法則」、パスカルは確率論といったところでしょうか。
ただ、彼らがどういう人だったのか、その業績がどういう過程で生まれたのか、などはほとんど知られていないし、多くの人は知ろうともしないです。
本書は、数学の巨人たちのあまり知られていない伝記です。原書が出版されたのは1937年、相当古いです。原題は「ツェノンからポアンカレにいたる大数学者の生涯と業績」。1953年に、イギリスのペンギンブックスで2分冊本として出版され、その前半分だけが1943年に日本語訳で刊行されました。日本語全訳は、1962年に東京図書から出ました。
数学が退屈なものではなく、「大なり小なり、精神の劇的なドラマだということを、本書ほど鮮やかに描き出したものは少ない」(p.12)と「訳者挨拶」に書かれています。早川書房の文庫版では3冊に分かれていて、その第1冊に登場する数学者は以下のとおりです。
ツエノン、エウドクソス、アルキメデス、デカルト、フェルマ、パスカル、ニュートン、ライプニッツ、ベルヌーイ家の人々、オイラー、ラグランジュ、ラプラース、モンジュ、フーリエ。ツエノン、エウドクソス、アルキメデスは古代ギリシャの数学者です。それから、フランス人が多いのに気づきます。
数学の概念と結び付けて紹介すると、アルキメデス、ニュートンは微積分学、フェルマは無限論、パスカルは確率論、デカルトは解析幾何学などです。数理物理学や天文学との関係で、近代数学が発展していくさまには、今回、認識をあらたにしました。
数学者はそれぞれに個性的な生き方をしている。相互の論争があった。それぞれが生きた時代がまだ科学の光が弱い、宗教の権威としきたりが支配的な蒙昧の社会だったことも頭に入れておかなければなりません。当時の権力者との微妙な関係もありました。
そのような時代に生きながら、有る人は才能を十分に開花させたが、有る人は才能をもてあまし、不本意な人生をおくったのです。数学の天才の誰もが変人、奇人だったわけではありません。ニュートンが行政官としても仕事をなしたとは驚きましたが、デカルトの最期などはさびしい限りでした。
最新の画像[もっと見る]



















