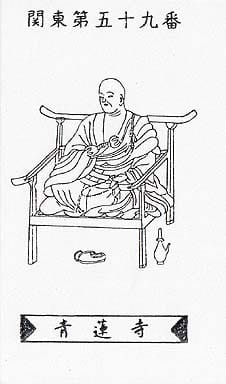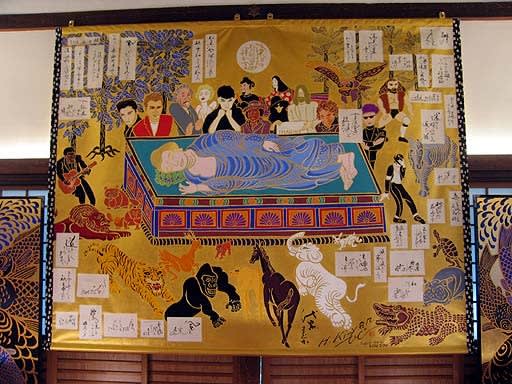7/4(日)高松市内→女木島→高松市内→神戸(続き)
12時を回りました。今回は2時間延長しているため未知の世界になります。

午後に入ると気温が上がってきました。風は通るのですが次第に気温が上がってきています。エースワンでもらった保冷用の氷は飲み物と一緒に保冷袋に入れていますが、どんどん溶けています。水になってもしばらくは水温が低いので涼しく過ごせます。ぬるくなったらポリ袋を破いて水を捨てればゴミは僅かになります。
飲み物は2本目のお茶が1/3程残っています。お茶と非常用のイオンウォーターとは未開封です。
50は相変わらず8と沖縄が聞こえます。EAQさんはずっと聞こえていて面白いでしょうね。8はほぼ出尽くした感じで、諦めた3の局がアンテナを西に向けてくれるようになり少し稼げます。
144/430は出ている局が少なく、430は朝からずっと同じ周波数でCQを出し続けているクラブ局などに限られます。呼び回りをしないとスコア伸びないと思うんですけどね。
最後の追い込みで144で09ができました。ふわふわとSが上がってきてQSOできました。これは大きなマルチです。
帰りのバスは14時40分発です。14時10分で終了、片付けましょう。いつもより2時間延長したのですが、その間に19局できていますから効果があったように感じています。
バスに間に合いました。女木島からは50MHzで61局、144MHzで17局、430MHzで17局の計95局でした。
15時40分に高松港到着です。帰りは16時20分発のフットバスの神戸経由大阪行きにしました。三宮到着が19時になるためもう一度エースワンに立ち寄って酒と夕食を買ってバスに乗り込みます。もちろん氷も忘れずもらっておきます。この便は独立3列ですからで隣の席に人はいないのでゆっくりできます。
ここのところ続けている中原めいこさんのアルバム、今回は1984年7月に発売された5枚目の「ロートスの果実」です。
1982年のデビュー以降いい曲を作り業界では注目されてきた中原さんですが、一般にはあまり知られていない存在でした。「ヒット曲さえあれば」と言われていたところに舞い込んだのがカネボウからの夏の化粧品キャンペーンのCMソングでした。これが1984年4月にリリースされた「君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。」で、テレビでの露出もあって瞬く間にヒットします。
中原さんに対し正直あまり期待していなかったレコード会社の東芝EMIはこの曲のヒットにより中原さんを本格的に売り出すことになります。前3作のアルバムよりも制作費が増額され、ジャケットからして予算がかけられたことが分かります。
ちなみにこの1984年は杏里さんは前年の「CAT'S EYE」のヒットの勢いを保ったままアルバム「COOOL」を出していますし、竹内まりやさんは休養から復帰し「VARIETY」を、女王ユーミンは「NO SIDE」と女性シンガーソングライターの名盤が次々と世に出ています。東芝EMIはこの3人に肩を並べる存在として売り出したかったのだと思われます。
1曲目は「魔法のカーペット」で、ポップな世界に誘っています。歌詞の最後を少し上げてうきうきした演出がされています。2曲目の「ロートスの果実」はアルバムのタイトルと同名で、ファンタジーの世界に誘います。
3曲目の「エモーション」は7枚目のシングルのA面で、筒美京平さんの影響を強く受けた曲という印象です。4曲目の「I MISS MY VALENTINE」で落ち着いたバラードを聴かせて5曲目の「メランコリー TEA TIME」に持ち込んでいます。中原さんの得意とするリゾートの恋を全面に押し出した曲です。
B面は「君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。」からスタート。この奇妙なフレーズは広告代理店からの依頼であったと言われています。歌詞中で8回出てくるのですが、7回目と8回目はバックコーラスがついていない特徴があります。その一方で冒頭に「ドライなシェリー」が入っており、お酒(もしくはカクテル)の名前が出てくることが多い中原さんらしい特徴も出ています。
2曲目の「こんな気分じゃ帰れない」は「エモーション」のB面でポップな曲調、3曲目の「スコーピオン」は5枚目のシングルA面で一転して重い曲に仕上がっています。そこから軽めの「気まぐれBad Boy」「Cloudyな午後」と続けて締めています。
「2時までのシンデレラ」や「mint」のA面のような流れで一気に聴かせるスタイルではなく「君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。」で中原さんを知った層向けの「こんな歌も歌えるんですよ」みたいなアルバムに仕上がっています。中原さんも制作も降って湧いたようなヒットに浮き足立ったのかも知れませんね。
3号神戸線はスムースだったものの高松市内での乗車に時間を取られ10分ほど遅れた19時10分に三宮到着です。
2日間合わせて50MHzで79局、144Mhzで19局、430MHzで22局の計120局でした。ありがとうございました。
コンテストに出る局が大きく減っており、年々QSOsが減っています。コンテスト対象外のFT8に移行しコンテストにQRVしない、戻らない局が多いためです。言ってしまえば「コンテストなんてつまらんことをやっているよりFT8の方が楽しい」と思われているわけで、これ以上設備を改善してもスコアを取り戻せないところに来ています。
内紛以来あらゆることが後手後手に回っているJARLがコンテスト離れに対して現状認識すら正しくできている様子はなく、対策なんて打ちようがないのではないかと思われます。
12時を回りました。今回は2時間延長しているため未知の世界になります。

午後に入ると気温が上がってきました。風は通るのですが次第に気温が上がってきています。エースワンでもらった保冷用の氷は飲み物と一緒に保冷袋に入れていますが、どんどん溶けています。水になってもしばらくは水温が低いので涼しく過ごせます。ぬるくなったらポリ袋を破いて水を捨てればゴミは僅かになります。
飲み物は2本目のお茶が1/3程残っています。お茶と非常用のイオンウォーターとは未開封です。
50は相変わらず8と沖縄が聞こえます。EAQさんはずっと聞こえていて面白いでしょうね。8はほぼ出尽くした感じで、諦めた3の局がアンテナを西に向けてくれるようになり少し稼げます。
144/430は出ている局が少なく、430は朝からずっと同じ周波数でCQを出し続けているクラブ局などに限られます。呼び回りをしないとスコア伸びないと思うんですけどね。
最後の追い込みで144で09ができました。ふわふわとSが上がってきてQSOできました。これは大きなマルチです。
帰りのバスは14時40分発です。14時10分で終了、片付けましょう。いつもより2時間延長したのですが、その間に19局できていますから効果があったように感じています。
バスに間に合いました。女木島からは50MHzで61局、144MHzで17局、430MHzで17局の計95局でした。
15時40分に高松港到着です。帰りは16時20分発のフットバスの神戸経由大阪行きにしました。三宮到着が19時になるためもう一度エースワンに立ち寄って酒と夕食を買ってバスに乗り込みます。もちろん氷も忘れずもらっておきます。この便は独立3列ですからで隣の席に人はいないのでゆっくりできます。
ここのところ続けている中原めいこさんのアルバム、今回は1984年7月に発売された5枚目の「ロートスの果実」です。
1982年のデビュー以降いい曲を作り業界では注目されてきた中原さんですが、一般にはあまり知られていない存在でした。「ヒット曲さえあれば」と言われていたところに舞い込んだのがカネボウからの夏の化粧品キャンペーンのCMソングでした。これが1984年4月にリリースされた「君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。」で、テレビでの露出もあって瞬く間にヒットします。
中原さんに対し正直あまり期待していなかったレコード会社の東芝EMIはこの曲のヒットにより中原さんを本格的に売り出すことになります。前3作のアルバムよりも制作費が増額され、ジャケットからして予算がかけられたことが分かります。
ちなみにこの1984年は杏里さんは前年の「CAT'S EYE」のヒットの勢いを保ったままアルバム「COOOL」を出していますし、竹内まりやさんは休養から復帰し「VARIETY」を、女王ユーミンは「NO SIDE」と女性シンガーソングライターの名盤が次々と世に出ています。東芝EMIはこの3人に肩を並べる存在として売り出したかったのだと思われます。
1曲目は「魔法のカーペット」で、ポップな世界に誘っています。歌詞の最後を少し上げてうきうきした演出がされています。2曲目の「ロートスの果実」はアルバムのタイトルと同名で、ファンタジーの世界に誘います。
3曲目の「エモーション」は7枚目のシングルのA面で、筒美京平さんの影響を強く受けた曲という印象です。4曲目の「I MISS MY VALENTINE」で落ち着いたバラードを聴かせて5曲目の「メランコリー TEA TIME」に持ち込んでいます。中原さんの得意とするリゾートの恋を全面に押し出した曲です。
B面は「君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。」からスタート。この奇妙なフレーズは広告代理店からの依頼であったと言われています。歌詞中で8回出てくるのですが、7回目と8回目はバックコーラスがついていない特徴があります。その一方で冒頭に「ドライなシェリー」が入っており、お酒(もしくはカクテル)の名前が出てくることが多い中原さんらしい特徴も出ています。
2曲目の「こんな気分じゃ帰れない」は「エモーション」のB面でポップな曲調、3曲目の「スコーピオン」は5枚目のシングルA面で一転して重い曲に仕上がっています。そこから軽めの「気まぐれBad Boy」「Cloudyな午後」と続けて締めています。
「2時までのシンデレラ」や「mint」のA面のような流れで一気に聴かせるスタイルではなく「君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。」で中原さんを知った層向けの「こんな歌も歌えるんですよ」みたいなアルバムに仕上がっています。中原さんも制作も降って湧いたようなヒットに浮き足立ったのかも知れませんね。
3号神戸線はスムースだったものの高松市内での乗車に時間を取られ10分ほど遅れた19時10分に三宮到着です。
2日間合わせて50MHzで79局、144Mhzで19局、430MHzで22局の計120局でした。ありがとうございました。
コンテストに出る局が大きく減っており、年々QSOsが減っています。コンテスト対象外のFT8に移行しコンテストにQRVしない、戻らない局が多いためです。言ってしまえば「コンテストなんてつまらんことをやっているよりFT8の方が楽しい」と思われているわけで、これ以上設備を改善してもスコアを取り戻せないところに来ています。
内紛以来あらゆることが後手後手に回っているJARLがコンテスト離れに対して現状認識すら正しくできている様子はなく、対策なんて打ちようがないのではないかと思われます。