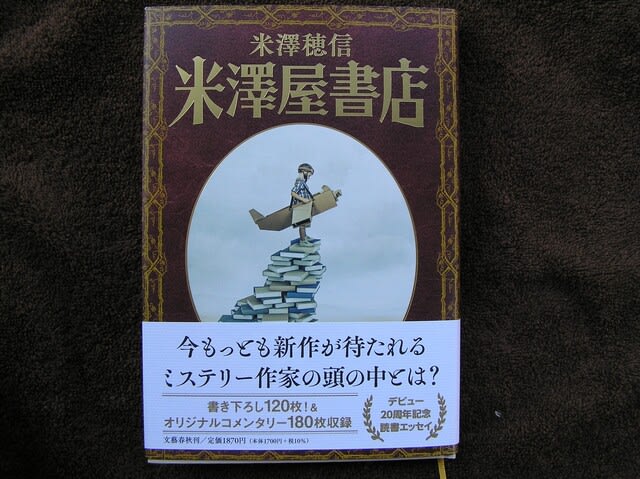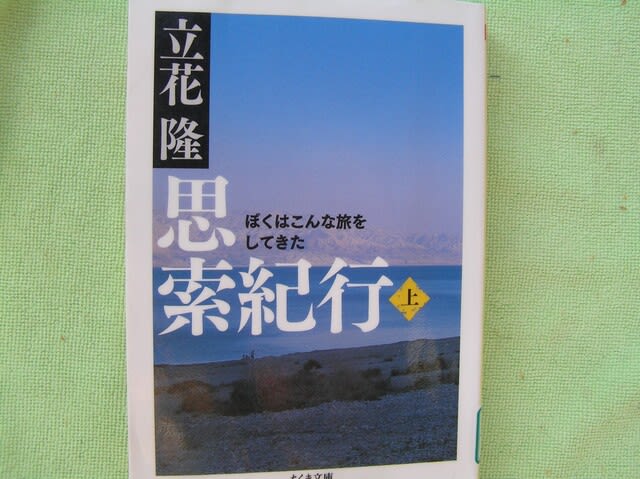「ウマの、嬉し恥ずかしミーハー交遊録(こうゆうろく)」
娘たちによく云われます。「おとーちゃんはミーハーや…」
女房のキャロラインさんは、どんな有名人に会っても態度が全然変わらない人。だからウマみたいに有名人に会うとわくわくソワソワする人間は、余計にミーハーに見えるんやろなあ。ま、しゃーないよなあ。
ウマがちょっと口をきいた有名人、ほんのひと言ふた言も含めるとけっこうたくさんいるよ。
坂本九、吉村まり、阿部公房、司馬遼太郎、大原麗子、サミー・ディヴィスJR、(無名時代の)村上春樹、ジュリエット・グレコ、ジューン・アダムス、伊丹十三、コシノヒロコ、市川吉衛門、加山雄三、田中邦衛、桂枝雀、桂三枝、桂文珍、和田アキコ、ディジー・ガレスピー、サラ・ボーン、カウント・ベイシー、横山フック、坂上二郎…、もっといると思う。
30分以上口をきいたり、一緒に呑んだり食事をした有名人…
日野皓正、中島らも、中井貴恵、長谷川きよし、小林麻美、高村薫(直木賞作家)、笑福亭鶴瓶、八千草薫、五代目桂米團治(小米朝)、五木寛之、C.W.ニコル、藤あや子、永島敏行、赤井英和、田辺聖子、斉藤由貴、風間トオル、藤原紀香、コシノヒロコ、元ゴールデンハーフのエヴァ…もっといると思う。
これもきりがない。ほんまかいな?と疑う人もいるでしょうね。しかしやね、こんな話、わざわざウソついてでっち上げてもしゃーないでしょうが。自慢にもならんし…
上記の有名人たちと御一緒した経緯(いきさつ)、いちいち、ああなるほどと、あなたが納得出来る説明は出来ますし証明も出来ますよ。ま、どうでもエエことやけど…
ここでは、いままで御一緒したなかで、特に印象深い有名人…北村英治さん、中島らもさん、中井貴恵さん、永島敏行さん、そして藤原紀香さんの事などを…そうそう、藤あやこさんや八千草薫さんのことも書いとこうかな…
まず、北村英治さん…
ジャズ雑誌の人気投票、そのクラリネット部門で、もう半世紀もずっとナンバーワン、世界的に見てもトップミュージシャンです。
このきれいな白髪のクラリネット奏者とは、僕が企画・構成したディナーショーでお会いしたのが最初だった。僕のMC(司会)にずっこけるぐらい感心した彼と、その後、縁あってよくご一緒することとなった。プロモーターの仕事をしていた妹の純子は、仕事上、北村さんとは親しかったらしい。
で、その日のステージ…、MCの僕はまず…
…創成期のNHKの技師をしていたお父様が英国留学中に生まれたので英治と名付けられたんですよと切り出し、御両親・御兄弟は皆さんどなたも楽器を嗜(たしな)んだけど、五男坊の英治少年だけは音楽嫌いだった。
戦争で焼け出され、半分焼けたピアノの脇でサンマを焼き「これでピアノの練習をしなくて済む、あゝ嬉しい」…、そんな彼が如何(いか)にクラリネットに出逢い、如何に慶応大学在学中にプロデビューしたか…などなど、様々なエピソードを紹介したあとで彼をステージに呼び出した。
「さあ皆さん、世界最高のクラリネットをお楽しみください。北村家の偉大な五男坊、どうぞっ!」ステージの脇で北村さん、ずっこけてたそうです。
大いに盛り上がったディナーショーのあとの打上げの席、もちろん北村さんの席は一番奥の上座です。僕はミュージシャンたちにサービスせんといかんから座敷の入り口の脇にいた。
「皆さんご苦労さんでした」と乾杯したあと、北村さんが 「ウマさん、ちょっとこちらに来て」とおっしゃる。で、一番上座の彼のところに行くと、なんと彼、脇の席に移り「ま、ここに座って」と、自分が座ってた席に僕を座らせるんです。つまり一番下座にいた僕が、一番上座に座っちゃったんです。
「ウマさん、きょうはほんとにありがとう」とわざわざおっしゃった(ふつうミュージシャンはそんなこと言わん)。
「僕ね、長いことミュージシャンしてるけど、あんな風に紹介されたの初めて。もう、びっくりしちゃった」と、ニコニコ顔でかなりご機嫌なんです。そして
「僕ね、こんなの練習してるんですよ」と、ブリーフケースから赤茶けた古いモーツァルトの楽譜を出して僕に見せるんです。さらに
「今でも月に一度、芸大の先生についてクラリネットのレッスンを受けてるんですよ。ところがね、クラシックの世界では日本最高のその先生ね、僕よりうんと若い方なんだけど、彼がクラリネットを始めたきっかけが、僕のクラリネットを聞いたからなんですって。だからレッスンをお願いした時、とんでもないって、最初、断られちゃった。なんかおかしいよね」
この北村さんの話を聞いて、よく似た話を思い出した…
ラプソディ・イン・ブルーほか、数々の名曲を残したあの偉大な作曲家ジョージ・ガーシュイン…その彼が、現代音楽最大の巨匠ストランビンスキーに弟子入りを乞(こ)うた時、巨匠は 「あなたに教えることなんてありません」と困惑したという。
双方どちらもスーパースター、その謙虚さを大いに感じるこのエピソード、僕はとても好きなんですよね。
世界でも最高峰のジャズクラリネット奏者・北村英治さんが、クラリネットを今でも習っておられる…、御本人から、超意外なその話を聞いた僕は、もう上座に座っていることなど忘れて感激しましたねえ。北村さんは
「ホラ、ウマさん、焼けてますよ」と、七輪の炭火焼の丹波ビーフを、僕のお皿に乗っけてくれました。
「ずいぶん以前の話なんだけど、ダブリンのジャズフェスティバルで演奏した時ね、一番前の席でハンカチを握(にぎ)りしめ食い入るように僕を見つめてる御婦人がいたのね。その彼女、あとで楽屋に来て、かなり興奮して僕に言うんです。
―エイジ!あなたのクラリネットでわたし失神しそうだわ―って…そして僕に強烈なハグしてほっぺに何度もキッスするんです。で、彼女が僕の歳を訊(き)くので64歳ですって答えたら、彼女、もう、すんごく喜んじゃって、あーらエイジ! 私の息子とおない歳だわ!ですって…」
北村さんは、大阪での仕事を終えたあと、北新地にあったジャズクラブ、僕も親しいドラマー浜崎衛さん経営の「A-ラック」に寄るたびに僕に電話をくれた
「ウマさん、来ない?」
この店で、僕の親友と言っていいクラシックのピアニスト吉山輝の伴奏でクラリネットを吹いた北村さんには吉山も感激していた。ほんとに偉い人ってぜんぜん偉そうにしてないんだよね。
クラリネットを吹くために生まれてきた北村英治さん…そのクラリネットを支える右手親指に大きなタコがある北村英治さん…とても素敵な方です。いつまでもお元気で!
中島らもさん…
らもさんの灘高時代の一番の親友が僕の呑み仲間のシンちゃん。そのシンちゃんの結婚披露パーティーで、らもさんとは同じテーブルだった。
新郎新婦とも、日頃から僕の息子のジェイミーを可愛がってくれたので、ジェイミーもパーティーに呼ばれた。彼は七歳ぐらいだったかな。
らもさんの隣りにジェイミーが座ったのはちょっとまずかった。ジェイミーは好奇心旺盛なやつで、例えば、銭湯で「桜吹雪」や「昇り龍」の背中のおっちゃんをみると、すぐさまそのおっちゃんのところへ行き、「おっちゃんの背中、なんでこんなんやの?」 普通の子供やったら、まず親に訊くやろ「おとーちゃん、あのおっちゃんの背中、なんであんなんやの?」
で、らもさんのとなりに座ったジェイミー、さっそく好奇心を発揮した。
「おっちゃん、なんで毛が馬のしっぽみたいに長いの?」
「おっちゃん、なんで黒いメガネかけてんの?」
「おっちゃん、なんで帽子かぶってんの?」
はじめ、「おっちゃん散髪代がないねん」などと答えていたらもさん、ジェイミーの止まらない質問の連発に、とうとう 「この子、なんとかしてください」
当時、朝日新聞連載の「中島らもの明るい悩みの相談室」は、ひょうきんと云っていいその愉快な問答に、僕も含めて多くのファンがいたと思う。で、らもさんにお願いした。
「明るい悩みの相談室」に質問を投稿しようと思ってるんですけど、ぜひ僕の質問を採用していただきたい、つきましては、コレ賄賂(わいろ)です」たまたま持っていた英国の5ポンド紙幣を彼に渡そうとした。もちろん冗談ですよ。ところが、らもさん、超真面目に「そ、そんなん受け取れません」
誰でもわかる冗談を真面目に受け取った彼に、まわりの誰もが大笑いやった。
そのあと、らもさんとは50年代60年代のアメリカンポップスなど音楽の話で盛り上がり、「このあと、ゴンチチのパーティーに呼ばれてるんですけど、ウマさんとジェイミー、一緒に来ませんか」と誘われた。だけど、その時、ウマは、ゴンチチが有名なギターデュオだとは知らなかった。いまから考えると行っとけばよかったよなあ。ジェイミーがたこ焼き食べたいっちゅうもんやから、らもさんとはご一緒しなかったんや。
御一緒した席で、彼は一滴も飲まなかった。後年、彼の小説 「今夜、すべてのバーで」を読んで、自身の壮絶なアル中体験を知った。あの作品は芥川賞級の彼の最高傑作だと今でも信じている。
彼が、階段から墜ちるという不慮の事故で亡くなったとき、僕は「あゝ、彼らしいなあ」と思って、別に驚かなかった。
唯我独尊(ゆいがどくそん)とは別の意味で、日本の文壇とは隔絶した孤高の人だったように思う。彼が僕にくれた自宅の住所や電話番号は今でも持っているよ。
中井貴恵さん…
1970年代はじめ頃だったと思う。中井貴恵さんと、渋谷の「インデイラ」というカレー屋で食事したあと、東急会館の喫茶店でコーヒーを飲みながら、かなりだべったことがあった。
厳密に言うと、その時、彼女はまだ有名人じゃなかった。彼女が主演した市川昆監督の「女王蜂」の撮影がすべて終わり、来月公開という、つまり女優としてデビュー直前だったんですね。だけど、あの佐田啓二の娘だとは聞いていた。弟の中井貴一はまだ高校生じゃなかったかな。
当時、早稲田の学生だった彼女は、テニス部のほか「放送研究会」に所属していたが、その同じサークルにいたのが、僕の親しい友人だった舟橋君で、彼の紹介で会ったわけなんです。
カレーを食べてる時、漬物(らっきょや福神漬など)の容器を、わざわざ僕の前に置いてくれたり、お水を注(つ)いでくれたりした。この人、気配(きくば)りする育ちのええ人やなあ、というのが第一印象。
そのあと、場所を変え、コーヒーを飲みながら映画の話になった。映画の話ならウマに任せなさい。
「カサブランカ」で、ハンフリー・ボガードが、自分の経営する店のピアニストに、「その曲は弾くなと言ってあるだろ」と、アズ・タイム・ゴーズバイを止(や)めさせる有名なシーンのことを彼女は知らなかった。女優を目指すんだったら、イングリッド・バーグマンやキャサリン・ヘップバーン、ダイアン・キートンの映画は観なくちゃだめですよなんて偉そうに云っちゃった。
「第三の男」のアントン・カラスによるテーマ、ニーノ・ロータによる「太陽がいっぱい」のテーマも、彼女、知らなかった。でも「是非、聴いてみます」 その素直さにはすごく良い印象を持ちました。もちろん、一世を風靡(ふうび)した菊田一夫の名作「君の名は」で、岸恵子の相手をした彼女のお父さん、佐田啓二さんの話をするのは遠慮した(彼女が幼い時に交通事故でなくなったからね)。
自分の父親が有名俳優だったことなどおくびにも出さないその控(ひか)えめな性格に、ウマはとても好感を持ちましたね。のちに有名女優になることがわかってたら、もっと仲良くしておくんだった。いや、いかんいかん、やっぱりミーハーやウマは…
そうそう、前述の舟橋君とはぜひ再会したいと願ってるけど、一緒に中井貴恵さんともまた会いたいなあ…
続く