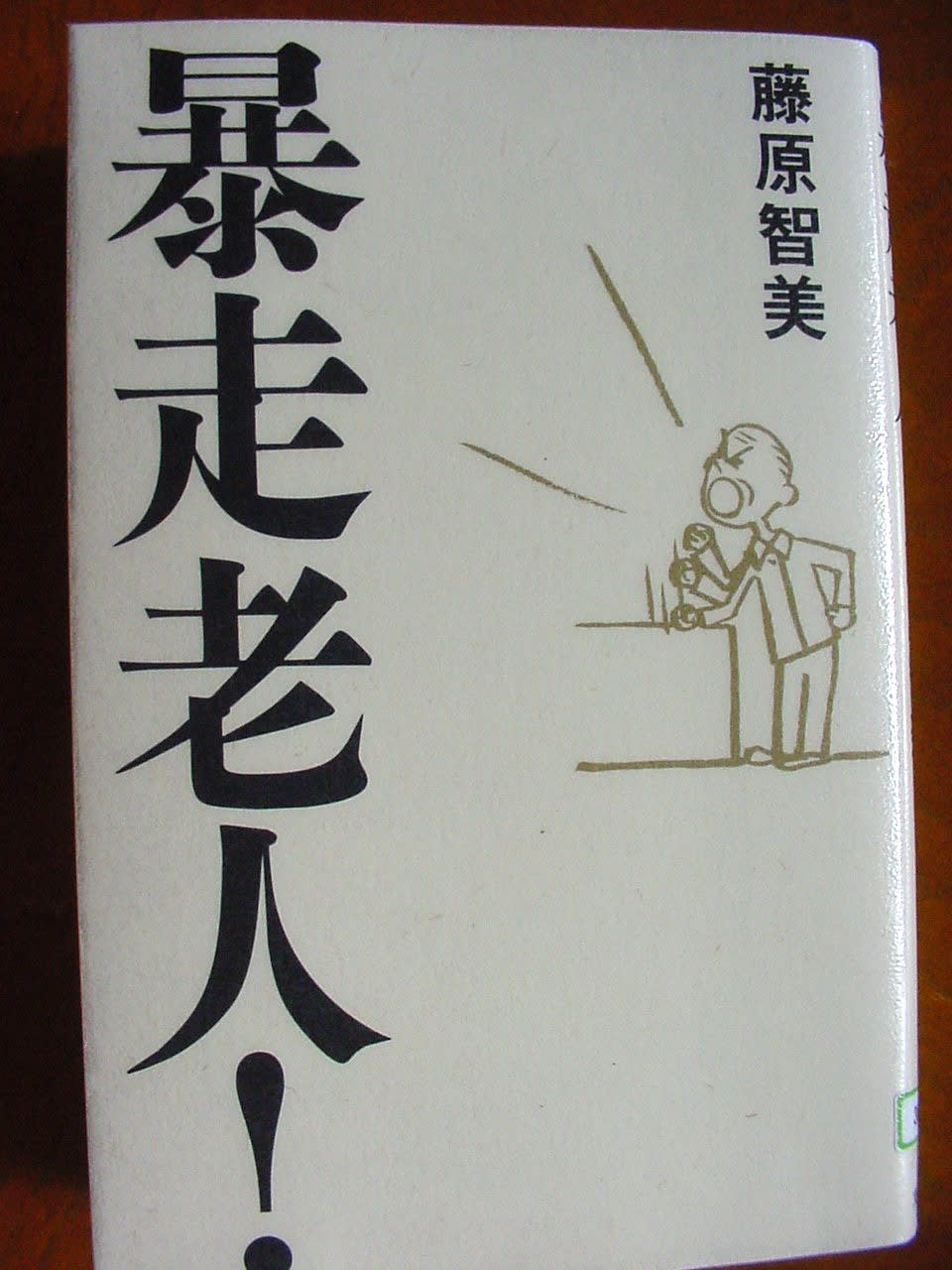「秘すれば花なり」という言葉があります。平たく言えば「秘密にするからこそ価値がある」という意味合いだそうです。
たとえば手品を連想すると分かりやすいかもですね。手品のタネを知らないと「凄い」と思うが、いざタネを知ってしまうと「なんだ、そんな簡単なことか」と呆れることが多いです。
このブログでいつもグダグダ書いているオーディオシステムにしても、これと似たようなもので読者にとっては「聴いていないからこそ値打ちがある」とも言えそうですよ(笑)。
たとえば全国津々浦々の読者の方々の中にはもしかして「この人はかなり珍しいスピーカーや古典管を使っているようだし、一度、音を聴いてみたいものだ」と思っている方がいらっしゃるかもしれないですね。
な~に、大したことないです(笑)。
そりゃあ、聴いた当初は物珍しさも手伝って「素敵・・」かもしれませんが、次第に慣れてくるとアラにも気が付いて「な~んだ、我が家の音にもいいところがあるじゃないか」という成り行きが十分考えられます。
やっぱり「聴かぬが花」なんじゃないかなあ(笑)。
たしかずっと昔の「ステレオ・サウンド」誌だったと思いますが、ジャズ・オーディオの大御所「菅原昭二」さんの投稿した記事の中で、懇意にしている和尚さんのオーディオシステムを聴きに行ったところ、その和尚さん、世間話をするばかりでとうとう聴かせてもらえず、そのうち亡くなられたという逸話が妙に記憶に残っています。
「音は実際に聴いてみるとそこで終わってしまう。想像の中に留めておくからこそ時間と空間を超越して無限の豊かさと広がりを持つ。」というのが和尚さんの当時の心境だったのではなかろうかと、今にして分かるような気がします。
これはオーディオに限ったことではありませんよね。高齢者になると「あれは想像の中に閉じ込めておく方が良かったかもしれない」ことに、いくつか思い当たります(笑)。
そして、もう一つ~、今度はホスト側からの「聴かせぬが花」。
「2・6・2」の法則というのがあります。別名「パレートの法則」とも言われていてご存知の方も多いと思います。
「人間が集団を構成すると、『優秀な人が2割、普通の人が6割、パッとしない人が2割』という構成になりやすいという法則。例えば、集団で何らかの活動をすると、2割の人が、率先してリーダーシップを発揮し、6割の人が、そのリーダーシップに引っぱられて働き、2割の人が、ボーっとしてる、という傾向がある。
次に、その2割のサボった人達を除いて、残りのメンバーだけで同様の活動をすると、やはり、メンバーの中の約2割の人が、新たにサボり始めます。逆に、サボった人ばかりを集めてグループを作り、活動をさせると、その中の約2割の人がリーダーシップを発揮し始め、6割の人は、それに引っぱられて動き始めるそうです。
これは、優秀な人ばかりを集めてグループを作った場合も同様で、6割は普通に動き、2割はパッとしなくなるといいます。スポーツの世界でも、お金をかけてスタープレイヤーを集めても、ズバ抜けて強いチームができるわけではないというのはこういうことなのでしょう。逆に、スタープレイヤーを引き抜かれてしまったチームには、次のスタープレイヤーが出てきたりします。
実は、生物の世界にも、似たような現象があります。アリは働き者というイメージがありますが、数%のアリは、働かずにふらふら遊んでいるそうです。そして、このふらふらしていたアリたちだけを集めて別の場所に移して、しばらく観察していると、その中の数%のアリだけがふらふらと遊び出し、他のアリたちは働き者に変身するそうです。逆に、働き者のアリばかりを集めて集団を作っても、まもなく数%のアリは遊び出すといいます。この数%という比率は、いつも変わらないそうです。」
敷衍(ふえん)すると、組織をはじめどんな事柄にも「緩み」が必要なんですかね・・、たとえば自動車のハンドルにも「遊び」みたいなゆとりが必要だし、精鋭ばかりだとたしかに息が詰まりそうな気がします(笑)。
さて、我が家のオーディオシステムを実際に聴いた人も実はこの「パレートの法則」が当てはまるのではないかと思うのです。
全体の2割は「なかなかいい音だ!」、6割は「な~んだ、口ほどにもない普通の音じゃないか!」、残る2割は「この音には感心しない!」
結局、8割方の人たちはガッカリするというのがせいぜいの図式でしょう。
しかも、絶賛してくれた肝心の2割も2~3日経って “ほとぼり” が醒めてみると、結局「我が家の音が一番いい」と、こうなります。
人間とは最終的には都合のいいように解釈して己を納得させる人種ですからね(笑)。
したがって「四面楚歌」になるのは目に見えているのでホスト側からすると「聴かせぬが花」が一番だと思います!
そこで質問・・、読者の皆様方は「聴かぬが花」と「聴かせぬが花」のどちらに加担しますか?
えっ、両方とも賛成・・、まさかあ(笑)
クリックをお願いね →
「40Hzの低音(あるいは40Hzの音波や振動)は、認知症の予防や改善に効果がある可能性があると注目されています。これは、特にアルツハイマー病に関連して研究が進められており、40Hzの音や光の刺激が脳のガンマ波を活性化させることで、脳内の老廃物(アミロイドβなど)の除去や神経細胞の機能改善に役立つと考えられているためです。
🌟 40Hz刺激の研究と効果
-
MIT(マサチューセッツ工科大学)の研究
-
2016年にMITの研究チームが、アルツハイマー病モデルマウスに40Hzの音や光を当てたところ、脳内のアミロイドβが減少し、認知機能が改善したという報告があります。
-
40Hz刺激により、脳内でガンマ波(40Hz付近の脳波)が誘導され、これが**ミクログリア(脳の免疫細胞)**を活性化してアミロイドβの除去を促したとされています。
-
-
人への応用
-
その後の臨床研究でも、40Hzの音や光による刺激が記憶力や集中力の改善につながる可能性が示されています。
-
40Hzの音楽をヘッドフォンで聞いたり、40Hzのリズムで光を見たりすることで、軽度認知障害(MCI)の症状が改善した例も報告されています。
-
-
振動刺激
-
最近では、40Hzの振動を手や足に与えることで効果を狙う研究もあります。
-
振動刺激が脳に伝わることでガンマ波を誘発し、認知機能や記憶力の改善が期待されています。
-
🔬 なぜ40Hzが効くのか?
-
脳の**ガンマ波(30〜100Hz)**は、注意力・認知・記憶などの機能に関与しています。
-
アルツハイマー病患者ではガンマ波の活動が低下していることが知られており、40Hzの刺激でこのガンマ波を回復させることが脳機能改善に役立つと考えられています。
-
ガンマ波の増強により、
-
ミクログリアによるアミロイドβ除去
-
神経可塑性(シナプスの強化)
-
神経炎症の抑制
が促進される可能性があります。
-
🎧 実践的な方法
-
40Hzの音楽やノイズを聞く(YouTubeやアプリに40Hzの音楽がある)
-
40Hzの光刺激デバイスを使用する(市販されているガンマ波誘導ライトなど)
-
40Hzの振動刺激デバイス(手や足に当てるもの)
🧠 効果や課題
✅ 認知機能や記憶力の改善報告あり
✅ アミロイドβの減少が確認された
✅ 副作用は少ない(音や光に敏感な人は注意が必要)
⚠️ 研究段階であり、個人差がある
⚠️ 効果が出るまでに時間がかかる可能性
⚠️ 強い刺激や長時間の使用には注意
「完全に効果が証明された」とまでは言えませんが、研究結果は期待できる内容です。手軽に試せる方法もあるので、認知症予防の一環として取り入れてみる価値はあるかもしれません。興味があれば40Hz音源を試してみますか?」
以上のとおりです。
「趣味と実益」を兼ねて「40ヘルツの低音」を聴きましょうよ~(笑)。