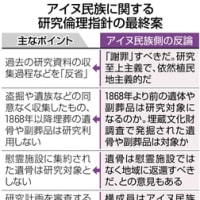(毎日新聞 2010年5月30日 東京朝刊)
(文藝春秋・1575円)
◇半身を追う宿命的冒険
昭和二十年六月、ボルネオ島のジャングルの中で、ひとりの男が消息を絶った。三上隆、大正五年、和歌山県田辺生まれの冒険家である。当時、三上が強く惹(ひ)かれていたのは、台湾先住民族のあいだに残る小人伝説で、文献を博捜し、フィールドワークを重ねるにつれ、三上は先住民より前に、ネグリトと呼ばれる古矮小(わいしょう)民族が実在したのではないかと考えるようになる。
姿を消す前、三上は中学時代の旧友村上三六(さぶろう)に、蝶(ちょう)を追っているうち小人の村にたどり着く夢を見たと手紙を書き送っていた。そして、戦後も生きているという噂(うわさ)が絶えなかったため、村上は、昭和三十年から昭和五十七年にかけて三度の捜索隊を組織し、友人がボルネオの奥深い集落に住み、現地の娘と結婚していたことを突き止める。ただしその妻を残して、ふたたび行方をくらましていたこともわかった。
本書は、一九九六年、偶然三上隆の存在を知って興味を抱いた語り手が、その後の足取りを追う報告書であり、過去三度行われた捜索の、精緻(せいち)な再話の試みでもある。文献と捜索隊参加者の証言、及び聞き書きからなる物語の再構成が全体の三分の二を占め、残りが語り手自身の冒険譚(たん)となっている。
注意すべきは、村上三六の名のなかに、三上の文字が含まれていることだ。つまり村上は三上の分身にほかならず、消えた半身を追うのは宿命だったかもしれないのである。とすれば、語り手がこの宿命を負っているのも当然だろう。なぜなら彼は村上三六の息子であり、しかも、語りをなりわいとする小説家だからである。
三上はボルネオを去ったのち、チベットでラマ僧になっているという説があった。そこで語り手は、二〇〇九年、あらたな捜索隊を組織して、チベットに乗り込もうとする。しかし当時のチベットは政情不安で、とても奥地まで入り込むことができない。そこで考え出されたのが、なんと雲南省の松茸(まつたけ)狩りツアーに便乗し、途中で抜け出すという大胆な計画だった。
ところで、本作はほぼ五年かけて少しずつ雑誌に発表されたものだが、初出時は「イタリアの秋の水仙」という麗しいタイトルが付されていた。この詩のような言葉の意味は作中で明かされているけれど、単行本化にあたり、著者はあえて『闇の奥』と改題することを選んだ。言うまでもなく、これはコンラッドが一八九九年に刊行した小説のタイトルであり、著者は明らかにその作品世界を意識している。
コンラッドの『闇の奥』は、ロンドンのテムズ河に浮かぶ帆船で、語り手がマーロウという船乗りの思い出話に耳を傾け、それを転記する聞き書き形式をとっている。話の舞台はアフリカ大陸の奥地。マーロウは貿易会社の社員として現地に赴き、象牙を代表とする品々を現地の人間を使って調達していた、クルツというカリスマ的な男が瀕死(ひんし)の状態にあることを知る。三上の位置は、このクルツに相当するだろう。
あえて古典とおなじタイトルを選んだのは、コンラッドに対する愛と敬意の表明ばかりではない。著者は距離を保った聞き書きの領域を抜け出し、語り手自身が主人公となる物語を最後に加えることで、先例を超えようとする。実際、須永という、じつはチベット出身の魅力的な女性医師が絡んでくることで、探索は冒険活劇さながらの展開となり、二十一世紀の闇の奥に、物語だけに許された光が射(さ)しはじめるのだ。タイトルの深い意味が納得されるのは、まさにその瞬間なのである。
http://mainichi.jp/enta/book/news/20100530ddm015070003000c.html
(文藝春秋・1575円)
◇半身を追う宿命的冒険
昭和二十年六月、ボルネオ島のジャングルの中で、ひとりの男が消息を絶った。三上隆、大正五年、和歌山県田辺生まれの冒険家である。当時、三上が強く惹(ひ)かれていたのは、台湾先住民族のあいだに残る小人伝説で、文献を博捜し、フィールドワークを重ねるにつれ、三上は先住民より前に、ネグリトと呼ばれる古矮小(わいしょう)民族が実在したのではないかと考えるようになる。
姿を消す前、三上は中学時代の旧友村上三六(さぶろう)に、蝶(ちょう)を追っているうち小人の村にたどり着く夢を見たと手紙を書き送っていた。そして、戦後も生きているという噂(うわさ)が絶えなかったため、村上は、昭和三十年から昭和五十七年にかけて三度の捜索隊を組織し、友人がボルネオの奥深い集落に住み、現地の娘と結婚していたことを突き止める。ただしその妻を残して、ふたたび行方をくらましていたこともわかった。
本書は、一九九六年、偶然三上隆の存在を知って興味を抱いた語り手が、その後の足取りを追う報告書であり、過去三度行われた捜索の、精緻(せいち)な再話の試みでもある。文献と捜索隊参加者の証言、及び聞き書きからなる物語の再構成が全体の三分の二を占め、残りが語り手自身の冒険譚(たん)となっている。
注意すべきは、村上三六の名のなかに、三上の文字が含まれていることだ。つまり村上は三上の分身にほかならず、消えた半身を追うのは宿命だったかもしれないのである。とすれば、語り手がこの宿命を負っているのも当然だろう。なぜなら彼は村上三六の息子であり、しかも、語りをなりわいとする小説家だからである。
三上はボルネオを去ったのち、チベットでラマ僧になっているという説があった。そこで語り手は、二〇〇九年、あらたな捜索隊を組織して、チベットに乗り込もうとする。しかし当時のチベットは政情不安で、とても奥地まで入り込むことができない。そこで考え出されたのが、なんと雲南省の松茸(まつたけ)狩りツアーに便乗し、途中で抜け出すという大胆な計画だった。
ところで、本作はほぼ五年かけて少しずつ雑誌に発表されたものだが、初出時は「イタリアの秋の水仙」という麗しいタイトルが付されていた。この詩のような言葉の意味は作中で明かされているけれど、単行本化にあたり、著者はあえて『闇の奥』と改題することを選んだ。言うまでもなく、これはコンラッドが一八九九年に刊行した小説のタイトルであり、著者は明らかにその作品世界を意識している。
コンラッドの『闇の奥』は、ロンドンのテムズ河に浮かぶ帆船で、語り手がマーロウという船乗りの思い出話に耳を傾け、それを転記する聞き書き形式をとっている。話の舞台はアフリカ大陸の奥地。マーロウは貿易会社の社員として現地に赴き、象牙を代表とする品々を現地の人間を使って調達していた、クルツというカリスマ的な男が瀕死(ひんし)の状態にあることを知る。三上の位置は、このクルツに相当するだろう。
あえて古典とおなじタイトルを選んだのは、コンラッドに対する愛と敬意の表明ばかりではない。著者は距離を保った聞き書きの領域を抜け出し、語り手自身が主人公となる物語を最後に加えることで、先例を超えようとする。実際、須永という、じつはチベット出身の魅力的な女性医師が絡んでくることで、探索は冒険活劇さながらの展開となり、二十一世紀の闇の奥に、物語だけに許された光が射(さ)しはじめるのだ。タイトルの深い意味が納得されるのは、まさにその瞬間なのである。
http://mainichi.jp/enta/book/news/20100530ddm015070003000c.html