
今回のお気に入りは、「英国鳥類図譜」です。
先日ネットオークションで「英国鳥類図譜」が出品されました。
全6巻がバラで売りで出ていたので、この機会に何としても1冊だけ入手したいと思いました。
万が一にも1冊も落札できないということがないように、念のため複数冊で入札参加しました。
入札し、高値更新され、また入札する、ということを繰り返している内に、うっかり2冊落札してしましました。
1冊数万円もする高価な本を2冊も買うことになるとは思ってもいなかったので、落札が決まったときには頭を抱えました。
思いきり予算オーバーです。
オークションの難しさを改めて実感しました。
今後しばらくの間は欲しい本やウイスキーがあっても控えなくてはなりません。シクシク・・・。
そんな愚痴を並べていても仕方がありません。
こうなったら関連資料をとことん調べて、今回の図譜をたっぷり楽しもうと思います。
本書の原題は「A history of British birds」。
日本では「英国の鳥の歴史」「英国鳥類図譜」「英国鳥類史」「英国鳥類誌」などというタイトルで紹介されています。
1851年から1857年にかけて全6巻がロンドンで刊行されました。
300葉に及ぶ細密な原色図版を収め、イギリスで最初の普及版鳥類図譜として爆発的な人気を呼びました。
著者は、F.O.モリス(Francis Orpen Morris、1810年~1893年)。
イギリスの牧師、博物学者、英国王立鳥保護協会の初期設立メンバー。
図版画家は、B.フォーセット(Benjamin Fawcett、1808年~1893年)。
版画技法は、Wood Engraving / 木口(こぐち)木版画、Hand Coloured / 手彩色。
別の資料では「多色木版画手彩色補助」と紹介されています。
フォーセットによる多色木版画に、彩色画家であるフォーセット夫人が手彩色して仕上げたということでしょう。
今回無理をしてでも何とか入手したいと思ったのには理由があります。
私が博物図譜の鑑賞にハマる原因になった荒俣宏氏が著書の中で本書を褒めている上、図版を載録しているのです。
荒俣氏のコレクションと同じ図譜を入手するチャンスなんて滅多にある訳がありません。
彼が所有するオーデュボン、メーリアン、グールド、ルヴァイアン、ブロッホなど有名どころの図譜は金額の桁が違うので、宝くじにでも当たらなければ購入できません。
それを考えると今回はギリギリ手が届く貴重な機会。
そんな訳で何としても入手したいと考えたのです。
さて荒俣宏氏は本書をその著書の中で次のように紹介しています。
「世界大博物図鑑」
=====
図版1葉を載録。図書解説は次の通り。
=====
19世紀後半のベストセラー。
初版以来多数の版を重ねたのは、手彩色木版図357葉(後年には400葉まで増加)の美しさによる。
今日でもモリスの鳥類誌はビューイングのそれと並び英国民に愛されている。
=====
「図鑑の博物誌」(リブロボート)
=====
図版1葉を載録。図書解説と本文は次の通り。
=====
(F.O.モリスが)多色木版制作家ベンジャミン・フォーセットと組んで刊行した「英国鳥類図譜」(1851-1857)は300葉に及ぶ図版を収めた最初の普及版鳥類図鑑として爆発的な人気を呼んだ。
手がこんでいないがサラリとした各図版は木版の素朴さと色刷りの魅力を兼ね備え、かなり満足のできる作品となっている。
=====
油性ではなく水性---ときには水彩絵具を使って木口木版の彩色印刷を完成させたのは、ベンジャミン・フォーセットという人物だ。
かれはF.O.モリスの名著「英国鳥類図譜」に収められた美しい図版の制作者として知られており、その味わいは、日本の浮世絵の刷りあがりによく似ている。
かれはみずから手がけた印刷物を”クロモズィログラフ” Chromoxylograph(多色木版)と名づけた。
=====
最後に。
今回入手した2冊について。
1895年にロンドンで刊行された増補改訂第4版で、図版が394葉に増えています。
第4巻は、ライチョウ・ウズラ・ノガン・チドリ・ツル・サギ・コウノトリ・フラメンゴ・シギなどの図版が68葉掲載されています。
第5巻は、シギ・ツル・カモ・ハクチョウ・アイサなどの図版が68葉掲載されています。
木口木版という細密技法と手彩色の微妙な加減を1枚1枚堪能しています。
ときにはメガネを外して顔を寄せ、細部を観察。
気になる図版については英和辞典を片手に解説文を拾い読み。
今回は敬愛する荒俣氏が「かなり満足できる作品」と評した図版の美を共感できたことが最大の収穫でした。
それだけでも無理をして入手した価値があります。
先日ネットオークションで「英国鳥類図譜」が出品されました。
全6巻がバラで売りで出ていたので、この機会に何としても1冊だけ入手したいと思いました。
万が一にも1冊も落札できないということがないように、念のため複数冊で入札参加しました。
入札し、高値更新され、また入札する、ということを繰り返している内に、うっかり2冊落札してしましました。
1冊数万円もする高価な本を2冊も買うことになるとは思ってもいなかったので、落札が決まったときには頭を抱えました。
思いきり予算オーバーです。
オークションの難しさを改めて実感しました。
今後しばらくの間は欲しい本やウイスキーがあっても控えなくてはなりません。シクシク・・・。
そんな愚痴を並べていても仕方がありません。
こうなったら関連資料をとことん調べて、今回の図譜をたっぷり楽しもうと思います。
本書の原題は「A history of British birds」。
日本では「英国の鳥の歴史」「英国鳥類図譜」「英国鳥類史」「英国鳥類誌」などというタイトルで紹介されています。
1851年から1857年にかけて全6巻がロンドンで刊行されました。
300葉に及ぶ細密な原色図版を収め、イギリスで最初の普及版鳥類図譜として爆発的な人気を呼びました。
著者は、F.O.モリス(Francis Orpen Morris、1810年~1893年)。
イギリスの牧師、博物学者、英国王立鳥保護協会の初期設立メンバー。
図版画家は、B.フォーセット(Benjamin Fawcett、1808年~1893年)。
版画技法は、Wood Engraving / 木口(こぐち)木版画、Hand Coloured / 手彩色。
別の資料では「多色木版画手彩色補助」と紹介されています。
フォーセットによる多色木版画に、彩色画家であるフォーセット夫人が手彩色して仕上げたということでしょう。
今回無理をしてでも何とか入手したいと思ったのには理由があります。
私が博物図譜の鑑賞にハマる原因になった荒俣宏氏が著書の中で本書を褒めている上、図版を載録しているのです。
荒俣氏のコレクションと同じ図譜を入手するチャンスなんて滅多にある訳がありません。
彼が所有するオーデュボン、メーリアン、グールド、ルヴァイアン、ブロッホなど有名どころの図譜は金額の桁が違うので、宝くじにでも当たらなければ購入できません。
それを考えると今回はギリギリ手が届く貴重な機会。
そんな訳で何としても入手したいと考えたのです。
さて荒俣宏氏は本書をその著書の中で次のように紹介しています。
「世界大博物図鑑」
=====
図版1葉を載録。図書解説は次の通り。
=====
19世紀後半のベストセラー。
初版以来多数の版を重ねたのは、手彩色木版図357葉(後年には400葉まで増加)の美しさによる。
今日でもモリスの鳥類誌はビューイングのそれと並び英国民に愛されている。
=====
「図鑑の博物誌」(リブロボート)
=====
図版1葉を載録。図書解説と本文は次の通り。
=====
(F.O.モリスが)多色木版制作家ベンジャミン・フォーセットと組んで刊行した「英国鳥類図譜」(1851-1857)は300葉に及ぶ図版を収めた最初の普及版鳥類図鑑として爆発的な人気を呼んだ。
手がこんでいないがサラリとした各図版は木版の素朴さと色刷りの魅力を兼ね備え、かなり満足のできる作品となっている。
=====
油性ではなく水性---ときには水彩絵具を使って木口木版の彩色印刷を完成させたのは、ベンジャミン・フォーセットという人物だ。
かれはF.O.モリスの名著「英国鳥類図譜」に収められた美しい図版の制作者として知られており、その味わいは、日本の浮世絵の刷りあがりによく似ている。
かれはみずから手がけた印刷物を”クロモズィログラフ” Chromoxylograph(多色木版)と名づけた。
=====
最後に。
今回入手した2冊について。
1895年にロンドンで刊行された増補改訂第4版で、図版が394葉に増えています。
第4巻は、ライチョウ・ウズラ・ノガン・チドリ・ツル・サギ・コウノトリ・フラメンゴ・シギなどの図版が68葉掲載されています。
第5巻は、シギ・ツル・カモ・ハクチョウ・アイサなどの図版が68葉掲載されています。
木口木版という細密技法と手彩色の微妙な加減を1枚1枚堪能しています。
ときにはメガネを外して顔を寄せ、細部を観察。
気になる図版については英和辞典を片手に解説文を拾い読み。
今回は敬愛する荒俣氏が「かなり満足できる作品」と評した図版の美を共感できたことが最大の収穫でした。
それだけでも無理をして入手した価値があります。


















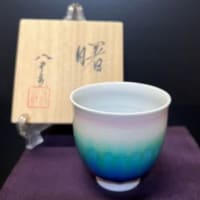

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます