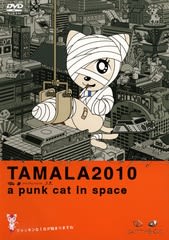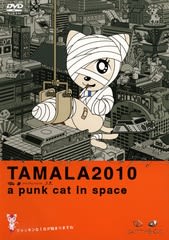2012年の12月に行われた総選挙では大方の予想通り自民党の圧勝となった。理由は民主党が勝手にコケたから・・・・というのも大きいが(笑)、何と言っても大半の国民の関心事であった景気対策に言及したからだと思う。ちなみに民主党をはじめとする他党の公約は、このあたりが実に貧弱であった。
発足した安倍政権は、さっそく総額20兆円規模の緊急経済対策を打ち出した。さて、果たしてこの政策、本当に日本経済を活性化させることが出来るのだろうか。
何でも、公共事業(財政政策)、金融政策、成長戦略を「3本の矢」として推進していくらしい。まあ、成長戦略は別としても財政政策と金融政策は教科書通りの景気対策であるし、これらを実施することには異存は無い。アホなマスコミの中には「そんなのはカビの生えた古い手法に過ぎない」と論難する向きもあるらしいが、古かろうが何だろうがこれらしか方法はない。今までずっと日本経済が低空飛行を続けていたのは、この「古い手法」を効果的にやっていなかったからだ。
じゃあ、安倍政権の政策で景気が刺激されて経済が上向くのかというと、そう簡単に事は運ばないと思う。
まず、金融緩和は結果的にあまり大きな効果は望めないと思う。何しろ現時点での超低金利でも投資額は増えないのだ。なぜなら市場に消費需要が無く、当然のことながら投資の需要も無いからである。金融政策による景気の拡大というのは、あまりデフレが深化していない時点では有効かもしれないが、今のような慢性的な需要不足で不況が長引いている状態ではさほど意味は無い。まあ“やらないよりはマシかもしれない”というレベルの話だろう。
そもそも経済マクロ的に「景気が良い」というのはどういう状況を示すのかというと、早い話がGDPが順調にシフトアップしていくことであろう。そのGDPの6割程度を占めるのが個人消費だ。つまりは個人消費を増大させることが景気回復の重要事項の一つなのである。では、安倍政権の政策で個人消費は増えるのだろうか。
金融政策については前述の通りだが、財政政策はどうか。確かに公共事業のテコ入れでマクロの投資額は増えるから、GDPの総額は大きくなるはずだ。ならば、公共工事の発注で潤った各企業は従業員にその分を還元してくれるのだろうか。
昔の高度成長時代には“企業が儲かり、それと平行して所得水準も上がる”という構図があったらしいが、今はそうではない。いくら企業の利益が大きくなっても、人件費には反映せずに内部留保で貯め込むだけだろう。これに対して安倍政権は、企業が給料や雇用を増やすとその人件費増加分の10%を法人税から差し引くという税制を打ち出すという話だ。しかし、人件費アップ分と法人税減額分とを天秤に掛けた結果、人件費増額の方を切り捨てる企業だって出てくるはずだ。つまりは各企業の事情によって結果はまちまちになり、確実なマクロ的所得水準の向上には結びつかない。
所得が増えなければ個人消費がアップするわけはなく、GDPの上昇も一時的なものになる。最初に確実な個人消費の増大を狙うのならば、減税あるいは(麻生政権下で行ったような)給付金を大規模にやるべきだ。なお、こういうことを言うと“いくら減税しても国民は貯め込むだけで消費に回らない”という突っ込みが入るかもしれないが、国民の懐がいくらか暖かくなればそれを狙って企業活動も活発化するはずだから、その分経済波及効果を生む。
それから安倍政権の政策に対して危惧することをもう一つあげると、消費税率のアップが予定されていることだ。景気が回復すれば消費税増税を実施する(回復しなかったら取りやめる)という条項はあるが、もしも財政政策でいくらかGDPの伸び率が好転して“さあ、これで景気は持ち直した。次は増税だ”という筋書きになってしまうと、上向きかけていた景気は一気に冷え込む可能性が大きい。
麻生政権時には麻生首相は“日本経済は全治3年だ”と言っていたが、3年ではなく1年足らずで回復基調にあるのかどうかを早々とチェックして増税に持って行くというのは、拙速に過ぎる。一時的な景気好転ではなく、恒常的な経済成長を見極めた上で増税を検討すべきではないのか。
なるほど安倍政権の経済政策は、民主政権時の政策や小泉構造改革路線に比べれば遙かにマシかもしれない。しかし、国民の所得水準上昇に関しての明確なスキームが提示されていないこと、そして消費税増税が控えていること、この2点が大きなネックとなって諸手を挙げての賛同は出来ない。
まあ、2013年には参院選もあることだから、国民は政府に対する注文があるならばその時に意思表示すべきだろう。今後の推移を見守りたい。