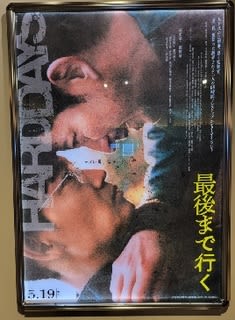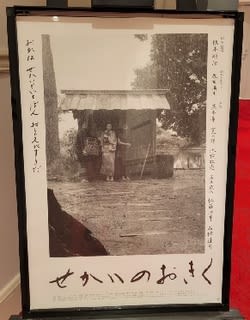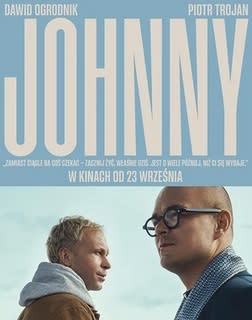(原題:SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE )観る価値はある。何より、シモーヌ・ヴェイユという政治家を知ることができただけでも、この映画に接して本当に良かったと思う。東洋の島国に住んでいる我々には、世界中の重要な仕事を成し遂げた為政者をすべて認知するのは難しいのかもしれないが、それでも映画を通じて紹介してくれたのは意義深い。
主人公シモーヌは1927年南仏ニースの生まれ。ユダヤ人であったことから、第二次世界大戦中に親ドイツのヴィシー政権が成立した際に検挙され、家族と共に収容所送りとなる。何とか生き抜いた彼女は、戦後はパリ大学で法学を学び、司法試験合格し法曹界へと進む。やがてポンピドゥー政権下で司法官職高等評議会の事務総長に任命され、政治家としての道を歩み始める。

ヴェイユのことをネット上で検索しただけでも、かなりの実績を上げた人材であることが分かる。もちろん、本作は彼女が残した功績をクローズアップすることが狙いなので、マイナス面があったとしてもそれを殊更論うことは無い。それでも誰も手を付けていなかった人権問題、しかもそれまで“問題”として認識もされていなかった案件の数々を取り上げて解決への道筋を示した手腕には感服するしかないのだ。
脚本も担当したオリヴィエ・ダアンの演出は巧みで、あえて時系列をランダムに配置し、1974年での中絶法の可決を実現させると共に79年には女性として初めて欧州議会議長に選出された事実を最初に提示して、この仕事の背景になった彼女の生い立ちをそれぞれピックアップしていく構成が効果を発揮している。単に史実を順序立てて追うだけでは、これほどのインパクトは無かったはずだ。その手法が真にモノを言うのが、終盤近くで紹介されるアウシュビッツ収容所でのエピソードだ。この辛い体験があるからこそ、非人道的な事柄にアグレッシブに対峙するシモーヌの姿勢が鮮明になる。

キャストでは中年以降の主人公を演じるエルザ・ジルベルスタインのパフォーマンスが際立っている。本当に政治家にしか見えないのだから大したものだ。もちろん、同じユダヤ系であることも大きいだろう。若い頃のヒロインに扮したレベッカ・マルデールも良い仕事をしている。エロディ・ブシェーズやオリヴィエ・グルメなどの他の面子も申し分ない。
シモーヌ・ヴェイユは2017年に世を去ったが、その時は国葬が催され、パンテオンに合祀されている。その功績を考えれば当然と思われ、実際には多くの国民がそれを支持した。勝手に閣議決定だけで元総理の国葬の実施を決め、国会の議決どころか世論の賛同も得ないまま断行してしまったどこかの国とは大違いである。
主人公シモーヌは1927年南仏ニースの生まれ。ユダヤ人であったことから、第二次世界大戦中に親ドイツのヴィシー政権が成立した際に検挙され、家族と共に収容所送りとなる。何とか生き抜いた彼女は、戦後はパリ大学で法学を学び、司法試験合格し法曹界へと進む。やがてポンピドゥー政権下で司法官職高等評議会の事務総長に任命され、政治家としての道を歩み始める。

ヴェイユのことをネット上で検索しただけでも、かなりの実績を上げた人材であることが分かる。もちろん、本作は彼女が残した功績をクローズアップすることが狙いなので、マイナス面があったとしてもそれを殊更論うことは無い。それでも誰も手を付けていなかった人権問題、しかもそれまで“問題”として認識もされていなかった案件の数々を取り上げて解決への道筋を示した手腕には感服するしかないのだ。
脚本も担当したオリヴィエ・ダアンの演出は巧みで、あえて時系列をランダムに配置し、1974年での中絶法の可決を実現させると共に79年には女性として初めて欧州議会議長に選出された事実を最初に提示して、この仕事の背景になった彼女の生い立ちをそれぞれピックアップしていく構成が効果を発揮している。単に史実を順序立てて追うだけでは、これほどのインパクトは無かったはずだ。その手法が真にモノを言うのが、終盤近くで紹介されるアウシュビッツ収容所でのエピソードだ。この辛い体験があるからこそ、非人道的な事柄にアグレッシブに対峙するシモーヌの姿勢が鮮明になる。

キャストでは中年以降の主人公を演じるエルザ・ジルベルスタインのパフォーマンスが際立っている。本当に政治家にしか見えないのだから大したものだ。もちろん、同じユダヤ系であることも大きいだろう。若い頃のヒロインに扮したレベッカ・マルデールも良い仕事をしている。エロディ・ブシェーズやオリヴィエ・グルメなどの他の面子も申し分ない。
シモーヌ・ヴェイユは2017年に世を去ったが、その時は国葬が催され、パンテオンに合祀されている。その功績を考えれば当然と思われ、実際には多くの国民がそれを支持した。勝手に閣議決定だけで元総理の国葬の実施を決め、国会の議決どころか世論の賛同も得ないまま断行してしまったどこかの国とは大違いである。