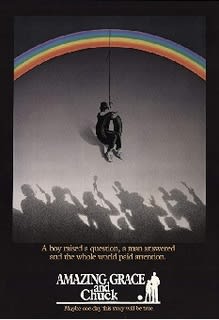良い映画だ。誰しも若い頃に抱いていた悩みや苦しみ、将来への不安、そして微かな希望etc.そんな哀歓が全編を覆い、切なくも甘酸っぱい気分になる。そして登場人物達は複雑な内面を音楽に乗せ、聴衆に訴える。鑑賞後の印象も格別の、青春映画の佳編である。
久澄春子(通称ハル)がバイト先のクリーニング工場で声を掛けたのは、上司に叱られて不貞腐れていた同僚の西野玲緒(通称レオ)だった。ハルはレオに一緒に音楽をやろうと持ちかけ、フォーク・デュオ“ハルレオ”を結成する。路上ライブから始めた2人だが、次第に人気が出てくる。ハルレオはライブツアーに出るためローディを探すが、そこで名乗りを上げたのが、元ホストの志摩一郎(通称シマ)であった。ツアーは当初は順調で売り上げはアップする一方だったが、やがて3人の音楽に対する微妙なスタンスの違いが表面化。やがて関係がこじれて解散を決意し、結成から数年目で最後のツアーに出発することになる。
30年ほど昔ならば、少しばかり逆境にあっても楽天的な気分で乗り切れたが、今では若者を取り巻く状況は厳しい。格差は広がり、しかも固定化してしまう。人付き合いの苦手なハルとレオも、鬱屈した心情を押し殺したまま退屈なバイトに明け暮れるしかなかった。
しかし、彼女達は音楽に出会えた。音楽によって社会との接点が出来て、大きく視野が広がった。ただしそれは、以前は漠然としていた屈託が明確化することを意味している。ハルが引きずっていた“秘密”も、レオが抱えるコンプレックスも、シマが封印してきたはずの“過去”も、生々しく頭をもたげてくる。登場人物達はそれらにどう対峙するのか、どうやって折り合いを付けるのか、そのプロセスをやはり音楽を通して描くというアイデアは出色だ。
塩田明彦の演出は余計なケレンを廃し、じっくりと彼らの懊悩と成長を追っていく。彼にとっても初期の「どこまでもいこう」(99年)と並ぶ代表作になることは間違いない。主演の門脇麦と小松菜奈のパフォーマンスは万全で、演技力は門脇の方が上ながら、無手勝流の存在感を活かした小松も健闘しており、絶妙のコンピネーションを見せている。シマに扮する成田凌も、この若さですでに名バイプレーヤーとしての貫禄さえ感じさせる。
そして何より、ハルレオの歌と演奏が素晴らしい。とびきり上手いというわけではないが、門脇と小松のひたむきさも相まって、目を見張る求心力がある。秦基博とあいみょんが提供した楽曲も文句なしだ。3人以外のキャラクターはあまりクローズアップされていないが、その中にあってハルレオの“追っかけ”の女子高生を演じた日高麻鈴と新谷ゆづみが儲け役だった。