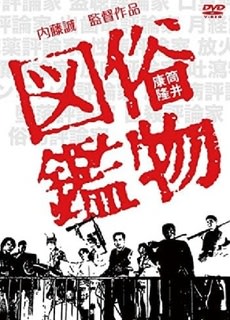2019年作品。密かに贔屓にしている(笑)若手女優、玉城ティナが主役というので観てみたが、まさに箸にも棒にもかからない出来で大いに盛り下がった。何のために作ったのか、どういう層をターゲットにしているのか、まるで不明。プロデューサーは一体何をやっていたのか、これも不明。これだけ存在価値が見出せないシャシンも珍しいだろう。
殺したいほど憎んでいる人間を地獄に送ってくれるという、“地獄通信”というサイトがあることが都市伝説で語られていた。深夜0時にそこにアクセスし、死んで欲しい人間の名前を入力すると、地獄少女が現れて赤い紐で結ばれた藁人形を渡される。依頼者がその紐をほどけば契約成立だ。しかし、依頼した者もいずれ死ぬときは地獄行きになるという。
女子高生の市川美保は、大好きなロックミュージシャンの魔鬼のライブで痴漢に遭うが、居合わせた南條遥に救われる。美保は奔放な遥を気に入るが、遥は魔鬼のコーラスのオーディションに合格したときから様子がおかしくなり、それが魔鬼の仕業だと知った美保は彼に殺意を抱く。一方、ジャーナリストの工藤は“地獄通信”について調べていたが、偶然に美保と接触する。TV用オリジナルテレビアニメの実写映画化だ。
とにかく、マトモなメンタリティを持った人間が存在せず、観ていて感情移入する相手がいないのには閉口する。美保も遥も平気で暴力を振るう性格破綻者だし、その他“地獄通信”に関わる者にも正常な人間は見当たらない。呪った本人も地獄行きになることが事前に説明されているにも関わらず、あえて破滅の道を選ぶという心理を分かりやすく説明するには、本作のような御膳立てでは無理だ。
そもそも、地獄少女を演じるお目当ての玉城は“主人公”でさえなく、ただの狂言回しである。もっと脚本と演出を練り上げて、彼女を“依頼する側”に配置して次第に正気を無くしていくという設定にすれば、盛り上がったかもしれない。監督の白石晃士の仕事ぶりは精彩を欠き、映像もチープである。
美保に扮するのは最近売り出し中の森七菜だが、本作では低調なパフォーマンスに終始。仁村紗和に大場美奈、片岡礼子、波岡一喜、橋本マナミ、そして麿赤兒といった他のキャストは機能していない。魔鬼のバンドのサウンドも大したことがなく、劇中での人気も疑わしいものがある。




殺したいほど憎んでいる人間を地獄に送ってくれるという、“地獄通信”というサイトがあることが都市伝説で語られていた。深夜0時にそこにアクセスし、死んで欲しい人間の名前を入力すると、地獄少女が現れて赤い紐で結ばれた藁人形を渡される。依頼者がその紐をほどけば契約成立だ。しかし、依頼した者もいずれ死ぬときは地獄行きになるという。
女子高生の市川美保は、大好きなロックミュージシャンの魔鬼のライブで痴漢に遭うが、居合わせた南條遥に救われる。美保は奔放な遥を気に入るが、遥は魔鬼のコーラスのオーディションに合格したときから様子がおかしくなり、それが魔鬼の仕業だと知った美保は彼に殺意を抱く。一方、ジャーナリストの工藤は“地獄通信”について調べていたが、偶然に美保と接触する。TV用オリジナルテレビアニメの実写映画化だ。
とにかく、マトモなメンタリティを持った人間が存在せず、観ていて感情移入する相手がいないのには閉口する。美保も遥も平気で暴力を振るう性格破綻者だし、その他“地獄通信”に関わる者にも正常な人間は見当たらない。呪った本人も地獄行きになることが事前に説明されているにも関わらず、あえて破滅の道を選ぶという心理を分かりやすく説明するには、本作のような御膳立てでは無理だ。
そもそも、地獄少女を演じるお目当ての玉城は“主人公”でさえなく、ただの狂言回しである。もっと脚本と演出を練り上げて、彼女を“依頼する側”に配置して次第に正気を無くしていくという設定にすれば、盛り上がったかもしれない。監督の白石晃士の仕事ぶりは精彩を欠き、映像もチープである。
美保に扮するのは最近売り出し中の森七菜だが、本作では低調なパフォーマンスに終始。仁村紗和に大場美奈、片岡礼子、波岡一喜、橋本マナミ、そして麿赤兒といった他のキャストは機能していない。魔鬼のバンドのサウンドも大したことがなく、劇中での人気も疑わしいものがある。