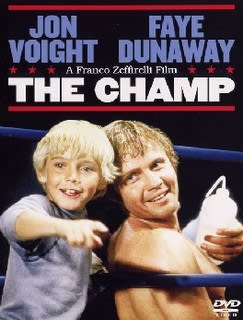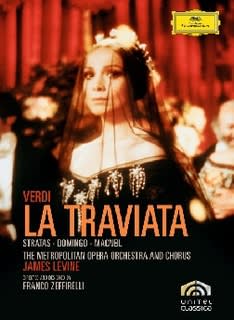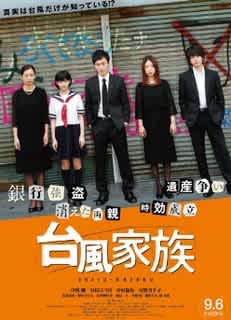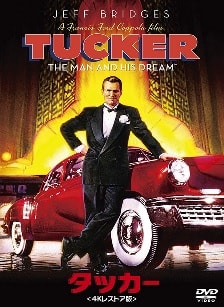(英題:Larks on a String )1969年にチェコスロバキアで撮られた作品だが、一般公開は90年で、その年のベルリン国際映画祭において大賞を獲得している。シビアな題材を扱いながら、タッチはしなやかでユーモラス。この“重いテーマを軽妙に綴る”という芸当は実力派の作家にしか出来ないが、本作はそれを存分に見せつけている。
1948年のチェコでは、社会主義とは相容れない(と思われる)者たちを再教育するためのプロジェクトが実施されていた。ある町のスクラップ工場では、7人の男たちが再教育と対象として働かされていたが、彼らは別に反体制というわけではなく、普通の市民である。その中でも一番若いユダヤ人の元コックであるパヴェルは、担当教官と衝突してばかりいた。

ある日彼は、工場の隣にある思想犯の収容所にいる若い娘イトカと知り合い、恋に落ちる。そしてついに彼女と結婚することになるのだが、そんなめでたい出来事とは裏腹に、工場には不穏な空気が流れ始める。仲間の大学教授が共産党員と口論になった挙げ句にどこかに連行されたのを皮切りに、次々と男たちが姿を消す。そしてパヴェルの身にも災いは降りかかってくる。
69年といえば、前年に“プラハの春”がソ連によって潰され、暗い時代に逆戻りした頃だ。体制批判を扱った本作は上映禁止になっている。しかしながら、イェジー・メンツェル監督は祖国から離れなかった。だからよっぽどこの映画は重々しい内容なのだろうと思ったら、これがけっこう明るくて屈託が無い。
もちろん、その中には重大な歴史の真実がある。ただ映画としては観ていて胃が痛くなるようなことはなく、平易で誰しもスッと中身に入って行ける。この洗練が訴求力を高めている。庶民に過ぎないパヴェルたちがこの工場に入れられたのは、単なる“事故”のようなものだ。反政府の闘志など存在しない。
ブルジョワ的楽器だという理由だけでブルジョワ扱いされるサキソフォン奏者がいるのもおかしいが、とにかく社会主義のナンセンスぶりを皮肉っているのが痛快だ。後半になるとストーリーは厳しくなるが、それでも登場人物たちは“いつかは真実が解る”と達観している。あくまで人間を信頼しているメンツェル監督の真摯なスタンスが伝わってくるようだ。主演のヴァーツラフ・ネッカーシュをはじめ、キャストは皆好演。反骨精神とカツドウ魂を忘れない映画作家の矜持が伝わってくる、見応えのある好編である。
1948年のチェコでは、社会主義とは相容れない(と思われる)者たちを再教育するためのプロジェクトが実施されていた。ある町のスクラップ工場では、7人の男たちが再教育と対象として働かされていたが、彼らは別に反体制というわけではなく、普通の市民である。その中でも一番若いユダヤ人の元コックであるパヴェルは、担当教官と衝突してばかりいた。

ある日彼は、工場の隣にある思想犯の収容所にいる若い娘イトカと知り合い、恋に落ちる。そしてついに彼女と結婚することになるのだが、そんなめでたい出来事とは裏腹に、工場には不穏な空気が流れ始める。仲間の大学教授が共産党員と口論になった挙げ句にどこかに連行されたのを皮切りに、次々と男たちが姿を消す。そしてパヴェルの身にも災いは降りかかってくる。
69年といえば、前年に“プラハの春”がソ連によって潰され、暗い時代に逆戻りした頃だ。体制批判を扱った本作は上映禁止になっている。しかしながら、イェジー・メンツェル監督は祖国から離れなかった。だからよっぽどこの映画は重々しい内容なのだろうと思ったら、これがけっこう明るくて屈託が無い。
もちろん、その中には重大な歴史の真実がある。ただ映画としては観ていて胃が痛くなるようなことはなく、平易で誰しもスッと中身に入って行ける。この洗練が訴求力を高めている。庶民に過ぎないパヴェルたちがこの工場に入れられたのは、単なる“事故”のようなものだ。反政府の闘志など存在しない。
ブルジョワ的楽器だという理由だけでブルジョワ扱いされるサキソフォン奏者がいるのもおかしいが、とにかく社会主義のナンセンスぶりを皮肉っているのが痛快だ。後半になるとストーリーは厳しくなるが、それでも登場人物たちは“いつかは真実が解る”と達観している。あくまで人間を信頼しているメンツェル監督の真摯なスタンスが伝わってくるようだ。主演のヴァーツラフ・ネッカーシュをはじめ、キャストは皆好演。反骨精神とカツドウ魂を忘れない映画作家の矜持が伝わってくる、見応えのある好編である。