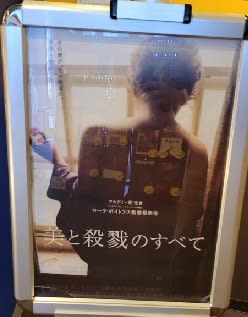(原題:長空之王 BORN TO FLY)国威発揚映画だということは承知しているが、けっこう楽しんで観てしまった。スカイアクションものとしては、ひょっとして「トップガン」シリーズよりも志が高いのかもしれない。主人公たちと敵対する某国の戦闘機群こそ出てくるが、切った張ったの命のやり取りはその局面では出てこない。代わりにメインとして描かれているのは、あくまで訓練の様子なのだ。それだけにネタの普遍性は際立っている。
中国空軍パイロットのレイ・ユーは腕は立つが、任務中に起こしたトラブルにより、前線から新世代ステルス戦闘機のテスト飛行チームに回される。中国西部の沙漠の中にある訓練基地での生活はハードで、しかもテストパイロットに選ばれるには厳正な選考を経なければならない。このプロセスが興味深く、まずは集められたメンバーたちを出し抜く必要がある。とはいえ、苦楽を共にする仲間を切り捨てるほど非情になれるはずもなく、そのあたりの葛藤が過不足なく捉えられているのは評価して良い。

レイ・ユーたちを襲うトラブルはエンジンの不調はもちろん、脱出装置の誤動作や鳥類と衝突する所謂バードストライクなど多種多様で飽きさせない。特にパラシュートに焦点が当たるのは高得点だ。また、訓練中に殉職してしまった教官に関するエピソードは悲痛で、葬儀の場面は無常さを漂わせる。
さらに、犠牲になったパイロットたちが眠る大規模な共同墓地の様子は、いくぶん作り物めいてはいるが、映像的には目覚ましい効果をもたらしている。終盤のシークエンスはいかにも中国軍のプロパガンダながら、そこで終わることなくもう一波乱あるという流れは悪くない。レイ・ユーたちの成長の跡を見せてくれるし、二転三転するドッグファイトには思わず見入ってしまう。
監督のリウ・シャオシーはこれが商業映画デビュー作とは思えないほど手堅い仕事ぶりで、第36回金鶏奨新人監督賞を受賞している。主演のワン・イーボーとライバル役のユー・シー、他にチョウ・ドンユィにフー・ジュンという顔ぶれは、馴染みは無いがよくやっていると思う。それにしても、ステルス戦闘機は米露の専売特許と思われていたが、中国も着々と開発中であるのは、やはり周辺諸国にとっては脅威だろう。日本としてもそれ相応の対策を立てねばなるまい。
中国空軍パイロットのレイ・ユーは腕は立つが、任務中に起こしたトラブルにより、前線から新世代ステルス戦闘機のテスト飛行チームに回される。中国西部の沙漠の中にある訓練基地での生活はハードで、しかもテストパイロットに選ばれるには厳正な選考を経なければならない。このプロセスが興味深く、まずは集められたメンバーたちを出し抜く必要がある。とはいえ、苦楽を共にする仲間を切り捨てるほど非情になれるはずもなく、そのあたりの葛藤が過不足なく捉えられているのは評価して良い。

レイ・ユーたちを襲うトラブルはエンジンの不調はもちろん、脱出装置の誤動作や鳥類と衝突する所謂バードストライクなど多種多様で飽きさせない。特にパラシュートに焦点が当たるのは高得点だ。また、訓練中に殉職してしまった教官に関するエピソードは悲痛で、葬儀の場面は無常さを漂わせる。
さらに、犠牲になったパイロットたちが眠る大規模な共同墓地の様子は、いくぶん作り物めいてはいるが、映像的には目覚ましい効果をもたらしている。終盤のシークエンスはいかにも中国軍のプロパガンダながら、そこで終わることなくもう一波乱あるという流れは悪くない。レイ・ユーたちの成長の跡を見せてくれるし、二転三転するドッグファイトには思わず見入ってしまう。
監督のリウ・シャオシーはこれが商業映画デビュー作とは思えないほど手堅い仕事ぶりで、第36回金鶏奨新人監督賞を受賞している。主演のワン・イーボーとライバル役のユー・シー、他にチョウ・ドンユィにフー・ジュンという顔ぶれは、馴染みは無いがよくやっていると思う。それにしても、ステルス戦闘機は米露の専売特許と思われていたが、中国も着々と開発中であるのは、やはり周辺諸国にとっては脅威だろう。日本としてもそれ相応の対策を立てねばなるまい。