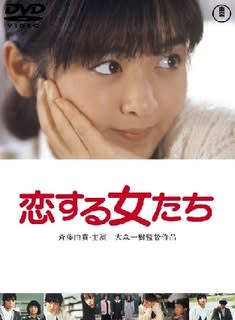容赦の無い描写の連続で、実に観ていて“痛い”映画である。同じ子供を主人公にした作品でも、先日観た「サバカン SABAKAN」のような偽善的なシャシンとは格が違う。子供なりの“生き辛さ”が前面にクローズアップされ、私をはじめとする大人の観客がとうの昔に忘れたはずの屈託が、生々しく提示される。好き嫌いは分かれるかもしれないが、見応えのある力作と言える。
広島県の海沿いの町で暮らすあみ子は少し風変わりな小学5年生。優しい父親と、書道教室の先生で妊娠中の母、そして面倒見の良い兄の4人家族だ。ところが赤ん坊はとうとう産まれなかった。そして母を慰めるつもりで取ったあみ子の軽率な行動が、逆に母に大きな心理的ショックを与えてしまう。そんな状況に嫌気がさした兄はグレて家に寄り付かなくなり、父はオロオロするばかりで何の役にも立たない。やがて時が経ちあみ子は中学生になるが、相変わらず周囲から浮いた存在のままだ。芥川賞作家である今村夏子が2010年に上梓したデビュー作の映画化である。
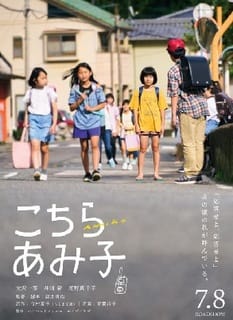
有り体に言ってしまえば、あみ子はたぶん発達障害だろう。他者との距離感が、まったく掴めない。自分ではよかれと思っている言動も、それが他人にどう思われるのか想像できない。ただ、誰も相手にしてくれない境遇を表現するかのように、誕生日にもらった電池切れのトランシーバーに“応答せよ、応答せよ。こちらあみ子”と話しかけるだけだ。
これを“特定の問題を抱えた子供に限定したようなハナシだろう(こちらには関係ない)”と切り捨てられる者がいるとすれば、それはそれで結構なことである。しかし、思うようにいかない子供時代を少しでも経験した人間ならば、あみ子の立ち位置はシャレにならないほど切迫していることが分かる。
そして、映画はあみ子に対して甘い顔は一切見せない。逆境に次ぐ逆境を冷徹に描くだけだ。その思い切りの良さは観ていて清々しいほどである。もちろん、ヒロインがどんなに面白くない目に遭おうとも、人生はこれからも続いていくのだ。その意味では、とてもポジティヴな作品でもある。
これが長編デビュー作になる森井勇佑の演出は堅牢で、向こうウケを狙うような素振りは見せない。ドラマを一つ一つ積み上げるだけで、その姿勢は評価に値する。あみ子に扮する大沢一菜は怪演と言うしかなく、目覚ましい存在感を発揮している。母親役の尾野真千子は奇しくも「サバカン SABAKAN」にも出ているが、こっちの方が遥かに訴求力が高い。父親を演じる井浦新も好調だ。舞台になる広島の町も風情があって実によろしい。
広島県の海沿いの町で暮らすあみ子は少し風変わりな小学5年生。優しい父親と、書道教室の先生で妊娠中の母、そして面倒見の良い兄の4人家族だ。ところが赤ん坊はとうとう産まれなかった。そして母を慰めるつもりで取ったあみ子の軽率な行動が、逆に母に大きな心理的ショックを与えてしまう。そんな状況に嫌気がさした兄はグレて家に寄り付かなくなり、父はオロオロするばかりで何の役にも立たない。やがて時が経ちあみ子は中学生になるが、相変わらず周囲から浮いた存在のままだ。芥川賞作家である今村夏子が2010年に上梓したデビュー作の映画化である。
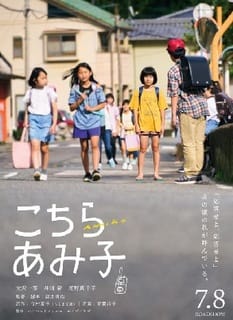
有り体に言ってしまえば、あみ子はたぶん発達障害だろう。他者との距離感が、まったく掴めない。自分ではよかれと思っている言動も、それが他人にどう思われるのか想像できない。ただ、誰も相手にしてくれない境遇を表現するかのように、誕生日にもらった電池切れのトランシーバーに“応答せよ、応答せよ。こちらあみ子”と話しかけるだけだ。
これを“特定の問題を抱えた子供に限定したようなハナシだろう(こちらには関係ない)”と切り捨てられる者がいるとすれば、それはそれで結構なことである。しかし、思うようにいかない子供時代を少しでも経験した人間ならば、あみ子の立ち位置はシャレにならないほど切迫していることが分かる。
そして、映画はあみ子に対して甘い顔は一切見せない。逆境に次ぐ逆境を冷徹に描くだけだ。その思い切りの良さは観ていて清々しいほどである。もちろん、ヒロインがどんなに面白くない目に遭おうとも、人生はこれからも続いていくのだ。その意味では、とてもポジティヴな作品でもある。
これが長編デビュー作になる森井勇佑の演出は堅牢で、向こうウケを狙うような素振りは見せない。ドラマを一つ一つ積み上げるだけで、その姿勢は評価に値する。あみ子に扮する大沢一菜は怪演と言うしかなく、目覚ましい存在感を発揮している。母親役の尾野真千子は奇しくも「サバカン SABAKAN」にも出ているが、こっちの方が遥かに訴求力が高い。父親を演じる井浦新も好調だ。舞台になる広島の町も風情があって実によろしい。