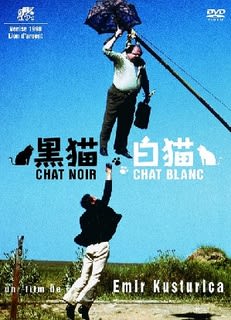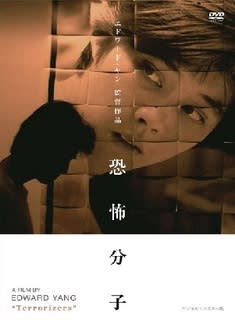興味深いドキュメンタリー作品だ。しかし、私が興味を覚えた点は、おそらくは作者が狙っていた線とは違う次元の事柄だろう。映画に対する批評というのは、必ずしも作り手が主張したいテーマを中心として展開されるわけではないのだ。観る者によっては、そこから外れたモチーフに反応してしまうことがある。だからこそ、映画というのは面白いと言えるのだ。
大阪の毎日放送に所属するディレクターの斉加尚代が、2006年の教育基本法の改正に端を発する教育現場への国家権力の介入を描いた番組「映像’17 教育と愛国 教科書でいま何が起きているのか」に、追加取材と再構成を施して映画版として仕上げたものだ。元のTVプログラムは、2017年のギャラクシー賞テレビ部門大賞を受賞している。

2006年以降、戦後初めて学習指導要領に“愛国心”が盛り込まれ、道徳は“特別の教科”として位置付けられた。それと同時に、教科書検定制度に関して当局側からの目に見えない圧力が増し、現場の自主性は制限されていく。有り体に言ってしまえば、本作は教育問題を“左方向(リベラル方面)”から扱ったものだ。
作者としては反動勢力によって教育や学問の自由が攻撃される様子を描きたかったのだろうが、あいにくこちらは斯様な図式には与しない。当局側の指示の通り、慰安婦問題をめぐり誤解を招くおそれがあるため“従軍慰安婦”ではなく単に“慰安婦”という記述が適切だし、戦時中の“徴用”をめぐっては“強制連行”や“連行”といった用語は避けた方が良い。そもそも、慰安婦問題に関しては当時政府当局や軍による強制連行の記録は存在しないという“事実”をもって、政府レベルでは“終わり”にすべき事柄なのだ。また、当事者の証言とやらも信用できるものではない。
しかしながら、それでもこの映画は観る価値がある。それは、声高に愛国教育とやらを唱える者たちの胡散臭さを見事に活写しているからだ。
大威張りで“戦後レジームを脱して美しい国日本を作ろう!”などと述べている政治家が国会で百回以上も虚偽答弁をしていたり、お偉い大学の名誉教授が“歴史から学ぶものは何もない”と言ってのけたり、改憲に積極的な政党の構成員が首長を務める自治体は、未曽有のコロナ禍の感染者数を記録していたりと、まさに“この界隈にはマトモな人間はいないのか!”と言いたくなる。
どんなに高邁な理想を語っても、どんなに正論じみたコメントを残そうとも、そう述べる本人の普段の言動がロクなものではなかったら、信用するに値しないのだ。
また、この映画は日本を覆う反知性主義にも警鐘を鳴らす。例の日本学術会議問題に代表されるように、憂国・愛国界隈に属している者、およびそれを支持している層は、たぶん学術書など読んでもいない。威勢よく“憲法を改正しろ!”と叫ぶ者も、憲法の条文に目を通したことは無いのだろう。知識・教養を軽視すれば、亡国への道をまっしぐらだ。
斉加の演出は時として話が脇道に逸れる傾向があるものの、概ね真摯に映画に向き合っている。井浦新によるナレーションも的確だ。観る者によって意見は分かれるかもしれないが、幅広い層に奨めたい作品であることは論を待たない。
大阪の毎日放送に所属するディレクターの斉加尚代が、2006年の教育基本法の改正に端を発する教育現場への国家権力の介入を描いた番組「映像’17 教育と愛国 教科書でいま何が起きているのか」に、追加取材と再構成を施して映画版として仕上げたものだ。元のTVプログラムは、2017年のギャラクシー賞テレビ部門大賞を受賞している。

2006年以降、戦後初めて学習指導要領に“愛国心”が盛り込まれ、道徳は“特別の教科”として位置付けられた。それと同時に、教科書検定制度に関して当局側からの目に見えない圧力が増し、現場の自主性は制限されていく。有り体に言ってしまえば、本作は教育問題を“左方向(リベラル方面)”から扱ったものだ。
作者としては反動勢力によって教育や学問の自由が攻撃される様子を描きたかったのだろうが、あいにくこちらは斯様な図式には与しない。当局側の指示の通り、慰安婦問題をめぐり誤解を招くおそれがあるため“従軍慰安婦”ではなく単に“慰安婦”という記述が適切だし、戦時中の“徴用”をめぐっては“強制連行”や“連行”といった用語は避けた方が良い。そもそも、慰安婦問題に関しては当時政府当局や軍による強制連行の記録は存在しないという“事実”をもって、政府レベルでは“終わり”にすべき事柄なのだ。また、当事者の証言とやらも信用できるものではない。
しかしながら、それでもこの映画は観る価値がある。それは、声高に愛国教育とやらを唱える者たちの胡散臭さを見事に活写しているからだ。
大威張りで“戦後レジームを脱して美しい国日本を作ろう!”などと述べている政治家が国会で百回以上も虚偽答弁をしていたり、お偉い大学の名誉教授が“歴史から学ぶものは何もない”と言ってのけたり、改憲に積極的な政党の構成員が首長を務める自治体は、未曽有のコロナ禍の感染者数を記録していたりと、まさに“この界隈にはマトモな人間はいないのか!”と言いたくなる。
どんなに高邁な理想を語っても、どんなに正論じみたコメントを残そうとも、そう述べる本人の普段の言動がロクなものではなかったら、信用するに値しないのだ。
また、この映画は日本を覆う反知性主義にも警鐘を鳴らす。例の日本学術会議問題に代表されるように、憂国・愛国界隈に属している者、およびそれを支持している層は、たぶん学術書など読んでもいない。威勢よく“憲法を改正しろ!”と叫ぶ者も、憲法の条文に目を通したことは無いのだろう。知識・教養を軽視すれば、亡国への道をまっしぐらだ。
斉加の演出は時として話が脇道に逸れる傾向があるものの、概ね真摯に映画に向き合っている。井浦新によるナレーションも的確だ。観る者によって意見は分かれるかもしれないが、幅広い層に奨めたい作品であることは論を待たない。