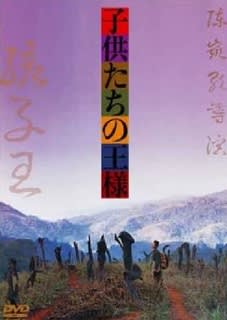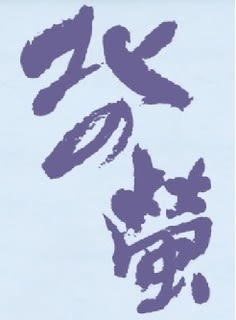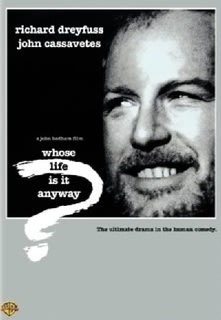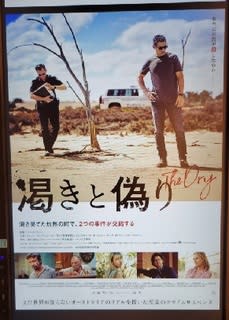(原題:Flic ou Voyou )78年作品で、日本公開は80年。本国で公開された際には、パリで一週間で24万人の観客を動員。ロードショー23週目にして100万人の動員を突破。当時としては目覚ましい記録を作り上げた。パリの興行成績としては、歴代の映画で18本目、フランス映画では7本目だったらしい。だからさぞ面白いシャシンだろうと期待して観たのだが、何とも荒っぽい作りで戸惑った。まあ、勢いだけはあるので、そのあたりがウケたのかもしれない。
南フランスのとある町(マルセイユとモンテカルロの間)では、暗黒街を2人のボスが取り仕切り、カジノや麻薬、恐喝、売春などの縄張りを二分していた。しかも、警察官の中には暗黒街から当然のごとくワイロをもらい、目を瞑っている者が多数いた。抗争の中でついに一人の現職警部が殺人死体として発見される。対応に困った所轄の警察は、その土地にまったく縁が無いパリから一人の“警部”を呼び寄せた。それが名物刑事のスタン・ホロヴィッツで、持ち前の強引すぎる手法により事件の核心に迫っていく。ミシェル・グリリアによる警察小説の映画化だ。

主人公はポパイ刑事とハリー・キャラハン刑事を合わせたような暴れん坊で(笑)、特に前半での派手な立ち回りはハリウッド製のポリス・アクションを思わせる。しかし、後半になると元悪徳刑事がさんざん利用した挙げ句に最後に始末されたり、事件の証人の家を勝手に燃やしてしまったりといった、やり過ぎ捜査と見られる場面が多くなり応援する気が失せる。しかもジョルジュ・ロートネルの演出が丁寧とは言い難く、何やら短期間で撮り上げて編集も精査しないまま公開してしまったような案配だ。
とはいえ主演のジャン・ポール・ベルモンドの存在感は大したもので、出てくるだけで画面が華やいでくる。共演は何とあの「太陽がいっぱい」(1960年)のマリー・ラフォレで、封切当時は15年ぶりの出演作の日本公開だったらしい。相変わらずの美人で見とれてしまうが、彼女もベルモンドも今は鬼籍に入ってしまい、寂しい限りだ。撮影はアンリ・ドカエで音楽はフィリップ・サルドという手練れが担当しており、堅実な仕事ぶり。なお、本作は「警視コマンドー」の邦題で80年代にVHSが発売されたことがあったとか。何とも安易なタイトルで笑ってしまう。
南フランスのとある町(マルセイユとモンテカルロの間)では、暗黒街を2人のボスが取り仕切り、カジノや麻薬、恐喝、売春などの縄張りを二分していた。しかも、警察官の中には暗黒街から当然のごとくワイロをもらい、目を瞑っている者が多数いた。抗争の中でついに一人の現職警部が殺人死体として発見される。対応に困った所轄の警察は、その土地にまったく縁が無いパリから一人の“警部”を呼び寄せた。それが名物刑事のスタン・ホロヴィッツで、持ち前の強引すぎる手法により事件の核心に迫っていく。ミシェル・グリリアによる警察小説の映画化だ。

主人公はポパイ刑事とハリー・キャラハン刑事を合わせたような暴れん坊で(笑)、特に前半での派手な立ち回りはハリウッド製のポリス・アクションを思わせる。しかし、後半になると元悪徳刑事がさんざん利用した挙げ句に最後に始末されたり、事件の証人の家を勝手に燃やしてしまったりといった、やり過ぎ捜査と見られる場面が多くなり応援する気が失せる。しかもジョルジュ・ロートネルの演出が丁寧とは言い難く、何やら短期間で撮り上げて編集も精査しないまま公開してしまったような案配だ。
とはいえ主演のジャン・ポール・ベルモンドの存在感は大したもので、出てくるだけで画面が華やいでくる。共演は何とあの「太陽がいっぱい」(1960年)のマリー・ラフォレで、封切当時は15年ぶりの出演作の日本公開だったらしい。相変わらずの美人で見とれてしまうが、彼女もベルモンドも今は鬼籍に入ってしまい、寂しい限りだ。撮影はアンリ・ドカエで音楽はフィリップ・サルドという手練れが担当しており、堅実な仕事ぶり。なお、本作は「警視コマンドー」の邦題で80年代にVHSが発売されたことがあったとか。何とも安易なタイトルで笑ってしまう。