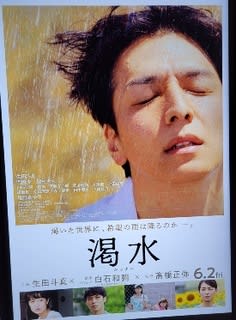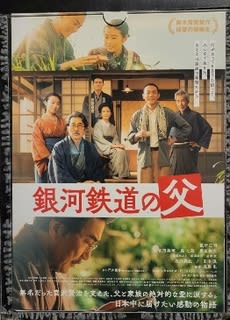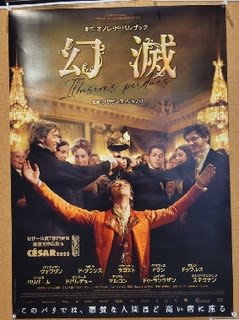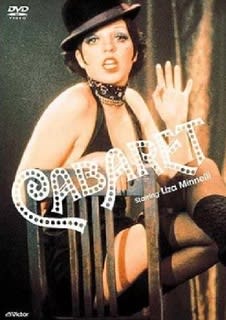観終わって呆れた。第76回カンヌ国際映画祭にて脚本賞を獲得しているが、こんなヘタなシナリオでも“取り上げられた題材”によっては不必要に評価される世の中になったことに思い当たり、タメ息が出た。元より是枝裕和は出来不出来の幅が大きい映像作家だが、本作は間違いなく出来が悪い部類に入る。
大きな湖のある郊外の町に住む息子を愛するシングルマザーと生徒思いの若い教師、そして子供たちという3つのスタンスから見た、小学校で起きたトラブルとそれに続くハプニングの数々を描く本作。言うまでもなく黒澤明監督の「羅生門」(1950年)の形式を踏襲しているが、内容はかなりの差がある。
「羅生門」のストーリーの土台は、山中で発生した殺人事件という、映画内での確固とした“事実”である。この前提があるからこそ、関係者たちの食い違う証言の数々が紡ぎ出す物語性がスリリングな興趣を生んだのだ。対してこの「怪物」には、土台になる“事実”が無い。一応、学校で子供同士のケンカがあったらしいというモチーフは出てくるが、それが本当のことなのかは分からない。
結果として、関係者たちの手前勝手な言い分が並ぶばかりで、そこから何か大きなテーマに収斂されていくという趣向は存在しない。これは私が嫌いなファンタジー物と一緒で、つまりは“何でもあり”の世界なのだ。この“何でもあり”というのは“何もない”のと一緒であり、ドラマの核が無ければ自己満足の絵空事の積み上げにしかならない。
それにしても、いくらファンタジーとはいえ各エピソードのレベルの低さには閉口する。保護者を前にしての教師たちの不遜な態度や、校長にまつわるワザとらしい“疑惑”、当事者生徒の一人の“図式的な家庭環境”など、よくもまあ斯様な恣意的かつ表面的なネタばかり繰り出してくるものだと、観ていて失笑するばかり。
極めつけは終盤の処理で、いったいこれは何の冗談なのかと絶句した。そういえばカンヌではコンペティション部門の各賞発表に先んじて、本作はクィア・パルムという独立賞を獲得しているが、このアワードの趣旨を勘案すれば当然この映画の主眼は何か気が付いたはずだ(我ながら迂闊だった)。とにかく、このような冴えないシャシンに付き合わされ、「羅生門」がいかに革新的な映画であったかを再確認した次第だ。
安藤サクラに永山瑛太、高畑充希、中村獅童、田中裕子らキャストは皆熱演だが、映画の内容がこの通りなので“ご苦労さん”としか言えない。なお、坂本龍一の最後の映画音楽ということで話題にもなっているが、過去の彼の実績に比べると、取り立てて優れているとは思えなかった。




大きな湖のある郊外の町に住む息子を愛するシングルマザーと生徒思いの若い教師、そして子供たちという3つのスタンスから見た、小学校で起きたトラブルとそれに続くハプニングの数々を描く本作。言うまでもなく黒澤明監督の「羅生門」(1950年)の形式を踏襲しているが、内容はかなりの差がある。
「羅生門」のストーリーの土台は、山中で発生した殺人事件という、映画内での確固とした“事実”である。この前提があるからこそ、関係者たちの食い違う証言の数々が紡ぎ出す物語性がスリリングな興趣を生んだのだ。対してこの「怪物」には、土台になる“事実”が無い。一応、学校で子供同士のケンカがあったらしいというモチーフは出てくるが、それが本当のことなのかは分からない。
結果として、関係者たちの手前勝手な言い分が並ぶばかりで、そこから何か大きなテーマに収斂されていくという趣向は存在しない。これは私が嫌いなファンタジー物と一緒で、つまりは“何でもあり”の世界なのだ。この“何でもあり”というのは“何もない”のと一緒であり、ドラマの核が無ければ自己満足の絵空事の積み上げにしかならない。
それにしても、いくらファンタジーとはいえ各エピソードのレベルの低さには閉口する。保護者を前にしての教師たちの不遜な態度や、校長にまつわるワザとらしい“疑惑”、当事者生徒の一人の“図式的な家庭環境”など、よくもまあ斯様な恣意的かつ表面的なネタばかり繰り出してくるものだと、観ていて失笑するばかり。
極めつけは終盤の処理で、いったいこれは何の冗談なのかと絶句した。そういえばカンヌではコンペティション部門の各賞発表に先んじて、本作はクィア・パルムという独立賞を獲得しているが、このアワードの趣旨を勘案すれば当然この映画の主眼は何か気が付いたはずだ(我ながら迂闊だった)。とにかく、このような冴えないシャシンに付き合わされ、「羅生門」がいかに革新的な映画であったかを再確認した次第だ。
安藤サクラに永山瑛太、高畑充希、中村獅童、田中裕子らキャストは皆熱演だが、映画の内容がこの通りなので“ご苦労さん”としか言えない。なお、坂本龍一の最後の映画音楽ということで話題にもなっているが、過去の彼の実績に比べると、取り立てて優れているとは思えなかった。