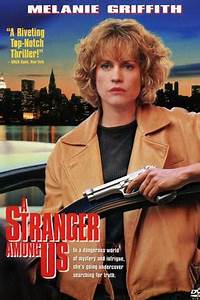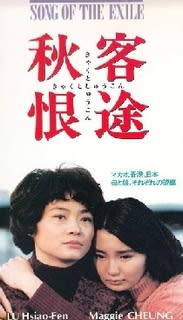(原題:ZELIG )84年作品。ウディ・アレンのフィルモグラフィの中では、1,2を争うほど“冗談のキツい”映画である。卓越かつ屈折したキャラクター設定と玄妙な筋書き。そして高いメッセージ性。しかも見事にコメディ映画の枠内に収まっているという、作り手の(良い意味での)意識の高さを見せつけられる。
1930年代のアメリカ。人々はゼリグという風変わりなユダヤ人を目撃するようになる。彼は周りの環境に順応し、身体的にも精神的にも変貌を遂げるという特異な体質の持ち主で、数々の有名人と“まるでその関係者であるがごとく”一緒にいる様子を多くの者が目にしていた。彼に興味を持った女医のユードラはゼリグを診察するが、彼はたちまち精神分析医に変身してしまう有様だ。
実はゼリグは子供の頃に疎外され、いつしか身を守るため周囲の環境に合わせて姿かたちを変えるようになったのだ。ユードラはそんな彼に同情するうち、恋心を抱くようになる。だが、ゼリグの姉ルースの恋人マーテはゼリグを見せ物にしようと画策する。
当時のニュース映像や記録フィルムの中にゼリグを登場させてアンマッチな笑いを誘うだけではなく、随所に識者による回想シーンがもっともらしく挿入されるのがおかしい。ギャグの繰り出し方は、さすがアレンだと感心させられる。ゼリグの立ち位置はユダヤ人全般の暗喩なのだろうが、転じてトレンドに付和雷同する一般ピープルをも皮肉っていると言えよう。
本当はゼリグが周りの環境に合わせているのではなく、確固としたアイデンティティを持たない大衆が揺れ動いているだけで、ナイーヴなゼリグはその度にやむ無く対応しているだけという図式が内包されている。それが表面化するのが、ゼリグがヒットラーの背後に立っている場面だ。独裁者に対しては盲目的な支持者に“変身”するしかないという、作者のアイロニーが際立っている。
ゼリグに扮するのはもちろんアレン自身で、屈折した内面を巧みに笑いに転化させている。ユードラ役のミア・ファローをはじめ、ギャレット・M・ブラウンやステファニー・ファローなどの脇の面子も良い味を出している。ゴードン・ウィリスのカメラによる凝った映像も見ものだ。