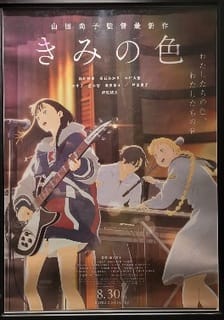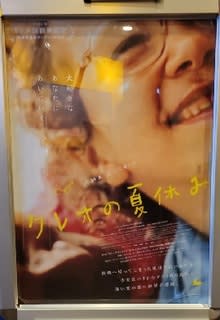(原題:THEY CAME TO CORDURA)1959年作品。西部劇スターとして名を馳せたゲイリー・クーパー主演のウエスタンだが、監督が社会派のロバート・ロッセンということもあり、通常の娯楽映画とは一線を画する含蓄のある内容に仕上がっている。特に、極限状態に置かれた人間の生き様を容赦なく描くあたりは感心した。キャストも万全だ。
1916年のアメリカ南部。ソーン少佐の所属する騎兵隊は、メキシコの革命家パンチョ・ビリャ率いる反乱軍と国境付近で交戦状態に入る。米軍は何とか勝利し、ソーンは戦いで活躍した5人の兵士を叙勲するため、そしてメキシコ軍に便宜を図ったという疑いで牧場主のアメリカ人女性アデレード・ギアリーを軍当局に引き渡すため、7人でテキサス州のコルドラ陸軍基地を目指して出発する。

ところが、ソーンの触れられたくない過去が明るみに出ると兵士たちは彼を敵視するようになる。しかも道中でゲリラ兵の襲撃を受け、馬を失った挙げ句に徒歩での移動を強いられる。さらにアデレードをめぐって男たちの欲望が横溢し、水と食料も残り少なくなり、病人まで出る始末。彼らの苦難の旅は続く。
冒頭近くの戦闘シーンこそスペクタクル性が感じられるが、映画の大半は主人公たちの苦闘が綴られる。人間、逆境に直面すると不条理な怒りや欲望に囚われてしまう。叙勲の名誉なんかどうでも良くなり、いかにして生き延びるかという根源的な欲求だけが表面化する。そんな中にあって、ソーンだけは軍の規律とプライドを頑なに守る。
ここで“高潔な軍人VS.下世話な者たち”という単純な構図に陥らないのが本作の長所だ。ソーンにはこの旅を貫徹しなければならない事情があり、それは決して崇高なものではない。兵士たちにしても、こんな修羅場になれば八つ当たりするのも当然なのだ。しかし、ソーンはそれでも自らの任務を放棄しない。そのことが自身の過去を清算することに他ならないからだ。ソーンの意図が明らかになる終盤は十分に感動的であり、ロッセン監督のヒューマニストぶりが窺われる。
G・クーパーは内面で屈託と使命感がせめぎ合う様子を上手く表現した妙演で、観ていて引き込まれるものがある。アデレード役のリタ・ヘイワースは荒涼とした沙漠の中にあっても魅力的だし、敵役とも言えるチョーク軍曹に扮するヴァン・ヘフリンも憎々しい好演だ。リチャード・コンテにタブ・ハンター、ディック・ヨーク、マイケル・カラなど当時の演技派が脇を固めている。また、バーネット・ガフィのカメラによる荒野の風景は実に効果的だ。
1916年のアメリカ南部。ソーン少佐の所属する騎兵隊は、メキシコの革命家パンチョ・ビリャ率いる反乱軍と国境付近で交戦状態に入る。米軍は何とか勝利し、ソーンは戦いで活躍した5人の兵士を叙勲するため、そしてメキシコ軍に便宜を図ったという疑いで牧場主のアメリカ人女性アデレード・ギアリーを軍当局に引き渡すため、7人でテキサス州のコルドラ陸軍基地を目指して出発する。

ところが、ソーンの触れられたくない過去が明るみに出ると兵士たちは彼を敵視するようになる。しかも道中でゲリラ兵の襲撃を受け、馬を失った挙げ句に徒歩での移動を強いられる。さらにアデレードをめぐって男たちの欲望が横溢し、水と食料も残り少なくなり、病人まで出る始末。彼らの苦難の旅は続く。
冒頭近くの戦闘シーンこそスペクタクル性が感じられるが、映画の大半は主人公たちの苦闘が綴られる。人間、逆境に直面すると不条理な怒りや欲望に囚われてしまう。叙勲の名誉なんかどうでも良くなり、いかにして生き延びるかという根源的な欲求だけが表面化する。そんな中にあって、ソーンだけは軍の規律とプライドを頑なに守る。
ここで“高潔な軍人VS.下世話な者たち”という単純な構図に陥らないのが本作の長所だ。ソーンにはこの旅を貫徹しなければならない事情があり、それは決して崇高なものではない。兵士たちにしても、こんな修羅場になれば八つ当たりするのも当然なのだ。しかし、ソーンはそれでも自らの任務を放棄しない。そのことが自身の過去を清算することに他ならないからだ。ソーンの意図が明らかになる終盤は十分に感動的であり、ロッセン監督のヒューマニストぶりが窺われる。
G・クーパーは内面で屈託と使命感がせめぎ合う様子を上手く表現した妙演で、観ていて引き込まれるものがある。アデレード役のリタ・ヘイワースは荒涼とした沙漠の中にあっても魅力的だし、敵役とも言えるチョーク軍曹に扮するヴァン・ヘフリンも憎々しい好演だ。リチャード・コンテにタブ・ハンター、ディック・ヨーク、マイケル・カラなど当時の演技派が脇を固めている。また、バーネット・ガフィのカメラによる荒野の風景は実に効果的だ。