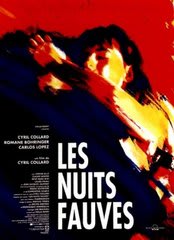(原題:United 93 )9.11同時多発テロ事件において、ハイジャックされた4機の中で唯一目標に到達することなく墜落したユナイテッド航空93便の“当日の様子”を描くノンフィクション風ドラマ。
厳しい映画が目立つ本年度のアメリカ映画界だが、これは最右翼と言えよう。何しろ乗員役には業務経験者をキャスティングし、管制官に至っては当日実際に勤務していた本人までも登場してしまうのだから(しかも複数)。
乗員・乗客はすべてこの世にいないので、実際機内で何が起きたのかは分からない。しかし、絶望的な緊張感から一縷の望みを託して最後の賭けに打って出る乗客達と、悲愴な使命感を抱いて凶行に及ぶテロリスト側との攻防は、たぶん実際もこうだったのだろうという極上の説得力を持って観る者に迫ってくる。ラストシーンなんて、あまりの衝撃で声も出ないほどだ。綿密なリサーチによる堅牢そのものの脚本も相まって、スタッフ・キャストの“あの事件を風化させてたまるものか!”という並々ならぬ覚悟が伝わってくる。
「ボーン・スプレマシー」で切れ味鋭い作劇を見せたポール・グリーングラス監督の演出は快調で、臨場感を全開にしたケレン味がふんだんにありながら、わざとらしさや強引さを微塵も感じさせない。力業とスマートさを兼ね備えた俊英ぶりは今後も要チェックである。
それにしても、アメリカ映画は・・・・ある意味本当に“偉い”と思う。この題材をストレートに扱い、それに娯楽性を加味させた一般劇映画を堂々と作れてしまうのだから。我が国にも忘れてはならない事件が沢山あるはずなのに、どうしてそれらに目を向けないのだろう。プロデューサーの怠慢か、あるいは映画会社の後ろ向きのスタンス故か。いずれにしろこの点では日本映画は負ける。まさに完敗だ。