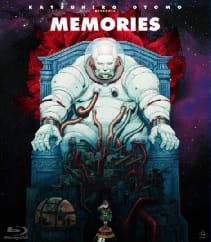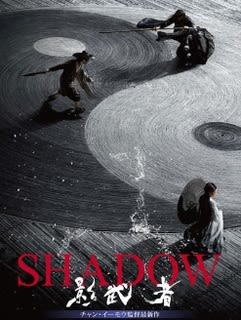御都合主義的なモチーフはけっこうあるのだが、全体的に真面目にかつ丁寧に作られた映画という印象を受け、好感度が高い。特にこの“真面目に”というのが重要で、真面目さのカケラも無いようなシャシンが目立つ昨今の邦画界において、この姿勢は貴重である。また同性愛という、描きようによっては変にセンセーショナルになったり、または反対に及び腰になったりする素材を扱っていながら、無理なくメッセージが伝わるような自然なタッチを貫いているのも納得できる。
岐阜県加茂郡白川町に一人で暮らす若い男・井川迅は、以前は東京でサラリーマン生活を送っていたが、周囲に自分がゲイだと知られることを恐れてこの地に移り住んだのだ。ある日、かつての“恋人”だった日比野渚が迅を訪ねてくる。しかも、6歳の娘まで連れていた。聞けば渚は留学中に“勢いで”結婚してしまったが、妻は相手が同性愛者とは知らなかったらしい。それがいつしか妻にバレてしまい、現在離婚調停中だ。渚は迅にしばらく置いてほしいと頼む。戸惑いながらも3人での生活を受け入れた迅だが、ある時渚の妻が突然やってきて娘を東京に連れ戻してしまう。
舞台になる山間の町は、珍しいほど“よそ者”に寛容だ。それは迅が来たときはもちろん、渚が住み着いた後も変わらない。これは瀬々敬久監督の「楽園」をはじめとして、日本映画がしばしば取り上げてきた閉鎖的な地方の状況とはまるで違う様相である。
また、渚は有能な“専業主夫”であるのに対し、妻の玲奈は絵に描いたような仕事一筋でその他のことは関知しない人物として設定される。さらに、大らかな白川町の雰囲気と対比するように、東京での法曹関係者や玲奈の親は頑迷で、偏見を隠そうともしない。斯様に単純な御膳立ては、なるほど欠点には違いない。
だが、本作にはそれらの短所をカバーするだけの作劇のパワーがある。それは主人公2人の純愛を正面切って描くことにより、一種の“真実”を我々に叩き付けていることだ。劇中で登場人物が発する“優しくなかったのは世界じゃなくて自分だった。自分が優しくなれば、世界も優しくなる”というセリフには胸を突かれるものがある。
生きづらい世の中を、斜に構えて見ようとすればいくらでもネガティヴなテイストが湧いて出てくる。否定や憎しみを先行させてしまうと、家裁の判事や弁護士そして玲奈の親のように、一時は溜飲を下げることは出来るかもしれないが、それでは少しも前に進まない。まずは他人や自らの置かれた立場を受け容れて、それからどうすればいいか考えれば良い。そんな簡単なことを実行するだけで、世界は明るくなるのだ。斯様なポジティヴなスタンスが横溢する終盤の処理は、観ていて大いに納得するものである。
今泉力哉の演出は正攻法で、まったく無理がない。主演の宮沢氷魚と藤原季節は初めて見る役者だが、どちらも演技が達者で好印象。上質のルックスを含めて、これからも活躍しそうだ。松本若菜に松本穂香、鈴木慶一、根岸季衣、堀部圭亮、戸田恵子といった脇の面子も良い仕事をしている。白川町の落ち着いた佇まいが印象的で、これは観て損の無い佳編だ。