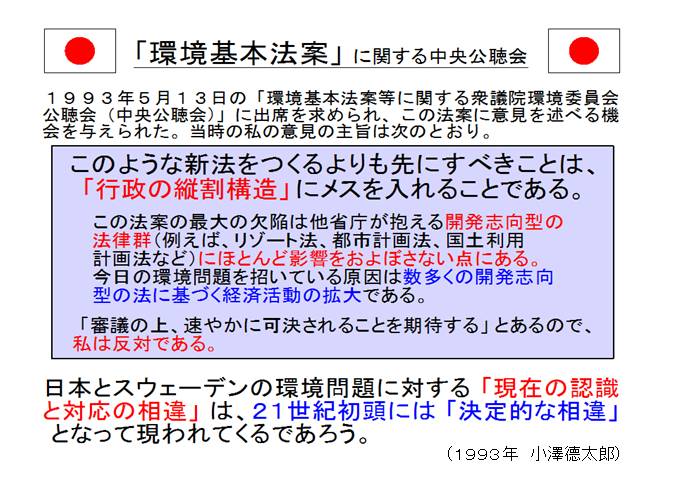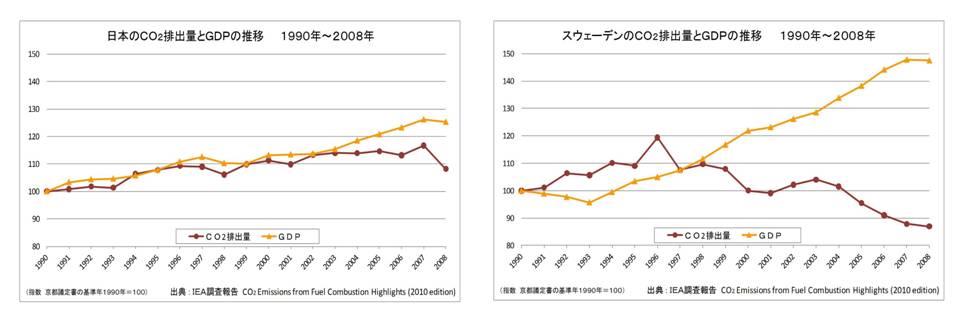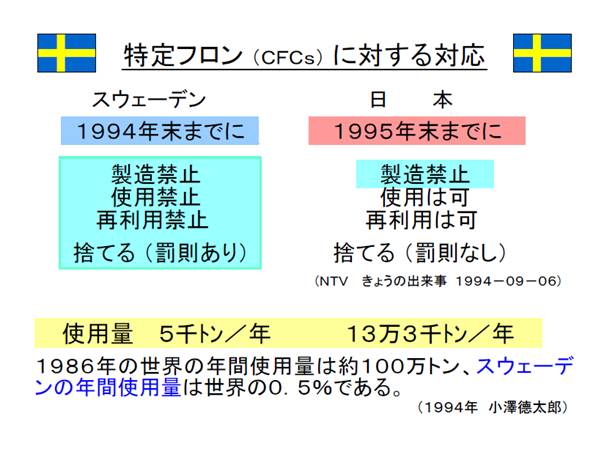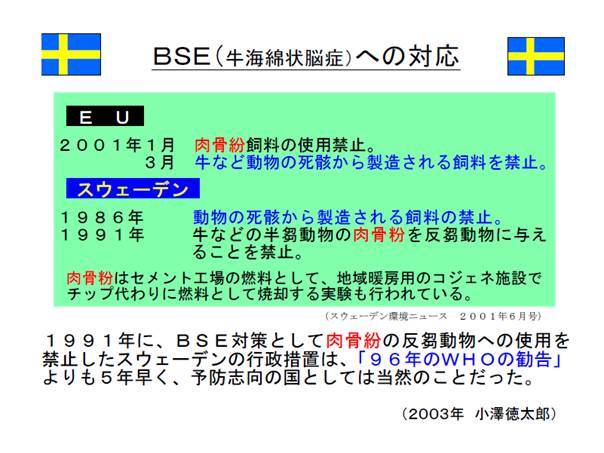私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック
お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック




1.2011年2月のブログ掲載記事
2.低炭素社会:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-27)
3.地球サミット20年:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-26)
4.オゾン層保護:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-22)
5.動物福祉:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-17)
6.酸性雨汚染 地球を巡る:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-11)
7.地球サミット 新時代の号砲:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-04)
8.再び、「あべこべの国」 日本とスウェーデン(2011-02-01)
お問い合わせはここをクリック アーカイブ(公開論文集) 持続可能な国づくりの会のホームページ(HP)は、ここをクリック




1.2011年2月のブログ掲載記事
2.低炭素社会:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-27)
3.地球サミット20年:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-26)
4.オゾン層保護:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-22)
5.動物福祉:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-17)
6.酸性雨汚染 地球を巡る:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-11)
7.地球サミット 新時代の号砲:日本とスウェーデンの対応の相違(2011-02-04)
8.再び、「あべこべの国」 日本とスウェーデン(2011-02-01)